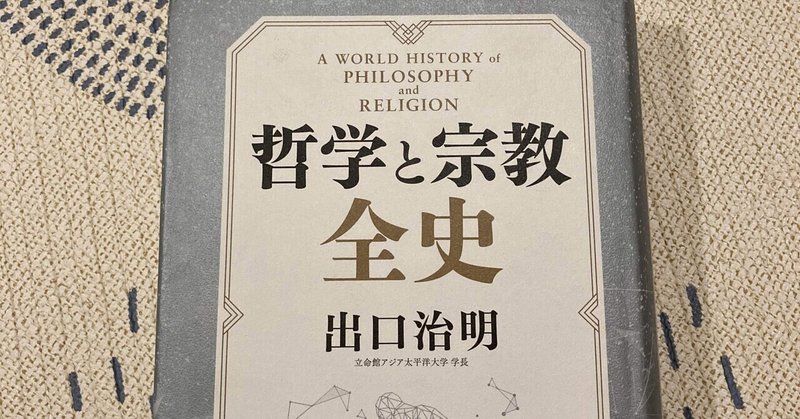
【哲学と宗教 全史】日本人の弱点を体系的学ぶ名著
オススメ度(最大☆5つ)
☆☆☆☆☆
〜時系列順に学ぶ哲学と宗教〜
めちゃめちゃ面白い!
これは間違いなく今年僕が読んだ本の中で、NO.1だ。
哲学や宗教、というのはなんともとっつきにくい分野で、僕もかなり苦手な分野だ。マルクスの「資本論」やプラトン、アリストテレスなどに挑戦したことがあるが、いずれも途中で読むのをやめている。
聖書にも挑戦したこともあるが、こちらも同じ結果だった。
哲学と宗教に関する本を、原文だけを読み始めるとよくわからなくなる。
本書の素晴らしいのは、哲学・宗教を歴史と絡めながら、哲学者や思想家の生み出す思想がその当時の情勢からどのような影響を受けて考案・発展していったのかを時系列順に丁寧に解説しているところだ。
例えば、僕は「資本論」を一度挫折している。しかし、本書のマルクスの項を読む事で、ヘーゲルが人間の歴史の最高の状態である「絶対精神」というものを、マルクスは「生産力」に置き換える事で、歴史の原動力は何かということを説明した、ことが理解できる。
そうすれば、その本が書かれた背景を理解した上で読むことが出来るようになる。各哲学書や思想の本に興味が出てきたならば、本書は入門書として非常に良い。
僕はこの本をきっかけに哲学や宗教の本にもう一度挑戦してみようと思っている。
〜世界や人間の不明瞭な部分に思いを馳せる〜
本書は単に哲学と宗教の歴史を順に紹介していくだけではない。
哲学者や思想家たちがその思想に到達するまでの、過程が非常にドラマチックでロマンに溢れているのだ(一部、著者の想像が含まれていることもあるが)。
そもそも、哲学と宗教はどちらも「人間はどこからきてどこへ行くのか?」「世界はどのようにできたのか?」「世界はどのように動いているのか?」など、世界の成り立ちや人間の存在を問う事を始まりとしていた。
現代のように宇宙の成り立ちから人の一生まで様々な事が科学的に解明されているわけではない時代において、哲学者や思想家たちは様々な想像をめぐらせて神の存在を創り出したり、不可分な物質(今で言う原子)を想像したりしていたのだ。
わからないことに想像を膨らませる考察は非常に興味深い。哲学者たちが、今の自然科学の正解に近いところまで想像を巡らせていたことに驚きを隠せない。
かくして、哲学が全ての学問の始まりである、と言っても過言では無いように思える。
今は、エビデンスが重要視されている世の中ではあるが、本書を読むことで想像を膨らませて思考することの重要性と面白さを知ることにもなった。
〜哲学や宗教はもう不要なのか?〜
さて、最後に著者も書いていたことだが、現代は宇宙の成り立ちから自然の仕組み、人間の一生、はたまた脳科学や心理学で人間の精神に至るまであらゆる事が解明されている。
哲学における問いは、科学的に解明されている事が多く、哲学そのものが不要なのではないか?
宗教についても、科学が発展した現代では「神」や「スピリチュアル」といった類のものはどこか怪しげな印象を持たれることが多い。
しかし、未だに某新興宗教の問題はあるし、資本主義民主主義の代表のようなアメリカでも新興宗教の数は年々増えているそうだ。
もちろん、不当に経済的な負担を強いるような宗教を肯定するつもりはないが、それでも人々はどこかで神の存在や人の生きる意味などを求めているのは現代でも変わらないのだと思う。
ここからは僕の意見だが、本書を読んで感じた哲学における重要なことは、「疑って考える」「よく観察して考える」事だ。見方を一つ変えてみると、「科学を信用することも一つの宗教である」と考えることだってできる。
科学だって、突き詰めてみれば不明瞭なところはいくらだってあるし、世の中で当たり前だと思われて通説がひっくり返ることもいくらだってある。
これまでの著名な哲学者たちがそうであったように、哲学とは「考え続ける学問」なのだ、と僕は考える。
過去の哲学にはすでに答えが出てしまったものも多い。しかし、だからといって考えることをやめてはいけない。
答えのないことに答えを出そうと考え続ける。それが哲学なのだと僕は思う。
哲学の歴史そのものではなく、哲学のマインドを人類は持ち続けるべきだろう、と僕は思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
