
自信過剰な指導者が戦争を始める:Overconfidence and War (2004)
自信に満ち溢れていることは、さまざまな社会生活を送る上で望ましい態度であると考えられています。特に指導者は自信を持っているように振舞えなければ、大きな集団をまとめ上げ、彼らに忠誠を誓わせることは難しくなります。しかし、オックスフォード大学セント・アントーニーズ・カレッジのDominic Johnson教授は、このような傾向が行き過ぎることによって、戦争のリスクが高まると論じています。
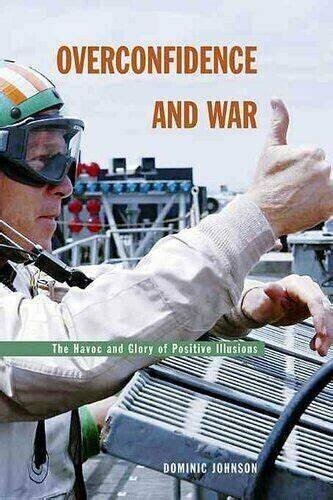
以前から研究者は指導者の心理状態、特に強い楽観主義が開戦の決め手になる可能性を認識してきました。ある分析によると、16世紀以降の戦争の歴史で開戦した国家のうち25%から50%が手痛い敗北を喫しています。これは戦争を始める指導者が自国の能力を過大に、そして敵国の能力を過小に歪めて認識する傾向を持っていることを示唆しています。著者は、これが戦争の原因を考える上で一般的に考えられている以上に重要であることを明らかにしようとしています。
著者の見解によれば、対立する場面で人間は自信過剰(overconfidence)になる心理的な傾向を持っています。一般に自信過剰な人間は、敵対する人間を自分より弱く劣ったものだと思い込みます。これは敵と味方の能力の優劣を誤認することに繋がりますが、同時に目標を達成するために投資してもよいと考える時間や労力を大幅に増加させる効果もあります。つまり、最終的に勝利するのは自分だと自らを欺くことによって、より長期にわたり、より懸命に努力を持続させることができるようになります。自信過剰な態度を示すことによって、対立する相手に自分を実態以上に強い存在であると見せかける効果も期待されます。つまり、自信過剰な人間は、自分だけでなく、相手を欺いて優位な立場に立てる可能性があるのです。
国家の指導者を被験者として、一般の人々よりも自信過剰に陥りやすい傾向にあることを実験で裏付けるような研究は未だに実施されたことがなく、直接的な証拠が不足していることは否めません。しかし、著者は国家の指導者が、自信過剰に陥る傾向は、平均的な個人よりも高いと推測できる状況証拠があると考えています。政界で活動することは、金銭的にも精神的にも強いストレスに晒されることになります。政治家は世間から絶えず批判される仕事でもあり、自分の考えこそが正しいと信じられなければ情緒の安定性を保つことも容易ではありません。選挙、メディア、議会を通じた厳しい監視のメカニズムは、自信がなく、心理的不安を感じやすい性格を持った個人のパフォーマンスを低下させるため、結果として国家の指導者に就任する人物がより自信過剰なタイプである可能性は高いと考えられます。
著者は、指導者の自信過剰が戦争の意思決定に影響を及ぼしたことを裏付ける事例として、第一次世界大戦(1914~1918)の二次分析を行っています。第一次世界大戦が勃発した原因に関しては歴史学者の間でさまざまな議論がなされていますが、国際政治学では政治学者スティーヴン・ヴァン・エヴェラの研究で示された「攻勢のカルト(the cult of the offensive)」と呼ばれているジレンマが重要であったと考えられています。ヴァン・エヴェラの説によれば、当時のヨーロッパでは鉄道網が広範囲に整備されており、以前よりも大規模な陸上戦力を広域にわたって、しかも迅速に機動させることが可能となっていました。このため、前進する敵を待ち構えるような受動的、防衛的な態勢では、側面から攻撃されることや、あるいは後方を遮断されることを恐れなければなりませんでした。したがって、国際的な緊張が高まった時点で、時間をかけて外交交渉を進めることは、敵軍に先制を加えることを許し、味方に壊滅的な損害を被らせる可能性があり、各国は可能な限り早く軍隊の動員と展開を始めなければと焦り、それが結果として大規模な戦争を引き起こしたと考えられています。
攻勢のカルトは、ヨーロッパの各国が第一次世界大戦に向かって突き進んだ過程を説明する上で示唆に富んだ学説です。しかし、敵を先に攻めることで、有利な態勢を作り出すという議論は軍事戦略の分野で何ら目新しいものではありません。著者は、この学説だけでは当時の各国の指導者がいずれも自国の勝利を確信して開戦に踏み切ったことを説明することはできないと批判しています。ヴァン・エヴェラ自身も認めているように、第一次世界大戦の要因は一つではありません。著者が重視している要因は指導者の心理的要因であり、イギリス、フランス、ロシア、ドイツ、オーストリア=ハンガリーの指導者が戦争で年内に勝利を収め、有利な条件で終戦を迎えることができると予測していたことです。各国の指導者は同じ時期に同じような楽観的な幻想を抱いていたのです。
著者は、第一次世界大戦の交戦国の指導者が陥った自信過剰の影響について国別で検討しており、戦争計画の前提となる状況判断に深刻なバイアスをもたらしていたと論じています。例えばドイツの皇帝ヴィルヘルム二世は、1914年8月に、これから戦地へと向かうドイツ軍の将兵を前にして「木々の枯れ葉が落ちる前に、諸君は家に帰れるだろう」と発言しました。参謀総長ヘルムート・フォン・モルトケは開戦から4週間でフランスを打ち負かし、4か月で残りの敵国を打倒できると見積もっていました。しかし、同時期のフランス陸軍はまったく違った予測を立てていました。
ドイツ軍の進撃はフランスに達する前に、ベルギーで食い止められるはずだとフランス陸軍の内部では予測されており、特にリエージュの要塞を攻略するためには予備役の動員が必要で、これには相当の時間を要すると予想されていました。フランス軍は砲兵の火力支援を受けた歩兵の攻撃によって敵の部隊を簡単に退けると期待していましたが、それが簡単ではないことが明らかになったのは開戦後のことでした。著者は、日露戦争(1904~1905)の記憶が新しいロシアは比較的、戦争に対する自信が乏しかった方だと述べていますが、それでも動員の責任者であるウラジーミル・スホムリノフ陸軍大臣は戦争を数か月で終わらせることに強い自信を示し、皇帝のニコライ二世の開戦決定を後押ししています。
この著作は政治指導者の意思決定過程を考える上で有益な考察ですが、著者が提示する証拠がいずれも逸話的なものであり、二次文献に依拠した事例分析にとどまっている点で限界があると思います。著者は自信過剰が政策決定に与える影響を抑制する方法について考察しており、その指導者が置かれた政治体制の形態についても議論し、ベトナム戦争でアメリカの歴代大統領の政策決定を分析していますが、この主張はいささか不明確であるという感想を持ちました。ただ、指導者が軍事情勢をどのように認識していたのかを研究者が正確に把握し、記述することが難しいという事情を考慮すれば、実証において課題が残されていることは当然でしょう。
関連記事
調査研究をサポートして頂ける場合は、ご希望の研究領域をご指定ください。その分野の図書費として使わせて頂きます。
