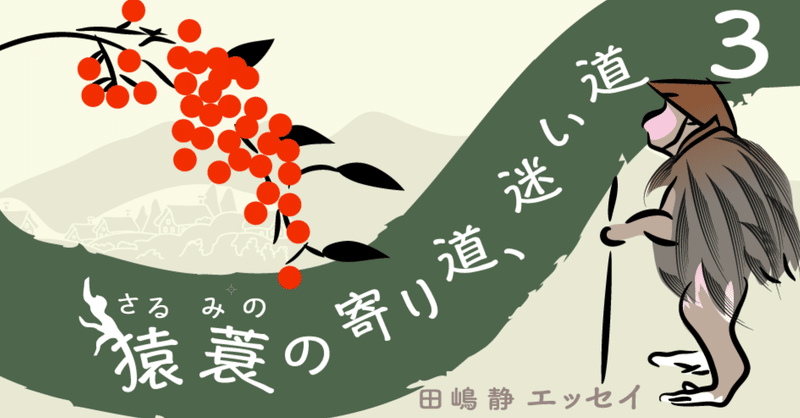
#3 第1章 「五徳(ごとく)」
かな書道は活動中止
健康塾、かな書道「フジタ会」は活動中止となった。コロナ禍でメンバーが集まって学習する機会が失われ、自宅でひとり、「評釈 猿簔 幸田露伴・著」の俳句を、半紙に散らし書きをしていく日々となった。
「評釈 猿蓑」の頁を捲っていると、どこやら懐かしい言葉に出会うことがある。すると、(ン?)と筆を持つ手が止まる。
俳句の墨書も楽しいが、
「何、それ」と筆を擱き、寄り道、迷い道*1 をするのはもっと楽しい。
*1 寄り道、迷い道
アレコレと追いかけ発展しては調べ、それを書き留める事
今回は、「評釈 猿蓑」の文中に登場する其角*2 序である。文中、「五徳」*3 という言葉に出会った。
私にはなにやらゆかしい[ゴトク]である。
其角 序の五徳が出てくる行を少し記す。
俳諧の集作ること古今にわたりてこの道のおもて起すへきときなれや(中略)不変の変をしらしむ五徳はいふに及はす心をこらすへきたしなみなり(以下略)
と、難しい。この序には、露伴の評釈がない。
私には、ボンヤリしか内容が分からない。
どうやら、「俳諧集を作るには、五徳の心掛けが必要ではないか」と述べているようである。
其角の語る五徳は、高邁な内容であるらしい。
しかし、私は、其角が述べている五徳とはまったく違う五徳で、寄り道、迷い道をすることになった。
*2 其角(きかく)【 榎本其角 】(1661-1707)江戸前・中期の俳人。
後に、宝井姓。蕉門第一の高弟。
*3 五徳(ごとく)
① 五つの徳目。仁、義、礼、智、信。
②武将が意を用いるべき五つの徳目。 知、信、仁、勇、厳。
③火鉢の灰の中に据えて、鉄瓶や釜などをのせる、三本脚の輪 形の台。
④家紋の一。③の全形をかたどったもの。

私は1944年、戦禍を避けて、祖父母の地・椿の里に疎開した。小学校(当時は、国民学校)に入学する前で、6歳であった。それから小学校3年の夏まで祖父母の家で暮らした。
祖父母は既に亡くなっていて、集落の人々が、とみ爺の家と呼ぶ空き家が残っていた。その家に、父の出征後、母と私と妹が暮らすことになった。
とみ爺の家は、典型的な百姓屋で、家の真ん中に囲炉裏*4 があった。
囲炉裏の中央に[ゴトク]が鎮座していた。
私が、[ゴトク]の漢字を知るのはずっと後のことである。
五徳は、炭火の上に据えて、鉄瓶などをその上にのせる。3脚だか4脚だかの輪形の器具である。
囲炉裏の中央には、上から自在鉤*5 がぶら下がっていて、その先に鉄鍋や鉄瓶が掛けられている。
夕餉の鉄鍋は五徳の上に下ろされて、みなで鍋を囲んだ。
正月には、五徳の上に網に置き、餅を焼いた。
火力が強い時は、燠*6 を広げて調節し、餅を網の隅のほうに並べた。
忙しく裏返しをして、プーと膨らんで来るのを待つ。
しばらくすると、餅の香ばしい匂いが家中に漂う。
母は、お手塩(小皿)に少量の醤油を垂らして、囲炉裏枠の板の上に置いた。
焼けた餅の角に、たじない(貴重な)醤油少しつけて頬張る。
焼き餅は何よりのご馳走であった。
母は、1日中、囲炉裏の火を絶やすことがなかった。寝る時は、燠火にして灰の中に埋めた。
朝になるとまず、それを掻き出して、壺から消しずみ*6 を取り出して加え、その上に小枝を細かく折ってのせた。
(母がマッチを使っているのを見たことがない。もう、物資が不足する世になっていたと思われる)
火吹き竹*7 を使うまでもなく、すぐ、炎が燃え上がり、煮炊き用の囲炉裏となる。
春夏秋冬、囲炉裏の火は絶えることがなかった。
五徳もずっと囲炉裏の中央にあった。
*4 囲炉裏(いろり) 室内の床を四角に切って、火を燃やし、暖を取ったり、煮炊きをしたりする所。
*5 自在鉤(じざいかぎ) 炉、竈(かまど)などの上から下げ吊し、鍋、釜、鉄瓶などを掛けるカギ。
*6 燠・熾(おき) 熾火と同じ。火勢が盛んで赤く熱した炭火。薪が燃えた後の赤くなったもの
*7 火吹き竹(ひふきだけ) 吹いて火をおこすのに用いる。先に小穴を開けた竹筒。
*8 消しずみ 熾った炭火や燃えた薪の火を消してつくった炭。火付きがよい。

3年間の疎開生活を終えて、私が小学3年生の夏休みに、一家は長崎市内に引越した。
父は、終戦から1年して、中国大陸から帰還した。
妹の下に男の子が生まれ一家は5人家族になっていた。
長崎市に移って囲炉裏のある生活は絶えたが、五徳は長く身近にあった。移り住んだ家は、粗末な応急住宅で、唯一の暖房が火鉢*9 であった。燃料は、練炭*10 であった。
その火鉢の中に五徳があった。
昼間は、五徳にヤカンがのって、緩やかな湯気を立てた。
正月になると、五徳の上に金網がのった。家中の誰彼が、入れ替わり立ち替わり、火鉢の金網に餅を置いた。
狭い家の中に焼き餅の匂いが充満した。
焼いた餅は、砂糖入りの醤油をたっぷり付けて食べた。
*9 火鉢(ひばち) 灰をいれ、中に炭火などをおく暖房具。料理にも使い、座敷の調度ともした。
*10 練炭(れんたん) 固体燃料の1つ。無煙炭、木炭などの粉末を混ぜて、粘着剤で固めたもの。円筒形で10本前後の穴がある。

昭和29年頃になりますか、私が高校1年生の時、家を新築する話が持ち上がった。
この頃から長崎市の景気がよくなって行った。
父は、造船所に勤めていて、頻繁に殘業をするようになった。
2時間残業と4時間残業をした回数を数え、給料日を待つようになった。
父の給料が増え、晩酌の回数も増えていった。
豊かになったところで、6畳1間に親子6人が寝る状態を何とかしなければと、新築の話が持ち上がった。
父は、私を連れて、故郷である 西彼杵郡長与村 まで、土地探しに行った。
しかし最終候補地は、すぐ近くの、通称 奥山と言われている所になった。
応急住宅の家から、徒歩30分ばかり上った所に50坪ばかりの借地が確保出来た。
ここにはK工務店の作業所兼住宅が1軒あって、Kさんとは、毎年の餅つきで交流があった。
浦上川の支流は行き行きて小川となる
応急住宅の真ん中を流れる浦上川の支流は、川幅は広く、洗濯のため下りる石段が設けられている程深い。
雨期には、毎日、川の中ほどの深さの水が蕩々と流れた。
台風が来ると、道路スレスレまでの濁流となる。
この支流には、上流に向かって3つの橋が架かっていた。
最後の橋の先で、川は地中深く潜り、岩の間を曲がりくねって上っていく。奥山の入り口で淵となって緑色に淀む。
そこへ注ぐ川は深さ1メートルである。川幅は、飛び越えることはできないぐらいの広さがある。
この川は、新築の我が家敷地までで、その先は、小川となり、雑木林の中に消えていた。
新築の家の前には、ハイキングコースの細道が、小江原地区まで通じていた。
その細道から、新築の家には頑丈な橋が架けられた。
電気は来ていたが、水道とガスはなかった。
煮炊きは、おくどさんで薪を使った。
水は、小川に下りて、上流から汲み上げた。
暖房は火鉢であった。
奥山の家でも火鉢が暖房器具として重宝された。
勿論、正月には餅を焼いた。
贅沢に海苔を巻いて食べた。
火鉢と五徳が消えたのは、エアコンが普及した頃である。
思えば長い五徳との付き合いであった。
私は24歳で結婚して、奥山の親の家を出た。
大阪の地で、無我夢中で仕事をした。悲しい出来事もあった。
ある時、フッと思い立って、ひとり長崎のへ帰省した。
昭和44年と記憶している。
いつの間にか、前の帰省から長い時間が経っていた。
奥山の家の前まで道が拡張され、車が行き交うようになり、立派な町となっていた。
住宅が建て込んでいて、タクシードライバーに道案内が出来なかった。
「この2、3年で急に家が増えました。無理もありません」
と同情される始末であった。
我が家の遙か上の方に、シロヤマ第二小学区が建設されて、河川に下水が流れ込むようになった。小川の清流は、只、流れるだけとなった。
新しい町名ができて、奥山の名は消えた。
辞書には色々な五徳の内容が記載されている。
火の中に4本足の鉄の足を入れて、その上の輪に鍋や釜を載せるという構図から、言葉が出ているようである。
逆さ様にして鉄の輪を被ると呪詛に使われることもあるとか。
五徳は、もう暮らしから消えたと思っていたが、どっこい、ガスの調理台に残っていた。
五徳の話はこれでお仕舞いです。
第2章は、「畳」で、寄り道をする。いかなる展開になりますやら。
(エッセイ)「猿蓑 の 寄り道、迷い道」 #3 第1章「五徳」
をお読みいただきましてありがとうございました。
2024年2月16日#0 連載開始
著:田嶋 静 Tajima Shizuka
当コンテンツ内のテキスト、画等の無断転載・無断使用・無断引用はご遠慮ください。
Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.
このエッセイが気に入ったら、サポートをしてみませんか?
下の 気に入ったらサポート から気軽にクリエイターの支援と
記事のオススメが可能です。
このnoteでは 気に入ったらサポートクリエイターへの応援大歓迎です。
ご支援は大切に、原稿用紙、鉛筆、取材などの執筆活動の一部にあてさせていただきます。
#エッセイ#有料老人ホーム#シニア向け#高齢者施設#高齢者#人生#芭蕉#露伴#俳句#かな書道#楽しい#懐かしい話#クスッと笑える#思い出#長崎#女性の生き方#電子辞書#古語辞典#意味調べ#意味を調べたらビックリだわ#懐かしい思い出#猿蓑#評釈#古典がすき
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
