
行離れて知なし。身体化認知の世界
📖 文献情報 と 抄録和訳
手の拘束は脳活動を低下させ、意味課題における言語反応速度に影響を与える
📕Onishi, Sae, Kunihito Tobita, and Shogo Makioka. "Hand constraint reduces brain activity and affects the speed of verbal responses on semantic tasks." Scientific Reports 12.1 (2022): 1-11. https://doi.org/10.1038/s41598-022-17702-1
🔗 DOI, PubMed, Google Scholar, プレリリース
🌲MORE⤴ >>> Connected Papers
※ Connected Papersとは? >>> note.
✅ 前提知識:身体化認知(Embodied Cognition)とは?
- 「身体化認知」とは、「身体的感覚が判断の助けとなる」という考え方に基づいた理論。
- 近年の研究では、冷たいコーヒーを持った後に比べ、温かいコーヒーを持った後の方が、他者を温かい人であると評価することが検証されている。
- 身体化認知(embodied cognition)という概念には、以下の異なる6個の主張が含まれている
- 主張1. 認知は状況に埋め込まれている(Cognition is situated)。
- 主張2. 認知は時間的制約の下にある(Cognition is time pressured)。
- 主張3. ひとは認知的作業を環境に肩代わりさせる(We off-load cognitive work onto the environment)。
- 主張4. 環境は認知システムの一部である(The environment is part of the cognitive system)。
- 主張5. 認知は行為のためにある(Cognition is for action)。
- 主張6. 環境から切り離されているときの認知も身体に基づく(Off-line cognition is body based)。
🌍 参考サイト① >>> site.
🌍 参考サイト② >>> site.
📕Wilson. Psychonomic Bulletin & Review 9, 625–636 (2002). >>> doi.
🔑 Key points
- 手の動きを拘束すると、手で動かせる物の意味を処理する脳活動と言語化の速度が低下する
- 言葉の意味を処理することと、体の動きは強く結びついており、脳内で体の動き含めて記憶しているという身体化認知の考え方を実証
[背景・目的] 身体化認知の理論によれば、意味処理は身体運動と密接に関連している。例えば、手の動きを拘束すると、手で操作できる物体に対する記憶が阻害される。しかし、体の拘束が意味処理に関連する脳活動を低下させるかどうかは確認されていない。
[方法] 我々は、機能的近赤外分光法を用いて、頭頂葉の意味処理に対する手の拘束の影響を測定した。手で操作可能な物体(例:カップや鉛筆)と操作不可能な物体(例:風車や噴水)の名前を表す一対の単語を提示し、参加者にどちらの物体が大きいか識別させた。判定課題における反応時間(reaction time, RT)と、左頭頂間溝(left intraparietal sulcus, LIPS)および左下頭頂小葉(left inferior parietal lobule, LIPL)の活性化(上頸部回と角回を含む)を分析した。

✅ 図1. (B)実験条件。左:拘束なし条件、右:手部拘束条件。手部拘束条件では、手の動きを透明なアクリル板で拘束した。被験者の疲労を軽減するために、各条件のセッションは別々の日に行われた。
[結果] 手の動きを拘束すると、手で操作可能な物体に対するLIPSの脳活動が抑制され、大きさ判定課題のRTに影響を与えることがわかった。

✅ 図2. サイズ判定課題における平均RT(反応時間)。オレンジ色の点(手の拘束あり)と青色の点(拘束なし)は、各参加者の平均RTを示す。平均値は横線で表示。縦線は、Cousineau-Morey法に従い、参加者のランダム効果を差し引いた後の95%信頼区間を示す

✅ 図3. サイズ判定課題実施中の血行動態。(a) AIP(IPS前部)、(b) CIP(IPS尾部)、(c) SMG(斜角回、BA40)および(d) AG(角回、BA39)にあるチャンネルの血行力学的活性を示す。サイズ判定課題における各参加者の血行動態反応の平均z scoreを示す。オレンジ色の点(手の拘束)と青色の点(拘束なし)は、課題中の各参加者の血行動態反応の平均zスコアを示す(n = 28)。平均値は横線で表示。縦線は、Cousineau-Morey法に従い、参加者のランダム効果を差し引いた後の95%信頼区間を示す。
[結論] これらの結果は、体の拘束が意味論に関与する脳領域の活動を低下させることを示している。手の拘束は運動シミュレーションを抑制し、その結果、身体に関連する意味処理を抑制するのかもしれない。
🌱 So What?:何が面白いと感じたか?
富士山頂からのご来光。
あれは、きれいだ。
きれいだが、ちょっとイメージしてほしい。
・あなたが超大金持ちで山頂までヘリでサッと移動し、見たご来光。
・途中山小屋に泊まり、高山病になりながら、嘔吐しながら命辛々たどり着いた山頂で見たご来光。
どちらが記憶に刻まれると思う?
車や飛行機やヘリコプターでは通れないルートがあるのだ。
アクティブタッチ、という。
僕たちは、出力-入力の関係性から、何かを知る。
具体例をあげよう。
いま、机の表面のざらざら具合を確かめてみてほしい。
あなたは、手で机に触れただけではないはずだ。
きっと、擦ったことと思う。
「あなたの手の出力に対して、この感じの入力だったら、こんなざらざら具合ですね」という統合が行われているのだ。
その過程では、1つの出力-入力の関係性だけでなく、いくつもの関係性を知ることによって、物体の特性や状況・状態を知ることができる。
そのためには、擦る、揺り動かす、振るなど、「自ら動かしてみる」ことが重要となる(例. ガイドポストの硬さを知るためのActive touchの利用)。
このような考え方をアクティブタッチ(Active touch)という。

『行』を伴った『知』にだけ、『意味』が付与される。
意味とは、出力に対しての入力を分析したときに生じてくる第3の価値だ。
自分が入れた力に対する触圧覚の入力を分析することで「重さ」という意味が生じるように。
人間のハードウェア(身体)とソフトウェア(脳)は離れては機能しにくい。
なぜなら、両者が協働しなければ生まれない第3の価値があるから。
どんなに時間がかかろうと、大変だろうと!この足で歩こう。この地面を踏みしめて歩こう。
身体化認知、重要なワード。
人間の乳児は、動くことを学びながら、学ぶために動きます
Adolph, 2021
○●━━━━━━━━━━━・・・‥ ‥ ‥ ‥
良質なリハ医学関連・英論文抄読『アリ:ARI』
こちらから♪
↓↓↓
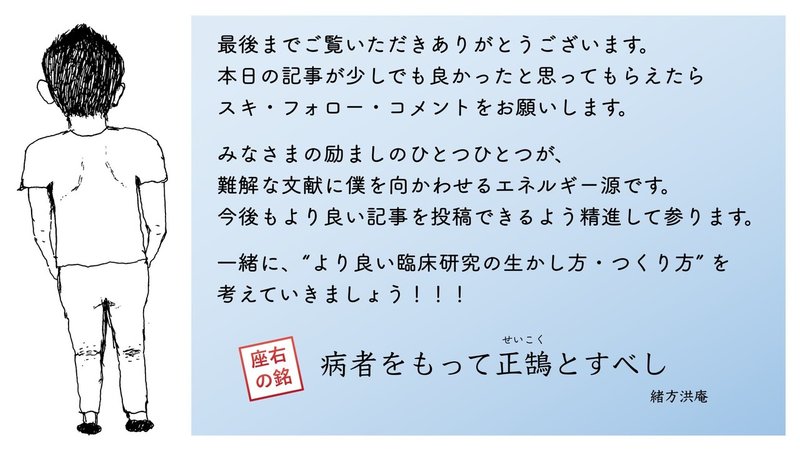
‥ ‥ ‥ ‥・・・━━━━━━━━━━━●○
#️⃣ #理学療法 #臨床研究 #研究 #リハビリテーション #英論文 #文献抄読 #英文抄読 #エビデンス #サイエンス #毎日更新 #最近の学び
