
茶の湯に通ずるサルの行動学
本日も寝る前にさらりと茶の話を。
昨年、私のところにカプセルホテルの喫茶サービスの話があり、何度か試験的に行ったのだが、私の力不足で結果的に導入できなかった。短い時間の中で心身が豊かになるプログラムが組み込まれた最新式のホテルで、私も何度かカプセル内で寝たが、とても心地が良かった。
喫茶サービスがどんなものだったかというと、「朝茶」だ。
パッと起きて、サッとシャワー浴びて出ていく外国人旅行客や日本人の出張マンたちに、抹茶をシャカシャカと出すサービスだった。
兼ねてから思っているが、現代、茶人は茶室から出なければならない。茶室だけでなく、日常のあらゆるところで喫茶の素晴らしさを伝えなければならない。であるからして、カプセルホテルほど最適な場所はない!という、とても意欲的な場所だったわけだが……残念至極。もちろん未だ諦めてはいない。

そんな時、中国に住むドイツ人の男性に出会った。最初は、朝から寿司をバクバク食べていて、乙だなあ、と思って見ていたら、自然と話をするようになった。彼は動物の行動学を研究してる研究員で、1週間ほど日本に滞在するためにカプセルホテルに泊まっていると言っていた。母国語の他に、日本語もペラペラで、中国語も二つの言語を話せると言っていた。頭の回転すこぶる良く、知識も深く、しかしそれ以上に笑い話をした気がする。
先日の何かの記事の中で、お茶を飲むときの危険性について語ったが、彼にも質問されたので、同じく答えた。
つまりは、かつて武士たちが飲んでいたお茶は今のような緑色ではなく、灰色がかっていて、それを暗くて狭い部屋で黒い茶碗で飲む。当時は毒を入れられる可能性も大いにあり、ただ、それ故にその状況下で客人が茶を飲んでくれれば信頼関係が構築される、という話だ。
彼はなるほど、と言ったあと、サルの話をしてくれた。
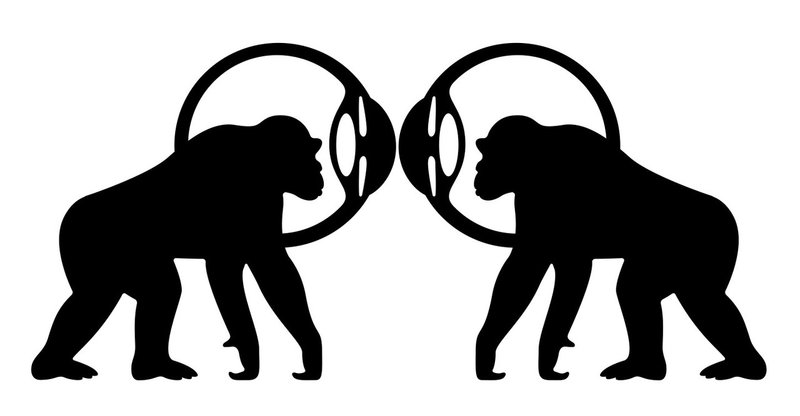
アフリカのとあるサルは、お互いの信頼度を確かめるため、互いに眼の中に指を突っ込むのだそうだ。その時間が長いほど、相手に対して心を許している、という証拠になるという。
喫茶と同じく、リスクが高まれば高まるほど、互いの関係性はより強固に結び付けられる。日本の茶の湯はそれと同じだね、と彼は言った。
敵対するグループ同士のボスが睾丸を握り合うことで平和的な解決を見る、というサルの行動は知っていたが、まさか目玉に指を入れ合うとは吃驚だった。
人間も、どの動物よりも多くの言葉を持つからと言って、それですべてを確かめられるわけではない。結局、相手をどう思えるかは、想いや気持ちという抽象的なものだけでなく、それを起点とした明瞭な行動であり、それはサルと全く同じなのだ。改めて人間の行動様式のベースが動物にあると思わされた時だった。
命がけの喫茶
今では、食中毒になったら、後に提供者を訴えることができるが、当時は、毒に当たって死ぬことは、本人の注意不足という他ない。死んだらそこで終わりだ。
このまま行ったら日本はなくなって、その代わりに、無機的な、からっぽな、ニュートラルな、中間色の、富裕な、抜け目がない、或る経済大国が極東の一角に残るのであろう。
有名な三島由紀夫の言葉を思い出す。彼の生涯の是非は置いておくとして、純然たる命の煌めきを主とする生き方など、安全が充満する日本において、誰もわからないだろう。だから、「命がけの喫茶」を理解することはできても、それを実行することは難しい。
むしろ、亭主を信じ切ってそこにいる客人に対して、命がけの行為を迫る茶の湯とは、一体どんな食文化なのだろう。改めて茶の湯の不思議さに慄く。
しかしながら、お茶を飲んで美味しいと感じたときに、ふと「命って大切だなあ」と思い返す日があることもまた重要であると思う。
安住の地にいると、どうしても命が見えなくなる。しかし、茶の湯の要素には、それまで受け継がれてきた命が宿っている。一瞬だけ灯される茶席の温かさに触れることは、命に触れることと同義である。
昨今の災害によって、日本全国民が命の危機を少なからず感じたのではないだろうか。お茶をより大切に頂く、重要なきっかけとなったと思う。
武井 宗道
これまでの記事
亭主、客を待つ
茶道人口の減少について
作法のすゝめ
茶道のお稽古とはなにか〜自粛、明けて〜
茶の湯の日常性と非日常性について
桑の魅力について
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
