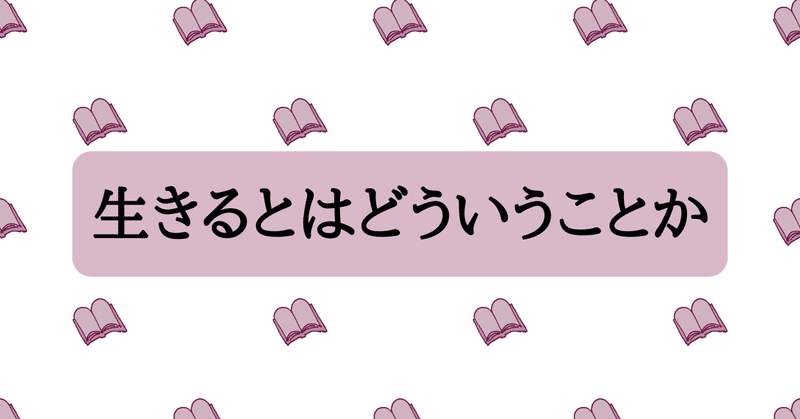
【読書記録】『生きるとはどういうことか』 #2
前回に引き続き、『生きるとはどういうことか』の読書感想です。
歳をとると、楽の思い出が増えるという。「昔はよかった」というのである。これはおそらく意識がそういわせるので、イヤなことも十分に覚えているはずである。ただそれを思い出したくないだけのことであろう。それなら「楽」が増えるはずである。さらにいうなら、苦しかったできごと自体は記憶から消えないので、それを「楽」に変換する作業を行っているのかもしれない。甘味をつけてしまうわけである。
苦い思い出を甘味にする。身近なことで考えれば、苦いコーヒーを砂糖で味つけする。そうすることで飲みやすくする。例えとして、これが近いのではないだろうか。
大人になれば、苦いコーヒーもそのまま飲める人もいる。それは、それくらいの苦さにはもう慣れていてへっちゃらだから、甘味をつける必要はない。つまり、苦しいできごとに慣れすぎて何ともないという状態だ。
苦いコーヒーを子どもの頃から飲める人は「大人だな」と言われたりする。これは中々言い得て妙な表現のように思う。つまり、その頃から辛いことには慣れているとも捉えられるわけだからだ。
(まあ、単に苦いことが好きな味という人もいるだろう)
また、現代社会は苦が悪という暗黙の了解があると言っている。
現代社会では、苦が悪であるという暗黙の常識が広がっている。私はそう見ている。その象徴が痛みであって、痛みは「ないほうがいい」。しかし痛みがなければ、生存が保障されない。そこを忘れているのである。痛む状態は、周囲からみれば「気の毒」なのであって、かならずしも「悪」ではない。痛みを撲滅することは、できないし、するべきではない。ところが現代人の潔癖症は、かなり進行している。だから痛みそのものを、取り除いてしまおうとする。そういう人たちは、「苦があるのは、悪い状態だ」と信じているに違いないのである。不安もまた同じである。危険を避けるために不安は不可欠のはたらきだが、その不安自体を除こうとして右往左往する。それによって、不安に思っている現状よりも、さらに悪い状況を引き起こしたりする。不安のために自殺したりするのである。それなら「人生、不安があるのは当然だ」と開き直るべきであろう。
これをさっき考えた、コーヒー論に紐づけてみたい。
少し古いが、上記リンクの2022年に行われた年代別のコーヒーに関する調査を元に書く。
コーヒーが好きな度合いの調査では、年代が上がるほどコーヒー好きな人が増えていることが分かる。

(上記リンクより)
このグラフの20代は30%がコーヒーが好きではない・飲めないと回答しており、やはり若い世代ほど苦みは嫌なことであり、避けたいと考えているのではないかと思った。
また、普段のコーヒーの飲み方のアンケートでは、ホットのブラックコーヒーを好んで飲む人は年代ごとに増加している。
しかし、予想に反して、20代がブラックコーヒーをアイスで飲む人が他の世代に多かったり、ミルクを一番入れるのも20代だと思っていたが、そうではなかった。

(上記リンクより)
そもそも、普段のコーヒーの゙飲み方はコーヒー好きの人のアンケート結果なので、苦手なことを避けるという点では一定水準を超えている。
なら、単にコーヒー好きな人が年齢層ごとに増加することが苦手に対する耐性がある証拠になるのではないだろうか?と思ったりした。
では、なぜ歳を取ると苦みを求めたくなるのか。
p93の引用によると、嫌なことは思い出したくないだけで覚えているはずだと。とは言っても、その苦しみと向き合いたい。そんな気持ちから苦みを求める。はたまた、p97のように、苦しみがあってこそ今の生活がある。そのことを思い出させるためにあえて苦いものを飲んでいる。
私は人生には多少の刺激のようなものが必要だと考えている。ずーっと甘いものだと飽きてしまう。逆に苦いものばかりだと苦しい。そんな状況に刺激を与えるものがコーヒーであったりするとも考えられる。
どれも万人には受け入れられないような答えに感じる。
*
理想は頭の中で、現実は外だ。それがふつうの常識であろう。でもよく考えてみると、どちらも頭の中なのである。頭がボケたら、中も外もない。だから「現実」は人によって違ってしまう。たとえ同じ人でも、脳の状況が違うのである。
最近感じるようになった。現実は変わらないのに、自分に置かれた状況を鑑みて現実を過ごすと、全く別物のように感じる。
自分の置かれた状況を加味するという行為自体が、頭の中のできごと。それを通して現実を見る。その現実を自分の状況を通して解釈するのも頭の中のできごと。そう考えれば、どちらも頭の中というのは分かる。
*
私自身の用いる自然の定義は単純である。「人間が意識的に作り出したもの」が人工だとすれば、そうでないものが自然である。
自然の定義は都合の良いように解釈されていると書かれている。地震や台風、噴火は頭から抜けており、移植や養殖した木も自然と言う。
ならば、こう考えたらどうだろうか?と。
自然と人工を自分自身に戻したほうがいい。仕方がないから、そう考えた。自分に戻せば、人工とは意識で、自然とは身体である。意識はあれこれ決めて、あれこれ指図する。ところが身体はそれを聞いてはいない。寝ているときを考えたら、よくわかるであろう。寝ることは自然というしかない。
なるほど。
例えば、身体に出来た傷に対して、意識がいくら「このまま放っておけ!」と思っても身体は勝手に直そうとする。私はこう考えて、確かに身体に対して人工と自然を当てても理解できるなと思った。
自然にこの考えを適用すると、自然の浄化作用に当たるだろう。汚染を勝手に取り除く働きがあり、意識的に自然を良くしようとは誰も思わなくても元に戻る。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
