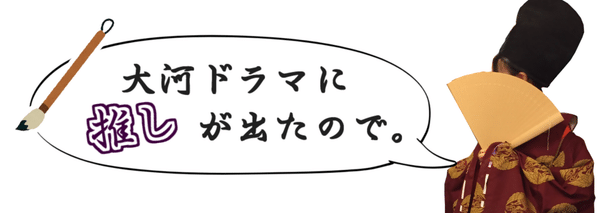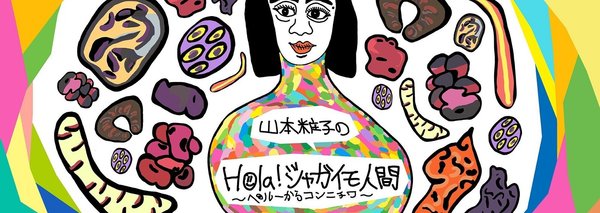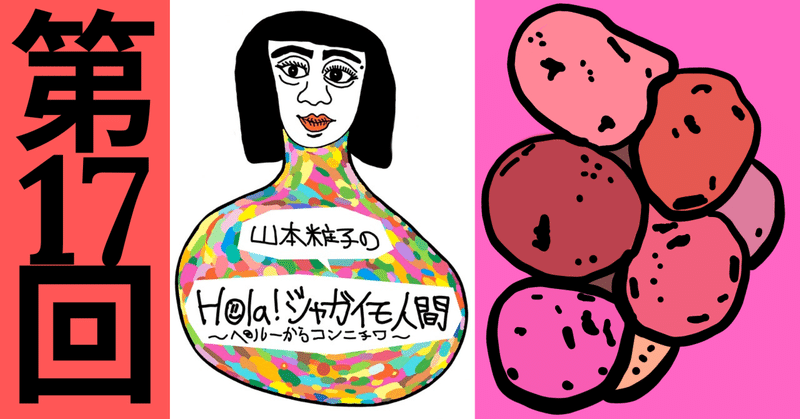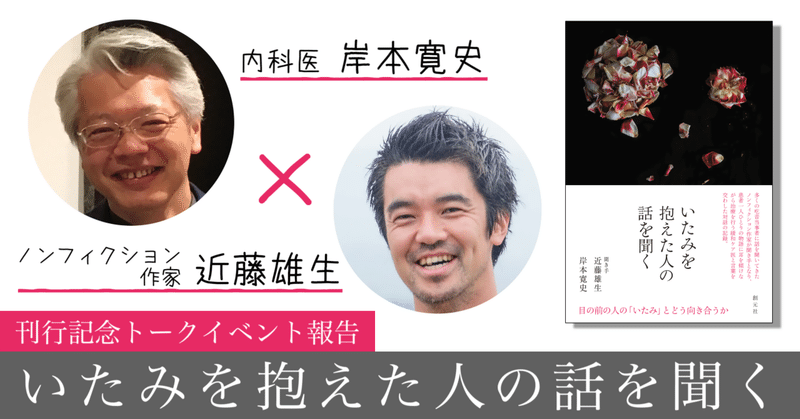最近の記事
マガジン
記事

大切な人の自死とグリーフをめぐる語り合い――wish you were hereの対話を通して|第2回 墓参りで母に語りかける習慣
母の自殺のことを家族から聞かされてから長い間、そのことをほとんど家族以外の人には話せなかった。自殺というできごとは、当時の記憶が残っていなくても重く苦しいものだった。 日々の生活のなかで、辛い出来事が起きて気分が落ち込んだときに、母の自殺のことを連想する癖がついていた。頻繁に落ち込んでしまい、気分が不安定なのは遺伝なのだろうと思っていたし、苦しいときに支えてほしい存在が、ずっと昔に自分を置いてこの世を去ってしまっていて、しかもその理由が自分自身のせいだったと思うと憂鬱だった