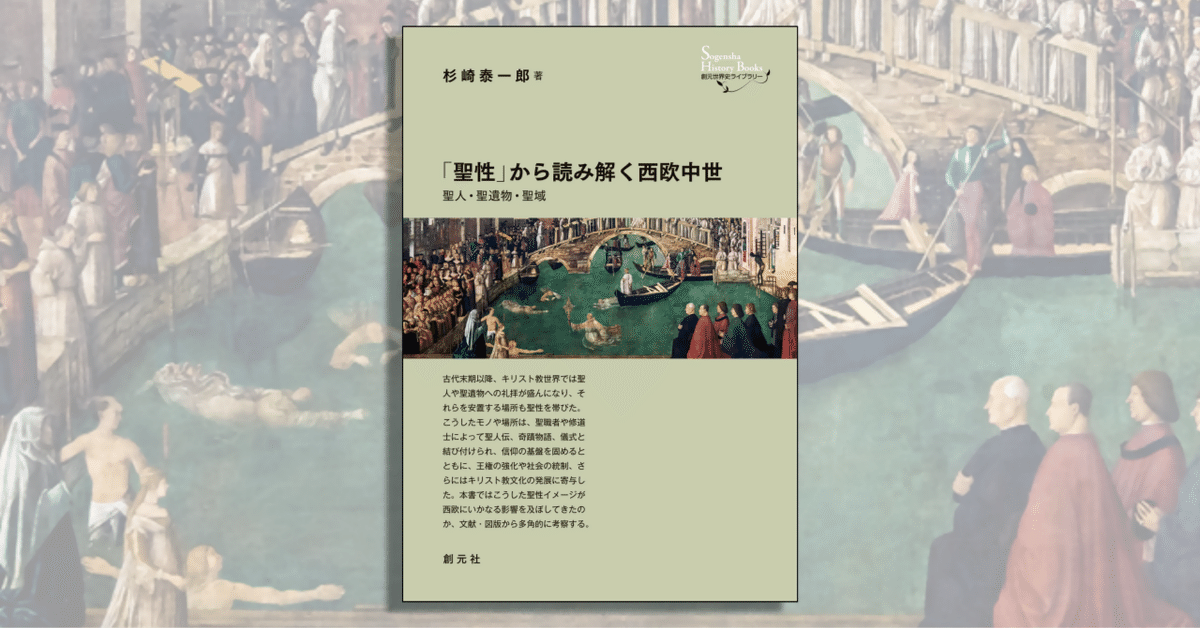
杉崎泰一郎・著『「聖性」から読み解く西欧中世』「はじめに」を無料公開
(本書より)
古代末期以降、キリスト教世界では聖人や聖遺物への礼拝が盛んになり、それらを安置する場所も聖性を帯びた。こうしたモノや場所は、聖職者や修道士によって聖人伝、奇蹟物語、儀式と結び付けられ、信仰の基盤を固めるとともに、王権の強化や社会の統制、さらにはキリスト教文化の発展に寄与した。本書ではこうした聖性イメージが西欧にいかなる影響を及ぼしてきたのか、文献・図版から多角的に考察する。
杉崎泰一郎著『「聖性」から読み解く西欧中世 聖人・聖遺物・聖域』が2024年5月に刊行いたしました。
本noteでは、著者・杉崎泰一郎氏による「はじめに」を無料公開いたします。
(書籍版と一部表記の異なる箇所があります)

はじめに
聖なる力に願いを託す人々
二〇二二年四月半ば、ロシアのウクライナ侵攻から二か月が過ぎようとするころ、ロシアの黒海艦隊の旗艦モスクワが沈没したというニュースが飛び込んできた。短期間でロシアがキーウを制圧するという予想を覆し、西側諸国の支援などによって戦争が長期化する兆しとして報道された。沈没は事故によるものか、ウクライナの攻撃によるものかは曖昧なまま続報が絶えてしまった。ただこの軍艦には、キリストが磔になった十字架の欠片、すなわち「真の十字架」「聖十字架」などと呼ばれる聖遺物が納められていて、不沈艦のはずだったという知らせもあった。日本のインターネット上では、これを壇之浦に沈んだ三種の神器にたとえる記事もあり、ロシア軍の精神的な動揺を伝えるものもあったが、こちらも詳しいことがわからないままになった。
「本物の十字架」の一部とされる木片のほか、キリストの受難に由来するモノ、とくにキリストの身体に触れた釘、槍、茨の冠、聖骸布などは、古代から中世のキリスト教世界において最も尊い聖遺物とされた。君主たちは統治権が神聖である証としてこれを獲得し、宮廷内の礼拝堂に安置し、後継者はこれを三種の神器のように受け継いだ。宮廷礼拝堂だけでなく、著名な聖人の遺体(聖遺物)を安置する各地の教会には多くの巡礼者が押し寄せ、教会の名声が高まるとともに、地域の経済効果も期待されたため、聖職者のみならず地域共同体も聖遺物を求めた。現在でもローマ・カトリックの地域(フランス、イタリア、スペインなど)の教会では、祭壇や地下の礼拝堂に聖遺物が安置されていて、参拝する人や遠方から来る巡礼者が、それぞれの願いを託して祈りを捧げている。
キリスト教の正統的な教えでは、キリストは没したあと肉体とともに天国に上がったとされるため、現世に残った生前のゆかりの品が聖遺物とされた。使徒と呼ばれるキリストの弟子や殉教者など聖人たちの遺体は、聖なる力を発揮する聖遺物と信じられ、有名な聖人の骨は分骨されて各地の教会に納められた。これは仏舎利のように遺骨を分けて礼拝することと似ている。とくに聖書に記載のある人物や、迫害時代の殉教者、キリスト教公認後の高名な聖人の遺体やゆかりの品は珍重され、これを安置する教会は多くの参拝者を集めた。
たとえばローマ教皇が座するローマのサン・ピエトロ大聖堂は、キリストの第一の使徒であり初代の教皇とみなされるペテロの墓の上に建てられていて、主要な巡礼地の一つでもある。また十二使徒のひとり聖ヤコブの墓が安置されたサンティアゴ・デ・コンポステラ大聖堂は、ローマと並ぶ主要な巡礼地として、いまなお多くの人が参拝する。中世のローマ・カトリック世界では、パリのノートル・ダムやケルンの大聖堂のように、それぞれの国や地域の拠点となる教会はもちろん、農村の小さな教会に至るまで、聖遺物を保有して祭壇に納めるか、祭壇の下の地下墓所に安置するようになり、そのなかには現代にまで残っているものも多い。
キリスト教は唯一神のみを崇拝するが、教会、修道院、礼拝堂はそれぞれの守護聖人を擁し、その聖遺物を礼拝して病気の平癒、罪のゆるし、国の平安、戦の勝利などを願った。多神教のように見えてしまうが、教義によれば聖遺物は神の力を仲介するのであって、聖遺物そのものが奇跡を起こすのではないという。そして教会や宮廷の礼拝堂は、聖なるモノを安置する聖なる空間とされ、そこは宗教儀礼だけでなく、戦勝祈願や契約締結などの場としても使われた。日本で天皇の即位式が寺社ではなく皇居で行われ、神職や僧侶を媒介としないのに対し、王をいただくヨーロッパの多くの国では、現代でも戴冠式は教会で聖職者の手によって行われる。これは正統な王位継承を宗教儀式によって聖なる場で行い、王権の正統性を広く知らしめる伝統にのっとっている。聖性をめぐる習慣は戴冠式に限らず、長い時間をかけて醸成され、ヨーロッパの日常のさまざまな場面に残っている。
キリスト教聖性の歴史を多角的に考察する
本書では古代末期から近世にかけて、西ヨーロッパすなわちローマ・カトリック世界の人々がさまざまな場面で聖なる力にたのんだこと、キリスト教聖性が成立し変化したことについて、時代を追って論じる。軸となる考察対象は聖人礼拝、聖遺物信仰、聖なる場の形成と、それらを証し広めた伝承(聖人伝、殉教記、移葬記、説教、列聖資料など)と、その担い手(王侯、聖職者と修道士、民衆)である。
第1章では、まずローマ帝国のコンスタンティヌス帝のキリスト教公認をめぐって、皇帝が聖なる力に頼るとともに、教会が聖人礼拝や聖遺物礼拝を通して広くローマ社会との関わりを持ち、民衆に歩み寄ったことを論じる。そして西ヨーロッパの支配者がローマ人からゲルマン人に移っても、ローマ・カトリック教会は存続し、聖なる力への信仰も続くことになった。そしてカール大帝が西ローマ皇帝の冠を教皇から受けたことで、西ヨーロッパの中世社会の基軸というべき教会と王侯の密接な関係が築かれた。王侯だけでなく民衆の素朴な聖人礼拝に至るまで、聖なる人、聖なるモノ、聖なる場はさまざまな次元で中世社会の中心となっていたことについて論じる。
第2章では、フランク王国が分裂したのちの紀元千年前後の西ヨーロッパについて、イングランド、フランス、ドイツを例にとって、権力者がどのように聖なる力にたのんだかを論じる。またこの時期の社会では、争いごとが起こった際には法律でなく慣習や話し合いで解決を模索することが多く、そこで聖なる力が大きな役割を果たしたことにも着目する。紛争の調停だけでなく、さまざまな誓約を行う場合にも、聖遺物を証として用いたことについて、さまざまな資料を用いて論じる。
第3章では、第2章と同じ時期の農村集落や都市に目を転じて、各地の修道院や教会に納められた聖遺物に、さまざまな身分の人々がそれぞれの願いをもって熱狂的に参拝したことを論じる。地域社会の聖俗の人々が、どのように聖遺物を礼拝したのか、近年研究が進んでいる聖遺物の移動、いわば聖遺物の旅について、具体例を紹介しながら論じてゆきたい。
第4章では、聖遺物への礼拝や聖遺物を用いた儀礼、聖人や聖遺物の社会的な働き、聖なる空間が創出されていった経緯について、詳細な史料が残っているクリュニー修道院とモワサック修道院の事例を取り上げて論じる。修道院は巡礼教会と違って、修道士たちが世俗から離れて修行に専念する脱俗的な聖域であるが、修道院が実際に世俗社会の境界線をどのように画定して聖なる空間を創出したのか、修道院においてどのように聖人礼拝や聖遺物礼拝が育まれ、営まれ、社会に影響したかについて考察する。
第5章では、農業生産が高まって流通も活発になり、都市の発展も見られた一二世紀に、人の移動が増えて遠くの聖地に向かう巡礼が盛んになったことを論じる。イベリア半島の西端サンティアゴ・デ・コンポステラ巡礼のために書かれた『巡礼案内書』を読み解き、各地に点在していた聖地が線で結ばれ、地域の聖人の物語や聖遺物が起こす奇跡を西欧社会が広く共有していったことを論じる。同時に聖母マリア礼拝や大天使ミカエル礼拝の流行が高揚していったことについて、フランス中南部のル・ピュイやロカマドゥールを例に、古いガリアの霊場がキリスト教の聖地へと転じたことも併せて考察することとする。またサンティアゴ・デ・コンポステラの『聖ヤコブの書』に書かれた聖母マリアと聖ヤコブの奇跡物語を考察し、次第に超地域的な聖人への礼拝が広まっていったことを論じる。
第6章では、十字軍遠征が繰り返し行われた一一世紀から一三世紀にかけて、聖人礼拝や聖遺物礼拝の力点がキリストや聖書にゆかりのある人物に移っていったことと、王や教皇がこれを促進した側面に注目する。言い換えるなら、王と教皇が権威を高めるために、聖性をどのように利用したのかを考察したい。そして王や教皇を中心とする体制が国と教会のレベルで整ってゆくのに沿って、聖人礼拝や聖遺物礼拝のあり方が変化してゆくさまを論じる。
第7章では、一三世紀に教皇庁と王権が統治組織を確立する過程で、聖なる力をいかに用いたか、聖性がどのように変化したかを論じる。まず教皇庁が組織を拡充させ、教会法が整備され、教皇特使を通して通達が徹底するようになり、教会改革、十字軍、異端迫害などが進められたことに触れる。その結果、列聖の手続きが教皇庁の審理に統一され、聖人や聖遺物崇敬について統一規格が導入されて、画一的な聖性の共有が進むことになったことについて考察する。ついで、フランスでは国王ルイ九世が死後二〇年余りのちに列聖されて、サン・ドニ修道院の王墓が整備され、瘰癧治しなどが儀礼化したことを考察する。そして王の権威が聖なるものであることが示され、王権が強化していったことを論じる。
第8章では、第7章と同じ時期に、教会が言葉を通してメッセージを末端まで伝えようとしたことを論じる。まずシトー会修道士が執筆した『奇跡に関する対話』を通して、聖なる場、聖なる人、聖なるモノを通して救済される理論がどのように伝えられたのかを論じる。ついで著名な聖人の伝記を集めた『黄金伝説』を取り上げ、ローマ・カトリック世界で礼拝されている聖人にまつわる物語や聖遺物が起こす奇跡物語などが集められ、広く共有されていったことを考察する。
第9章では、第7章や第8章で述べたように教皇庁が聖人礼拝を掌握して、均質化した聖性を定着させる動きが進む一方で、中世後期から近世に向けて信徒の自発的な宗教運動が高まりを見せ、各地の都市や村落の共同体では、地域のアイデンティティともいうべき聖人の礼拝が進んだことを論じる。そしてキリスト受難の聖遺物や聖書ゆかりの聖人への礼拝が進み、ルネサンスが近づくと信徒の自発的な宗教運動や個人的な信心業が盛んになったことにも、あわせて注目する。
イタリア都市では「市民的宗教」とも呼ばれる宗教性と社会性が一体となる傾向が指摘されており、ドイツなどアルプス以北では、宗教改革の進展とともに、教皇から自立したプロテスタント諸教会のもとで独自の信心と文化が展開してゆく。聖性の社会的・文化的な役割や聖なる力への期待が、聖俗のさまざまな次元で近世・近代にどのように移行していったのかを展望し、締めくくることとする。ヨーロッパ史について、聖性を通して考察した実験もしくは提案として本書をお読みいただければ幸いである。
【目次】
はじめに
第1章 コンスタンティヌス大帝からカール大帝へ――キリスト教聖性の醸造
1 コンスタンティヌス帝――聖人・聖遺物・聖域の重視
2 聖遺物礼拝の高揚
3 ローマからフランクへ――キリスト教聖性の継承
4 カール大帝の教会政策――中世キリスト教の聖性の展開
第2章 権力者と聖性
1 「ノルマン・コンクエスト」と聖遺物
2 聖なる力に頼るフランスのカペー王権
3 ドイツの王(皇帝)と聖遺物
第3章 地域社会と聖なる力
1 コンクの聖女フォアの聖遺物
2 聖遺物の移動
第4章 修道院による聖性の創出
1 クリュニー修道院の創立と発展
2 モワサック修道院――聖域の創出と聖遺物の力
第5章 巡礼と伝承
1 サンティアゴ・デ・コンポステラと巡礼案内
2 ル・ピュイ――ガリア人の霊場に由来する聖地
3 ヤコブと聖母マリアによる奇跡物語
4 サンティアゴ・デ・コンポステラの町と聖堂
第6章 教皇、王と受難のキリスト―十字軍時代の聖性を導いたもの
1 聖地エルサレムをめざす巡礼と十字軍
2 聖王ルイの聖遺物収集と十字軍
第7章 教皇による列聖、王権の聖化――聖なる力による普遍的な権威の形成
1 教皇による列聖の独占
2 ルイ九世の列聖と王権の聖化
3 聖なる王
第8章 言葉による聖性の拡散と共有
1 説教
2 聖人伝集 ヴァラッツェのヤコブス『黄金伝説』
第9章 俗人による宗教運動と地域共同体――ルネサンスから近世へ
1 生きた聖女に群がる人々
2 南仏のマリアたちと民衆の祭り
3 聖遺物のコレクションと顕示
あとがき
索引
【著者紹介】
杉崎泰一郎(すぎざき たいいちろう)
1959年東京都生まれ。上智大学文学部史学科卒業、同大学院文学研究科史学専攻博士後期課程修了。藤女子短期大学一般教育助教授等を経て、現在、中央大学文学部教授。博士(史学)。
著書:『12世紀の修道院と社会 改訂版』『欧州百鬼夜行抄』(原書房)、『ヨーロッパ中世の修道院文化』(NHK出版)、『修道院の歴史――聖アントニオスからイエズス会まで』(創元社)ほか共著多数。訳書:パトリック・ギアリ著『死者と生きる中世―ヨーロッパ封建社会における死生観の変遷』(白水社)、ジョルジュ・デュビィ『ヨーロッパの中世―芸術と社会』(藤原書店、共訳)、ジャン・ドリュモー著『千年の幸福』(新評論、共訳)ほか。
※著者紹介は書籍刊行時のものです。
