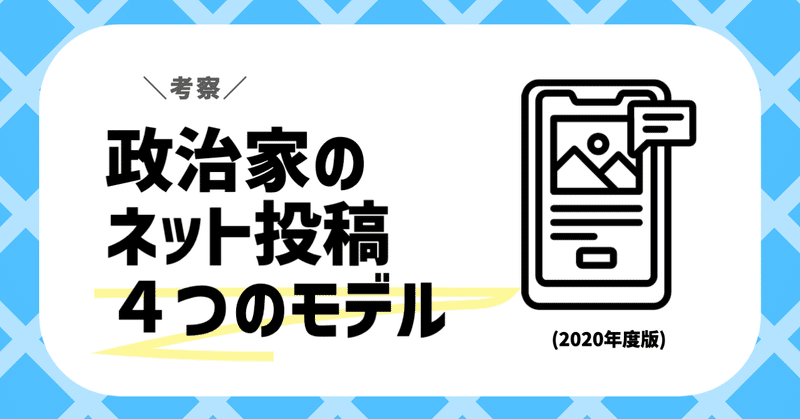
オンライン選挙における4つの投稿モデルー2020東京都知事選候補者の事例を踏まえてー
先日、産経デジタルironna様において執筆記事を掲載いただきました。ご協力いただきました関係者の皆様に、感謝申し上げます。
また上記の記事にも使用している「ソーシャル選挙」については、双方向的な会話戦略の意味合いに基づいています。日本においての「ソーシャル」という言葉は、LINEやTwitter、Facebookを使って、人と人とがつながることで、「多数の人々が参加する双方向的な会話」、「他のユーザーとコミュニケーション」と言い換えられており、対話の意味を含みます。
また今回のnoteでのタイトルは小池都知事が掲げるオンライン選挙に因んで付けています。ここで整理しておくと、オンラインとは、ネットワーク(主にインターネット)に繋がっている状態のこと、もしくは、SNSやオンラインゲーム等のウェブサービスにログインしている状態のことです。一方で、ネット選挙運動でのインターネットとは、コンピューターのネットワークシステムのことを指します。
さて、本日は上記の記事の中で少しだけ触れたネット選挙における4つの投稿モデルについて質問をいただいたので少しお話します。ネット選挙参謀した経験を踏まえつつ分析を進めていくと、従来の候補者の情報発信モデルは、具体的に大きく分けて四つのモデル型があるのではないかと筆者は考えました。

過去形で投稿を行う「報告型」、現在進行形で投稿を行う「実況型」、未来形で投稿を行う「告知型」、時系列を問わない「主張型」です。主に与党の候補者には報告型が多く、野党の候補者には告知型が多く含まれる傾向があります。以下現在行われている東京都知事選の事例と合わせて見ていきます。(都知事選の候補者SNSはこちらでまとめています。)https://note.com/yoshiminakamura/n/n634fa63b483c
※あくまで一個人の見解によるメモ程度としてご覧ください。
1 .報告型
軸としてアクションを終了後に報告として投稿しています。

今回の都知事選において当てはめていくと、小池氏、宇都宮氏、小野氏によく見られます。
東京都現代美術館を視察。
— 小池百合子 (@ecoyuri) June 23, 2020
都立施設では12日から「東京版新型コロナ見守りサービス」を運用中(本日時点122施設)。入館時QRコードを読み取り、クラスターが発生した場合に情報を提供します。
館内では展示方法も工夫し、感染拡大防止に配慮。引き続き安心安全な都立施設の利用を確保してまいります。 pic.twitter.com/EJtMiCrgpk
6月23日(火)午後4時から志村けんさんの地元東村山駅東口で街宣。街宣冒頭に、志村けんさんを始めとして新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方々に対し心よりご冥福をお祈りいたしますとともに現在も療養中の方々に対し心よりお見舞いを申し上げますと述べてから、演説を行いました。 pic.twitter.com/7ghP8RgU9y
— 宇都宮けんじ (@utsunomiyakenji) June 23, 2020
2.実況型
軸としてタイムリーな情報を届けたい場合に使用されます。

#宇都宮けんじ 狛江駅北口街宣 街頭演説 #東京都知事選挙 https://t.co/0lm5MM5mhA
— 宇都宮けんじ (@utsunomiyakenji) June 24, 2020
今回の都知事選において当てはめていくと、宇都宮氏・山本氏は比較的に街頭演説をツイッター生配信が当てはまります。
【動画生中継スタート!】
— 東京都知事は 山本太郎 れいわ新選組公認 (@yamamototaro0) June 24, 2020
東京都知事候補 山本太郎 街宣
6/23 15時
YouTubehttps://t.co/gLaXrgmE7G
リアルタイム字幕入れ UDトークVer.https://t.co/a1LlHWiDI1
ツイキャス https://t.co/rMLC64pPKB#たりないのは愛とカネだ #15兆円であなたを底上げ#期日前投票 #都知事選 #山本太郎
3.告知型
主に街頭演説のスケジュール・イベント等のお知らせを投稿しています。

今回の都知事選において当てはめていくと、小野氏、山本氏が事前告知内容が多いですね。
【6月24日(水) 遊説スケジュール】
— 小野たいすけ 東京都知事候補【公式】 (@taisukeono) June 23, 2020
8:00〜 王子駅北口
9:20~ 街宣車で北区内の遊説
12:00~ 赤羽ララガーデン交差点前
14:30~ 十条駅街頭演説
16:00~ 王子駅北口
17:00~ 田端駅
18:30~ 赤羽駅西口
19:30~ 赤羽駅東口 pic.twitter.com/5hNIr6MbUP
【動画生中継スタート!】
— 東京都知事は 山本太郎 れいわ新選組公認 (@yamamototaro0) June 25, 2020
東京都知事候補 山本太郎 街宣
6/25 17時〜
YouTubehttps://t.co/d9syan14Ih
リアルタイム字幕入れ UDトークVer.https://t.co/nv2eCvqJ2O
ツイキャス https://t.co/rMLC64HqC9#たりないのは愛とカネだ #15兆円であなたを底上げ#期日前投票 #都知事選
4.主張型
主に、時系列関係なしに候補者の思いや政策を語る投稿を行っています。

今回の都知事選において当てはめていくと、質問に回答する小池氏や小野氏のアカウントで多く見受けられます。
#小池ゆりこに物申す の中でも多く寄せられていた「豊洲移転」に関する質問にお答えしました。安全、安心を追求、確認し、必要な策を講じた上での移転です。
— 小池百合子 (@ecoyuri) June 22, 2020
昨日から改正卸売市場法が施行。市場はまた新たな局面に入ります。都民の食を預かる中央卸売市場の発展を支えます。https://t.co/5SJ3IomI3s pic.twitter.com/MBl5OaAbj8
私は一人でも多くのみなさんと向き合い、みなさんの声を政策に反映し、東京都政を担っていきたいと考えています。
— 小野たいすけ 東京都知事候補【公式】 (@taisukeono) June 22, 2020
今日から #こたえて小野たいすけ というハッシュタグにて、ご意見ご質問を募集することにしました。みなさんの声を聞かせてください。#小野たいすけ #東京都知事選挙 pic.twitter.com/waWwWkaMpa
そして、都知事選のオンライン選挙について少しメモさせてください。今回の都知事選はどの陣営もSNSを駆使している臨場感がとても伝わってきます。(天候の関係もあるでしょう)
各候補者の動き・特徴としては、小池氏は、オンライン選挙を中心にインスタライブを通じて有権者と対話を行い、ファンに自身の人柄と政策をアピール、またTwitterから”#小池ゆりこに物申す”として意見を召集しYoutubeにて回答しています(基本、報告型と主張型)そしてLINEを独自にカスタマイズしてメッセージを発信しています。
宇都宮氏は、地上戦中心ではありますが、エンゲージメントが高いご自身のTwitterを活かして生配信中心の街頭演説を行っています。文字より動画です。(実況型の投稿が多い様子)HPではPDFでのチラシを配布されていたりなど電子化に各種対応しています。
小野氏は、地上戦を中心に、報告、告知、主張型の投稿をミックスし、対談形式、意見募集など幅広いコンテンツを仕掛けています。(noteを活用しつつ人柄をアピールされている候補者は初めて見た気がします。)
山本氏の街頭演説は、基本的には実況型中心の投稿であり、ツイキャス、ニコ生、Youtube、Twitter、全て同時生配信のスタンスです。そしてアップロード編集、リアルタイム字幕を導入し、速球性が非常に高いです。#たりないのは愛とカネだ #15兆円であなたを底上げなどのハッシュタグのキャッチコピーもとても耳に残りますね 。(情報量が圧倒的に多い)
また、筆者は今回の都知事選において、日々候補者のアカウントにおける数値データを採取しています。各アカウントのフォロワーの差に留意はありますが、6/18-6/24までの一日あたりのツイート平均投稿数の多い順で見ると七海氏、山本氏、小野氏の順になっています。また公示日を迎えてから25日までの1ツイート当たりの平均RT数を比較すると、山本氏、宇都宮氏、小池氏、小野氏と言う並びになります。1ツイート当たりの平均いいね数を比較すると小池氏、山本氏、宇都宮氏となっていました。
そしてオンライン選挙で重要な視点として、発信者側に対して、受信者側を見ていきます。各候補者がどのくらい検索されているのか、ここでGoogletrendにおいて、ぽんっ!

ネットの検索数では、小池氏と山本氏が争いを繰り広げていますね。
そして、噂の後藤輝樹氏、本当に人気だと言うことが伝わってきますね、、!小池氏と山本氏と同等なほど検索されています。

どの候補者もやはり公示日が一番検索されています。有権者はネット検索で投票するための正しい情報を求めるだけではなく、⾃分の投票⾏動が間違っていないことを確認したいということもあるでしょう。

そして過去30日間。前回の都知事選の検索数結果においては、候補者の得票数と近い相関があるのではないかとも言われています。いずれにしても投票率が著しく低い日本において、ネット上に適切な情報があれば投票しようという気になるかもしれませんが、もし適切な情報がなければ投票をやめようと考えてしまうかもしれません。ネット選挙においても地上戦と同じ姿勢で、候補者の顔と名前を知ってもらい、対話し、有権者の感情を動かすことが重要なのです。

また東京大大学院情報学環が、2019年の参院選の投票行動と情報行動に関する調査の中に、選挙運動期間中の選挙に関する情報へのSNS接触頻度結果が出ています。

全体の接触率は、ツイッターが最も高く、僅差でLINEとユーチューブが続きました。年代別のトップは、10代と20代がツイッターで、30代はユーチューブ、40代と50代がLINE、60代はユーチューブとなっています。
2017年の衆院選の際に行われた同様の調査と比較すると、SNS接触率が高まっているという傾向が示されています。ここでは深く触れませんが、SNS接触が高まりつつある中で、その個々のサービスには長所と短所があります。さまざまな状況に応じて複数のSNSを戦略的に組み合わせて発信することで、有権者との対話が自然と生まれるような投稿の質に近づけることはとても大切です。例えば、ストーリーの閲覧履歴やいいね!などは表示の順番があり、時間順やランダムに並んでいるわけではなく意味のある順番になっています。足跡の中から自分への関心が高いユーザーが上に表示される仕組みになっており、コメント・いいね・閲覧数などが関係していると見えます。こうしたSNS独自のアルゴリズムを用いて表示されていることを前提に、自分に興味を持ってくれているユーザーは誰で、どんな人たちなのかを分析することがまずは大切です。
実際の選挙期間に入ると、投稿の量よりも質を重要視した発信する姿勢が求められます。(地方選の場合は、質より量を重視して検索結果を埋め尽くす手法も一部ある)現実的には、選挙区において得票数が高い年齢層を見極め、それぞれに落とし込んだ政策から有権者を「説得する」ためのメッセージ化を行うということが必要です。もし、日頃からS NSを積極的に活用して発信しているにもかかわらず、支持者が伸び悩んでいるとすれば、 ‘empathy’の能力の欠如の可能性が考えられます。‘empathy’とは、” 他者の立場を創造し、感情を分かち合う能力”のことで、自分と他者は違うと認める考え方として心理学の世界でよく使われます。
日常生活のコミュニケーションの中においても、「思いやり、同情、相手を気の毒に思うこと」といった“sympathy”は度々使われる感情に対して、“empathy”は自分と異なる他者の感情や経験などを理解する能力であり、知的作業を指します。選挙期間中の情報発信は、自らの政策を一方的に発信し対論するよりも、有権者の感情に訴え共感を得られるように双方向で対話することが重要になってくるため、日頃から自分と違う理念や信念を持つ人々が何を考えているのか、「他者の思考プロセスを想像する能力=“empathy”」を鍛えることが必要になってきます。
日頃から他人の立場から物事を捉え創造する力を鍛えることで、有権者に寄り添い関係を築くためのメッセージ化やキーワードを戦略的に生み出すことができるでしょう。
今回は、質的な調査の一面を紹介しました。東京都知事選の折り返し地点を間も無く迎えようとしておりますが、候補者のアカウントから採取したデータより候補者がどのようなツールでどのようなオンラインの動きを行っているのか、6月30日あたりで一度、制限付きで数値的な中間報告を公開するか考えています。(需要があるかは分かりませんが、、、苦笑)
もしこの記事が面白いと感じましたら、サポートをいただけますと幸いです。いただいたサポートは研究会の分析調査における活動費に充てさせていただきます。
