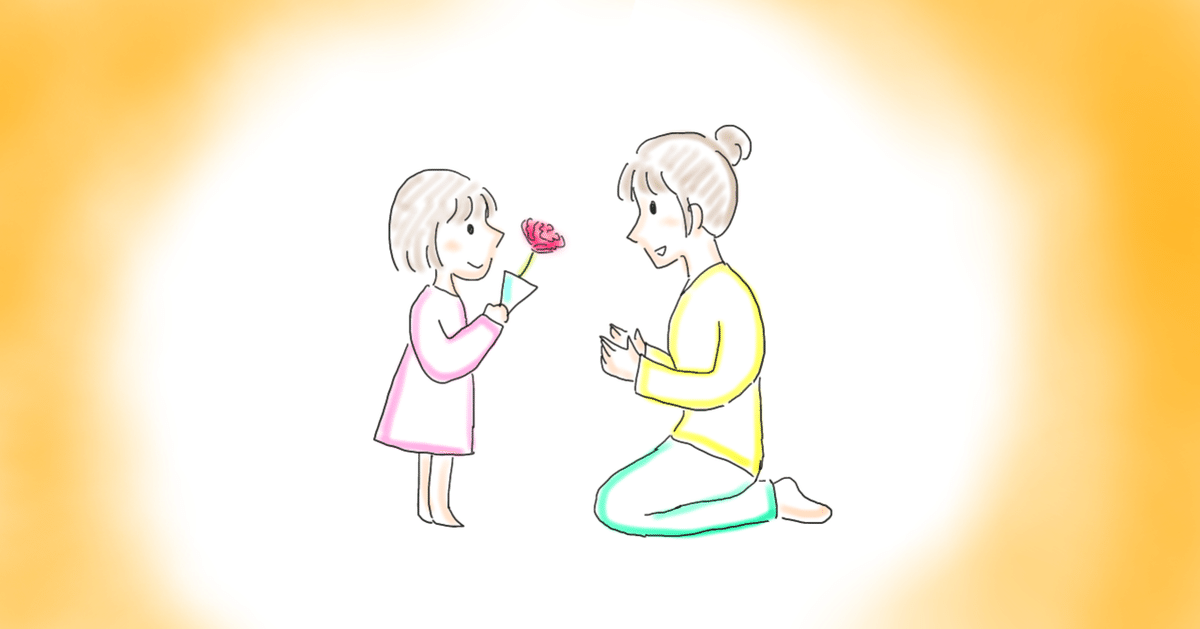
133人の韓国人孤児を育てた日本のお母さん 望月カズ
戦前、異国の地にたった一人放り出された日本人の子どもがいました。不運にも母と死に別れた彼女は、どんなに辛い目にあっても人生を投げ出さず、逆境に耐えて大きくなりました。ただ自分を生きただけではありません。その子は大人になってから、言葉も通じない異国の地で、かわいそうな孤児を引き取って面倒を見たのです。彼女の名は望月カズと言いました。
戦後韓国にわたり、養母として育てた孤児の数は、133人にも上りました。「38度線のマリア」と呼ばれた彼女の遺骨は、生涯の大半を過ごした韓国、そしてふるさとである日本、それぞれの地に眠っています。
カズの献身的な愛と、深い惻隠の情に、多くの韓国人・日本人が胸を打たれました。一体、カズという女性はなぜ、たくさんの孤児を引き取る運命になったのでしょう。それを知るには、彼女の不幸な生い立ちから話さなければなりません。
4歳で満州へ、そして母の死
カズは1927年(昭和2年)、東京杉並区高円寺に生まれました。物心ついた頃から父のいない母子家庭で育ちました。
カズは4歳の頃、母に連れられて満州へと渡ります。満州とは現在の中国東北三省と内蒙古の一部を加えた地域で、面積は日本のおよそ3倍もありました。戦前は職を求めた日本人の満州入植がさかんで、日本人街も多くつくられました。大連や奉天といった都市部は東京より開発が進んでいたほどです。
満州には日本人居留民を保護する目的で、日本陸軍の出先部隊である関東軍が駐屯していました。カズの母親は関東軍の親戚を頼り、そのつてで物品納入の仕事を得ます。お得意先が関東軍ということもあり、商売はすぐ軌道に乗りました。カズが「お嬢さん」と呼ばれるほど、母子の生活は豊かになり、どこから見ても幸せな家庭にしか見えませんでした。
ところが、ある事件をきっかけにカズの人生が一変します。母が急死したのです。原因不明の病死でした。このときカズはまだ6歳、とてもひとりで生きて行ける年齢ではありません。
悲劇はこれで終わりませんでした。望月家の使用人が、途方に暮れるカズを中国人農家に売り飛ばしてしまったのです。そして全財産を持ち逃げしました。
ここからカズにとって受難の日々が続きます。売られた先の農家では、家畜のごとく働くことを命じられました。固く冷たい土の上を小突き回されたかと思えば、むせ返るようなアヘン窟で重労働を命じられる日もありました。幼女を相手にするにはあまりに酷な扱いです。耐えられなくなって逃げだしたことも一度や二度ではありません。悲しいことに逃げてもすぐ捕まるばかりで、再びつらい労働の現場に放り込まれるのでした。
農奴の生活には一切の自由がありません。日本語の使用すら禁じられました。そんな中でもカズは絶望せず、自分をしっかり持つように励ましました。大切な言葉だけは絶対忘れないように、「自分の名前、母の名前、日本、富士山、日の丸、東京高円寺」を何度も繰り返し口の中で唱えてから眠りにつきました。祖国の記憶はほとんどなかったものの、母から高円寺の下町の風景や、日本の美しい自然を語り聞かされていたのかもしれません。いつの日かふるさとに帰れるとの想いが、カズを支えました。
寒冷の大地に細々と生える雑草のように、ただひたすら耐え忍ぶ日々が続きましたが、昭和13年の冬、とうとう脱出に成功します。逃げ落ちた先は、関東軍の駐屯地です。かつて母が商売で出入りした場所でもあります。ひょっとすると、天国の母が、愛しい我が子をここへ導いたのかもしれません。5年にも及ぶ農奴の生活からようやく解放され、人間らしい生活を取り戻すことができました。
カズはそこで洗濯や掃除などの仕事を与えられました。よかったのは、仕事だけでなく、読み書きと簡単な計算を軍人から教えてもらえたことです。学校とは縁のなかったカズにとって、基本的な知識を学べたのは救いでした。
しばらくお世話になった駐屯地を離れ、いくつかの職を転々とします。保険会社の外交員として働いていた頃、大連の理髪店の仕事を紹介してもらい、散髪の技術を身につけました。後に「愛の理髪師」と呼ばれる基礎は、ここで築かれることになります。
17歳のときはうれしい出会いにも恵まれました。朝鮮で永松夫妻という日本人と知り合い、そこの養子として迎えられたのです。カズは日本国籍を取得し、法的にも日本人になれました。それまでは偽の戸籍で満州を転々としていたのです。以後、死ぬ直前に母の姓である望月姓に戻すまで「永松カズ」として生きていくことになります。
日本がはじめた戦争は佳境に入っていました。幸い、戦火は満州に及ばず、カズはただ働くのみでした。比較的穏やかだった日常は8月15日の終戦で終わりを迎えます。日本の敗戦で満州国は消滅しました。
戦場に落ちた赤ん坊を抱えて、母となる
満州で暮らしていた日本人はその地にとどまることを許されず、追われるように日本へと去っていきます。カズもまた日本に戻ることになりました。
悲しいことに、カズが思い描いていた美しい国土は、どこを見わたしてもその影すらありませんでした。東京は廃墟と化し、がれきの山と壊れた家屋がいたるところで散見されました。路上にはお腹を空かせた市民であふれかえり、暗澹たる光景が広がっています。
カズには身寄りも知人もいませんでした。それどころか住む家すらありません。明日の生活もおぼつかないほど厳しい状況です。虚ろになって立ち尽くし、支えになるものはないかと思いを巡らすうちに、脳裏をかすめたのは在りし日の母の姿でした。母に会いに行こう。そう思い立ったカズは、日本を離れ再び満州へ向かうことを決意します。旧満州の地には母の眠る墓地がありました。今はただ母の墓にすがりつきたい。その思いがカズを動かしました。
旧満州では戦後の混乱が収まらず、政情不安が続いていました。カズが韓国に着いた頃は朝鮮半島情勢も緊迫しており、38度線以北へ足を踏み入れことは不可能でした。仕方なくソウルで月日を費やす中、朝鮮戦争がはじまりました。1950年(昭和25年)6月のことです。
韓国の首都ソウルは、38度線直下に位置しました。北朝鮮国境付近から砲弾を飛ばせば、やすやすと市街地に届く距離です。定石通り、戦争が始まるや否や、北朝鮮軍が怒涛のごとくソウルへとなだれ込んできました。銃砲火が激しく散る中、カズは目の前で若い女性が銃殺されるのを目撃します。その胸には赤ん坊が抱きかかえられていました。母親の返り血を浴びて、泣き叫んでいます。
逃げないと自分の命が危ないのに、カズはその場を離れることができませんでした。そして、気がついたら女性の前に立っていたのです。泣き叫ぶ赤ん坊を抱きかかえ、一目散に安全な場所へと駆けだしまました。カズの咄嗟の行動で、小さな命はかろうじて救われたのです。
23歳のカズは、この瞬間「母親」になりました。133人の孤児の面倒を一身に引き受けるという、前代未聞の慈愛に満ちた人生は、ここにはじまったのです。
北朝鮮軍によるソウル占領は時間の問題でした。傷ついた市民たちは戦禍を逃れるべく、南へと逃げ延びていきます。向かった先は、朝鮮半島最南端の町・プサンです。ソウルから直線距離にして350キロも離れた港町でした。南を目指して歩く一行の中に、乳児を抱えたカズの姿がありました。
戦争は容赦なく街を破壊しました。壊されたのは建物や道路だけでなく、そこに生きる市民の人生もメチャメチャにされました。離散した家族、親とはぐれた子ども、子を失った親。悲しい光景がいたるところにありました。カズの目にも、親を失い路頭に迷う子どもたちの姿が飛び込んできました。
孤児の辛さは、自身も孤児だったカズが誰より分かっています。プサンへ向かう途上、深く傷ついた幼い姉弟に出くわしたときは、見捨てることができず看護してやりました。そしてこの子たちをプサンに連れていくことにしました。赤ん坊の男児と、姉弟の3人。カズにとっては大事な、守ってやらねばならない家族です。
プサンに向かう途中では、家族4人にやさしく接してくれる韓国の人たちもいました。おばあさんからおにぎりを与えてもらうと、子どもたちはおいしそうに頬張りました。与える愛もあれば、もらう愛もある。重なり合った小さな愛は、暗くすさんだ状況にあっても希望の光を灯してくれます。
カズたち家族の新しい生活がプサンではじまりました。落ちていた材料や段ボールをかき集め、粗末なバラックを建てて家としました。食事は魚屋の余り物やクズ野菜でしのぐ以外に方法はありません。子どもたちが文句も言わず我慢してくれるのが救いでした。先に子どもたちに食べさせ、余ったものをカズが食べました。
カズと孤児3人ではじまったバラックでの生活、それが、いつの間にか5人、6人、10人と増えていきました。「一緒に住みたい」と言ってくる子どもが後を絶たなかったからです。いずれも戦争で親を失った孤児たちでした。自分が母とならなければ、この子たちには哀しい未来が待っている。そう思うと放っておけません。気がつけば扉を開けて招き入れ、家族になっていました。
家族を食べさせるためには、どんなきつい仕事でも引き受ける覚悟でした。港湾の荷揚げ作業みたいな、男性すら尻込みする重労働であっても、稼ぎがよければ躊躇なく選びました。そのように身を粉にして得たお金でも、あっという間に食事代に消えていきました。
理髪師の手伝いをしていたカズには、髪を整える技術がありました。青空理髪所を開いて商売をはじめると、これが思いのほかあたり、生計を支える柱になっていきます。ひいきにしてくれるお客さんも増え、カズの評判は周辺に聞こえるようになりました。
いくら近所で評判になっても、人の少ない田舎町では稼ぎも限界があります。そこでプサンを引き払い、ソウルへ戻ることになりました。戦争は三年たって休戦状態となり、人の流れは再び首都ソウルへ戻りつつあったのです。
カズはソウルでも青空理髪所をはじめました。お客さんには困らないものの、生活は一向楽になりません。それどこるか苦しくなる一方です。一緒に住む孤児がどんどん増えたからわけですから、無理もありません。子どもが増えれば苦労も増えるに決まっています。しかし孤児たちには家族ができます。カズにとってどちらを選ぶかは愚問でしかありません。
引き取った以上は、この子たちを飢えさせるわけにはいきません。理髪師の収入だけではとても足りないので、軍手編みの内職や、豆炭売り、時には体の血を売ってお金に変えることもありました。そこまでして何とかギリギリ食べさせていける状態でした。
カズの献身的な養育のおかげで、子どもたちはスクスクと成長していきます。もちろん、人間は体が大きくなるだけでは足りません。大事なのは精神です。魂の成長です。精神と魂にツヤが出るくらいやすりかけをしてようやく、まっすぐな人間になります。学校へもきちんと通わせました。
カズの教育は愛とムチが基本でした。曲がったことをやる子には、雷を落とすこともいといません。すべては、「厳しい境遇にも負けない、強くてやさしい人間に育てる」想いからです。そして、家の壁にダルマの墨絵を描き、「人生は苦労の連続。転んでも立ち上がるダルマのような人間になれ」と教えました。
カズの下で育てられた子どもたちは、みんな卑屈にならず、謙虚に、やさしく、強く育ちました。
子どもたちのやさしさ、親思いの情がどれほどのものか。それを示すこんなエピソードがあります。いつものようにカズがお客さんの髪にはさみを入れていたとき、警察の訪問を受けたことがありました。日本人のカズには韓国の国籍がなく、理髪業を営みながら免許は持っていません。折しも韓国内は北朝鮮スパイの暗躍が問題になっていました。素性を怪しまれたカズは、弁明も聞いてもらえず、警察署に連れていかれることになったのです。
子どもたちが職場や学校から帰ると、いつもそこにいるはずのオンマがいません。聞くと警察に連行されたと言います。すぐに警察署へ飛んでいきました。そして「オンマを返せ!」とみんなで騒ぎはじめたのです。カズの子ども32人による警察への一斉抗議でした。
まっすぐで頑固な子どもたちは、警察にしかられてもその場を離れず、座り込みを続けて一夜を明かしました。これには警察もたまりかね、翌日カズを釈放します。署の前は歓喜の渦が起こりました。何より喜んだのはカズだったかもしれません。ここまで自分を想ってくれる子どもたちの存在を、さぞ心強く思ったことでしょう。
この一件をマスコミが報じたことにより、カズの存在は韓国中に知れ渡ることになりました。「愛の理髪師」「38度線のマリア」世間ではカズをそう呼び、純粋で尊い行動を称えました。
いくら有名になっても、世間が騒がしくなっても、身を粉にして働く日々に変わりありません。仕事の量をわずかでも減らすと、家族が路頭に迷います。変わったことといえば、理髪師の免許を取得して商売がしやすくなったことくらいです。孤児の引き取りも、育児も、今までどおり続けました。
傍からみると、どうしてわざわざ苦労の道を選ぶのか、理解に苦しむところがあったかもしれません。しかし、家族の絆をつなぎとめておくことは、子どもたちにとって一番大切なことでした。何より、カズにとって、子どもたちの笑顔と成長こそ、生きる支えであり、希望だったのです。だから、孤児院をつくる誘いも断り、「オンマ」と呼ばれる生活を選びました。
愛は国境を越えて
カズのことを何も知らない人は、その姿を見て、「どこにでもいる普通のお母さん」と思うに違いありません。ただし、苦労の量だけは普通のお母さんと比べ倍以上で、実際の年齢よりだいぶ老けた印象はぬぐい切れませんでした。
ぶれない芯と、飾らない姿は、カズの個性であり、生き方そものもでした。いつもくたびれたカーディガンにモンペ姿という装いで、質素に生きる日本のお母さんといった印象です。服装にぜいたくをかけるわけにはいかない、そんなシンプルな理由以上に、カズには和装がよく似合っていました。生涯の大半を韓国で暮らしたカズですが、常に大事にしていたのは日本人としての誇りでした。
永松家では、端午の節句に三色のこいのぼりが空にはためき、天皇誕生日に日の丸が風になびく、日本的な習慣が守られました。カズはどんなに差別を受けても、自分が日本人であることを隠さず、堂々と振る舞いました。「卑屈になるな。常に前を向いて歩け」子どもたちに教えたことを、自ら率先し体現したのです。
とはいっても、自分のせいで子どもたちが差別を受けるのは本意ではありません。そのため、巣立っていく子どもには、この家で育ったことを口外してはならない、そう言い含めることも忘れませんでした。常に子どもたちのことを第一に考えるのがカズの変わらぬ信条だったのです。
それでは、韓国でのカズの生活は差別ばかりだったのでしょうか? いいえそんなことはありません。多くの韓国人はカズの行動を称賛しました。金銭面での援助も惜しみませんでした。日本人だからという理由でカズの行動が否定されることはなく、理解と協力の空気が大半を占めました。
韓国の人々は、お金や言葉だけでなく、「名誉」もカズに授けました。1964年(昭和39年)、カズにソウル市民栄誉賞が贈られました。さらに、1967年、第一回光復賞をカズに贈ることが決定されました。これは韓国の独立記念日である光復節に贈られるもので、韓国人の中では分けても特別な賞です。そんな栄えある賞が、第一回という記念すべきタイミングで、日本人のカズに贈られたのです。異例ずくめの受賞からわかるのは、愛の行動に民族も国境もない、という美しい真実です。
1965年(昭和40年)には日韓基本条約が結ばれ、日本と韓国の国交が回復しました。カズとその家族にとってもこの知らせはうれしかったに違いありません。この前後からカズの名前は日本国内にも聞こえるようになっていました。義援金を送ってくれる日本人や、カズを支援する団体が発足するなど、ここでも支援の輪は各方面に広がったのです。
1971年(昭和46年)、韓国名誉勲章・冬伯賞受賞。1976年(昭和51年)には日本の吉川英治文化賞を受賞します。
カズの半生を描いた映画も韓国で制作されました。日本でも『愛は国境を越えて』の邦題で上映され、多くの人の涙を誘いました。
家族の絆、母と子の絆
カズの苦労は一生続きました。いくら働いても生活が楽になることはありませんでした。理髪師に軍手編みの内職、子どもたちの食事作りと、寸ときも休まない日々を過ごして、ある日突然倒れてしまったのです。そしてそのまま帰らぬ人となりました。慈愛と真心、惻隠にあふれた56年の生涯でした。
子どもたちは涙が枯れるくらい泣きました。
最初に申した通り、カズのお墓は、ソウル市郊外のキリスト教墓地、そして静岡県富士市瑞林寺、それぞれにあります。瑞林寺にある墓碑には「日韓の孤児百三十余人を養育 三十八度線のマリアと呼ばれた望月(永松)カズ。1927年8月3日出生 1983年11月12日没。富士山の見えるところに眠りたいとの遺志をかなえてここに眠る」と刻まれています。
カズの行いを真似しようと思っても、とてもできるものではありませんし、理想とするにもあまりに現実離れしています。今の私たちにできることは、戦後の貧しい時代に、異国で大勢の孤児に愛を捧げた日本人女性がいたという事実、その生き方や行動に思いを馳せることくらいかもしれません。
カズもまた孤児でした。六歳で母を失うという、辛い経験をした身です。天涯孤独となった子どもがどれだけ悲惨か、カズ自身がよく分かっていました。自分自身の孤児体験が、「見捨てられない」という想いを駆り立てたといえないでしょうか。
また、カズにも大切な母の存在がありました。その人は、不幸にも幼いカズを残してあの世へ旅立ってしまったけれど、彼女の中ではいつまでも偉大な母として生き続けていました。
売り飛ばされた農家で日本語の使用を禁止されたカズが、母の名前だけは絶対忘れないよう暗唱をつづけた日々がありました。戦後、廃墟と化した日本に希望を失い、温もりをもとめて向かった先が、母の眠る墓地でした。苦しくなったとき、母にすがりたい思いでその影を追いかけていました。
カズは自分がもう長くはないと悟ったとき、母の姓である望月への改姓を強く希望しました。戦前の満州で亡くなった方の戸籍ということもあり、この作業は非常に難航を極めたものの、日本の支援団体の援助もあって何とか叶えることができました。カズは最後の最後で「望月カズ」を名乗れるようになったのです。これでまたひとつ、母との結びつきが強くなり、生きる力が与えられました。
母親としてのカズの愛情は、海のように深く、大地のように豊かでした。その愛は子どもたちとの間で共鳴し、大きく反響してわが身で受け止めました。
生前、嫌がらせをする大人が家に現れたとき、「オンマをいじめるな。俺たちが相手をするぞ」とかばってくれたのは子どもたちです。拳も体も小さいのに、その姿は、大人に負けないくらい堂々としていました。
そんな子どもたちの愛に接したときは、オンマの目から自然と涙がこぼれるのでした。
#歴史 #物語 #近現代史 #戦後 #日本 #韓国 #望月カズ #ソウル #ライター #webライター #歴史ライター #note #家族 #家族の物語 #ノンフィクション #実話
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
