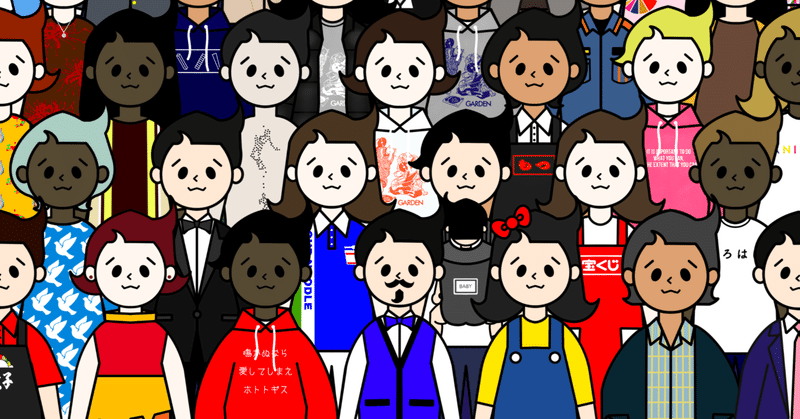
外国人技能実習制度改正に向けた最終報告書を読む【8】
外国人技能実習生・特定技能制度の抜本的な改正を前に、改正内容を考える上で重要となる最終報告書を読む連載を実施している。今回は第8回目となる。これまでの連載は以下の通りだ。
前回は提言3の5について読み、その内容にふれた。今回は、特定技能制度に関する提言を行っている提言3の6について読んでいく。
提言3 「6 特定技能制度の適正化方策」
提言3の6は、特定技能制度の適正化方策に関する提言である。本最終報告書では、外国人技能実習制度・特定技能制度の両方に対する提言であるもののその多くが外国人技能実習制度を中心に扱っている。
それだけ現行の外国人技能実習制度が深刻な問題を抱えていたと言える。だからといって特定技能制度を軽んじているわけでなく、また特定技能制度に問題が少なかったわけではない。
本提言を通して、現行の特定技能制度が抱えていた問題、それをどのように適正化し、解消へと導こうと考えたのかを追っていきたい。もっとも、書かれていることの多くは外国人技能実習制度が関わっている内容ではあるのだが。
提言①について
① 新たな制度において育成がなされた外国人の特定技能1号への移行に ついては、従前の技能検定試験3級等以上又は特定技能1号評価試験の合格に加え、日本語能力A2相当以上の試験(日本語能力試験N4等)の 合格を要件とする(注)。 ただし、日本語能力試験の要件については、当分の間は、当該試験合格 に代えて、認定日本語教育機関等における相当の日本語講習を受講した場合も、その要件を満たすものとする。
新たに創出される育成就労制度において、技能実習生から特定技能へと移行する際の要件を厳格に定義する必要性について提言されている。現行制度においては、移行にあたって複数の経路があり、経路によって試験の合格を要するもの要しないものといった差異が生じていた。
だが、特定技能に移行する外国人は、長期的に国内の人手不足分野において活躍が期待されている人材である。その点に鑑みると、業務上必要な能力のみならず、共生社会実現の観点においても何らかの手段で日本語能力の確保が図られるべきなのは、異論を俟たない話と思われる。
よって、一定の日本語能力の保持を確認するための方向性として、本提言がなされている。本提言については、国外から就労に訪れている多くの人々にとっても益となる話であり、私としても悪くない方向性に感じる。
提言②について
② 新たな制度を経ない特定技能1号の在留資格取得については、従前のとおり、特定技能1号評価試験等及び日本語能力A2相当以上の試験(日 本語能力試験N4等)の合格を要件とする。新たな制度において育成途中の外国人がこれらの試験に合格した場合の特定技能1号への在留資格変更の在り方については、上記4の提言③の本人の意向による転籍の要件 等も踏まえて検討するものとする。
育成就労制度を経ない外国人が在留資格における特定技能を得る場合に関する提言である。この点については現行通りで良いのではないかとされている。続いて、育成就労制度を経るものの3年の期間の間に特定技能制度へと移行する外国人に関する提言である。
こちらについては、とりわけ特定技能移行後に転籍可能になる点を踏まえて、転籍に関する制限を設けるべきでないかとの声があった点に触れられている。いわゆる外国人技能実習生を安く使える労働力、日本人を採用できないことによる代替労働者程度にしか思っていない勢力によるものでなかろうか。
最終的にどのような建て付けの制度になるかは分からないが、制限に対する否定の声があった点は付記されており、私としてはその声を取り入れるべきだと考える。そもそも職業選択の自由の前提がある中で、労働者から捨てられる程度の企業に優れた労働力を留めておくのは、社会的損失が大きいためである。
提言③について
③ 新たな制度で育成を受けたものの、特定技能1号への移行に必要な試
験等に不合格となった者については、同一の受入れ機関での就労を継続
する場合に限り、再受験に必要な範囲で最長1年の在留継続を認める。
特定技能への移行については、①の通り試験の合格を求める方向性となる。一方で、だからといって試験に一度落ちただけで帰国を求めるのは、余りにも配慮に欠ける。
そもそも人手確保のお題目がある中で、試験に落ちたから帰ってなどとやっていては、いつまで経っても人手不足のままである。そもそも日本語は、多くの国の言語に比べて習得難易度が高い。
そこで、仮に一度試験に落ちたとしても再挑戦できる制度を設けるべきとの提言である。私に限らず、多くの人々にとって納得度の高い提言であると思われる。しかし、再挑戦の余地が1年で足りるのかは議論が分かれそうである。
提言④について
④ 特定技能外国人に対する支援については、支援業務を委託する場合に は、その委託先を登録支援機関に限ることとした上、支援業務が適切にな されるよう、登録支援機関について、支援責任者等の講習受講や支援の委託元となる受入れ機関数等に応じた職員の配置の要件を設け登録要件を 厳格化するとともに、支援実績や支援委託費等の開示を義務付け、情報の 透明性を高める。また、本人の希望も踏まえ、特定技能2号の在留資格取得に向けた1号特定技能外国人のキャリア形成の支援も行わせることと する。
登録支援機関の役割や支援業務委託に関する提言である。まず、支援業務委託先は登録支援機関に限定すべきと提言されており、本提言への否定の言はなかったようである。多くの支援制度に言えるが、支援業務の委託先に制限を設けない場合、不正の温床になりやすい。
昨今社会的に大きく問題視されている生活困窮者支援や女性支援に関する話題を見ても分かる通り、本来の目的が達成されないままに公金等が消費され、しかもその利用使途が明瞭にならないといった、あってはならない問題が生じかねない。
そもそも支援業務委託先に適切な支援能力があるかどうかの問題も生じる。そうした様々な問題、リスクがある以上、支援業務を委託する場合の委託先については、厳しく制限を設けるべきであり、制限を設けるべきだとする提言には合理性がある。
登録支援機関の役割に対する言及や透明化に関する言及も、上記の話を踏まえれば妥当性があり、好感を覚える。本提言について異論が少ないのは、多くのステークホルダーが、問題点を共有できている印象を受ける。
提言⑤について
⑤ 特定技能外国人の受入れ機関については、特に登録支援機関を利用しない場合に適切な支援を行えるよう、上記④も踏まえてその要件を適正化するとともに、より良い受入れのインセンティブとなるよう、優良事例等の公表、優良な受入れ機関に対する各種申請書類の簡素化や届出の頻度軽減などといった優遇措置を講じる。
特定技能制度に関する受入れ機関についても、技能実習制度同様に適正化を図るべきとの提言である。加えて有料機関にはインセンティブ施策を提供する点について書かれている。本内容については、何ら異論が出ないものと思われる。
提言⑥について
⑥ 特定技能2号の在留資格取得については、従前の特定技能2号評価試験等の合格に加え、日本語能力B1相当以上の試験(日本語能力試験N3 等)の合格を要件とする。
(注)上記2の提言③の(注2)のとおり、日本語能力に関しては、現行の技能実習制 度における取扱いを踏まえ、各受入れ対象分野でより高い水準の試験の合格を要件とすることを可能とする(②、⑥において同じ。)。
特定技能2号取得のための要件について、一定水準以上の日本語能力を要件とすべきといった内容である。およそ異論が出ない話と思われる。一方で、GPT、Gemini(ジェミニ/ジェミナイ)、Claude(クロード)等の生成AIにより、言語の壁が薄れつつある昨今、果たして日本語能力にこだわる妥当性はどれ程のものだろうかと考えずにはいられない。
ましてグローバルな視点で考えれば、日本語はマイナー言語である。むしろ日本人の英語能力を上げる方が、世界的には適正とも言える。それは母国語を軽視する意味合いではなく、生活/仕事の観点において、よりスムーズな環境を作る上での必要性という意味合いである。
ともすれば、外国人技能実習制度・特定技能制度そのものが差別的な制度になる瀬戸際に来ていると考えられなくない。そうした時代の潮流、テクノロジーの動向を見て、モダナイズをどうやっていくのかは気になるところである。
以下は広告です。ぜひクリックして読んでください。
AIナビゲーター2024年版―生成AIの進化がもたらす次世代ビジネス
生成AIスキルとしての言語学 誰もが「AIと話す」時代におけるヒトとテクノロジーをつなぐ言葉の入門書
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
