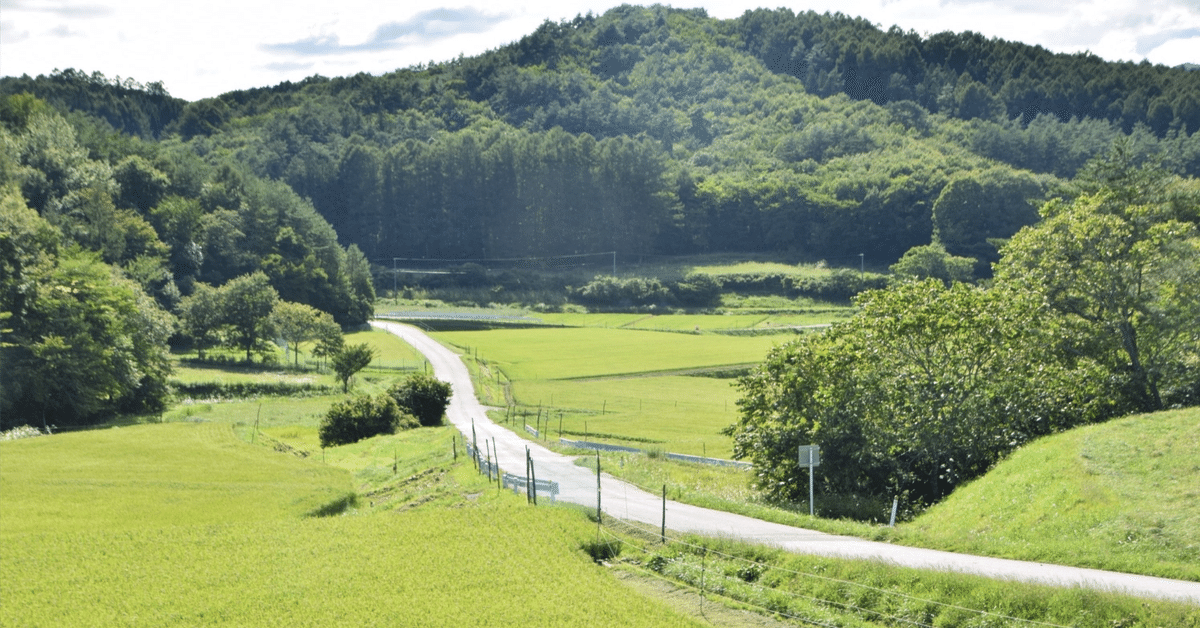
ありたい姿(Being) -ソーシャルに働く。ローカルに生きる。-
ダイバーシティ(=多様性)時代、人生100年時代と呼ばれる昨今。多様かつ主体的なキャリア(=人生)を歩む必要性・可能性が指摘されながらも、地方⇨都市&大企業主義という従来からの生き方・暮らし方の潮流は変わりません。
社会のため・地域のために働きたい・生きたいと思考錯誤してきた3年間の社会人生活を振り返りながら、自身のキャリア(=人生)の歩み方としての指針『ソーシャルに働く。ローカルに生きる。』を考えてみました。
1. 『ソーシャルに働く。ローカルに生きる。』とは
1-1 「ソーシャル」との出会い
初めて、「ソーシャル(=社会課題(+解決))」に触れたのは高校生の時。
親の教育方針であまりTVをみる機会がなかったため、流行りの情報収集は毎朝の新聞(当時は、長野県に住んでいたので信濃毎日新聞というローカル紙)でした。
とはいえ、興味があるのは、スポーツ情報程度。
毎日10面代にあるスポーツ情報を見るために、1・2・3・・とペラペラペラペラ。
スポーツ情報目当てではあるものの、なんだかんだ目に入る政治・経済・社会・国際欄。
全く興味のなかった彼ら(=政治・経済・社会・国際欄)とも毎日顔を合わせていれば興味も湧いてくるものです。最初は5秒、10秒で通過していたものの、気づけば15分、30分と目を止めるようになりました。
こうして政治・経済・社会・国際欄を見ていく訳ですが、日々、見ていくなかでは、もちろん色々な気づき・発見があります。
1つは、「ソーシャル(=社会課題(+解決))」に係る記載が紙面のほとんどを覆っていること。国会における政策議論、国際問題、顕在化してきた社会問題などなど。また、ローカル紙なので地元のお話も(当時は外国による水源地の買収問題やマツノザイセンチュウによる森林の被害対応など)。
もう1つは、「ソーシャル」は「ソーシャル」でも、『+の話』と比べて『-の話』が多いこと。こんな社会課題があったんだけどこんな風に解決されています。なんて話題は少なく、こんな社会課題が存在している問題だ(なんとかしろ)。という話題が多数を占めていました。
こんな、経緯で、「ソーシャル(=社会課題(+解決))」と邂逅したわけですが、
世界・日本には、毎日の話題に尽きないほどの多くの課題が山積している+それが10年20年経っても解決されないばかりか、社会情勢の変化に伴いさまざまな新しい課題が顕在化してきている。さらに、これは世界・日本といった大きなマクロ視点でのものだけでなく、長野県といったミクロ視点で見ても様々な課題が存在しているのだ。
新聞を通じて抱いた「ソーシャル(=社会課題(+解決))」に対する課題意識が、ふと中学生の時の記憶とリンクします。『坂の上の雲(著:司馬遼太郎)』という歴史小説を読んだ時に抱いたある想いです。
この本の舞台は、明治時代初期。主人公は、伊予松山藩出身の3人の若者。1人は俳人、1人は陸軍、1人は海軍とそれぞれの道に進みます。各人が、それぞれの道において使命感を抱き時代に揉まれながらも明治という時代を駆け抜けていくというストーリーです。
260年続いた江戸時代が崩壊。開国し近代化に向けて国を創っていくという混沌とした中において、多くの若者が、自分が国を創っていくのだという想いを持ち、政治・軍事・学問と各世界において志をたて、人生を送っていた明治という時代。現代よりもはるかに情報・技術もない中でバイタリティ溢れる若者が、その後の国の礎を創っていった。時代は違えど、日本には・世界には多数の課題が存在している。「ソーシャル(=社会課題(+解決))」の文脈で自分自身にも何か出来ることがあるのでは。(よし、やろう!)
これまでの夢から大きな路線変更を決意した高校3年の秋でした。
1-2 「ローカル」との出会い
大学では、農山村に関わる事象全てが研究対象という岩手大学農学部共生環境課程に進学。これを機に、岩手県に移住します。
ここで、どっぷりと「ローカル」に浸かります。
▷沿岸部の災害公営住宅におけるコミュニティ形成支援活動
▷住民協働による地域課題解決に向けた取り組み
▷地域の伝統文化(お祭り・地域維持活動)のお手伝い
などなど。様々な形で「ローカル」に触れていく中で、人・自然・文化といった面での魅力(=豊さ)を感じる一方、多くの課題も目にします。既存地縁組織の課題(町内会組織の高齢化など)や産業の担い手不足に伴う課題(耕作放棄地の増加など)です。こうした課題をみるにつけてフツフツとした想いが湧いてきました。
「ローカル」の課題解決には学生の参画が有効ではないか。学生個人で考えると4年間で卒業してしまうため持続性の点で課題があるが、大学生という属性で捉えると常に数千人の大学生が入れ替わりはあれど老いることなく存在し続けている。大学生という主体が持続性を持ち「ローカル」の課題解決にコミット出来るような仕組みを作ろう。
他方、自分自身を含めた大学生のあり方については下記のような課題感を抱いていました。
大学生の本分は『学び』である。これには、机上の理論に加え、実践を通じたリアルへの認知も必要では無いか。(研究における仮説の設定も机上からだけでは本質を捉えられないのでは無いか。)しかし、多くの学生は時間がなく、自宅⇆学校⇆バイトの3点で4年間の学生生活を送っている。
この現状にいかに「ローカル」を織り込んでいけるかを考え、トライしたのが、「ローカル」をフィールドに「ソーシャル」に係る活動を通じた既存のバイトの代替となりうる"稼げる"仕組みづくりでした。
▷大学生×地域(農山漁村)/町づくり研究会
農村における住民参加型町づくり支援活動や被災地におけるコミュニティ形成支援活動などを実施。協
働先のNPOからの収入や活動地域の物産販売を通じた"稼げる"仕組みづくりへのトライ。

▷大学生×産業(農業)/遊休地活用プロジェクト=畑ラボ=
遊休地を活用した農産物の栽培・加工・販売。遊休地の学術活用。栽培した農産物の販売を通じた"稼げる"仕組みづくりへのトライ。

これらのトライは、自分にとって、「ローカル」と「ソーシャル」が自分ごととして捉えられた実践経験(理論(知識)が実践として昇華された経験)でした。
1-3 ソーシャルに働く。ローカルに生きる。
高校時代の「ソーシャル」との出会い。
大学時代の「ローカル」との出会い&「ソーシャル」×「ローカル」の実践経験。
これらの経験を通じ、そして、大学4年生となり将来を考えるにつけて、自分自身の中でのありたい姿(=人生の指針)として浮かび上がってきたのが、『ソーシャルに働く。ローカルに生きる。』でした。
<ソーシャルに働く。>
社会に存在する様々な課題の解決に寄与しうる、より良い社会を創ることを生業としていきたい。
<ローカルに生きる。>
人・自然・文化と地域にある豊かさに触れながら暮らしたい。
こうした、人生の指針を持ち、社会人生活をスタートさせていきました。
2. 『ソーシャルに働く。ローカルに生きる。』への挑戦
2-1 社会人1年目・2年目 @岩手県雫石町
="地域"の1歩先2歩先に触れる・考える=
社会人1,2年目は、岩手県盛岡市・雫石町の3温泉地9施設で構成される観光企画会社「株式会社いわてラボ」にて。エリアとしての価値向上に向けたイベント実施や商品企画開発などを。
地域経済の起爆剤と期待をされた観光産業における国家政策の1丁目1番地であるDMO・DMC領域で、宿泊施設はもちろんのこと行政や1次産業、その他サービス産業の皆さんとともに、地域を観光面から盛り上げる様々な取り組みをさせていただきました。
2-2 社会人3年目 @宮城県仙台市
="東北"の1歩先2歩先に触れる・考える=
社会人3年目は、東北で社会課題をビジネスで解決しようとする"社会起業家"の育成支援プログラムや小中高大学生向けアントレプレナーシップ教育プログラム等を手がける「一般社団法人 IMPACT Foundation Japan(INTILAQ東北イノベーションセンター)」へ。各種のプログラム運営を。
東日本大震災以降、"課題先進地"となった東北。そして、昨今のコロナ禍でも社会課題が顕在化してきています。その中において、地域のため・社会のためと挑戦を始めた社会起業家が様々な業界・地域で活躍しています。地域のため・社会のためと挑戦する社会起業家が持続的に生まれ育つエコシステムの構築に向けたAccelerator programや次世代起業家育成(小中高大)WSなどを。東北の地域の・社会の課題に触れ、こうした課題解決に向けた事業支援や次世代人材育成に係る取り組みに関わる日々です。
4. 『ソーシャルに働く。ローカルに生きる。』のあり方を考える
『ソーシャルに働く。ローカルに生きる。』を指針に様々動いてきた社会人生活も4年目に突入しました。終わりに、これまでの歩みを振り返りと今後の展望について書いていこうと思います。
社会人生活の中での大きな転換点は、社会人2年目⇨社会人3年目での転職でした。転職により大学時代から数えて6年間暮らした岩手県を離れ宮城県仙台市へ移住。今年で移住2年目となります。地方⇨都市の移住経験は、『ソーシャルに働く。ローカルに生きる。』という自身の人生の指針を改めて考えるきっかけとなりました。
それは、『ソーシャルに働く。ローカルに生きる。』の根幹にある、「豊かさ」を測る尺度です。
ただ社会的意義のために働きたいわけでも、ただ地方で暮らしているという状態でありたいというわけでもなく、そこに手触り感があるかという点が大切なのだと。
「隣のおばあちゃんがこんな問題を抱えている」が見えるからこそ、ソーシャルに働く意味を見いだせること。そして、それは、ローカルに生きているからこそ見えてくるものなのだと。
仙台は、岩手と比べ、人口規模も・産業規模も・地域の歴史や文化も全く異なります。
100人いれば100通りの暮らしがあり、この1人1人の暮らしの中に社会課題が潜んでいるわけです。
現職である社会起業家支援の中間支援組織では、社会課題の解決に向けた取り組みに触れる機会は多いわけですが、これは、2次ソースです。自分自身がしっかりと1次ソースに触れていく。
「現場に出てリアルに触れる」+「各種の原典データに触れる」
この原点に立ち帰り、思考を続けていこうと思います。
ー『ソーシャルに働く。ローカルに生きる。への挑戦(模索)はこれからも続くー
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
