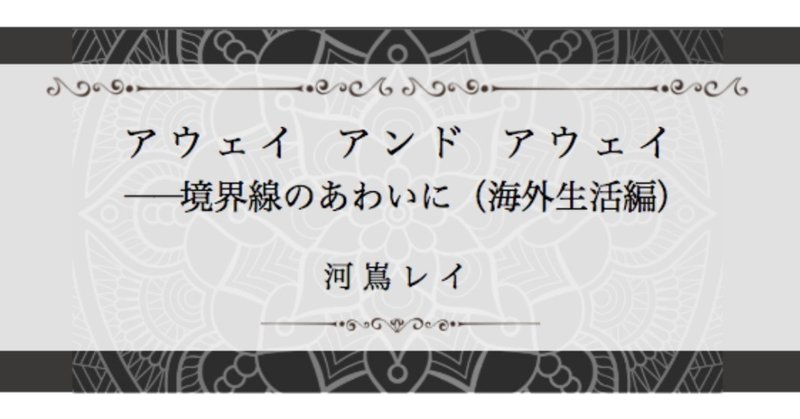
アウェイ アンド アウェイ―境界線のあわいに(海外生活編)
南回りは遠いが安い。そう聞いていたので、フライトはクアラルンプールとドバイ経由でも構わなかった。フルーツの香りがするクアラルンプールの空港で、パイナップルジュースを飲んだ。言葉もわからなかったが、喉が乾いていたのでジュースは飲みたかった。ドバイの空港では、銃を持つ兵士があちこちにいた。息が浅くなった。空港では家電も売っているらしかった。でもそこで家電を買う理由はなかった。ロンドンでは下宿をするのだ。きっと映画で観たようなキッチンのあるお宅だろう。そこでならきっとわたしは息ができるだろう。まずは逃げ出すことから始めなければ。逃げる。逃げて新境地へと辿り着く。それだけを夢みながら、最後の給油を終えた飛行機へと戻った。
わたしが過去を振り返る時、いつも心に浮かぶのは「ホームとアウェイ」というフレーズだ。そのフレーズが一般的になったのは、Jリーグの試合がテレビで放映されるようになってからだと思う。「次回の試合はアウェイゲームですから、厳しいものになるでしょうね」。サッカー解説者は、放送の最後には決まって次回の試合がホーム(本拠地)かアウェイ(敵地)かを強調する。わたしとしては、そんなことってあるのかなと思うだけだ。逆に言えば、ホームゲームなら追い風が吹くものなのかと。試合の厳しさなら同じじゃないか。スタジアムで試合をする。それには変わりないはずだから。戦いにホームもアウェイもあるものか。そこには真剣勝負でしか得られない勝ち負けの世界しかない。
わたしが生まれて初めて飛行機に乗り、イギリスでの生活を送るに至ったのには理由があった。過去に家を出て一人暮らしも二回ほど経験したけれど、家を出ただけでは収まらなかったわたしは、その後大人になるまで過ごした故郷にはもういられないと決意し、地方の若者の夢「東京」を飛び越え、海を渡った。当時のわたしにとって、「ホーム」には奇妙なアウェイ感が漂っていて、今思えば、そこから遠ざかるためには本当のアウェイまで行き着かなければならなかったのだろう。そして本当のアウェイとは、故郷や国の外側にあるのだろうと、ある種の期待をしていたのだと思う。わたしにとっての「奇妙なアウェイ」とは、自分の身の回りの環境のことだった。
ある種の「居心地の悪さ」を抱えたまま、わたしは大人になった。幼い頃からひとりっ子で鍵っ子。幾人かの他人に預けられて育った。家には誰もおらず、小学校へ上がっても、学校から帰ったらすぐさま他人様のお宅へとひとりで歩いて行く毎日だった。夏休みには少し離れた親戚の家に預けられた。バスで四十分くらいかかる。そして肝心のそのバスは一時間に一本しかなかった。
引っ越しもたくさんした。引っ越すたびにお世話になるおばさんの顔が変わった。顔はよく覚えていない。たぶん相手は誰でもよかったのだろう。結局遊ぶときは自分ひとりなのだ。ひとりというのは気楽だったが、よその家にいると息が浅くなった。それも徐々に慣れていったのだけれど。自宅の思い出は、置き時計のチクタクという音だけだった。他人の家で過ごす時間の方が多く、だんだんと自宅とよその家の境目が薄れていった。そしてそれは、わたしの中の「家(ホーム)」という境界線をも曖昧にしていった。
中学生になると、周りがよく見渡せるようになった。女子はよくグループを作り対立していた。もしくはお互い仲良しを演じながらも他グループを批判した。一緒にトイレに行かない子は仲間意識が薄い証拠だと認定するのが女子のやり方だった。男子は上手にグループを作り替えながら、自分よりも弱い者を探し、叩いた。同級生と自分の話題がなんとなく違うと感じるようになったのは、この頃からだった。外の世界にはたくさんの境界線が存在していた。やがてわたしが夢中になっている洋楽のバンドや傾倒している漫画の話をスルーされることにも慣れ、なんとなく適当に話題を合わせることを覚えた。
高校に進学すると、「共通の話題問題」はますます顕著になった。「わたし」と「同級生」の間には、くっきりと見える境界線のようなものが多数引かれていて、わたしの日常はつまらないものとなった。図書館と漫画と音楽だけがわたしの好奇心を満たしてくれた。わたしはその後もいくつかの境界線を何度も何度も経験した。そしてそこから逃げ出したかった。その境界線は、話題の違いだけに収まらず、「若さ」だったり「女性であること」だったりした。そして時には「同世代」であることも境界線になった。中でも「同じタイミングで同じことをすること」。それはわたしがもっとも苦手としたことのひとつだった。
高校卒業後、働き始めた。大学は勉強したいことが決まったら行こうと思っていたし、まずは働いてみたかったからだ。けれど家庭環境に変化が起こった。散々ひとりで生きていたのに、ある時から家には家族がいるようになった。それが性に合わず、家から出たいと思うようになった。しかも就職先では若く、女性であるだけで、今で言うセクハラにあった。
当時はセクハラという言葉もなく、「男性の先輩方への慰安サービス」という位置づけだった。初日のこと。違う部署の先輩男性社員に背後から胸を掴まれ、「今年の新人は胸が小さいな」と挨拶された。きっと毎年同じことをしていたのだろう。入社後体を触られるのは「洗礼」で、それは「スキンシップを兼ねる、職場を円滑に保つための冗談のひとつ」だった。先輩はとても面倒見の良い人だったが、わたしはセクハラまがいの冗談が死ぬほど嫌いだったし、職場のひととスキンシップを図る文化はそもそも持ち合わせていなかった。
古く馬鹿らしい慣習に縛られるのも死ぬほど嫌だった。お酒を強要されるのも、年齢で当たり前の行動を制限されるのも、自分の意見を押さえつけられるのも嫌だった。職場は数回変えた。アパート暮らしもしてみた。けれどやっぱりなにも変わらなかった。だからそこから逃げたかった。より深く息ができる場所へと。そしてガムシャラに働きお金を貯め、わたしは生まれて初めて空を飛んだ。
ロンドンの街には、たくさんの人がいた。驚いたのは中東系がたくさんいたことだ。わたしの頭の中ではロンドン=金髪碧眼の人々の街だったのに、お店に入れば肌の色と髭の濃い店員さんがいた。クイーンズイングリッシュの勉強をしに来たのに、彼らの英語は訛っていた(ように思う)。けれど後々考えたら、クイーンズイングリッシュを話しているイギリス人はあまりいなかったように思う。
通っていた英語学校には主にヨーロッパ系の学生がたくさんいたが、かなりの数のアジア系もいた。英語の勉強をしに来たのにも関わらず日本人同士でつるむ学生も多かったが、それは日本人同士だけではなく、イタリア人もフランス人もそうだった。みなが何かから自分達を守ろうとしていて、学校から一度出れば、わたし達は他人だった。
肝心の大家のおばさんは、わたしにはまるで興味がなく、唯一一緒にテレビドラマを観る時だけ会話が成立した。「テレビ観る?」彼女には一緒にテレビを観てくれる人が必要だったのかもしれない。彼女は料理が大の苦手で、わたしが払う下宿料から食費を上手く浮かせて生活費を稼いでいた。お腹が空くからもう少し食事の量を増やしてもらえないかと頼むと、わたしは小食だから気づかなかったわと言い、翌日も今までと同じ食事量を提供した。おばさんの料理は大抵不味かった。
言葉がうまく伝わらないのは酷く悔しいことで、わたしは十分大人なのに子供のように接してくる人や馬鹿にしてくる人もいて、最初の一ヶ月でストレスからかお腹を酷く壊してしまった。言葉をうまく操れないため、パブのカウンターでは常に注文を後回しにされ、見た目のせいか、公共の場所では不当な目にあった。常に「良い日本人」であろうとしたけれど、大抵はあまり好い目を見ず、わたしはわたしを守るために、他人に舐められないために、荒っぽい所作や言葉遣いを身につけなければいけなかった。
とうとうそのときはやってきた。たまたま日本人の友人二人と大通り沿いを歩いていた時のことだ。通り過ぎる車の中から罵られた。まだ高校生くらいの男の子達だった。その直後は声さえ出なかった。あまりにも突然だったからだ。その後、ロンドンの喧騒に嫌気がさして、わたしは地方都市へと移った。
某有名大学のある小さな学園都市にはたくさんの語学学校もあり、インターナショナルな空気が漂ってはいたが、酷いヘイトも経験した。学校の前には広い芝生の公園があり、同級生たちとよくピクニックをした。ある日老紳士が現れ、持っていたステッキを振りかざし、「ここから去れ!」と叫び出した。わたし以外はヨーロッパ系の学生で、彼は一点わたしだけを見つめていた。わたしはよそ者で、しかもアジア人で、ことばも通じないような輩なのだ。郵便局のおじいさんからは切手もすぐには売ってもらえなかった。まともに切手の注文もできないのかと冷たくあしらわれ、「次の方!」と言われるのが悔しかった。わたしは彼らの境界線から一歩も中には入れなかった。
境界線といえばこんなこともあった。ある日旅行から帰って来ると、下宿先の女性がリビングでテレビニュースを観ていた。ただいまとひとこと伝えても、ニュース映像を食い入るように観ている。何かあった?と訊くと、「ベルリンの壁崩壊のニュース。旅行中だったから知らなかった?」とそのニュースに夢中になっている。わたしは頭の中が真っ白になった。ドイツ・ベルリンを西と東で分断していたあの壁が崩れるということは戦争でも始まるのだろうか。わたしはヨーロッパにいて、ドイツはすぐそこだった。たった一秒の間でそんな思いが脳内を巡っていた。
当時はインターネットもなく、下宿先でそうそうテレビを観ることもできず、わたしは情報難民になっていた。ヨーロッパにいたにもかかわらず、ヨーロッパ情勢に疎くなっていたのだ。貧乏学生は毎日新聞を買って読むこともできず、ベルリンの壁の件も予見できなかったのだろう。もちろん語学レベルの低さも影響し、英語で時事問題を理解しようとする努力もしていなかったのかもしれない。
ニュース映像では、東ドイツの大勢の民衆が壁の上に立ち並んでいて、その様子は実に平和だった。「壁を越える=射殺」のイメージしかなかったわたしは、とても驚いた。戦争は始まりそうになかった。第二次世界大戦後のドイツ・ベルリンを分断していた壁はあっけなく崩壊した。人が作った境界線は人の手により壊される。少し明るい気持ちになったことを覚えている。
イギリスはまぎれもないアウェイだった。勘違いしようのないアウェイだった。人々の見た目も言葉も全く違う地にいて居心地の悪さは感じたが、それはわたしに、ある種清々しいほどの理由をくれた。アウェイなのだから、居心地は悪くて当然なのだと。
一年三ヶ月という滞在期間の終わりが近づくと、わたしは不安を感じ始めた。海の向こうでは少しは自分という存在を受け入れてもらえるかもしれない、という幻想は儚く終わり、かつ日本に帰国してもそのまますんなりと受け入れられるという期待も薄かった。わたしは女性であるだけで「セクハラ」を我慢しなければならない文化も嫌いだったし、この年齢だからこれをしなければならないという文化も嫌いだった。「若さ」をないがしろにすると同時に「若さ」を消費する文化も嫌いだった。嫌いなものは嫌いと言った。ホームには誰もおらず、ホームと称するアウェイがあっただけだった。
実際ホームに帰るとそこには、新たな沼が待っていた。「留学したんだ!すごいね!」と「日本じゃそううまくはいかないよ?」の板挟みだ。地方都市のホームに帰っても経験を生かせるような仕事はそう上手くは見つからない。わたしはいつの間にか大層扱いにくい人材になってしまっていた。扱いやすい人材とは?ホームには境界線がいくつもあった。これじゃあアウェイと同じじゃないか。
結局また働いてお金を貯め、やっとのことで大学へ進んだ。年齢的には院生でもおかしくない年頃だった。学びたいことは専門的なことだったので、またもや海を越えた。ハワイ州オアフ島ホノルルだ。太平洋に浮かぶ楽園として有名だけれど、マリンスポーツに一切興味のないわたしには、Tシャツ短パンで済む、普通の常夏の島だった。学費が足りないので三年で卒業しなければならかったけれど、サーフィンの誘惑にも勝つ自信があったので、そこは心配していなかった。
大学生活の始まりは驚きに満ちていた。同じクラスには十八歳の若者も三十過ぎの社会人経験者も、六十五歳の定年世代もいた。ほとんどが真面目な学生だったけれど、中には行方不明になる学生もいた。留学生の数も多く、中には大層裕福な家庭出身なのだろうと思われる学生もいた。とりあえず学びたいと思った時が学び時なのだ。そして幸いにも、アメリカには遅いスタートを切った社会人学生をバカにするような文化はなかった。
けれど、しばらく住んでいるとうっすらと見えてくるものがあった。ハワイ州にはアジア系も多く、全人口の四割弱。先住ハワイアンは約一割ほど。白人は二割くらいだ。印象では人種のミックスも多い。ハワイは人生初めての「メルティングポット」ということで楽しみだったが、ハワイの住民は、人々を「ロコ(ローカル住民)」、「旅行客(留学生含む)」、そして「ハオレ(Haole=外国人・白人)」で分けていることに気づいた。
特にワイキキのショッピングモールで買い物をする時はそうだったけれど、「あー日本人観光客ね、はいはい」とばかりにあしらわれた。「どうせ観光客だから」という扱いは、有名観光地特有の諦めにも似た態度だ。それはロンドンでもそうで、きっと京都でも同じなのだろう。当時のハワイ、特にワイキキの観光客は主に白人観光客と日本人観光客が多く、旬を過ぎた苦学生のわたしも傍目から見れば立派な日本人観光客だった。ハワイという観光資源を消費するためだけに来たカモネギだ。それにしても、アジア系の店員さんに冷たくあしらわれるのは悲しかった。それともわたしの期待が高過ぎたのだろうか。それよりも白人店員さんの方が優しかった。彼ら、彼女らもロコから「ハオレ」と呼ばれ、日本でいう「ガイジン」扱いされるからだろうか。同じアメリカ国民でありながら、白人というだけで「ハオレ」と呼ばれる。例えハワイ生まれだとしてもそれは同じで、それでは誰ならハワイ人なのかといえば、それは先住ハワイアンなのである。歴史的背景が複雑に入り組んだ社会には、そう簡単には理解できない事情があるのだった。
年齢を重ねる度に、住む場所を変える度に、わたしはたくさんの境界線を感じてきた。これまでの話は、実は二十五年以上も前の話だ。現在わたしは、ホームとなりつつあるシンガポールに住んでいる。多民族国家で、仏教寺のすぐ近所にモスクやヒンドゥー寺院があるような国だ。しかも全人口の四割弱が外国籍で、公用語は英語を含め四つもある。英語が日常生活における共通言語となっているので、生活上に不便は感じない。
多民族多言語のこの国で、わたしは未だに屋台飯を頼むときに、ローカル訛りの英語「シングリッシュ」を使うおやじさんの言うことが聞き取れず、何度も聞き返したりする。それでも大抵のおやじさんは動じない。メニューの番号や写真を指で指したりして懸命にわたしの注文を引き出してくれるのだ。食欲がすべてなのだ。あとはなんとかなるのだ。向こうは売り上げが欲しく、わたしはランチを食べたいのだ。両者の利益が一致する。なんとシンプルな解だろうか。番号と写真、そしてサムズアップと笑顔。まだシングリッシュをマスターできないでいるわたしとおやじさんが歩み寄るツール。円滑なコミュニケーションとは、こういうツールを媒介として成り立つのだろうなと思う。
つくづくわたしにはツールが必要だと思う。アウェイをホームにする魔法のツールが。そしてそのツールを使いこなす柔軟な思考が。境界線とその周辺を見つめ直すことで、お互いの幸せのために、こちらとあちらを繋げたり、程よい距離を見つけられたら、わたしはうれしい。
それでも境界線は決して消えない。その鮮やかさにため息が出ることもまだ多い。ただ、柔軟な思考で境界線をうまく乗り越えたり、引き替えたり、引き分けたりしている場や文化圏を、わたしは居心地がいいと感じるようになった。海の外だから居心地がいいわけでは決してない。コミュニティ次第なのだ。発想の転換や緩やかな許容度、お互い最低限度のリスペクトを示しながら、しなやかに境界線を引き直していく。もしくはもうすでにそれが当たり前の社会になっていて、そこに住む人はそれをそうと認識せずとも暮らしている状態なのかもしれない。プログラミングが済んだ機械のように、後はもう自動運転に任せ、定期的なアップデートやメンテナンスに時間をかけるだけなのかもしれない。
たくさんの境界線があるようでないような国シンガポールで、わたしはふと考える。境界線はわたしを豊かにしただろうか。答えは、その境界線の周辺に溢れているような気がするのだが、その姿はまだ見えないでいる。
河嶌レイ @ray_kwsm
シンガポール在住の根無し草。文芸サークル「嶌田井書店」店主。ことばと写真を通して自分が見たり感じていることを再解釈・表現することがライフワーク。カフェラテと文房具が好き。
-------------------
嶌田井ジャーナル0号(2018年11月発行)より
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
