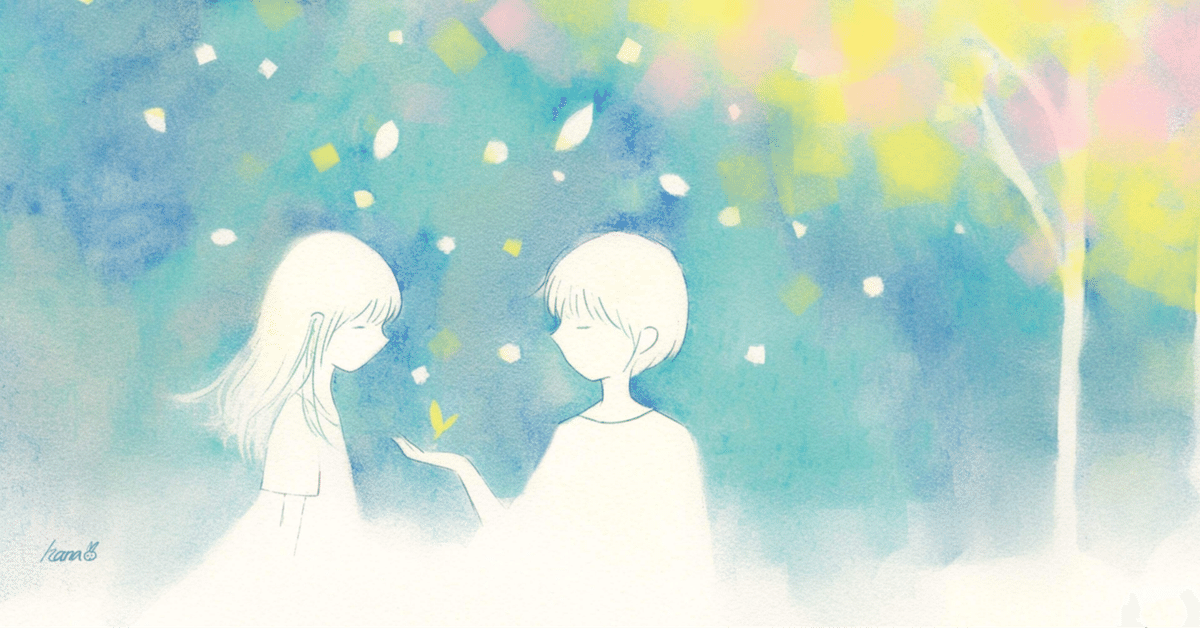
最初で最後の彼女。 (中編)
前回からの続き。
あれから。
彼女の育った街を出発して、途中でドライブインに立ち寄り休憩をしたあと。
今夜泊まる 予約していたビジネスホテルへと向かう為、秋田市内へと車を走らせた。
秋田へ何度か家族旅行で来たことはあったけど、あらためて市内の駅前まで出向いたのは、はじめての事だった。
ホテルの駐車場へ到着し、
ロビーでの受け付けを 彼女がそつなく済ませてくれると、僕らは部屋へと向かう。
まだ太陽は燦々と輝いていたけど、長時間運転した疲れもあったせいか、横になって眠りたい気持ちに駆られた。
自分もそのとき、まだ20代。
ビジネスホテルで女性と二人きりというシチュエーションは、人生で生まれてこのかた、" 初めて "の事であった。
情けない限りだが、自分の人生において、女性に好意を持たれたり、積極的に関わりを持ってもらえたことなど、人生で一度たりとも ありはしなかった。
中学での自分は、まわりの女子たちには奇異な目で見られていたし
クスクスと陰で笑われたり、グループを作って受ける授業で対面をしても、視線も合わせて貰うような事もなく それとなく避けられたりしていたし
高校は高校で、クラスでは殆どひとりぼっちで孤独に過ごしていた事と、
女子と関わりがあったのは、あくまでも" 部活を通して "だけのことだったからだ。
専門学校では、人間に対しての苦手意識をそれなりに克服をして、クラスメートの異性に対しても、ある程度は普通に会話ができるようにはなっていた。
(まわりの気さくな人たちによる影響が大きかったが。)
この頃に働いていた職場といえば、自分たち少数の若者と、そして殆どが中年、そして 年老いた老人たちしか現場にいなかったので
悲しい事に、日常のそもそもが 出逢いなどとは無縁の生活でもあった。
二十余年あまりを生きてきて
これほど異性と何の関わりもない人生というものを、これを読んでいる皆さんは、想像が出来るだろうか……?。
モテない、冴えない男のこれまでの人生なんて、つまるところ" こんなもの "なのだ。
そして、(はじめての彼女という存在ができた) 当時に至る。
こんな自分に対し、
" ひとりの男性 "として、ちゃんと自分を見てくれていた唯一の女性が 彼女だった。
僕は備え付けられたベッドに大の字で
「疲れたーー!」と仰向けに横たわり、いたずらにイビキをかいたフリをし、寝たふりをして見せると
彼女は、「えー!寝ちゃうのー?! (^^;」と駄々を捏ねるのだった。
お互いのその様子を見て、二人して笑う。
そして。僕はいつになく真剣な眼差しで
傍に立つ彼女の手首に触れると
そのまま自分の傍へと、彼女を優しく引き寄せたのだった………
溢れ出した気持ちを押し留めることは、どうしても出来なかった
部屋の窓からは西日が射し込んでいた
蛍光灯の明かりも付けずに
僕らは、互いの孤独と寂しさを埋め合うように、強く抱き締めあった
あのときの気持ちを、どう表現したらいいのか、自分でも未だによく分からない
ただ、
人と愛し合うということを
ふたりの想いと、互いの身体を、
優しく、時に激しく、重ね合うという経験を
産まれてはじめて
自分は 知ることができた のだと思う
人間がこれまで、いつの世も営んできた
「恋」や「愛」という普遍的なもの……
人生において 最も大切なもの について………。
……………………
…………………
………………
……………
…………
………
……
…
それから目を覚ましたのは、
夕方を過ぎて、夜の20時半過ぎ頃のことだったと思う。
部屋から見えた窓の外はすっかり真っ暗で、
駅前のビル街のきらびやかな明かりが灯っている。
確かに疲れもあったが、
彼女の柔らかな体温を肌で感じ、心から安心をしたことも、理由としてあったのだと思う。
人生において、これほどまでに心から安らげた時間は、未だかつてなかった。
眠い目を擦りながら、身体を起こすと
彼女も、小さなうめき声をあげて
「いま何時……?」と同じように瞼を擦り、目を覚ましたのだった。
部屋の丸時計を見やると時刻を伝え、
「さすがにちょっとお腹空いたね。」とベッドから出て立ち上がり、散乱していた洋服を着直す。
部屋の明かりを点け、備え付けられたソファーに腰掛けてテレビをつけると、バラエティー番組から笑い声が聞こえてくる。
彼女も起き出し、眼鏡を掛けて着替えも済ませると、僕のとなりに並んで腰掛け
「はい。私が作ってきたお弁当。」と、昼間ゆっくりと食べることが出来なかったお弁当を、あらためて差し出してくれたのだった。
サンドイッチや唐揚げや玉子焼きを、遠慮なく頬張る。
「今朝は早起きして、頑張って作ったんだよ」
「少しだけ、お母さんに手伝って貰ったけどね」と彼女はいたずらに笑って見せた。
女性が作ってくれた" 手伝りのお弁当 "を食べたのは、産まれてこのかた、はじめての事だった。
「すごい美味しいよ!」
「ありがとう。」と素直な感謝の気持ちを彼女に伝える。
日中、ドライブはしたけど、楽しい場所へと何処にも連れて行ってあげられなかった負い目もあって
「晩御飯、どっか食べに行かない?」と尋ねると
「ううん。大丈夫。」
「そんなにお腹は空いてないんだ。」と彼女。
それでも何かしてあげたい気持ちから、
「ちょっと(ホテルの)下のコンビニに行ってくるけど。なんか欲しいものある?」と聞くと
「お腹は空いてないけど」
「飲み物がいいかな。」と返事。
ゴールデンウィークの駅前のコンビニということもあって、夜になっても人はごった返していたが、
お弁当や飲み物、お菓子をひとしきり物色し、買い物カゴに適当に詰め込んで会計を済ませると、僕は彼女の待つ部屋へと足早に戻っていった。
恋愛とは不思議なもので
あれほど人が街のなかにたくさん往来しているにも関わらず、
僕が見えているのは、彼女の存在。ただそれだけだった。
買い物をしてきたけれど、彼女は自分の作ったお弁当をゆっくりと 細々とつまむ程度で、コンビニで買ってきたお弁当やお菓子には、あまり手を付けてくれなかった。
お腹が空いていたので、残りは自分が平らげてしまったのだった。
それから。
「さすがに疲れたよね」
「お風呂、先に入ってきていいよ」と彼女に促し、
バスルームに向かう彼女はいたずらに、「お風呂からあがって来たらいなくなってたりして」とはにかむので、
「それはないでしょ!」と
僕は笑いながら全力で否定をした。
シャワーを浴びてさっぱりとした様子で、バスルームから戻ってきた彼女と入れ換わるようにして
自分も、浴槽にお湯をためて湯船に浸かり、疲れたその身体を癒したのだった。
彼女が髪の毛を洗って乾かしたシャンプーの残り香がバスルームに広がり、その香りがなんだか、自分にはとても心地よく思えた。
それから翌朝まで。
部屋の電気を消して、
僕は、再び彼女と抱き合って、眠りについたのだった。
翌朝。
自分が目覚めたときには、彼女はすでに起きていて、バスルームで身支度を整えていた。
悪いと思ったのか、陽が登っていてもカーテンは開けず、洗面所の電気だけを点けて、なるべく静かに気を遣ってくれていたようだ。
起きてしばらく裸のままぼーっとしていると
着替えて身支度を整え終えた彼女が、
「おはよ。」と声をかけてくれた。
「おはよ」「早いね。」と挨拶を返すと
「もう9時過ぎてるよ?」と彼女は呆れた様子で部屋の片付けをしてくれていた。
自分も起き出して着替え、カーテンを開けると
外の天気は快晴の青空が広がっていた。
テレビをつけて今日の秋田県内の天気の情報だけを見る。
昼間は快晴のようだったが、夕方から夜にかけては雨の予報だった。
チェックアウトの時間が迫っていたので、自分も洗面所で髭を剃ったり、歯を磨いたりして、急いで身支度を整える。
部屋を出てロビーまで赴くと、昨日と同じように、彼女がチェックアウトの手続きを済ませてくれたのだった。
今日の予定も特には決めてはいなかったが、まだまだ1日の時間があったのと、彼女が「大学の友達に渡すお土産を買いに行きたい。」と言うので、近くの駅ビルで買い物をすることになった。
僕は家族に「友達のところに泊まってくる」と言って言い訳をしてきた手前、正直なところ、お土産は不要であった。
彼女が、「家族にお土産は?」と言うので、苦笑いをしながら 半ばそれに促されるように、駅ビルのお土産コーナーをとりあえず一通り物色しに行くのだった。
秋田県には" ご当地ヒーロー "なる実写の特撮ヒーローのキャラクターがいる。
お土産のお菓子のパッケージを見、彼女に「これなに?!」と尋ねると
「" ネイガー "だよ。知らないの?」
「秋田県民ならみんな知ってる。」と逆に真顔で返されてしまった。
自分はヲタクなので、特撮ヒーローやアニメや漫画の話題には事欠かない自信はあったが、このご当地ヒーローなる存在については まったく知らなかった。
お土産の中身は至って普通のクッキーではあったが、特撮ご当地ヒーローのパッケージに惹かれて、思い出として自分用にひとつだけ買ってゆくことにした。
お会計を済ませようとレジの脇に立つと、そこにはキーホルダー用にデフォルメされたネイガーが陳列されており。
じーっと顔を近づけて見やると彼女は、
「買ってあげよか?」「記念に。」と、そのキーホルダーを買ってくれ、プレゼントとしてあとから手渡してくれたのだった。
ひととおりお土産コーナーを見て回り、駅ビルの階段を降りてゆくとき。
彼女はおもむろに、
「手を繋ぎたい……」と言ってくれた。
情けない事に僕は、人前でイチャイチャしたり 手を繋ぐというスキンシップに対して、どうにも慣れていなかった。
というか、その経験がまったくなかった………
彼女のささやかな申し出に対して、
「いや、恥ずかしいから💦」と、差し出してくれた手を、思わず振り払ってしまったのだった。。
彼女は明らかに怒っていて
「わたしのこと嫌いなんだね 」と拗ねて、
「じゃあ、もういい……!」とすたすたと足早に先に行ってしまった
思わず追いかけて「ごめん……」と隣に並んで歩くも、彼女は口を尖らせ、怒りがおさまらない様子であった…………。
あのときほど、自分の" 男としての情けなさ "を痛感したことはなかった。。
愛してくれる女性が傍にいるのに
自分に自信さえ持てない
彼女の願いひとつ、叶えてやれないとは………。
ホテルの駐車場に戻り 車に乗り込むと、彼女もなんとか機嫌をなおしてくれたのか、ふたりして次は何処へ行こうか?と行き先を決めかねていた。
ふと……
以前、家族旅行をした際に、" 男鹿半島 "へ来たことがあったのを思い出していた。
よくよく考えてみれば、中学校の修学旅行も秋田の男鹿半島だったような気もする。
たいして思い入れがなかった当時の修学旅行も、思わず記憶の中から抜け落ちてゆくところだった。
彼女にその旨を説明し、
「久しぶりに、男鹿半島に行ってみたいんだけど、いい?」と尋ねると
「私もあんまり行ったことないから、いいよ?。」と了承してくれたのだった。
秋田市内から男鹿半島までは、ゆっくり運転をして約1時間半くらい。
ゴールデンウィークで混み合っていたこともあり、それなりに時間がかかっていたような気もする。
当時はガラケー全盛期で、自分の車にはカーナビもついてなかったので、体感でどのくらい運転をしていたのか、実はよく分からなかったのだ。
市内から男鹿半島へは大方一本道だった記憶があり、ゴツゴツとした岩場の浅瀬が海岸沿いに湾曲しながら、道路が続いていたと思う。
先に進めば進むほど、次第に登り坂になっていって、海を見下ろす そのドライブコースの岸壁の高さから、日本海の地平線が遥か遠くまで見えていたのだった。
水面が太陽に照らされ、きらきらとした青い海を見やっては、ふたりで「めっちゃ綺麗!!」と車窓からその美しい景色を眺めていた。
全開にした窓から吹き込んでくる 潮の香りを含んだ風が、いつになく爽やかで、とても心地が良かった。
岸壁の高台にある駐車場に車を停めて、持参したインスタントカメラで男鹿半島の風景を2、3枚撮影をした。
確か、小さな漁港の傍だった気がする。
二人してその景色を暫く眺めていた。
途中。
" 男鹿水族館 "に近付いたのだが、
ゴールデンウィークということもあって、施設は家族連れの長蛇の列に、駐車場もどうやら観光客を乗せた大型バスや自家用車で満杯の状況だった。
遠くからその様子を見やり、
「凄い混んでる💦」
「せっかく来たけど、どうする?」と彼女に聞いてみるも、
「人いっぱいだし、並んでまで行かなくてもいいかなぁ。。」と言って返す。
「じゃあ、ドライブ続けて どっかでご飯食べようか」と、半ば後ろ髪を引かれながら、僕らはその場をあとにしたのだった。
そのあと、お昼も過ぎていたので 途中のコンビニに立ち寄り、軽めの昼食を取るため、休憩をすることにした。
「何処かレストランとか ドライブインとか入ろうか?」とあらためて彼女に尋ねたが、相変わらず彼女は「そんなにお腹空いてないから、コンビニで大丈夫だよ」と言う。
自分は正直、軽食だけで特に不満はなかったが、彼女に対して同時に申し訳なさも感じていた
彼女が心から喜んでくれるようなことを、自分は何ひとつ、この旅のなかでしてあげられていない
それがずっと心残りだった……。
しばしの休憩を挟み、男鹿半島から由利本荘市のほうへと秋田県内をさらに南下する。
運転すること、約1時間半ほど。
来た道と同様、彼女の住む街までは殆ど一本道だった。
車の往来は激しく、時折渋滞もしていたが、それさえ彼女と一緒なら苦にはならなかった。
彼女の住む小さな街へと到着し、
いちばん最初に行った、遠くに干拓地が見える " 小高い丘の公園 "の駐車場へと、車を停車させた。
快晴の青空は夕方になるにつれて次第に曇天に移り変わり、雨粒がぽつぽつと降りだしていた。
昼間の蒸し暑さとは打って代わり、今となっては心なしか、肌寒さを感じる。
停車させた車の窓からその景色を眺めながら、僕らは他愛のない会話をひとしきり交わし続けた。
ドライブ中にかけるのを忘れていた、彼女に聴かせるために選んで持ってきたお気に入りのCDを鞄から取り出すと、それをふたりで一緒に聴きながら、今回の小さな旅の余韻に浸っていたのだった。
パソコンに読み込ませたお気に入りの楽曲を" オリジナルのプレイリスト "として作成して焼き増したCDRを、プレゼントとして彼女に手渡す。
彼女は「ありがと。」「もし、(家に帰ったあと) 寂しくなったら聴いてみるね。」と素直にお礼を言ってくれた。
時間を忘れて話し続けていたので気にならなかったが、外は曇天も相まって段々と日も暮れていたので、僕らは 彼女の住む家の近くの無人駅まで行くことにしたのだ。
最初に待ち合わせた無人駅へと到着すると、肌寒さも増して、いよいよ雨も本降りになっていた。
駐車場に停車した車のなかで二人。
彼女は、「まだ一緒に居たい」と悲しげに呟く。雨粒が車の屋根をぽつぽつと叩いていた。
「まだ時間あるから大丈夫だよ」と僕は、自分も同じ気持ちでいることを伝える。
街灯の明かりが灯り、外はもう、すっかり日が暮れ落ちていた。
帰りの長い道のりが少しだけ頭によぎったが、それも自分ひとりならば、たかが8時間程度の運転など、大した問題ではないように思えた。
当時はまだ若かった自分だから 出来たことであったように思う。
素直に高速道路を使えば良かったのだが、
彼女と二人で過ごした時間を振り返りながら、たとえ時間が掛かっても、その帰り道の工程を、自分はどうしても 大事にしたかったのだと思う。
無人駅の駐車場に停車した車のなかで
座席のシートを倒すと、僕らは互いの時間の許す限り、長い沈黙のまま、
ずっと手を繋ぎ合っていたのだった。
……………………
…………………
………………
……………
…………
………
……
…
いつの間にか。
心から安らげるような、安心した深い眠りに落ちていたようだった
目を覚ますと、彼女がこちらを見つめてくれていたのだ。
「ごめん。また眠ってしまった……」と申し訳なく告げると
「大丈夫だよ」と優しい声色で諭してくれたのだった。
携帯を開いて時間を確認すると、一時間ほど眠ってしまっていたようだった。
体感で何時間も眠り続けていたような気もする。
彼女の体温は、あたたかくて、やわらかくて。優しさに包まれているようで、なんだかとても不思議な感覚だった。
雨脚は少しだけ弱まり
僕らはそれぞれ、帰途につかなければいけなかった
" 別れの時間 "が、刻々と迫っていた…….
車のシートを戻すと、
「そろそろ行かなきゃ……」と彼女に告げる。
彼女はとなりで 涙を流して泣いていたのだ
その様子を見、
「大丈夫……?」と声をかけると
彼女は涙を両手で拭いながら、短く
「うん……。」と答えた。
夜の19時頃になっていただろうか。
「帰り道の運転、大変だよね。遠いし。」
「夜遅くになっちゃうといけないから、私ももう行くね」と、彼女は後部座席にあった荷物をまとめる。
自宅が近くなのは聞いて分かっていたが、
「心配だから、家まで送って行こうか……?」とあらためて投げ掛けると
「うち 見られるの恥ずかしいから……ここでいい。」と彼女は泣き晴らした目をしながら、悲しみを笑い飛ばすように そう答えた。
その様子に安堵し
「じゃあ、ここで見送る。」と言うと
「うん。」
「ありがとう。」
「家に着いたら必ず連絡してね」と
僕の事を 気にかけてくれた。
車のドアを閉めて、彼女は自宅のほうへと向かって、歩き出したのだった。
車から。その後ろ姿を見送ると
彼女は一度だけ、僕へと振り返り……
その手を控えめに振ってくれたのだった。
その姿が、街灯に照らされていた
僕も、同じように小さく手を振り返す。
彼女の姿が遠く、次第に 見えなくなっていった…………。
車のエンジンをかけて、
僕は帰路へと向かう。
彼女の住む街を背にして。
アクセルを踏み込むと 僕は、
込み上げてくる寂しさを 払拭するようにして
振り返ることなく…. 、
夕闇に染まった帰りの道のりを 急いだのだった
彼女との小さな旅の余韻を、
大切に 思い返しながら。
最初で最後の彼女。(中編)
おわり。
後編へとつづく。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
