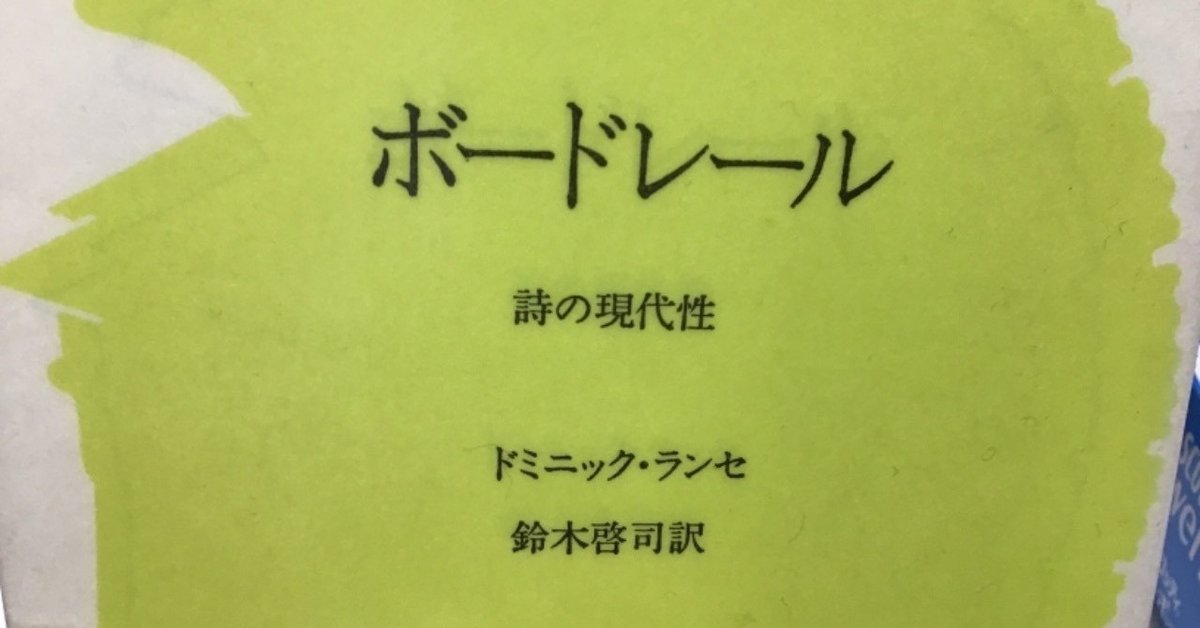
今日読んだ本19/05/07 『ボードレール 詩の現代性』ドミニック・ランセ
割と1日1冊のペースで読める気がしてきたので、可能な限り読んだ本の感想をメモしていきます。
今日読んだのはランセの『ボードレール 詩の現代性』です。
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E2%80%95%E8%A9%A9%E3%81%AE%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E6%80%A7-%E6%96%87%E5%BA%AB%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B8%E3%83%A5-%E3%83%89%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF-%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%BB/dp/4560057303
最近リルケの『若き詩人への手紙』やバシュラール の『蝋燭の焔』を続けて読み、詩学に強く興味を持ったので手にとってみました。
『悪の華』で有名なボードレールの詩作について、彼の芸術評論なども参照しつつその思想を読み解くのが本書の試みです。僕はボードレールについては『悪の華』の一部を読んだに過ぎず、故に本書に対して批判的に検討することはできないのですが、本書を読んだ限りでは若干単純化しすぎているきらいはありつつも見事にボードレールを分析しています。
ボードレールはユゴーと並んで現代詩の最も重要な作家として扱われていますが、ユゴーとはその作品数や生前の評価に天地の差があります。
『悪の華』の非道徳性から裁判にかけられたこともある彼が、なぜこのような地位を手にするに至ったのか。それはひとえに、ボードレール以前・以後で分けられるほどの詩学に対する圧倒的な貢献があったからです。
この点で僕はボードレール観を大きく改めることになりました。僕の中でボードレールはバタイユによって言及された詩人であり、「バタイユ的な美」を代表する詩人でしかありませんでした。しかし本書を通して、またこれまでに読んだ詩学・美学の書と関連づけて、ボードレールが切実なる彼の内的体験と研究を通して詩作にパラダイムシフトを起こした偉大な詩人であると学びました。
ボードレールは詩についてそのあるべきあり方を直接記述することはほぼありませんでしたが、彼が詩作より先に生業とした芸術評論には彼の美学に対する思考が非常に明晰な言葉で述べられています。そしてそれは彼の詩そのものに反映されているのです。
特に印象深かったのは3点。
ひとつめは、詩の構造について。日本語で詩を読む場合、それがもともと日本語であったにせよ和訳されたものであるにせよ、何らかの古典的なルールに従っている感覚は非常に薄いように思います。俳句や短歌・和歌は文字数に関する特有の構造がありますが、例えば枕詞などはルールというよりテクニックに属します。現代詩となると、それぞれでテクニックが使われているにしても、共通の構造というものはほぼ見られないように思います。フランス語の詩を和訳したものも同様です。
しかしフランス語で『悪の華』を読んだ場合、それは改行や押韻などにおいてかなり古典的なルールに忠実に書かれているそうなのです。もちろん例外はありますが、それはテクニックとして挑戦されたものであり、ほとんどはフランス詩の構造に則っています。
この背景には、詩人として世界を体験することを通して得た感覚を自由に表現したいという力と、構造の中でそれを表現すべきだという力の混ざり合うところに、真の詩的な美が現れるというボードレールの考えがありました。ゆえにボードレールはただ押韻などを正確に行っただけではなく、『悪の華』を始まりと終わりのある一連の詩として見事に関連づけたのです。ゆえに裁判にかけられても問題のある一節を取り除くことさえ頑なに拒絶したそうです。
この文脈からのボードレールの革新性のひとつに、都市的な言葉を用いて韻を踏んだことが挙げられます。ボードレールはパリという街で群衆を見ながら、その雑多な都市性に憂鬱を見出し、それを詩に落とし込むことで現代的な感覚を見事に表現しました。
ふたつめは、時間に対する感覚です。彼は憂愁“spleen”という言葉でもって、日常が我々に課す責苦を敵視しました。そして「時間」は、すなわち持続性はそれと完全に一体化せずに、憂愁の不快感をひたすら助長するのです。この「時間」の暴力を振り払うべく、ボードレールは時間をひたすら輪切りに、細分化しようとします。ボードレールの理想は、「特筆に値する」「甘美な刹那」なのです。
しかし理想とは現実に流れる時間を否定することで訪れるものではありません。例外的で予測不可能な「楽園」はただ突発的に訪れるのです。そして瞬く間に過ぎ去ってしまうがゆえに、詩の中でも時間の憂鬱に沈み込んでしまいます。
一方でこの一瞬に見出されるものはまさに「楽園」であり、ボードレールは『パリの憂鬱』にて「ほんの一瞬にせよ悦楽の無限を見出した者のことだ、地獄堕ちの永遠などかまうものか?」と言い切っています。
この点についてはバタイユとの呼応を感じざるを得ません。バタイユもまた、過去との因果や未来への隷属から切り離された「瞬間」に訪れる内的体験を至高としています。そしてやはり、それは何か目的意識を持って得られるものではなく、ただ訪れるのです。
みっつめは、死についてです。ボードレールは日常を生きる憂愁を述べ、幾度か自殺を図りつつも、最期に病が彼の命を奪うまで自ら死ぬことはありませんでした。これにはボードレールの死に対する緊張を伴う感覚が影響するように思います。
ボードレールはその作品の中で死せるものをたびたびモチーフにしています。彼にとって死とは彼岸、この世ならざるものです。この世ならざるものにことさらに近づこうとする。詩というものを用いて。それはひとえに、死という彼岸に「未知のもの」を見出そうとしていたからです。
ボードレールは「旅」にて死を船長に例えます。そして、「この土地は退屈だ!おお死よ!船出しよう!」と呼びかけるのです。これは非常に象徴的に彼の死への態度を物語ります。いま私たちは生きる憂愁の世界で見いだせる美しさが飽和し、退屈を感じる。ここで死こそが、死にゆく運命こそが、私たちの「新しい太陽」となって救いになり得るのです。
ではなぜ彼は自ら死んでしまわなかったのか。ここに僕が非常に美しさを感じた姿勢があります。ボードレールは、切迫した詩への欲望をもって、死を獲得しようとしたのです。詩によって死を掴みとり、危険にさらされながら生きることでこそ、それと引き換えの「全」あるいは「新」が得られると考えたのです。肉体の死という安易な手段ではなく、あくまで詩人として、詩を通して未知のものを得ようとしたのです。そして救いにたどり着こうとしたのです。
誰もが一度は希死念慮を抱えたことがあると思います。ボードレールはそれを強烈な意思と思考と詩の天才で与し、糧としたのです。
以上、本書から学んだことのまとめでした。
詩とは書き方のことだと、多くの人は思っています。ですがそれ以上に、詩とは世界の見方であり、ふるまいそのものなのです。
生きることと詩の距離がここまで近く、もはや一体であったとすれば、僕はより切実に詩への探索を深めなければなりません。僕がこれまで書いてきた文章は未熟な詩だったとも言えますし、これから書く文章も詩になっていくでしょう。
その果てに一瞬のきらめき、あるいは救いのようなものを目指して、読書と創作に励みたいと思いました。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
