
【自粛生活:Zoom飲み会がおススメ】自律神経の深い話【ポリヴェーガル理論】
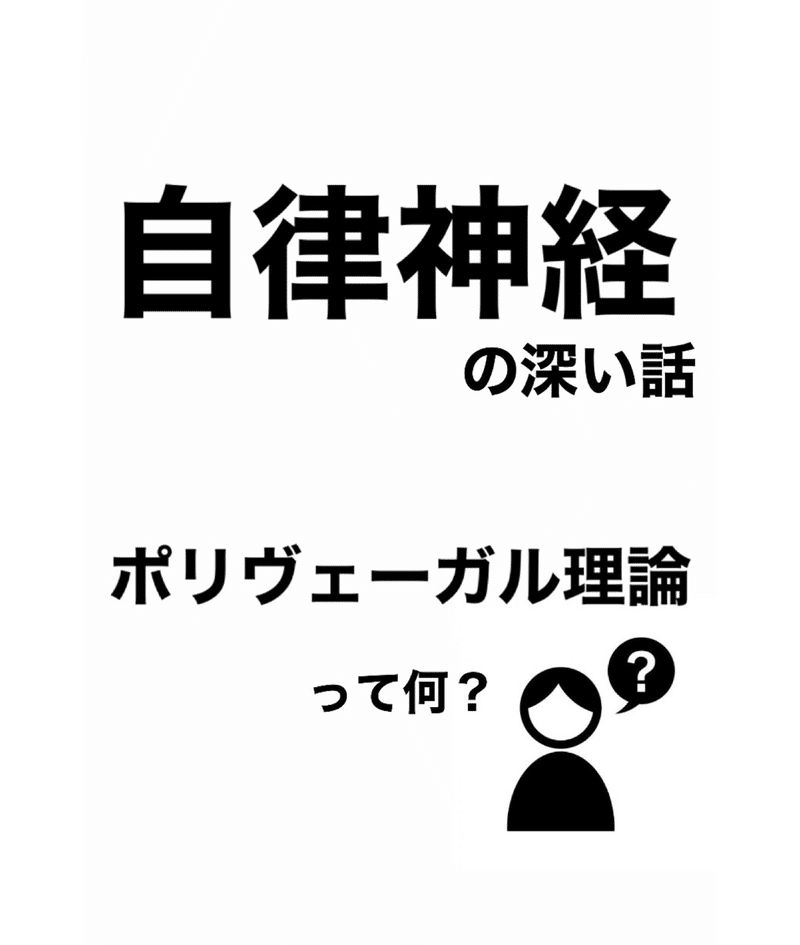
【自粛生活:Zoom飲み会がおススメ】自律神経の深い話【ポリヴェーガル理論】
新型コロナウイルスによる自粛生活も、気が付けば1か月が過ぎました。。
僕も休職中の身となってしまいましたが、
自粛生活をしてると、ほんとに外にも出なければ、人と会話することもなく
気が滅入りますよね。。
そんなときにはZoom飲み会!
やってみると、意外と楽しくてハマりますよ!
僕はだいぶハマりました!(笑)
やはり、画面越しであっても
人と顔を合わせてコミュニケーションは気持ちが晴れますね(^^)/
人間には、コミュニケーションが本能レベルで必要なんです。
ということで、今回は【自律神経の深い話】
「ポリヴェーガル理論」について。のお話です!
とてもマニアックな話ですが、面白いので是非お付き合いください(笑)
※ZOOM飲み会は、あんまり関係ないです(笑)
ポリヴェーガル理論とは?聞いたことある?

ポリヴェーガル理論・・・聞いたことありますか??
結構マニアックな話なので、詳しい方も少なめなんじゃないかな??
と思います。
”自律神経” こちらは聞いたことあると思います。
”自律神経の乱れ”は身体や精神面の不調の原因だ、と
よく取り上げられていますね!
そもそも自律神経とは?
一応説明を入れておきますと、
自律神経とは
呼吸や循環系、消化系、体温の調節など、
無意識化で行われる機能の制御を担っており
体内の内部環境を保ち、恒常性を保つ役割を担っている神経です。
従来の見解や一般的な認識としては、簡単にいうと
交感神経・・・興奮のスイッチ
副交感神経・・・リラックスのスイッチ
こんなイメージです。この2つがバランスをとりあって機能しており、
たとえば交感神経が優位になりすぎると、イライラしたり、眠れなくなる。。
2つのバランスを保つことが重要という認識です。
しかし、従来のこの考え方ではなく、
哺乳類のみに進化の過程で備わった、もう一つの神経がある、
2つの拮抗関係な神経支配ではなく、階層的な神経支配によって
人間の身体は恒常性を保つことができている。
これが【ポリヴェーガル理論】です!
ポリヴェーガル理論とは?

ポリヴェーガル理論は、1994年に発表され、徐々に発展と応用が進んでいる理論だそうです。
この理論では、哺乳類に備わる自律神経は3つに分類されます。
交感神経・・・興奮、闘争、逃走
背側迷走神経・・・不動、フリーズ
腹側迷走神経・・・社会的関わりを可能にする
これらが階層的に働くことによって、
人間の恒常性は維持され、生命活動を行うことが出来ている。
背側迷走神経と腹側迷走神経は、どちらも”副交感神経系”とされています。
背側迷走神経とは?
背側迷走神経は、発生起源でいうと、自律神経の中で最も古いのだそうです。
主に横隔膜より下の臓器の機能を調節しており、
臓器から得た情報を脳幹に伝えたりしてます。
この神経による主な反応でいうと、
緊急事態のとき(猛獣に襲われたときなど)
「不動」の反応・・・じっとして敵から隠れてやりすごす
「フリーズ」の反応・・・死んだふり
のような反応を引き起こします。
また、日常では、休息・回復・消化など生命活動を維持するうえで欠かせない機能も持っています。
腹側迷走神経とは?
発生起源的には、もっとも新しい自律神経であり
哺乳類のみが持つとされています。
主に横隔膜から上(心臓、肺、耳、喉頭、顔面)に分布しています。
また、他の自律神経とくらべ、伝達のスピードが最も速い、という特徴もあります。
腹側迷走神経は、脳神経とコラボして高度なコミュニケーションを可能とし、
哺乳類が進化の過程で社会的行動(群れをなす)
を営む上で、獲得したものだそうです。
この、脳神経とのコラボ(協働システム)を
腹側迷走神経複合体といいます。

腹側迷走神経複合体とは??

腹側迷走神経複合体は、腹側迷走神経と脳神経が連動し協働して機能するシステムのことです。
哺乳類はこのシステムにより、群れをなして、
同種別個体とのコミュニケーションを可能としています。
特に人間の場合、自然界の中で個体で生き残るには戦闘の能力が低く、
集団で助け合い生きていく必要があった。。
ちなみに
たとえば爬虫類の自律神経には”交感神経”と”背側迷走神経”のみしかなく、
その行動は”個別”であり、基本的には個体間での”親密さ”はないです。

爬虫類までの本能だと、「近い」=「危険」という認識がなされます。
結果、”交感神経”あるいは”背側迷走神経”の支配によって
「原始的な防衛本能」が働きます。
しかし、哺乳類や、人間が生存のために協力しあい、
同種の別個体とコミュニケーションをとるには、
必然的に”近づく”必要があります。
近づくたびに「防衛本能」が働いていたら、
常時猛獣に襲われているのと同じ。。。
心身ともにダメージを負ってしまいます。。
そこで、この時「原始的な防衛本能」が働かないように、
自律神経が脳神経とコラボし、
表出的な表現(表情・まなざし・声のトーン・声の抑揚など)
によって相手に”安心・安全”を伝える
=”敵じゃないよ”と伝えることにより
原始的な防衛本能を抑制するのが腹側迷走神経複合体の役割です。
この機能により社会的行動は可能となっているんです・・・!
自立神経の階層

従来の自律神経の考え方だと、
交感神経と副交感神経の2つでバランスをとっている、そんなシンプルな感じでしたが、
ポリヴェーガル理論では、その構造は階層的になっています。
ざっくりと説明していくと、
腹側迷走神経複合体によって、
交感神経、背側迷走神経の働きは”社会的行動”にチューニングがされる感じです。
例えば、
スポーツやゲームで「相手に勝とう」というとき。
また、意欲的・挑戦的に行動するとき。
この時は”社会的行動”の範疇で「交感神経が優位」になっています。
また、
リラクセーションや瞑想などといったものは
「不動」「フリーズ」とまではいかないまでの
”社会性を保った低覚醒状態”によって
「背側迷走神経を優位」にしています。
この腹側迷走神経複合体の支配下における範囲を
”ストレス耐性の範囲”の指標とすることができます。
この”範囲”を超えてくると、
たとえば、スポーツで熱中しすぎて喧嘩にまで発展してしまうような
過度な攻撃性を発揮してしまったり、
あるいはあまりに”低覚醒”な状態が続きすぎると「鬱」のような症状に発展してしまったりします。
一般的に「自律神経が乱れて、心身に不調をきたしている状態」は
腹側迷走神経複合体の働きが弱く、
「本能的な自己防衛」のシステムを抑制できないために
引き起こされてしまう不調ということがいえるんですね!
ストレス耐性

ストレス耐性の領域を考えていくときに、
「一番ストレス耐性が弱い状態はいつか?」を探すと、
おそらく「生まれたての赤ちゃん」の時だといいます。
母胎から外の世界に出てきて、様々な刺激・環境の変化によって
赤ちゃんの自律神経はもう、乱れに乱れます。。(笑)
しかし、そのたびに親や家族、周りの人間たちの関わり
「安心・安全」だよ。という表出的な表現(表情やまなざし、声質など)により自律神経の乱れは修復がなされていきます。
赤ちゃんはこのプロセスの繰り返しによって鍛えられ、
徐々にストレス耐性の領域を広げていきます。
ということは、他者からの
腹側迷走神経複合体による表出的な「安心・安全」の表現
それを受けとることで、
赤ちゃん自身の腹側迷走神経複合体も活性化がなされていく
ということが言えるとおもいます。
ストレス耐性の範囲を広げるためには??

このポリヴェーガル理論での学びを活かし、
自身のストレス耐性の領域を広げるためには。。を考えると
赤ちゃんの事例からも
社会的行動・関わり、他者とのコミュニケーション
これによって「安心・安全」を与えたり受け取ったりを繰り返していくことで
腹側迷走神経複合体は活性化され、ストレス耐性の領域は広がるといえます。
これは、例えば電話などでの「声だけ」のコミュニケーションよりも
顔を突き合わせて、表情や眼の動きなど、
様々な非言語的なコミュニケーションも含めて情報をやり取りするほうが
情報量が多いため、より腹側迷走神経複合体の活性化がなされるといえます。
また、”意識的に”表情を豊かに表現したり、声の質や抑揚の意識、
立ち振る舞いを「安心・安全」を与える表現にしていくことで、
自身の腹側迷走神経複合体を鍛えるとともに、
相手に「安心・安全」を与えることで「承認」を得られ、
相手からの返答としての「安心・安全」によって、
より自身のストレス耐性が高まるといえます!

まとめ
腹側迷走神経複合体。。とか漢字ばかりで長い名前ですし、
なんだかややこしい内容にまとまりましたが、
簡潔にいうと
自律神経のレベルで見ても、本能的に人は他者と助け合い生きるようにできている。
コミュニケーション「安心・安全」「仲間だよ」を伝えあい、承認しあうことで人の健康レベルは向上できる。
ということが言えるというワケですね!
コロナ騒動で、なかなか外出もできず
人と会話する機会も減っている人も多いかとおもいます。。
気づかぬうちに”ストレス耐性”の領域は狭まっている可能性もあるわけです。。
幸い、現代は技術の進化によりZOOMみたいなテレビ電話などで、
離れていても顔を突き合わせて情報をつたえあうことができます!
(実際に対面には及ばないですが)
こんな時こそ、是非活用をしていきたいですね!
あとは、困ったとき、悩んだとき、一人で抱え込んで下した決断は
「本能的な防衛反応」に引っ張られた判断かもしれません。。
まわりに相談してみて、腹側迷走神経複合体を刺激し
「本能的な防衛反応」を抑えることが、
自身も一番冷静で「社会的」な思考になれますから、
何かあったら誰かに軽くでも話してみることがおススメですね(^^♪
というわけで、ややこしい【自律神経の深い話】でした!
最後までお読みいただきありがとうございました(^^♪
記事に投げ銭していただけると非常に喜び、励みになります(^^♪
支援してくださった方には
■アカウントをフォローしにいきます。
■記事への「スキ」をしにいきます。
■Twitter、インスタグラムもしくはNOTE内での記事のシェアをさせていただきます。
是非よろしくお願いいたします(^-^)
よろしければサポートお願いいたします。いただいたサポートは、記事にするためのインプット活動費に充てさせていただきます!
