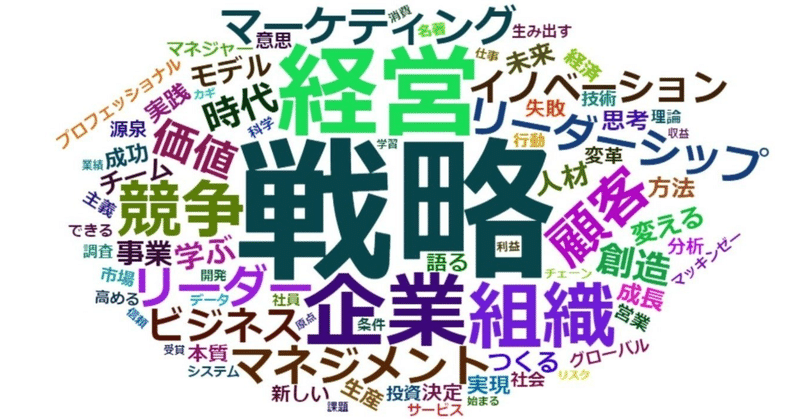
- 内部統制に必要な「法務観点」 -
「内部統制」というと、会計周りを中心(金商法メイン)が思い浮かびますが、「法務観点」(会社法メイン)を見落としてしまうと、あとで問題が発生します。
内部統制における法務観点とは? その重要性は?
今回はその内容を説明します。
(約5分程度でお読みいただけます。)
内部統制の2種類をご存知ですか?
以前「会社法と金商法の、それぞれの『内部統制』」をご紹介しました。このなかで、内部統制に2種類あること、そして会社法と金商法の「内部統制」の概要についてお話ししましたが、内部統制と言っても、会社法と金商法ではその意味と内容が違います。
会社法、金商法の内部統制に関する条文は、先の記事又は皆さんで該当する条文をご参照ください。
今回の記事では、2つの内部統制のうち、会社法の内部統制について、その意味と内容について説明します。
【会社法の内部統制の意味】
取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
会社法では、会社は適正な企業経営を行うことを目的として、組織と制度を構築すべきことを定めています。
例えば、会社の憲法とも言うべき「定款」を定め、適正な業務を行うために各種規程、業務マニュアルを定める。また、これらを適正に行うために部門/部署を置き、適正な人員配置を行い、適正な職務権限を与えて適正な業務を行う。・・・このようになります。
上の条文では「その他株式会社の・・・」とある部分ですが、これは会社が組織を編成するにあたり心得ておく必要のある体制の整備のことを言っています。
(*「その他」とありますが、じつはここが大きな意味を持っている部分です。)
話は少し逸れますが、よく「管理系部門はコスト部門だ」とお聞きします。これは、前述の「適正な企業経営を行うことを目的として組織と制度を構築する」の意味をよく理解していただけましたら、その誤解は必ず解けます。なぜならそれは、「適正な企業経営」のための組織編成には、「牽制機能」が必要だからです。
" 牽制 " といっても、お互いをチェックし合うのではなく、『部門/部署の業務上の責任を補完するための機能』であると考えてみてください。
営業部門は、会社の売上高を担いますが、その " 売上高 " が正しく計上されているか? 契約関係はどうなのか? を営業部門自身がすべてチェックしていたら、どれだけ業務量と業務負担が増えるでしょうか? おそらくどこかで抜け漏れが発生し、そのミスのまま売上計上されてしまったら、会社は「適正な財務諸表」をステークホルダーに開示できず、会社の信用は落ちます。
そこで管理部門は、その業務上の責任として確認作業を行ない、その確認のうえで財務諸表を作成し、ステークホルダーに開示するのです。これによって、どれだけ営業部門は業務の責任と負担を軽くできるでしょうか。
そのためにも、会社の組織は「業務上の負担を分担して、業務上の責任を補完する機能」を持った組織編成をする必要があるのです。
管理部門の皆さん、ぜひ胸を張って業務に邁進してください!!
内部統制は「法務観点」が重要
上では会社法の条文から細かめに説明をしましたが、なぜ細かい説明が必要かというと、会社法の内部統制では、いわゆる「決まったかたち」が無いためです。例えば次のような点です。
定款上の取締役、監査役の員数等の構成
(※会社の規模等によって「設置会社」の基準はあります。)コーポレート・ガバナンス体制の構成と内容
職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制の構成と内容
(※執行役員や使用人の配置の有無など。)その他法務省令で定める体制の設置とその内容を規定する規程の整備
他にもありますが、これらの点について「決まったかたち」はありません。
ここでひとつ例を挙げます。
上場するためには「取締役会の設置」が必須ですが、員数は3名以上であれば、社外取締役も含め何人でも構いません。このとき「コーポレート・ガバナンス体制」にも配慮しなければなりませんので、会社の規模、業種、業界団体内の他社との兼ね合いなど社内外の環境を念頭に員数を決めなければなりません。
この観点は、まさに「法務観点」でみなければならないもので、特に上場準備中の会社にとっては、最重要ポイントです!
もしこの法務観点が、内部統制を構築するうえで " 抜けて " しまったら…
証券取引所の上場審査は通過しませんし、その前の証券会社による事前審査も通過しません。いわば " 門前払い " になります。
また、これらの点を誤った理解のまま体制を構築した場合、先の例に挙げました取締役の員数で、アンバランスな員数(会社規模と比較して極端に多い。組織編成上、必要な員数を確保していない。など。)である場合は、
社内外の社会環境を踏まえたコーポレート・ガバナンス体制を整備していない。
コーポレート・ガバナンスへの理解を深めていない。
=>ゆえに、上場会社としてのコーポレート・ガバナンス体制を確保していない。
このように見えてしまうことになります。
ただし、逆に過度な意識を持つ必要はありません。要するに
「当社のコーポレート・ガバナンス体制は、社内外の社会環境を鑑み、・・・の基本方針を定め、これに基づいて体制を整備した。」
と説明できるようになることが必要なのです。
ほかにも理由はありますが、このようなわけで、内部統制の構築には「法務観点」から十分に理解を深め、これを社内できめ細やかに検討を行うことが必要なのです。
会社法が求めている内部統制の内容について
次に、会社法が求めている内部統制の内容について、お話しします。
どのように構築すれば良いかは、さきほどご紹介しました会社法第362条第4項6号に
取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
このようにありますので、その法務省令(会社法施行規則)を確認しましょう。確認する先は、会社法施行規則第100条です。(*長いので、引用は省略します。皆さんでご確認ください。)
上場企業(だけではないのですが)は、この第100条に定めている各体制を整備したうえで、「内部統制システムの基本方針」にその整備状況を対外的に表明します。
ただし、「これ」という形をきめ細やかに定めているわけではありません。この点は、会社の経営方針に基づいて構築すべき点である、という理解ですので、各社はこの点をかなりきめ細やかに検討を重ねて構築されております。
ひとつ例に挙げますと、以前から「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行する会社が増加しています。十分に検討を重ねたうえで移行された会社がいる反面、「常勤監査役を置く必要がなくなる」とか、「役員の員数を抑えられる(業務執行取締役1名+監査等委員の取締役3名以上=最低4名)」という会社もいらっしゃるのではないでしょうか。
この監査等委員会設置会社の本来の意図は、「会社全体の監査・監視機能の強化」というコーポレート・ガバナンス体制の強化であり、これが重要なポイントです。この重要なポイントを抑えておかないと、取締役会運営が停滞したり、体制変更に伴うコスト増となったりと、体制変更前には想像しなかったような事態が襲いかかってくることがあります。
そのためにも、経営者層で中期計画またはそれより先の「会社の方向性」を十分に検討して、当社のあるべき姿をかなり明確に形作る必要があります。
以上のように、特にIPO準備中の会社でこれから/いま内部統制を構築されているのであれば、会社法が求めている内部統制の構築に目を向けてください。金商法の内部統制は、J-SOX対応していくうちに自然と構築できますが、会社法の内部統制は少々時間をかけて準備して構築していくことになります。また、会社法の内部統制には「正解のかたち」がありません。経営方針や会社規模など多くの要素が束ねられて構築していきますが、そこには会社法の理解を深めたうえでの「法務観点」で内部統制を構築していく必要があることを、十分ご理解ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
