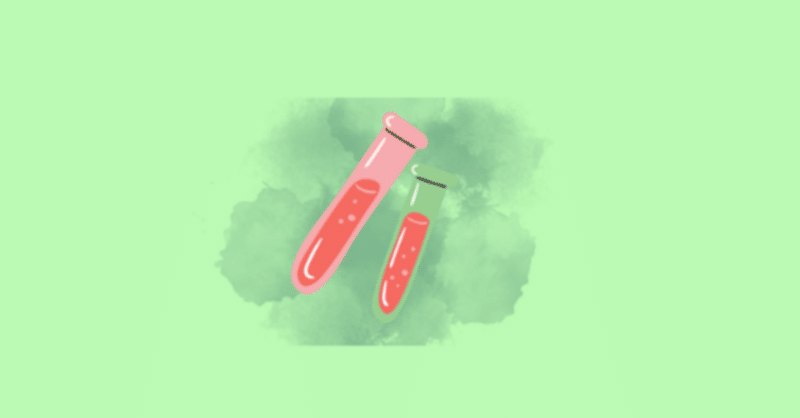
近未来SF連載小説「アフロディシアクム(惚れ薬)」No.2 朋美の事情(1)
連載15話くらい(予定)、プロットと前回までの回はこちらのリンクに:
* * * *
飯野朋美は2020年10月、感染性疫病で前代未聞の強制的ロックダウン下のシンガポールのマウント・エリザベス病院で生を受けた。
細菌防御服を着て医療ヘルメットを被った父親が、生後間もない朋美を抱いている写真が残っている。
2015年に日本から移住して、小さいながらもコンサル会社を経営していた父親飯野純は、疫病蔓延での経済ロックダウンで多くの日本の顧客を失って倒産の一歩手前までいったが、幸いにも3年続いた疫病禍の後、逆にシンガポールの現地企業の顧客が増えてどうにか生き残った。
ビジネスはその後も鳴かず飛ばずではあったが、家族経営のコンサル会社の経理業務を切り盛りする朋美の母の尽力もあり、永住権も確保し、物価高で住みづらくなっていったシンガポールではあったが、一家はそれなりに幸せな日々を送っていった。
父飯野純の口癖は「英語圏は広い、21世紀これからの時代は英語あってのサバイバルだ」。あたかも、このアジアの英語圏の小さな島での子育ての選択の正しさを自分に納得させるかのようにいつもそう言っていたが、それは自分の英語コンプレックスの裏返しであったともいえた。
朋美は、その後続いて生まれた2人の妹と、小中高とシンガポールの現地校で学ぶ。長女の朋美は、父の教えに素直に英語圏でサバイバルと早くから手に職をつけて自立したいと思い、シンガポールとは旧英連邦つながりの当時まだUKの一部であったウェールズの看護学校に進学する。成績はよかったのでまわりからは大学進学を強く勧められたが、不安定な父親のビジネスでは既に年間10万ドル超えに高騰した大学授業料は無理だろうと勝手に思ったこともあり、また、親から遠く離れて住んでみたいとなんとなく思っていた。
そして、2040年にはウェールズ西部のスウォンジーの学校を卒業して、当時のUKの看護師の資格を得る。その資格はシンガポールやオーストラリアでも有効であった。また、2048年のウェールズのカムリ共和国として独立後も、その資格は既に死語になりかけていたが20世紀前半まで存在した「旧英連邦」(コモン・ウェルス)の枠組みで、それらのどの国でも看護師としての登録が可能な資格であった。まさに英語圏でのサバイバルだ!と父親は喜んだ。それが朋美は嬉しかった。あくまでも家族には、良き長女という立ち位置を続けていたかった。
当年、33歳、スウォンジー中央病院勤務看護師。独身。
一見、おとなしい、日本にいたとしても実際の年より5歳くらい若く見える、かわいらしい感じ。欧州だとさらに5歳くらい若く見えるのか、よく病院の隣にある大学の学生と間違えられる。
三人姉妹の長女タイプとして世界のどんな国にでもよくいる性格。おっとりしているようで、かなり芯はしっかりしている。しっかりしているがゆえに、あまり浮いた話はなく、自分が敷いたレールの上を着実に前に進んでいる。両親からみたら、あと残りの二人のお目付け役というか、自分たちの子育ての同志として頼れる教え子といった感じであったが、朋美本人もその役割をきちんと演じてきた。スウォンジーに行きたいと言いだす前までは。
病院で看護師として勤務していても、同僚にも、医者にも、そして患者にも好かれる模範的なナースであった。いつも笑顔を絶やさず、ポニーテールを軽快に揺らしながら病室をすいすいと無駄のない動きで巡回しているのが朋美であった。
「(トモミー、君はエンジェル(天使)のようだ)」
よく年配の患者に言われた。それに対して、朋美は静かにほほ笑む。教会に描かれたエンジェルのようにというより、彼らにとっては謎の、遠いアジアの奥ゆかしい微笑みでもって。
実は、誰にも、親にも、親友にも絶対に話さないときめた、自分の心の奥深くに住まわせた、ある種の自我を分裂させたような存在があって、それで自分の心のバランスを保っていた。
看護学校の心理学の授業で、親から強烈な虐待を受けた子供が自分が傷ついていくのを守るために心の中に別の人格を分裂させてつくって、その人格が自我との間でバランスをとってくれる解離逃避行動があるというのを学んだ時、「あ、私にもそれある」と思った。
小学校高学年の頃だろうか、ある時、優等生的な、しっかりした長女を続けていくのが辛くなった出来事があった。
年上の中学生のシンガポール人の少年に乱暴な言葉をしつこく吐かれ、これまで無かったような怒りを感じた。言葉の暴力だったが、その言葉が自分の存在を否定し、自分の家族や出自まで卑下するようなひどいことを言われた。思わず我を忘れ思い切り怒鳴りたくなったが、そんな時、心の奥のほうなのか、脳の片隅なのか、どこかから声がしてきた。
「てめえ、ぶん殴って、マーライオンの噴水みたいに鼻血ブーにしてやるぞ」
それが、朋美がその夜「ワル美」と命名することになる、別人格の声だった。
優等生で優しい自分に代わって、ワルなことを心の中で言い放ってくれる存在。ワル美は、自分に敵対するすべてを罵倒し、暴力的に始末してくれる。そんなことを妄想しては、その後の人生、今日まで、どうにか心の平静を保とうとしてきた。そう妄想することで、辛いことも耐えられた。
世の中の人は多かれ少なかれみんなそんなことしてバランスを保ってるに違いないと思っていた。でも、自分のなかに「ワル美」がいますなんて、絶対誰にも言わないようにしようと決めたのであった。
よく、父親が朋美のことをシンガポール人に、漢字は朋と美だから、the Friendly Beautyという意味なんですよと説明していた。じゃあ、ワル美は the Evil Beautyかしらなんて思って、欧州に来てからは密かにこの別人格をそう呼ぶようになっていた。
「天使のようだ」と言ってくる老人にも、微笑みを返しながら、心の底では the Evil Beauty が「てめー、こないだ偶然のふりしてお尻さわっただろ、エロじじい」と悪態をついてくれていた。
20代の頃、ウェールズの看護学校時代にパーティで会ったウェールズ人のオワインという学生と半年ほど付き合ったことがあった。食事したり、キスしたり、セックスしたり、ごく普通のボーイフレンド・ガールフレンドの関係を一通りしたが、朋美にはその関係性がピンとこなかった。
ある日、「ピンとこない」という表現でしか言いようがない、醒めた自分を発見した。そんな感じだった。心の中の the Evil Beauty も「デートも割り勘だし、あんなイカれたのと付き合ってたら時間の無駄よ」と言い放っていた。それで別れた。
イカれたというのは、オワイン、彼の名前はウェールズが15世紀にイングランドによる支配に反旗を挙げた最後のプリンス・オブ・ウェールズであった英雄オワイン・グリンドゥールと同じ名前だというのもあって、彼の両親や家族、そして本人も熱狂的な独立支持派の活動家で、停学くらって学生でもないし定職もないのに、独立派の学生運動家を気取っていたというところ。オワインが熱く語る独立への主張の一言一言すべてが、朋美の耳にはまったく意味不明のギリシャ語の文法か物理の定理のように、ただ空虚なものに聞こえていた。
以来、ボーイフレンドはいない。
同性愛的関心もあるのかしらと思った時期もあったが、どう考えてもその関心はないようだった。
看護婦仲間の親友ノエリア・プジョル、愛称ノリーがよく朋美をからかった。
「(トモーミ、あなたはそれで人生楽しいの?出会いを夢見てわくわくして、キュートな彼氏と実際に出会って関係が深まっていくっていいわよ)」
「(ノリー、あなたはラテン系、私は東洋人、その違いがあるのよ。私にはそのわくわくはないし、そのわくわくがない人生なのかもしれないのよ。それにあなた、いつもぽーっとのぼせあがって、最後は手痛い別れで終わるじゃない。親友としてはそれを見るのが辛いのよ)」
「(まあそれは否定できないわね。いつも、失恋のどん底からあなたのその東洋的な悟りのような静謐な慰めの言葉に救われてるわね。でもね、人間の関係って、安定はしないのよ。ゆらゆら揺れ動かされながらも、どうにか続けていくのよ、私の祖国みたいにね)」
ノリーは、欧州のフランスとスペインの間のピレネー山脈の山奥の谷あいにあるアンドーラ王国という小国の出身だった。人口たった7万人。言語的にも文化的にもカタルーニャであるといえるが、紀元803年にフランク族が建国して以来、ずっと独立を保ってきた国である。
もちろん、中世から現代にいたるまで、欧州の政治に翻弄されながらの歴史であり、フランスとスペインという2つの大国の緩衝国として綱渡りの政治を続けてきた国ともいえる。建国後、2つのカタルーニャ系の伯爵一族が争った結果として2つの伯爵家の対等な共同統治となったが、中世末期にその一方が政略結婚でフランスのブルボン家となったことから、共同統治の一方がフランスの元首ということになる。その歴史から、アンドラ王国の軍事そして外交は基本的にフランスかスペインに委託しており、EUにも属さず、21世紀初頭まではタックス・ヘブンとして、山奥の雪深きスキーリゾートにすぎない一都市が、ひとつの独立国として存続しつづけてきた。
「(アンドーラはね、二人の男をじょうずに手玉にとってる自立した女性みたいにね、めんどくさいことは男に任せておいて、自分のやりたいこと、文化とかもっと奥深い事を極めている国なのよ)」ノリーはよくそう言っていた。
「(トモーミ、でもあなたにあの心を焦がすような、彼のことを考えたら夜も寝られなくなるような、あの恋の気持がないんだなんて言わせないわよ。人類みんなが持ってる感情なのよ。とても素敵な、それ自体が生きていることの目的のような気もするそんな感情。あなたも、心の奥にそれを隠している。そこにあるんだけど、なにかが邪魔して放たれてない密かな炎なのよ)」
「(『別れがこんなに甘く切ないなら、おやすみなさいと朝になるまで言い続けていたいわ』って、お隣イングランドのシェイクスピアも恋したジュリエットに言わせてる。
『君に出会った奇跡がこの胸にあふれてる、きっと今は自由に空も飛べるはず』)スピッツだったっけ、あなたの国のオールディーズの歌謡曲でもそう歌ってたでしょ。
あなたに、あの気持ちを感じでほしい。それが親友としての私の想いなの)」いつも、ノリーはそんなことを言う。
*
2053年のある朝、夜勤明けの朋美は寝ようとすると、ノリーからのメッセージがある。
「(トモーミ。これ見た?まだだったら見て。アセクシュアルの自主選択的治療のLINK)。」
「(バルセロナの医者がEU EMAに認可申請中の治療らしいのだけれど、カムリでも臨床試験を30人くらい募集しているのよ。メッセンジャーRNAでの脳内ホルモン活性化だからそんなにリスクは高くないと思うの。それに、成人の場合、パートナーや親友が「後見人」になって、治療の効果で精神的に不安定になりそうだったら本人が希望しても治療を停止できるってあるでしょ。私、あなたの後見人になりたいの。ぜひ検討してみて)」
徹夜で頭がぼぅっとしていた朋美は返事もせずメッセージを削除して、深い眠りにつく。
6時間後に目覚ましで起きると、そういえばメッセージが来ていたと携帯端末を開くが受信箱にないので削除ボックスをみる。するとノリーからのメッセージがある。
ああ、へんな治療の話ねと思い出すが、ふとそこにあったリンクを開いてみる。
そこには、ちょっとハンサムな医者が、治療法について熱く語る動画があった。バルセロナのリュイス医師の動画だった。この感情の喚起で人生が豊かなものになるとか言っている。
その時、朋美の心の奥に住むワル美、the Evil Beauty がつぶやいてくる。
「こういう熱く語るやつに限って、裏があるのよ。ワルよ。惚れ薬でもつくって女をいいように操りたいとでも思ってるのよ。これ、やってみなよ。治療が効いたふりして欺いて、最後はこいつに、大っ恥かかせてやればいい」
( No.3 リュイスの事情 (2)へと続く)
この小説はフィクションです。実在の人物や団体などとはこれっぽっちも関係ありません。医学的な知識はまったくでたらめで、SFなので政治的な内容はまったくの妄想で幾ばくかの根拠もありません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
