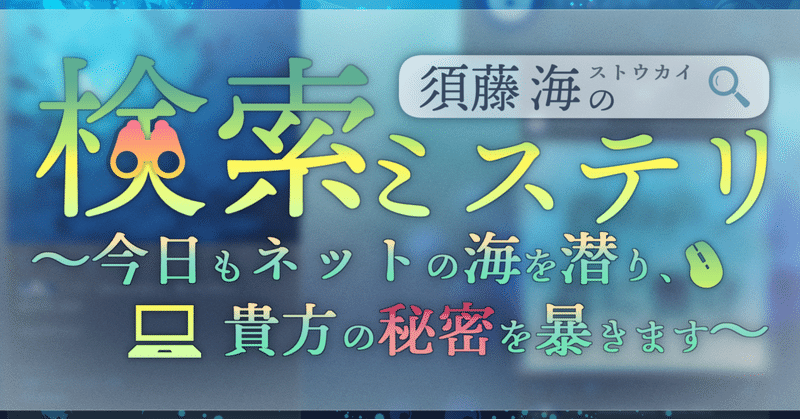
須藤海の検索ミステリ 第1章 行方知れずの友人(前編)
あらすじ
大学生の安西織貴(あんざいおるき)は、親友が急に音信普通になったことを心配していた。そんな中、変わった探偵がいるという噂を聞きつけ、隣駅の探偵事務所を訪れる。
出てきたのは探偵の須藤海(ストーカイ)。織貴が海の探偵能力を気にかけていると、彼は「ちょっと待って」とパソコンを触り始め、画面を見せる。
「君のアカウント、ひょっとしてこれ?」
「なんで分かったんですか!」
SNSに投稿された写真やネット配信の動画から、気になった人の居場所や誕生日を特定してしまうネットストーキング。これは、ネトストの技術を駆使して探偵をする見た目もやり口もストーカーな須藤海と助手になった織貴の、アブない連作短編ミステリ。
「よし、多分これだ!」
探偵の須藤海は、満足そうに顔を上げ、ノートパソコンに付けている覗き見防止フィルターを外す。そして、向かい合ったソファの真ん中にあるテーブルにパソコンを置き、液晶画面を俺に向けた。
「君のアカウント、ひょっとしてこれじゃない?」
画面に映っている映像を見て、俺の腕に鳥肌が立つ。それは紛れもなく、大学の友人にも教えていない、俺のTweeterのアカウントだった。
「なんで分かったんですか!」
驚いて叫ぶ俺に、向かいに座っている須藤さんは得意げに鼻をフッと鳴らす。その表情は、俺が使っているアイコンの犬によく似ている。
「たまたま、というか賭けみたいなものだったけどね」
画面を自分の方に向け直しながら、彼は説明を始める。
「織貴君は大学生ってさっき聞いたでしょ? で、話した感じは割と一般的な学生って印象だ。だから、おそらくウケ狙いのツイートやSNS映えする写真ばっかり投稿するタイプじゃなくて、日常のツイートもしてるだろうって思ったんだ。もちろん普段の印象とSNSの人格が全く違う人もいるけどね」
「はい、まあ、本当に大したことないこと呟いてますね」
「でね、この事務所って結構変なところにあるでしょ? 建物も色も薄いクリーム色で目立つ。だから、『こんなところに探偵事務所が』みたいなことを画像付きでツイートしてるんじゃないかなって考えた。それで探したんだ」
「探した……ってどういうことですか?」
「そのまんまの意味だよ。『ここ 探偵事務所』とか『こんなところ 探偵』とか、キーワードを変えて検索したんだ」
「えっ、さっきからずっとそれをやってたんですか?」
「そうだよ、色んなパターン試したからね」
俺がツイートしているとも限らないし、鍵をかけてるかもしれないのに……執念がすごい。
「で、一件ヒットしたんだよね。ちょうど数十分前、しかも写真もうちの事務所の建物だ。ただ、それだけなら通りすがりの人が写真を撮って投稿してる可能性もあるよね。これを投稿してるアカウントが織貴君って証拠がほしいんだけど、プロフィール欄には手掛かりはなかった。だから、メディア欄を漁っていったんだ。写真や動画にはヒントがたくさん載ってるからね」
メディア欄。投稿したもののうち、画像や動画だけをピックアップして表示できるタブ。
「その中で三ヶ月前の七月にお酒を投稿している写真があった。あと、六ヶ月前の四月にはノートと手を映してる写真があって、明らかに男の人の手だったから、二十歳以上の男子ってことは間違いない。でも他にめぼしい画像のツイートはなかった」
「そんな前まで……」
この半年間、結構写真を投稿していたはず。かなりしっかりチェックしているようだ。
「で、最後にツイート本文を見た。ヒントになりそうな文を探すのは結構根気がいるけどね。そうしたら、八か月前の二月に『社会学入門の試験だるい』ってツイートがあった。直近でうちの建物を撮影している、二十歳以上の男子大学生。ここまでくれば、恐らく織貴君に違いないだろうって思って訊いてみたってわけさ! どう?」
「はい……すごいです……すごいですけど……」
ずっと言うかどうか迷ってたことが喉までせりあがってきて、思わず逡巡する。でも、今の雰囲気なら言える気がする。
「なんか……ストーカーみたいじゃないですか」
「ええっ!」
俺の言葉に、心外とでも言いたげに目を丸くする彼を見ながら、俺は今日ここに来るまでのことを思い出していた。
■◇■
「何してるんだよ……」
テレビのない部屋で、パソコンで再生しているネット番組のニュースを見ながら、思わず嘆息する。事件の詳細な説明と共に、画面には「SNSに家の写真を投稿していたのを犯人に特定され、スプレーでいたずら書きをされた」と要約が記載されていた。
「ったく、それはダメだって」
もう一度深く溜息を吐きながらパソコンを閉じ、リュックの背中側のパソコンスペースに入れて背負う。一人暮らし、1Kの手狭な部屋の戸締りを確認し、玄関のドアを勢いよく開けて大学へ出発した。
本当にダメだと思う。自分の家の写真をアップするなんて。ロクなことにならないのに。
「うわ、寒いな」
十月に入ったばかりだけど、残暑は先月ですっかり消えてしまったらしい。太陽は照っているものの空気は冷えていて、ネルシャツの袖から風が入り込んでほんの少しだけ肌寒く感じるほどだ。
ただ、また歩いているだけで汗をかくような日も来るのだろうと思うと、秋は大好きな季節であるものの、気温差で体調を崩さないようにしないと、と心配になった。
埼玉から神奈川までを結ぶJR京浜東北線、東京都北区の王子駅。東京駅まで二十分、新宿まで二五分という都心へのアクセスの良さと、個人経営の居酒屋が点在する北区らしい下町感の融合する街。
博物館も入っている、広大な飛鳥山公園に沿うように歩き、そして大通りを南西に進むと右手側にキャンパスが見えてくる。家から徒歩十分。大学の近くに住むと、自転車すら使わずに移動できるのが便利だ。
「おっ、織貴、おはよ」
「おう、おはよ」
「安西君、何取るの?」
「アメリカ経済史だよ」
三年の下期にもなると、サークルに入っていなくても知り合いが大分増えてくる。キャンパスを歩いているだけで、クラスが一緒だった友人やゼミの仲間から声をかけてもらえた。
「講義棟三階は、と……」
一限のチャイムに間に合うように教室に入り、講義を受ける。社会学部は教育、歴史、文化、心理と多種多様な授業があり、授業に飽きがこないのは意外と良いところだと思う。
「第二次世界大戦後におけるアメリカのドイツ政策というのは、重要性が高いために戦前から二つの意見が対立していたわけです。片方はドイツの工業力を完全に無力化し……」
教授の話を聞きながら、下期の時間割を確認する。先週は各授業の紹介があり、今週から本格的な授業開始。教務課への受講登録は来週半ばまでだ。一年から三年上期まで真面目に単位を取っていたおかげで、今期は週八コマで済みそう。
しかもうまく火~木に集中させられたので、週三登校、週四休みという夢のような日程だ。サークルは入っていないから、残りの時間は読書や動画に充ててゆっくり過ごそう。あとはこれまで通り、一人旅をしようかな。
大学であまり友人を作ってないから、空き時間の使い方の選択肢は少ないし、一緒に授業を受ける人もほとんどいない。それでも、高校時代のあのことを思い出すと、なるべく他人との距離を取っておいた方が気が楽だった。
「この外交問題評議会が、影響力を飛躍的に拡大するきっかけは、国務省との間で行われた共同研究です。一九三九年にヨーロッパが戦争に突入して以降……」
抑揚のない、ほぼ念仏のような教授の話を聞きながら、眠くてくっつきそうな瞼を頑張って開く。気を紛らわすために五人掛けのテーブルの左端から右を向くが、誰も座っていない。そのことが、俺の心を仄かにざわつかせ、眠気が雲散霧消した。
数少ない友人、北藤赤都。彼を大学で見なくなって、もう四日目になる。もともと一年のときに第二外国語で分けられたクラスで一緒になったのが付き合いの始まり。学部も一緒、高校時代はサッカー部、でも大学では続けないなど、共通点が多く意気投合してから二年以上ずっと付き合いが続いている。
二人で旅行に行ったりするような仲ではないものの、生協で会えば隣でご飯を食べ、たまにクラスの仲間を集めて飲むときには必ず彼を誘った。
同じ学部なので、授業が被ったら並んで受けることが多い。実際、先週の授業紹介の際には、何回か彼と一緒に教室に入ったりした。しかし、今週に入ってから授業で顔を見ない、どころか、三日の月曜から六日の今日まで、キャンパスで彼を見かけない。
一体どうしてしまったのだろうか。何か病気だろうか。しかし先週会ったときはそんな兆候はなかった。もちろんただの風邪という可能性もあるが、それにしては時間がかかりすぎのように思う。旅行に行くような話も聞いていなかったし、何か身内にあったのだろうか。いずれにせよ、理由を想像していくと大分季節の早い雪のように不安が募り、想像はあまり良い方向には膨らまなかった。
「なあ、知ってる? ストーカー探偵の話」
教授が一瞬だけ退室した隙に、隣の席の男女が話し始める。
「隣駅に事務所があるんだっけ?」
「そうそう、東十条駅のね。なんか、結構見た目も捜査の仕方もやばい人らしいぜ。兄貴の知り合いが依頼したんだって」
「ストーカーを探してくれるの?」
「違う違う、なんか探偵なのに相手をストーカーするらしい」
「え、ホントに!」
それじゃ探偵じゃなくて犯人じゃないか、心の中でツッコミを入れる。
この時はまだ、彼が言っていた話を翌日自ら検証しに行くことになるとは、露ほども考えていなかった。
「これ、お願いします」
「はい、百円になります!」
二限は休み。生協の書店で午後受ける授業の教科書を買った後、横の売店でおにぎりを買う。お弁当からチルドカップのコーヒー、スナック菓子まで売っているが、生協オリジナルのねぎ塩豚のおにぎりは、ピリッとした辛みがあって何度もリピートしてしまう。
「んん……」
迷った末、スマホでチャットアプリを開き、赤都のページまで行く。やりとりは先週俺から送った「また飲もうぜ」というお誘いに「OK」というウサギがサムズアップしているスタンプで返事をしている先週のやりとりで止まっていた。
『大丈夫? 具合悪いなら差し入れとか行くからな!笑』
最後の「笑」に少しの照れ隠しを込めて、チャットを送ってみた。おにぎりを頬張りながら画面をちらちら見るものの、既読のマークはつかない。大抵こういうのは見てると更新されないんだよな、と思い液晶を裏返しにしてみるものの、食べ終えてすぐひっくり返してしまい、自分のせっかちさに思わず苦笑してしまった。
SNSを見れば何か分かるかな、と考えたものの、よくよく考えてみると赤都のアカウントを知らない。リアルでしょっちゅう会う仲間なので、別にアカウントを知る必要もなかった。電話番号は知っているが、もし実家に帰っていたり病院だったりすると着信が入るのも都合が悪いだろう。
結局、今の俺にとってはチャットだけが唯一の彼との連絡手段だった。
「……来ない」
三限、四限と終え、一六時を回っても返信どころか既読もつかず、キャンパスの図書館近くに設置されたベンチに座って首を傾げる。陽光は少しずつ燃え始め、薄墨色になっていく空を赤く染め上げる。日が短くなっていることを実感した。
「織貴、お疲れ。何、待ち合わせ?」
「おう、まあ、そんなもんだな」
図書館から出てきたクラスの友人と挨拶を交わし、諦めてスマホをネルシャツの胸ポケットにしまう。まだ送ってから五、六時間だ、何か日中に用事があれば返事が来ないことも十分考えられる。でも、相談でも雑談でも二日に一回はやりとりをしていたのに急に来なくなったことに関する疑念と不安がどうしても心に巣食ってしまい、大丈夫だと自分に言い聞かせることができないまま帰路についた。
家に帰って、鶏むねとカット野菜の野菜炒めで夕飯を済ませ、部屋の真ん中に置いたテーブルの高さを上げる。天板の下にあるレバーで学習机の高さにもこたつの高さにも調整できる一人用テーブルで、気分によって椅子と組み合わせて使っていた。
「んじゃ、やるか」
力なく呟きつつ、明日の講義に向けて読めと言われていた教育心理学の教科書を捲るものの、あまり頭に入ってこない。災害時に家族の安全が分からないと人間は冷静な判断がくだせない、という研究の話を休日流していたAMで聞いたのはいつだっただろうか。結局、指示されたページまで文字だけは読み、あとは気がかりをごまかすため、動画配信サービスのバラエティー番組を一気見して眠りに就いた。
翌朝、十月七日、金曜日。今日は授業がないので、俺は赤都の家に来ていた。何度か遊びに来たことのある、彼の一人暮らしの低層マンション。一階の俺の家に比べて二階の彼の家は床が暖かく、羨ましいと言いながら夜通しゲームをしたのを思い出す。
エレベーターがないため、オートロックのないエントランスを入ってすぐの階段を上がり、二階の彼の部屋に向かう。向かいがけにサッと横目で見た彼の郵便受けにたくさん広告が入っていたことは、頭の埒外に置いた。何か変なことがないか、細かいところまで気になってしまう。高校二年のときに怒りと恐怖の中で身に着けてしまった癖は、三年以上経っても変わらなかった。
ピンポーン
部屋のインターホンを押すが、何の反応もない。ピンポン、ピンポンと緊張で鼓動が速まるかのようにインターバルを短くして押していくが、いつものようにドタドタと廊下を掛けてくる音は聞こえなかった。
矢も楯もたまらず、電話番号を探して通話ボタンを押す。コール音を聞きながら心を落ち着けるが、それが三回、四回と繰り返されるうちに、「出ないだろうな」という諦めが頭の中を埋め尽くす。
ガチャ
「あっ! もしも——」
「おかけになった電話をお呼びしましたが、電波のとどかない場所にいるか……」
結局聞こえてきたのは機械的な女性の声だけで、赤都には繋がらない。彼と連絡を取る手段は潰え、何らかリアクションを待つしかなくなった。そして、それが当面返ってこなそうな予感もしていた。
何事もなければいいけど、今や何事もないという可能性の方が低い。身内に急病やご不幸でもあって実家に帰っているのだろうか。でも、月曜から金曜まで、どこかで少しでも時間があれば一言くれるはずだ。一緒に取っている授業で早速提出予定の課題もあったし、今朝元クラスメイトから飲み会の連絡もあったのに、全く連絡がない。嫌な想像ばかりが嵩を増していく。
警察に相談? 大学には緊急連絡先を提出している? でも、友人の男子大学生が数日連絡が取れないくらいでは、まともに取り合ってくれないだろう。
自分が心配しすぎなのだろうか。でも、実家の住所も連絡先も知らない相手と連絡が取れないとき、一体どこまで放っておけばいいのだろう。そしていざというときは誰に相談すればいいのだろうか。赤都にもっと近しい友人、は知らない。サークル、も入っていない。あとは全く違う人、例えば人を探すのが得意な……
「あっ」
ふいに、昨日の一限で聞いた男女の会話を思い出し、俺はすぐさまスマホを取り出して、キーワードで検索をかけた。
「こんなところにあるのか……?」
家と学校の最寄り駅、王子駅から京浜東北線で一駅の東十条駅で下車し、改札を出た。何かのドラマの恋敵役が「王子にはなれないから」という理由で東十条という苗字になっていた、という豆知識を思い出す。
「東十条銀座商店街」と銘打たれた商店街には激安の肉屋から老舗の和菓子屋まで多くの店が並んでいる。老若男女が入り混じって歩き、昼前にも関わらずしっかり活気づいていた。
そんな商店街の途中で曲がり、住宅街へ。スマホには「東十条 探偵 人探し」で検索して出てきた探偵事務所の住所が地図アプリで表示されている。ホームページもあったが、事務所名と住所しか書いていない手抜きのサイトで、表示されているタブは全て「COMING SOON」となっていた。
「多分この辺りに……あった」
住宅に囲まれた、薄クリーム色の古めかしい三階建てのビル。看板も何も出ていないものの、一階の郵便受けには「須藤海 探偵事務所」と書いてある。
少しだけスマホをいじってから階段を上がり、事務所のある二階へ。昔ながらのすりガラスのはめられた茶色いドアの上部に「須藤海 探偵事務所へようこそ!」といやにポップな文字で書かれた紙が貼られていた。インターホンがあるわけでもなく、まるで高校の部室の入り口のようだ。
どうしよう、本当に探偵事務所なんだろうか。騙されていないだろうか。半信半疑でしばらくドアの前をウロウロしたものの、他に手立てはなく、半ばヤケで勢いよくドアを叩いた。
「はい! はいはーい!」
近所から回覧板を回されたくらいの軽いトーンで返事をしながら、ドアの奥からバタバタと走ってくる音がする。やがて内鍵が開き、しっかりとシワのあるワイシャツにボサボサ髪の男性が顔を出した。
身長は俺より七、八センチは確実に高い。一八〇は優に超えているだろう。全く太っている部分がなく、胸元から足下まで同じ幅のため、余計に長身に感じられる。
年齢は二十代後半くらいに見える。青縁のハーフリムのメガネをかけており理知的に見える一方、目に若干クマができているため健康的な暮らしではないようだ。
「お待たせしました、須藤海です! どうぞ中へ!」
「あ、はい……」
俺がノックした以上の勢いで案内され、俺は「ささ、どうぞ」という声に引っ張られるようにして中に入った。
事務所の中に入ると、彼は咳払いを一つして背筋を伸ばした。
「改めまして、探偵の須藤海です。ここは事務所って言っても僕一人だけでやってるから、他に探偵はいないけどね!」
「あ、よろしくお願いします……」
見た目と勢いに圧倒されていると、彼は部屋の真ん中にある大きなローテーブルを指す。
「そのソファーに座ってください。狭いところで恐縮だね!」
部屋の中央にある灰色の二人掛けソファー。その向かい合った二つのソファーの間に、ガラスのテーブルが置かれている。俺は言われた通りに前に進んで腰掛けながら、須藤海を改めて観察してみた。
やはり特徴的なのは髪と服装。もともとくせっ毛なのか、好き勝手な方向にカーブしている髪が眉や耳を覆うくらい伸びていて、身だしなみの跡は限りなくゼロに近い。服は一応ワイシャツにスーツのパンツとなっているものの、どちらもクリーニングやアイロンとは無縁の生活を送っているらしい。
そういえば、昨日話してたカップルも危なそうな外見とか言っていたな。ニコニコと屈託のない笑顔を見せているけど、余計に怖く感じるのも頷ける。
「あの……ここって事務所なんですか?」
どうぞ、とアイスコーヒーを入れたマグカップを差し出してくれた須藤さんに問いかけると、彼は不思議そうに首を傾げる。
「うん、そうだよ! どうして?」
「いや、生活感があるなあと思って」
俺の言葉に、彼は分かりやすくギクリとした表情を浮かべた。
「やっぱり分かるかな? あー、居住用には使わないでって言われてるからバレたら困るなあ! なんで分かったの?」
「なんでって、この部屋見たら……」
分からない人の方が少ないだろう、という言葉は飲み込む。その代わりに、目で伝えようと部屋中を見渡した。
普通、「狭いところで」と言われたら謙遜というパターンが多いけど、全くそんなことはなく、言葉の通り狭かった。部屋自体は1Kの造りだが、部屋の面積は俺の二五ヘーベの部屋よりだいぶ大きい。間取り的に1DKくらいあってもおかしくなさそうな広さなので、面積の問題ではなく、事務所にしては随分物が多いということだろう。
まず、角度をつけて扉のように置かれた二つの本棚。棚には学術書から漫画まで雑多な本が入っており、入り切らない雑誌は横にして入れられている。本棚の間は人が一人ギリギリ入れるくらいの隙間が空いていて、その奥には明らかにベッドのフレームが見え隠れしていた。そのベッドの上には大きなベルをつけた目覚まし時計が乗っており、どう考えてもここで寝泊まりしている証だ。
壁にくっつける形で、中学や高校の先生が職員室で使っているような、引き出しのある銀色の机が置かれている。これは多分作業スペースだろう。その机にはカセットコンロと電気ポットが乗っていて、どこで食事をしているか容易に想像がついた。
机の後ろには須藤さんの背丈くらいある棚が置かれていて、シンプルな電子レンジと小さめの炊飯器と大量の食料があり、さらにその棚の横には二つドアの小型冷蔵庫がある。机からキャスター付きの椅子ですぐに調理に移行できる便利で怠惰な仕組みだった。
反対の壁のカラーボックスの上に畳まれているタオルは明らかにバスタオルサイズ。洗濯機はなさそうだけど、天井に謎の紐が通されているのは、コインランドリーで洗った洗濯物を干すためではないだろうか。寝泊まりを通り越して、完全にこの場所で生活していることがよく分かった。
「シャワーブース付きの部屋だから、ついつい住み込んじゃって……ビル管理の田中さんには言わないでおいてね!」
「言いませんよ」
田中さんの性別も分からないまま首を横に振ると、須藤さんは安心したように胸を撫で下ろした。
「ありがとう! えっと、名前……」
「あ、俺ですか? 安西織貴です」
「織貴君ね、珍しい名前だ。よろしくね! 久しぶりの依頼人だなあ!」
手を差し出され、握手をする。すると、彼は握った手をぶんぶんと上下に振る。俺はちょっと意地悪な質問をしてみることにした。
「ちなみに、ここまでで俺のことってなんか推理できたりするんですか?」
「えっ、織貴君のこと? ううん……」
彼はジッとを俺を見た後、難しそうな表情を浮かべ、下唇を突き出したまま考え込む。
手を握ったり少し観察しただけで、相手のことが分かる。それができれば、正しく名探偵じゃないだろうか。
しかし、そんな期待を軽々と裏切って、須藤さんはあごの骨が外れそうなほど首を傾げる。
「いや……何も分からない……若手の社会人かな……?」
唯一の推理を外し、俺が「大学生です」というと「そっちか、迷ったんだよねえ!」と悔しそうに顔を歪めたが、たぶん社会人と大学生以外にはほとんど候補はないので、二択に賭けたのだろう。
最近の学生って大人っぽいねえ、と感嘆の溜息を吐き出す彼を見ながら、「この人が頼りになるのだろうか……」と不安になる。赤都の住所を推理で見つけ出すなんてあまり期待できなかった。
「あの、こんなこと言ったら失礼かもしれないですけど……須藤さんっていつ頃から探偵をやってるんですか?」
「大学院を卒業してすぐだから四年前からだね。人探しとかは得意だよ。これでも大学と大学院で心理学、特に社会心理学を修めていて……」
専門分野の解説が始まったので、話半分に聞く。とりあえず知識はあるらしいけど、心理学を学んだからって探偵になれるものでもないだろう。だとしたら卒業生はみんな事件を抱えているはずだ。
「友人を見つけてほしいんですけど……本当にできるんですか?」
「うん、結構実績あるよ。少しずつヒントを集めていけば、追えると思う。例えば……ちょっと待ってね、うまくいくか分からないけど……」
そう言うと、彼は銀色の机に腰掛ける。そして、閉じていたノートパソコンを開いて嬉しそうにキーボードを叩きだした。
「んっと……あるとすると…………あとはこっちなら……」
外が明るいからか電気をつけていない部屋で、液晶のライトに照らされて須藤さんの顔がぼわっと光る。順調に進んでいるのか、口元がニヤリと笑っている分、とても怖い。暗闇で見たら、映画の中のハッカー役のようになるだろう。
「……よし、多分これだ!」
そして見せてくれたのが、俺のアカウントだった。
■◇■
「なんか……ストーカーみたいじゃないですか」
「ええっ!」
回想を終え、驚嘆の表情を見せる須藤さんをまじまじと見る。よく考えると、ストーカイという名前もどこかストーカーを思い起こさせる。
「待って待って、織貴君! 確かに僕はネットストーキングの技術を駆使して調査してるよ。でもこれはあくまで技術だから! 包丁もちゃんと使えば便利でしょ」
「まあ、それはそうですけど」
「僕はストーカーじゃないよ。相手のことが気になるだけだから。気になる人の情報がネットに転がってるなら、全部知りたいって思うのが当然だろ?」
「その発想がストーカーそのものじゃないですか!」
なんだろう、ちょっとヤバい探偵に当たってしまった気がする。
「ちなみに、そんな技術どこで身に付けたんですか? 実践……?」
「だから、僕はストーカーじゃない、須藤海だ!」
名前が似ていることは本人もちゃんと分かっているらしい。彼は座ったまま腰を捻り、後ろにある本棚を指差した。
「社会心理学を専攻してたってさっき話したけど、社会心理学って大学で触れてる?」
「社会学部なんですけど心理学系はあんまり取ってないですね……一年生の時に概論だけ受けました」
「そっか。社会心理学っていうのは、簡単に言えば社会の中で個人の思考や感情や行動がどんな影響を受けるかを研究する学問なんだよね。僕が専門的に研究していたテーマはSNSなんだ。SNSも今や一つの社会だからね」
SNSだけで繋がっている人もいるし、友人で趣味仲間とオンラインで飲み会を開催した人もいる。確かに、現実世界とは違う社会が構築されていると言っても過言ではないだろう。
「で、そこでネットストーキングってのを知ったわけ。それで学びの一環で友人をターゲットにしてやったら住所をほぼ特定できた。資質があったんだろうね」
「一発目でそこまでできるって……」
須藤さんは嬉しそうに「どうも」と目を細めた。別に褒めたわけではない。
「で、もともと博士課程まで進む気はなかったし、ネットストーキングをプラスの方向に使えたら面白いと思って、探偵を始めたんだよね。いつの間にか四年経って二八か、すっかりアラサーだよ。まあ、僕も背景を伝えたところで!」
ガラスのテーブルにドンッと手を付く須藤さん。メガネの奥の瞳が、難事件を求める探偵もかくや、輝いている。
「依頼、してもらえるのかな?」
俺は逡巡していた。表情にも出ていたかもしれない。どんな理由であれ、相手の知られたくことをネットで詮索するなんて褒められたことではない。高校時代を思い出ると、口の中に嫌な味の唾液が溜まった。
でも、他に頼める相手もいない。新しい探偵を見つける時間も勿体ない。何より、赤都を探すにあたって、少なくとも能力的には、これ以上の適任はいないと思えた。
「……よろしくお願いします」
俺の返事を聞いて、彼はカツンとガラスの机を指で弾く。そして、何かのスイッチが入ったかのように不敵な笑みを浮かべた。
「契約成立、よろしくね」
十月七日、金曜日。俺は初めて、謎解きを依頼した。相手は、俺のアカウントを見つけた、ストーカーのようでストーカーじゃない探偵。
「ふむふむ、北藤赤都君ね。今週から連絡が取れない、と」
「そうなんです。家にもいないし、電話にも出なくて……」
ばたばたと手書きで契約書にサインさせられた後、俺の話を聞きつつ彼はカタカタと打鍵してパソコンにメモを残していく。
なんとなく名探偵や刑事は紙のメモを書くイメージだったけど、俺がホームズやポアロのような古典推理小説を読んでいたからだろう。授業のメモをパソコンで取るように、時代はとっくにデジタルに移行している。
「……考えすぎですかね?」
胸に秘めていた不安を吐露する。どんな返事が来るのか、緊張で心音が増す。
「いや、そんなことはないよ」
擦り傷を放っておけば治ると言うように、彼はケロリと返した。
「頻繁に連絡取り合ってた仲なんでしょ? 急な用があったとしても、一言も送ってこないのはおかしいもんね。何か事件を疑うのは当然だと思うよ」
胸がグッと開いた気になり、息がしっかり吸える。「そんなに心配しないで大丈夫だよ」と言ってもらいたかった気もするけど、俺に同調してもらえることが嬉しかった。
「じゃあ早速調べていくかな。織貴君は北藤君とSNSとかで繋がってる?」
「いえ、繋がってないです。だからアカウントも知らないんですよね」
「じゃあそこからだね。検索してみよう。あ、織貴君、ご飯食べたりしてきてもいいよ」
時計を見ると十一時半前。確かにお昼の時間ではあるけど、そこまでお腹は減っていない。
「いえ、まだ大丈夫です。あ、でも須藤さんも行きますかね?」
「ああ、いや。集中して仕事したいから、適当にあるもの食べるよ」
そう言って棚に目を遣る。インスタントの食料がたくさん並んでいて、確かに外出する必要はなさそうだ。
「好きに食べに行ってね。時間かかるかもしれないから帰ってもいいよって言いたいところだけど、何かあったときにすぐ確認できるようにはしておきたいからね。あそこの本、自由に読んでていいよ。漫画は名作揃い!」
言いながら、彼はノートパソコンを持って銀色の机に戻る。俺は促されるままに本棚に行き、見たこともない全三巻の漫画「監視カレシ」を借りてソファーで読み始めた。
微糖のアイスコーヒーに口をつけながら読んでいると、キータッチの音に混じって、不思議な音が聞こえてきた。
ボリ……ボリボリ……
思わず音の発信源である須藤さんの方を見ると、彼は小皿に盛った茶色い粒上の何かをティースプーンで掬って食べていた。気になって、近くへ寄ってみる。何かの結晶のような、薄茶色の食べ物。
「あの……」
「ん? どうしたの? 一口食べる?」
「何ですか、それ?」
お皿ごと差し出した彼に尋ねると、彼は得意げに説明を始めた。
「よくフィクションの世界では、推理中にコーラやキャンディーを口にする探偵がいる。糖分は頭脳労働には大事だからね。でもコーラなんか常備するのも大変だし、総じて高い。案件の少ない貧乏探偵には避けたい商品だ。そこで、僕はもっと安価に、そしてダイレクトに補給しているというわけさ」
一息でそこまで話すと、またその粒を頬張り、ポリポリと音を立てて噛む。
「で、それは何ですか?」
「ふっふっふ、ザラメだよ」
「ザラメ……?」
わたあめを作るときに入れる、あの?
「砂糖を直接食べれば糖分は完璧。お腹も空かないし心地いい食感もあるし、何より安い。織貴君も試験勉強のお供にオススメだよ」
世紀の大発明のように誇らしげな表情を浮かべているけど、俺からすると変人認定の度合いが増しただけだった。砂糖を直接食べる探偵、なんて憧れにくいのだろう。
「そういえば、北藤君は昔部活か何か入ってた?」
「はい、高校時代はサッカー部でした」
「ふむふむ、それは良いヒントだね」
須藤さんは嬉しそうに視線を画面に戻す。どんなことをしているのか、興味をそそられて覗き込んでみると、それに気付いた彼は覗き見防止フィルターを外してくれた。「そこにあるの使って」と促され、黒い丸スツールに座る。
「まずは出身地を調べよう」
「できるんですか?」
「運動部なら比較的ね。個人競技の方が出やすいけど……」
そう言って彼は「北藤赤都 サッカー」と打ち込み、検索結果を何ページも見ていく。普段自分で検索するときは大抵最初の数個しか見ないので、こんなにページを送ってチェックしていくのを見るのは貴重な体験だった。
「ああ、ほら! 静岡の浜松出身らしい」
嬉々として俺の方を向き、画面を指差す。
出てきたのは、静岡の地域ニュースをまとめたWEB新聞。中学サッカーの地区大会の結果がずらっと出てきている。そのページの途中に、選手名として赤都の名前が表示されていた。
「この名前は珍しいし、掲載年を見るとたぶん年齢もドンピシャだろうね。大会がある部活は、人数が多い合唱や吹奏だと個人名まで出ることは少ないんだけど、サッカーや野球なら大抵地域の記事が出てきて出身県が分かる。勉強になったね、織貴君!」
「知識の使いどころがないですね……」
いかにも生活に役立つ豆知識を授けてくれたようなテンションだけど、あまり身に着けたくない知識で、俺は愛想笑いを顔に貼り付けた。
「さて、出身が分かったら……」
今度はTweeterで「赤都 静岡」「あかと 浜松」といった単語の組み合わせを幾つも試して検索していく。アカウントを調べようとしているらしい。
「ううん、大学生なら地方から来たってことで出身県を書いてることが多いと思うんだけどなあ。大学名も入れてみるか」
七、八分検索してもそれらしきものは出てこない。小さく嘆息する須藤さんに、俺はおそるおそる話しかけた。
「あの……水を差すようで悪いんですけど、赤都がTweeterやってるとは限らなくないですか?」
すると、彼はあっけらかんとした態度で「うん」と首肯する。くるくるの髪が、同調するようにファサッと揺れた。
「うん、限らないよ? でもいるかもしれないでしょ? だから探してるのさ。気になる人のことだしね」
「気になる人って……」
「気になるよ。友達にも黙って、理由も告げずにどっかに行ってしまった男子大学生。こんなに興味を惹かれるターゲットいないでしょ!」
メガネの奥で目をキラキラさせる須藤さん。どうやら彼の「気になる」のアンテナは相当広いらしい。有名人じゃなくても見目麗しくなくても、自分の好奇心の網に引っかかったらどこまでも追跡しそうだ。
「でも……検索って無限にパターンありますよね。どこまでやったら止めるんですか? 百回検索したら、とか?」
その質問に、こっちを向いた彼はきょとんとする。そして、子どもに諭すように目を細めた優しい表情になって、首を振った。
「自分の気が済むまで、諦めがつくまで、かな」
「それじゃ何時間も——」
「何時間もかかることもあるよ」
彼は椅子に深く座り、回転させて体を九十度横に向ける。そして右手の人差し指を立てた。
「例えば、織貴君に五歳くらいの、大事な子どもがいたとしよう。想像するのが難しかったら年の離れた弟や妹でもいい。その子がデパートの一階で迷子になった。上に行ったかもしれないし、エントランスを出て街に出てしまったかもしれない。どこまでやったら探すのを止める?」
「それは……もう一日中でも」
「同じことだよ」
開けていた窓から風が吹き込む。前髪が綺麗に分かれて、本当に一瞬だけ、彼がカッコよく見えた。
「ネットの中は現実の一部というには大きくなりすぎた。完全にもう一つの現実、巨大な社会だ。見つからないかもしれない、でも見つかる可能性もある。別のヒントに出会える可能性もある。迷子より探す場所は広いかもしれないけど、迷子と違って動かないからある意味見つけやすいかもしれないよ」
屁理屈にも思えたけど、どこか説得力がある。本当に探したいものは、どれだけ時間をかけても探さないといけない。探偵としてのその覚悟も、彼が赤都をそう捉えていることも、心強かった。
「さて、じゃあ赤都君を探そうかな! ネットの海で必ず君を捕まえてみせるからね!」
「せっかく良いこと言ってたのに……」
よれよれのシャツを腕まくりし、ザラメをボリッと砕きながら意気揚々と検索に戻る須藤さん。やっぱりこの人、かなりの変人だ。
「んー、これでもないとすると……案外こっちか……?」
ブツブツ言いながらパソコンに向かう。ソファーに戻ろうかとも思ったけど、何かまた新しい発見を教えてくれそうな気がしたので、スツールから動かないまま、彼の独り言をBGMに漫画の続きを読み始めた。
十数分経っただろうか。間もなく「監視カレシ」一巻が読み終わるというところで、彼は突然パチンと指を鳴らした。
「見つけた!」
「ホントですか!」
前屈みになり、須藤さんの横から液晶を見る。名前をもじったらしい「アッカード」というアカウントが映っていた。フォローもフォロワーも1000を超えていて、結構積極的に使っているらしい。自己紹介欄には、好きなものが並んで記されている。
「サッカー、東京、大学生って感じのキーワードだと、サッカー部の公式アカウントやら無限に候補が出てくるね。静岡のサッカークラブを幾つか入れてやっと見つけたよ。地元にクラブが多ければ、どこかのファンになってるんじゃないかと思ってさ」
初めて赤都のアカウントを目の当たりにし、彼のことをほとんど知らなかったのだと思い知らされる。しょっちゅう話していたし、海外リーグの話題はよく出ていたけど、地元のチームが好きだなんて初めて知った。きっとここには俺の知らない赤都のことがたくさん記されているのだろう。ひょっとしたら俺の悪口が書かれてるかもしれない、と思うと幾許かの不安が胸に去来した。
「とりあえずこれで何かヒントが出てきますかね?」
俺の質問が聞こえてるはずなのに、彼はジッと画面を見つめて、ツイート画面をスクロールしている。やがて、口を窄めてふうと息を吐いた。
「……裏アカ持ってるかもね」
▼ 第1章 後編
▼ もくじ
第1章 前編 https://note.com/rokujo_noel/n/n82224ba9a5e3
第1章 後編 https://note.com/rokujo_noel/n/nfcb676e6b87a
第2章 前編 https://note.com/rokujo_noel/n/nc7a327253212
第2章 後編 https://note.com/rokujo_noel/n/nd94f247a7cff
第3章 前編 https://note.com/rokujo_noel/n/nb62b81875fbb
第3章 後編 https://note.com/rokujo_noel/n/n3006b1d2ae3f
第4章 前編 https://note.com/rokujo_noel/n/n6acfe19aa003
第4章 後編 https://note.com/rokujo_noel/n/n2565f8de0fd7
※ページ上部の画像はデザイナー黒井澪さん(https://twitter.com/kuro_kuro_kuroi)の作品となります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
