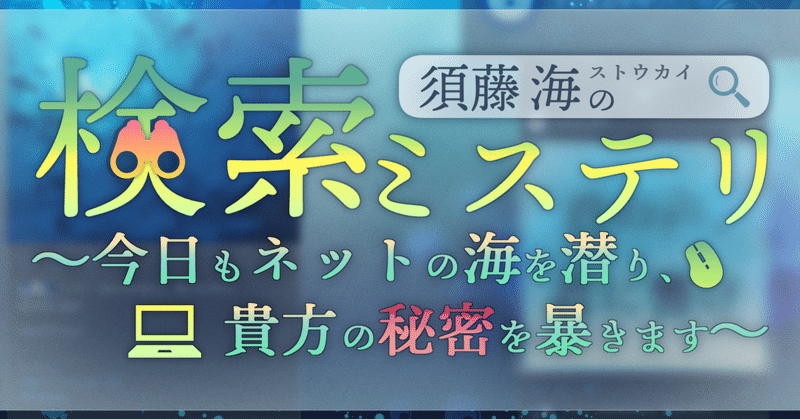
須藤海の検索ミステリ 第2章 元カレはどこに(前編)
「今日は全体的に気温が下がり、上着無しではかなり寒い一日になるでしょう」
テレビ画面の右上に「十月一七日(月)」と表示され、なんとなく年末が近づいてきた感じがする。あまり食欲がなかったので、食パンにバターを塗り、その上にふりかけをかけてもしゃもしゃと食べた。実家でよくやっていた食べ方だ。
「SNSをきっかけに相手の住所を知った男性が……」
今日も物騒なニュースをやっている。なんとなく、もじゃもじゃな髪の探偵を思い浮かべながら、薄出のダウンジャケットを着て部屋を出た。
「うわっ、寒……」
独り言を漏らしながら歩く。気温も低いけど、吹きつける風が冷たい。木々も相当に寒いのか、涙の代わりに葉を落とし、悲しげにワサワサと音を立てた。何日も雨が降っていないアスファルトは乾ききっていて、小石を蹴るとカツンと軽い音を立てて転がっていく。
王子駅に着き、JR京浜東北線から一駅、東十条駅で降りる。九時前だとまだ店は開いていないものの、ラーメン屋や定食屋が並ぶ店の前は、昼前の賑わいを予想させた。
商店街の途中で曲がり、住宅エリアに進む。白い戸建てや茶色い低層マンションが多い中で異彩を放つ、薄クリーム色の三階建てのビル。階段を上って二回に行き、すりガラスの造りの古い茶色のドアの前に立つ。「須藤海 探偵事務所へようこそ!」と手書きされた紙を見ながら、ノックをした。
「海さん、おはようございます」
返事がない。困った。ノックし続けるしかないのかとドアノブに手をかけてみると、何と鍵が開いている。そのまま暗い部屋に入ると、そこには人間が活動している気配はなかった。
部屋の奥、扉のように配置された本棚の奥にベッドがある。そろりそろりとそこまで行ってみると、毛布を被り、丸まって寝ている探偵の姿があった。
「海さん! 事務所開ける時間ですよ!」
「ううん……はぁい……」
空気の漏れたような声を出しながら、寝返りを打ちつつ目を覚ます海さん。枕の横に置かれたメガネをかけ、むくりと起き上がってブラウンの遮光カーテンを開けた。
「おはよう、オル君。気持ちの良い朝だね」
「それを言うには大分遅いですけどね」
長袖にトレーナーで寝ていた海さんを追い立てると、のそのそと起き上がって洗面所で顔を洗い、干してあったワイシャツに着替えた。
「そういえば、鍵開いてましたけど」
「ああ、ちょっと事件の捜査で遅くなったから、開けておいたんだ。泥棒に入られても大して盗られるものはないし、それならオル君が来て起こしてくれるギリギリまで寝られるメリットを取りたいと思ってね」
なぜか自慢げに語る海さん。自分の判断を褒めてほしいようだけど、起きられない時間までやってる方が問題だと思う。
「朝食……はまだお腹空いてないからいいか。じゃあオル君、今日も一日よろしくね!」
「はい、先に食器戻しちゃいますね」
昨日夜食で食べたらしい冷凍シューマイの袋と小皿と箸を戻しながら、俺は散らかった部屋を見て小さくため息をついた。
先週からこの事務所のアシスタントとしてアルバイトを始めた。基本的に土日は入らないシフトで、授業のない月曜と金曜は朝から夕方まで、授業のある火曜から木曜までのどこかで一日、数時間入るという形で働く予定。 アシスタントといっても推理を手伝うのがメインではなく、雑務が中心だ。
「あ、ちょっとお腹減ってきたかも。オル君、カレンダー見てくれる? 今日午前って来客入ってないよね?」
大して予定の入っていない卓上カレンダーを見ながら「大丈夫です」と答えると、彼は「簡単にご飯にするか」と言って水を張った片手鍋をカセットコンロの火にかけた。
料理をするとは意外だ。てっきり、チンしたご飯で卵ご飯とか、お茶漬けとか、そんな感じにすると思っていたから。
海さんは、二ドアの小さな冷蔵庫からもやしを取り出し、沸いたらしい鍋にガサッと入れる。そして数分後、そのお湯を洗面所に流し、普段依頼主との応対に使っている机の上に置いて、ソファーにゆっくり座った。
「いただきます」
ポン酢をかける音の後、事務所内にもしゃもしゃという音が響き渡る。
「あの、海さん、それは……?」
「ん? 野菜を摂った方がいいと思ってさ。これと野菜ジュースのコンボだね。一口いる?」
「いえ、いりません」
こんな「雑な男子大学生がそのままオトナになりました」という感じでよく生活できているな、と思いながら俺は掃除に戻った。
雑務、といっても仕事が多いわけではないので、掃除や紙類の整理が中心だ。海さんが壊滅的にそういったことが苦手らしく、金曜に片づけても月曜になると元に戻っている。
「あ、オル君、次はファイルの整理をお願いできるかな」
「分かりました……って、あっ! またファイル戻してないじゃないですか!」
「戻すのが苦手なんだよね。『いつかまた使うから』って置いておいちゃう」
そういうことをしてるから散らかるんだ、と思いながら、過去の依頼をまとめた資料を棚に戻していく。
依頼は週に一、二度らしい。短時間で終わる簡単な依頼もあれば、俺が赤都の件を依頼したときのように一日以上使うケースもあると言っていた。
「海さん、こことは別に自宅も借りてるんですか?」
「いや、解約したよ。この辺りの事務所は家賃も二十万近いからね、二重に払うのはちょっと厳しいよ」
「なるほど、確かにそれはちょっと……でもそしたら結構儲かってるんですね」
「いやいや、ネットで受け付ける仕事は安いしね。年を取ると色々入り用だし、贅沢はしないで暮らしてるよ」
それにしたって限度があるだろう。あまり心配になるような生活はしないでほしい。
「よし、仕事を始めよう!」
鍋を洗面所で洗い、サッとタオルで拭いて食器と食材が並ぶ棚に戻す。そして縦長のタッパーから茶色いものが入った袋を取り出し、小皿にじゃじゃっと開けた。すっかり見慣れたわたあめの原料、ザラメだ。
「といっても一件しかないなあ。はあ、もっと捜査がしたい! 何でもいいから興味のある誰かの何かを特定したい!」
「無差別ストーカーみたいな発言やめてください」
とんでもないことを口にしつつ、ザラメをぼりぼり頬張りながらパソコンを開く海さん。一通りの掃除を終えた俺に、彼は「それを使って」と座っている机の奥を指した。自分が使っているものより一回り大きいノートパソコンが置かれている。
「ホームページ、頼むね! ツールは入ってるから!」
「自信ないですけどね……」
先週末に言われていた依頼の一つが、このホームページ制作だった。俺が調べたときも、事務所名しか書いておらず全てのタブがCOMING SOONとなっており、完全に外側だけ作ったサイトだった。
起動すると、制作ツールが入っていて、テンプレートを利用した作りかけのサイトが出てきた。ふむふむ、基本的にはここでタブごとのページを作りこんだうえでリンクを取得して、そのリンクを埋め込んでいけば良いってことか。
「解決例紹介のページがあるでしょ? そこにこれをうまくまとめて入れてほしいんだよね」
そう言って彼から渡されたのはUSBメモリだった。中には文書ファイルが入っている。
『二十代男性の例
依頼:挨拶も手紙もなく、ある日一方的に出て行った彼女がどこにいるか探してほしい
捜査:まずは氏名や出身地をもとに、彼女のTweeterアカウントを発見しました。全ての画像をチェックし、見切れて映っていたレストランから都内にいることを確認。さらに動画に映っていた駅から沿線を把握し、ツイートを一件一件根気よく探すことで、駅前の特徴をもとに遂に最寄り駅を発見しました。
帰るときに使用している出口まで把握できたため、それを依頼主に共有、無事に会うことができたようです。ちょっとした誤解から彼女が身を引いたことが分かり、見事に復縁することができました』
「何ですかこれ……?」
「何って? 事件の解決例紹介だよ?」
「危なすぎて書けませんよこんなの」
アカウントを発見してじっくり見てることを公にしてどうする気なんだ。
「これ完全にストーカーじゃないですか!」
「だからオル君、ストーカーじゃないって! ストーカーっていうのは特定の人につきまとう人のことを指すんだよ? 僕は毎回違う人に張り付いてるんだから全く当てはまらないじゃないか!」
「そういう話ではないのでは……」
ダメだ、海さんは完全に自分を普通の人間だと思ってる。普通の人間はツイートを一件一件根気よく探したりしない。
「うまくボカしていいからね」
「ボカしたらほとんど内容なくなりますよ」
法に触れなそうな言い回しはないか考えながら、ゆったりとした時間が過ぎていく。それは、これから始まる事件の前の、束の間の静けさだった。
「さて、依頼を一件仕上げるか」
「依頼来てるんですか?」
正直なところ全く流行ってなさそうなこの事務所で依頼があることに改めて驚いてしまう。
「まあ僕個人に来てるわけじゃなくて、ネット上で請け負ってるんだけどね。スキルの提供サービスみたいなのあるでしょ?」
「ああ、最近結構ありますね」
描きたい絵や書きたい文があるのにできない人や、ビラのデザインを得意な人に頼みたい人が、サイト上で得意な人を見つけて発注できるサービス。海さんもそこに登録してるらしい。
「ほら、これだよ。『人探し、できます』細かいことは伏せてるけど、困ってる人はここで依頼をしてくれるからね」
「でもこれ、犯罪とかに悪用されませんか? 逃げた人の行き先が知りたい、みたいな」
「オル君、僕だって探偵の端くれだよ? オンライン打ち合わせで詳細な話を聞くときに大体見破れるよ!」
「ホントかなあ……」
任せてよ、と上機嫌に言いながら、彼はザラメを食べつつダウンロードした写真を開く。そこには、てっぺんまで見えないスカイツリーをバックに男性がピースをしていた。
「今回は、この写真をもとに、このとき彼がいたところを推理するだけだからね。大まかにさえ分かれば十分でむしろスピードが大事だっていうから、そんなに難しくはないよ」
「でも、スカイツリーってどこでも見えますよね。逆に難しくないですか?」
「そんなことないよ、ほら、ここ見てごらん」
画像を拡大した彼が、地面のマンホールを指差す。三角形の中心からそれぞれの辺の真ん中を通るように線が伸びているマークが、フタの中心に配置されている。
「マンホールの模様ってのは町ごとに違うし、東京なら区ごとに違う。そのマークは墨田区の区章だよ。これで大まかなエリアは分かった。あとはヒントはちょっと見切れて映ってる茶色のマンションくらいだね」
「ストリートビューでこのビルが見えるところを探すんですか?」
「おっ、オル君惜しい。確かにその手もなくはないけど、かなり骨が折れるから最後の手段だね。これは観光で来て撮ってるんだろうから駅から極端に離れたところにはいないはず。そういう前提で、駅近くの物件を調べていこう」
そう言って分譲マンションの検索サイトを開いた海さんは、条件欄に最寄り駅や駅からの徒歩時間を入れていく。手際の良さで、よくやっていることが窺えた。
「最寄り駅から徒歩一五分以内のマンションを調べれば、もし空きがあれば外観の写真付きで出てくる。そこで物件の住所が分かるから、場所を探す大きな材料になるね。これは高層マンションっぽいから、高層階は分譲、低層階は賃貸みたいな構図になってるパターンが多い。分譲と賃貸の両方で検索を進めていくよ」
言い切ると同時に「この条件で検索」というボタンを押すと、マンションの一覧が表示された。
「すごい……」
そのアイディアに、思わず唸ってしまう。なるほど、確かにマンションならサイトで見つける方が早い。俺が想像できないだけで、まだまだ特定できる方法はたくさんありそうだ。
「あったあった、東武線の曳舟駅に近いマンションだ! あとはストリートビューで絞り込めるぞ!」
そして、ネットストーキングはやっぱり使い方によってはとても恐ろしいと再認識する。ついつい昔を思い出してしまって、結局捕まらなかった犯人もこんな風に調べていたのか、と背筋がヒヤリと寒くなった。
海さんは事務所で済ませるというので、外の牛丼チェーンにお昼を食べに行く。戻ってきてからはなぜかさっきのストリートビューの手伝いをさせられ、カチカチと何百回もクリックして写真と同じ構図を探すことになった。
途中からすっかり飽きてモチベーションが下がってしまったので、こういう作業を嬉々として続けられる海さんを尊敬してしまう。
そして夕方、海さんは時折メガネを外し、よく効きそうな赤い目薬を差して悲鳴をあげながら、相変わらずパソコンの画面を食い入るように見つめている。例のスキルのサイトで、自分ができそうな依頼に対して「解決できますよ!」と売り込んでいるらしい。
「はあ、最近はまともな事件にはめっきりお目にかかれなくなったよ。せっかく僕ほどのスキルを備えていながら、職業のうえではあまり役にも立っていない」
「ホームズで聞いたようなセリフですね」
組んだ両手を頭を後ろにあてて椅子に寄り掛かった海さんに返事をすると、彼は驚きと喜びを交えた表情で首から上をクッとこちらに曲げた。
「正解! 『緋色の研究』の一部をいじってみたんだ。オル君も結構読んでるんだ」
「はい、読書は小学校の頃にホームズから入りました」
「ふっふっふ、じゃあその憧れの探偵と一緒に仕事できるなんて嬉しいことだね」
ザラメをガジャガジャと口の中に放りながら楽しげに目線を画面に戻す。推理力のほどはともかく、ホームズと同じくらい変人ということには間違いない。
「暗くなってきたな」
独り言を漏らし、そろそろ帰ろうかと思って時計をチラチラと見る。間もなく終了時間の十七時になろうとしていた。その長針が十二に差し掛かる直前、ドアに鈍いノックのゴンゴンと音が響く。
「依頼だ!」
母親が買い物から戻ってきたのを「ご飯が帰ってきた」と出迎える子どものように、海さんは座っていた椅子から慌てて降り、駆け出してドアに向かう。
ガチャリと開けると、そこには女性が立っていた。
二十代前半から半ばくらいだろうか。髪はキャラメルのようなかなり明るい茶色で、ウェーブしているミディアムヘア。白いブラウスにファーのついたピンクのジャケット、チェックのロングスカートにヒール高めの黒いシューズ。かなりオシャレが好きそうに見える。顔は結構メイクが濃くて、ぱっちりした目にバチバチのまつ毛が印象的だった。
「すみませんね、チャイムもなくて。改めて、須藤海探偵事務所の唯一の探偵、須藤海です!」
名前と探偵を連呼するまどろっこしい自己紹介を終えると、彼女は首だけ会釈し、気怠そうな声で挨拶した。
「こんばんはあ。あのお、ここって人探しもやってるって聞いたんですけど……」
「やってますよ。どんな相手も見つけてみせます。もし実力に不安があるようでしたら、少しお時間とヒント頂ければ、あなたのアカウントも見つけてみせます!」
「あーいや、それはちょっと」
相手が思いっきり苦笑しているし、なんなら軽くヒいている。完全にアピールミスだと思う。
「それで、一体どなたを探してほしいんですか?」
「えっとお、付き合ってた彼氏が逃げたんで、探してほしいんですよね」
俺は改めて理解する。わざわざこんな探偵事務所に依頼しに来るのは、二週間前の俺のように頼れる人がいないときか、こういう複雑そうなケースなのだ。
叶野咲菜と名乗った彼女は、ソファーに座り、依頼のための調査概要票に記載していく。二五歳、アパレルでアルバイトをしているらしい。
「では叶野さん、事件について話してもらえますか?」
海さんがメガネをくいっと持ち上げた。かなり探偵モードに入っているけど、事件と呼ぶほど大きなものではなさそうな気がする。
「えっとお……」
どこか眠気を誘うような声を出しつつ、彼女は顎の下に、摘まむような形の指を置いて話し始める。
「彼は天草虎月君っていうんですよ」
「芸名みたいですね」
「あ、そうなんです。芸名っていうか、まあハンドルネームですよね。めっちゃ声がいいんで、音声配信とかでネットラジオみたいなのやってるんです。別に事務所に所属してるとかではないんですけど」
咲菜さんと相対する形で二人掛けソファーに座っていると、隣で海さんがカタカタとパソコンを打ち、検索をかける。天草虎月、フォロワーは二千人程いて、本人も「イケボの人」と書いている。
彼女の言う通り、事務所に所属しているわけではなく、別に声優になりたいわけでもなく、ネットラジオやカラオケ放送を定期的に配信しているらしい。顔を出さない形でもこんな風にファンがつけば、誕生日に欲しいものをプレゼントされたり、投げ銭の形でお金を貰えたりと、ちょっとした副業にはなると聞いたことがある。
「立ち入った質問をしてしまってすみません。咲菜さんは虎月さんといつごろからお付き合いしてたんですか?」
「んーーっと、一年前くらいからですね。虎月君はそのときはまだ全然フォロワー数も多くなくて、私はたまたま聞いてファンになった感じでした。おじさんが地下アイドルに恋するみたいな感じですかね」
冗談っぽく言った後、「それでえ」と彼女は続ける。
「配信には毎回行ってたんで、名前覚えてもらってたんですよね。それでだんだんDMとかするようになって……で、通話アプリで話したり、東京に住んでるっていうから会うようになったりしてアタシの方から告白したって感じです。それで、順調に付き合ってたんですけど八月頭に引っ越したらしくて……引っ越し先の住所を教えてくれなかったんですよ!」
急に叫びだす咲菜さん。相当悔しかったのか、だいぶ感情的になっている。
「それで依頼に来たってことですね。すみません、僕から何点か質問させてください。虎月さんに連絡はつかないんですか?」
「つかないんです。ブロックされちゃってて。電話も着信拒否状態です」
「なるほど。立ち入った質問ですが……別れた原因というのは考えられますか?」
その質問に、彼女は一瞬黙り込んだものの、決意したようにフッと短く息を吐いて俺たち二人に向き直る。
「ケンカとかは無かったです。ただ……結構お金を貸してたんですよねえ。配信のためにマイクとかの機材買うって言うので、ちょこちょこバイト代渡してて。だから……ひょっとしたら……」
「持ち逃げされた、って可能性があると」
咲菜さんは黙ったまま、コクンと頷いた。これはかなりダメな彼氏のようだ。
「見つけて復縁したいんですか?」
「いえ、復縁とかは別にいいです。別に無理に付き合わなくてもいい。私よりお金が大事だったってことだと思うんで。でも、五、六十万貸していたので、そこだけはきっちりしたいなと思ってます……」
背中を小さく丸め、スンと小さく鼻を啜る咲菜さん。お金を貸した挙句逃げられて、連絡もつかない。ほぼ詐欺同然の扱いを受けたら、ここまで萎れてしまう気持ちもよく分かる。
「分かりました。でも、住所の特定はかなり時間がかかると思います。長期戦になるかもしれませんけど……」
「あ、いえ、そこまで細かくやらなくてもいいです。最寄駅さえ分かれば、と思ってました。頻繁に行けばいつか会えると思うので」
海さんに向けて、咲菜さんは右手を振って否定する。
「分かりました。一応、推理内容とかも説明したいので、一番初めは咲菜さんと一緒に最寄駅に行く形でいいですか? 現場に行って最終的に検証できることもあるかもしれないですし」
海さんの説明に、咲菜さんは「そんな、いいですよ!」とオーバーなくらい手を振る。
「申し訳ないんで、アタシ一人で会いに行きます。推理が違ってたら、それはそれで仕方ないと思いますし。もし会えたとしても、お金を返してもらって、今までありがとうってお礼が言えれば、それで充分です」
「そうですか、分かりました。では、これから捜査に入っていくので、先に契約を進めましょう」
海さんは隣に積んでいたファイルをサッと取り出し、契約書の紙を華麗に取り出す。ちなみにアレは今日の日中、俺が「また出しっぱなし」と言いながらしまったものだ。
「ここに料金の説明があるので、確認のうえサインお願いします。金額の限度があるようでしたら先にお伝え頂ければ、その金額でできる範囲でご支援しますね」
この事務所では、依頼料は基本料金に加えて、作業量に応じて追加料金を加算することになっている。調べるものが多かったり見つけにくかったりすればそれだけ捜査に時間がかかるので、そういう場合には金額も増えていく、という仕組みだ。ただ、依頼人からすれば青天井に見えてしまうので、海さんがやっているように上限がある場合には先に教えてもらうのは良い配慮だと思う。
「じゃあこれでお願いします。お金の上限とかはあんま気にしてないので、できる限り探してもらえると嬉しいです」
そう言って咲菜さんは、ボールペンで契約書に丸文字のサインを書いた。
「では早速調べていくので、虎月さんのアカウントを教えてもらってもいいですか?」
「あ、はい、んっとお……これです」
スマホを数回タップして、彼女は画面を見せてくれる。絵ですごく美化されたイケメンのアイコンが特徴的なトップ画面だった。
「ここにツイートキャスのリンクがあって、そこから過去の配信のアーカイブに飛べるんで」
「ありがとう、アーカイブがあれば色々材料は見つかりそうですね」
探偵は嬉しそうに揺れ、連動してもさもさの髪がふわふわと跳ね回った。ツイートキャスって何だっけ。聞いたことある気がする。あとで聞いてみよう。
「後は……咲菜さんのアカウントも教えてもらえませんか?」
「え、アタシのも!」
帰り支度をしていた彼女は、バッグを開いたまま、やや驚いた様子でこちらを振り向く。
「何かあったときに連絡しやすいなと思って。メールとか電話のメッセージよりDMの方がいいですよね?」
「あー、確かに。分かりました、ごめんなさい、ちょっと急ぎで出ないといけなくて、後でメールに送ってもいいです?」
「大丈夫ですよ、名刺にアドレス書いてあるので」
机に置いていた名刺をサッと渡すと、彼女は急いでそれを財布にしまい、手持ちカバンを持って「ありがとうございましたあ」と足早に出て行った。
「いやあ、新居は今のところ何の手がかりもないのが怖いところだね」
「確かに、日本全国どこでもあり得るって難しいですね……」
何か手がかりを見つけなければ、捜査は全く進まないだろう。
「お金を借りたまま一方的に別れた彼氏、これは興味深い。関心がある人のことは全部知りたくなるね、なんとしても突き止めなきゃ!」
相変わらずさらりとストーカーのようなことを言う海さん。でも、それが冗談ではなく本気だということも、ちゃんと分かっている。
きっと彼は本当に興味のアンテナが広くて、人間そのものへの関心が深い。警察じゃなくて探偵事務所に依頼に来るなんて、いなくなった人も探してる人もそれなりの事情や理由があって、だからこそそこに惹かれて捜査をしているのだと思う。じゃなければ、アカウントを一件一件チェックするような単純で退屈な作業にあそこまで全力では取り組めないだろう。
「オル君、もう帰っていいけど、どうする?」
「……少しだけ話聞いていきます」
そしてまた俺も、少しだけ興味が感染った人間の一人だ。
十八時を過ぎ、少しずつ外が暗くなってきた。十七時になると真っ暗で外で遊べなくなる冬にはまだ遠いものの、夏が完全に終わってしまったことを空から降りてきた紫の闇が告げる。事務所に流れ込む風が冷気をまとっていて、俺は急いで二ヶ所の窓を閉めた。
「まずは虎月君のツイートを見てみようか」
海さんの横で液晶画面を見ながら、行方をくらませた天草虎月さんのTweeterページを覗いてみる。何か住所や駅が分かるヒントのようなものがあれば、そこから推理を進められるだろう。しかし。
「ううん、見事に何もないね」
「そう、ですね」
出てくるのは「パスタ食べたい」「ライブ行きたいなあ」「冷蔵庫にプリンが入ってると思ったのに入ってなかった」といった日常のツイートばかり。写真も景色を撮ったものはほとんどなく、食べた料理や飲んだお酒、街で見つけた面白ガチャなどのアップが並んでいる。自撮りが全くないのは、声を中心に活動しているからだろう。イケメンアイコンのイメージを崩したくないのかもしれない。
「たまに告知してるのはネットラジオのお知らせか。日常ツイートしかしない人なんですかね」
「そうだね、あるいは意図的に場所が特定される内容を伏せているのか」
口に手を当てながら海さんはボソリと呟く。全く気付かなかったけど、急に姿を消したということであれば彼の説も頷ける。
最後までスクロールすると、妙なことに気付いた。
「あれ、海さん、九月からのツイートしかないですよ? 最近始めたんですかね?」
「いや、利用開始は三年以上前だ。人のツイートを見るためだけに使っていたか、あるいは……」
「ツイートを消したか、ですね」
俺の返事に、彼はゆっくりと頷く。ツイートクリーナー。一定の日付より前のツイートをまとめて消せるWEBサービスだ。
「引っ越したのは八月頭って言ってたね。九月以前のツイートがないってことは、八月中のツイートに新住所のヒントになりそうなものがあって、まとめて消したと考えて良さそうだね」
「ううん、そうすると探すのは難しい……あ、ツイートキャスはアーカイブがあるって言ってましたね」
「そう、僕たちにはキャスがある!」
突然大声で宣言した海さんは、右手の指をパチンと鳴らした。
「あの、ツイートキャスってなんでしたっけ」
「ツイートキャス、通称キャスは簡単に言うと、動画の配信をしたり、その動画の視聴が行えるサービスだよ。生放送・ライブ配信のリアルタイムコミュニケーションを楽しむことができるアプリだね。
キャスの特徴は気軽さだけど、配信を視聴するだけであればリスナーがログインなしで見ることができるっていうのが大きいね。逆に言うと、コメントとかを送りたいんであればログインが必要ってことで、固定ファンが掴みやすい仕組みになってると思う」
「今の説明が簡単……?」
ものすごく早口で大量の情報を摂取した気がする。
「とにかくオル君、アーカイブも残ってるから、今年虎月君が配信したネットラジオを聞けば、何らかヒントが掴めるかもしれないってことだよ!」
「分かりました。どこから聞けばいいですか?」
俺の質問に、海さんはアーカイブの一覧を見ながら「んん」と迷ったような声をあげる。
「引っ越す前にも新居について何か話してるかもしれないから、七月中旬くらいから聞いていこう。ヒントをメモしていく感じだね。」
アーカイブのページをスクロールすると、一ページまるまるサムネイルで埋まっているし、次のページまで続いている。これはかなり頻繁に放送しているようだ。
「作業のボリュームを整理しておこう。虎月君の冠番組『とらつきラジオ』は毎週火曜・金曜の二回、各回だいたい一時間、たまに一時間半だね。七月の十八日週から先週までで二六本だ。ってことは全部で三十時間ちょっとかな」
「三十……」
時間、まで言い切れず、途中で絶句してしまう。
ヒントが出てくるか分からない音声配信をずっと聞いていくなんて、並大抵の人にできることではない。彼の発言を聞くと、この検索探偵が務まるのはやはり一部の特殊な人だけだな、と考えてしまうのだ。
「オル君、まだ時間ある? あるなら始めの放送だけは一緒に聞こう。今度来るときにまだ僕が聞き終わってなかったら分担して聞いていけばいいと思う」
「大丈夫です」
二つ返事が嬉しかったのか、海さんは口角を上げてメガネのブリッジをクイッと持ち上げた。
そして彼の作業デスクの前まで黒い丸型のスツールを動かそうとすると、「長いから背持たれあった方がいいよ」と部屋の端に置かれたパイプ椅子を持ってきてくれた。彼はパソコン用のチェアに座り、並んでキャス配信の動画を見始める。
アーカイブの七月十九日の回を開くと、画面の左側に「とらつき!」という画像が表示された。再生ボタンを押すと、束の間の静けさが事務所を包んだ後、パソコンのスピーカーから挨拶が聞こえてくる。
「こんばんは、天草虎月です。今日は雨ですね。でも多少なら雨に濡れるのも嫌いじゃないって人、僕以外にもそれなりにいるんじゃないかな。それじゃあ『とらつきラジオ』、早速始めていきましょう」
なるほど、これは声をウリにするのも分かる。低音で、それでいて威圧感のない優しい声。女性ファンがたくさんつくのも納得だ。画面の右側のコメント欄には、「こんばんは」「今日もイケボ」「癒される!」など、リスナーからのコメントがどんどん付いていく。
「昨日ってすごく暑かったでしょ? だから久しぶりにコンビニでアイス買ったんだけど、アイスって『今日は絶対アイスクリームよりアイスキャンディーの日だ!』ってなるときない? 僕は昨日キャンディーの日だったんで、無事にパイン味のアイスをゲットしたよ」
ギターのアルペジオの静かなBGMに合わせて、虎月さんがゆっくりとオープニングトークを始める。芸人がやるようなハイテンションなラジオを想像していた俺は見事に裏切られた。でも、良い裏切りかもしれない。あまり騒がしいと、何時間も聞き続けるのは難しいだろう。
「ほら、オル君。ここに視聴してた人数が表示されてる。開始すぐなのにもう四十人も聞いてる、人気なんだね」
「本当だ、どんどん増えてますね」
比例して、コメントもどんどん増えていく。たまにコメントを読み上げて返事をしているのも、リスナーからしたら「自分のを読んでもらえるのかも」というドキドキ感があるのだろう。今回の依頼人である咲菜さんも「やっぱり最高の声!」とコメントしていた。
「じゃあ、もらってた質問に答えていこうかな」
匿名で質問を受け付けられる質問ボックス。そこに来ている質問に、虎月さんは丁寧に回答していく。
「『好きなかき氷のシロップはなんですか?』 ううん……王道だけどブルーハワイ好きなんだよね。なんかさ、イチゴとかレモンとかって他のお菓子でも味わえると思うんだけど、ブルーハワイってかき氷しかないじゃない? あのレアな感じが結構良いなって」
盛り上がりがあったり、爆笑するシーンがあるわけじゃない。ただ、虎月さんが部屋で話しているのを近くで聞いてるような空間。ながら聞きもできる、ゆったりした雰囲気の番組、そして虎月さんに惹かれる女性が多いのだろう。それは、咲菜さんも一緒だったに違いない。
その後も、コメントに絡む形で放送は続き、一時間で番組は終わった。
「ううん、ヒントになりそうなものは無し、か」
そもそもこの時点ではまだ新居に移っていない。引っ越し先の話題が出てくるかと思ったけど、その期待は脆くも崩れ去った。
「まあまだ材料はたっぷりあるし、気を取り直して聞いていこう。おっ、咲菜さんからやっとTweeterのアドレスが来た」
スマホでメールアプリを覗いていた海さんが呟く。すぐ送ると言っていたけど、急ぎで用事があるような雰囲気だったので、ようやく落ち着いて連絡できるようになったのだろう。
海さんは右手の人差し指を寝かせて一気にスクロールしながら彼女のツイートを見ている。
「咲菜さんは一年前にアカウントを開設してるんだね。虎月さんのファンになったのが一年前って言ってたから同じタイミングだ。たまたま聞いてファンになったから自分も始めたって感じなのかな。随分ツイートが少ないから、閲覧メインで使っていたのかもしれないね」
視線を液晶から窓の外に移すと、太陽が消えた街は黒に染まり、街頭が等級の低い星のように鈍く光っている。
俺の目線に気付いた海さんは、パソコンの時計をちらりと見た。
「もう二十時超えてるもんね。オル君、今日は帰って大丈夫だよ。次はいつ来る?」
「そうですね、本当は木曜にしようかと思ってたんですけど……」
でも、内容が気になるし、せっかくだから力になりたい。ただのバイトじゃなくて、助手っぽいことをしてみたい。
「明日、授業が終わったらまた来ようと思います」
そう告げると、海さんは「待ってるよ」と口角を上げ、ザラメを掬って食べた。
***
翌日、授業は午前中のみだったので、お昼を食べてすぐに王子駅へ向かう。平日昼間の飛鳥山公園は都心の駅前と思えないほどのどかで、外から見ても子どもや老人たちでそこそこ賑わっている。その様子を見守るように、ちぎれた雲がぽつりぽつりと秋の晴天に浮かんでいた。
東十条の商店街の途中を折れ曲がり、探偵事務所へ。ドアに手をかけると、すでに鍵が開いていた。ガチャリとノブを回して入ると、昨日と同じ場所でパソコンにイヤホンをつけ、画面を見つめている後ろ姿が見えた。
「海さ——」
「シッ!」
呼びかけを制し、彼はイヤホンを抜く。
「ちょうど良いタイミングだったね。ヒントが出てきたよ」
彼は何回かクリックして放送を戻し、音量を最大に上げた。パソコンのスピーカーから、虎月さんの低く優しい声が聞こえてくる。
「新宿なら割と近いからね、電車で三十分くらいだよ」
楽しそうに口を弓なりに曲げ、青緑のハーフリムのメガネをくいっとあげる。
「都内近郊にいるってことははっきりしたね」
▼ 第2章 後編
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
