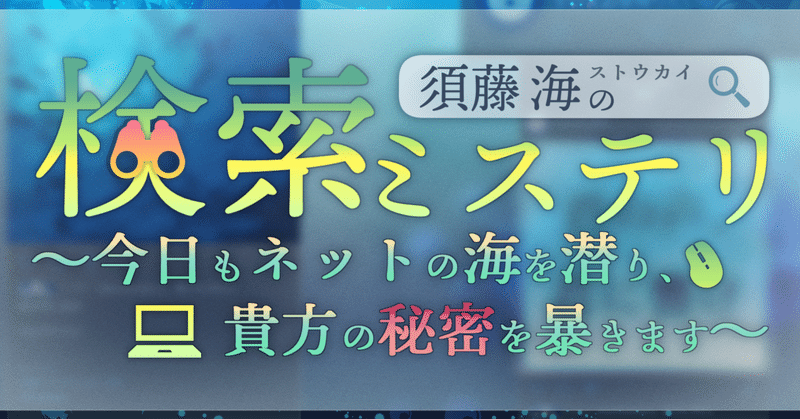
須藤海の検索ミステリ 第2章 元カレはどこに(後編)
「良かったですね! これで大分探しやすくなりました」
新宿から三十分くらいとなれば、東京・埼玉・千葉・神奈川に絞られる。それに、東京以外でもかなり東京寄りの場所に限られるはずだ。
「ずっと聞いてた甲斐があったよ。やっと手がかりを掴めた」
「ずっと……?」
「ああ、うん。あれから聞いてるよ。いやあ、虎月君って声が良いから聞き疲れないね! 色々プライベートなこと話してくれるからどんどん興味出てきちゃうよ!」
立ち上がってグッと伸びをしながら、彼は大きく欠伸をした。昨日よりかなりヒゲが伸びてる気がする。
「あの、今いつのを聞いてるんですか?」
「えっとね……八月三十日のだよ」
「八……月……」
昨日見たのは確か、七月一九日だった。ってことは……
「え、十二本くらい見てませんか」
「そうかもね。昨日からあんまり寝てないし」
九十分の配信もあるから十二本で十五時間くらいあるはず。俺が帰ったときから十七時間、ほとんど不眠で聞いてたということ。その桁違いの集中力に、俺は驚嘆を通り越して若干の畏怖を覚える。
いくら依頼だとはいえ、同じ人のネットラジオを半日以上一気に聞くなんてことができるのだろうか。飽きが来ないのか、眠気は来ないのか、信じられない気持ちで肩を回す彼を見ていた。
「でも僕は、初めてヒントが出たのがこの八月末の回だったってことに驚いてるんだ」
「驚く? なんでですか?」
「だってさ、オル君。この人はずっとこういう雑談ラジオをやってるんだよ? それで、八月の頭に引っ越しがあった。引っ越しなんて、一番身近でしかも面白いネタだ。リスナーから引っ越しあるあるを募集したっていいし、荷造りが終わってませんみたいな話だって面白い。なのにそこに一切触れてないんだよ」
「確かに……」
話題に困らなかったのかもしれないけど、それだって引っ越してからも数回放送してるんだから、一度くらい出てきてもいいだろう。
「だから間違いなく、これは故意にやっているんだろうね」
「故意、ってことはわざと?」
「そう。新居を明かしたくないから話してない。まさに、咲菜さんが困ってる理由だね」
関連する発言をなるべくしない。 徹底して隠しているのだ。
「よし、オル君が来たから二手に分かれて聞こう。お互いあと六、七本見ればいいはずだ。そこのパソコン使っていいから、九月二日回を聞いてくれる?」
「分かりました」
海さんが使っているものより若干古いノートパソコンを開きながら、応接用のグレーのソファーに虎月さんのアカウントを検索してリンク先からツイートキャスのアーカイブへ。指定された回をクリックして、昨日と同じように虎月さんの声を聞いていく。
「皆さん、こんばんは。今年、残暑がそんな厳しくないように思うけど、みんなはどうかな? 僕はスイカの食べ納めをしようと思って近所のスーパーに行ったらもう梨になってて、もう少し遠いところまで行って四分の一カットのスイカを買ってきたよ」
頭に響いて残る、良い声だ。たまに掠れるところも、女性なら堪らなく色っぽく感じるのかもしれない。
が、こういうラジオはゆっくり過ごしているときのお供にこそちょうどいいのであって、こうやって積極的に何本も連続で消化するものではないと思う。開始して二十分ですでに眠くなってしまった。倍速再生のような機能がないことをこんなに残念に思ったことはないかもしれない。
普通に質問を読んで、いつもみたいに雑談をする。雑談にも新居に絡むことは出てこない。この前の回で新宿に近いと明かしていたのだから、少しずつ気が緩んでいるのかもしれない。何か、尻尾を見せてほしい。
間もなく終了五分前という、その時だった。
「おおっ、揺れた」
急に大きくなった虎月さんの声に思わず腕がビクッと動く。冷静さを取り戻した彼は、「結構大きかったね」といつものトーンに戻っていた。
「地震かあ」
「えっ、地震!」
俺の言葉に海さんが瞬時に反応する。そしてスッとソファーまでやってきて俺の隣に座った。
「あ、今地震があったってことじゃないですよ? 放送中にって意味で」
「うん、知ってる。だから来たんだ。続き聞かせてくれる?」
海さんに頼まれ、俺も自分のイヤホンを外すと、さっきの続きが流れてきた。
「震度三、結構大きかったね」
その声を聞いた瞬間、彼はグッと拳を握って胸の前に突き出した。
「オル君、このときの時間分かる?」
「時間? あっ!」
彼の狙いに気付き、俺は放送時間を見る。放送開始が二一時で、五三分が経過している。
「九月二日のこの時間に地震があったのは……」
過去のニュースを検索し、地震情報をチェックする。震源地は福島、震度三を記録しているのは、栃木・群馬・埼玉の三県だ。
「新宿から三十分って条件を加えると、埼玉だけです!」
「これで県は絞り込めたね」
海さんにかかれば、地震も手がかりに変わってしまう。少しずつ虎月さんの住所が明らかになっていく。
「興味の対象が音声を残してくれてる。こんなありがたいことはないね」
彼は満足そうに頷いて自分のデスクに戻り、またイヤホンを耳に嵌めた。
それからしばらくは、お互い「とらつきラジオ」を聞く時間が続く。いつの間にか空が泣き始め、BGMのように優しい雨が静かに窓を打った。曇ってきたので部屋の電気を点けると広い部屋が一気に明るくなり、昨日俺が掃除したままの綺麗な状態が視界に飛び込んでくる。彼が半日動かずにいた証左だった。
九月二日、九日、十六日と聞き進めていく。海さんと同じペースで聞いているので、彼が火曜担当、俺が金曜担当というように自然と聞く曜日が決まってきているのが面白い。
特に成果のないまま二時間、海さんが「うわっ」と小さく叫んだのは、もうすぐ十月に突入しようというタイミングだった。
「来たよオル君、ビッグチャンスだ!」
イヤホンを外し、一口だけザラメを頬張ってから、パソコンを持ってまたソファーまでやってくる。その興奮の仕方は、さながら折り紙ですごいものを折ったのを自慢しに来た子どものようだった。
「ここ、聞いててね」
彼がパソコンのスピーカー部分を近づけてくれる。「今日さ」と、さっきからずっと聞いている虎月さんの声が流れてきた。
「電車で帰るときに事故があったみたいで……赤羽の駅で十分くらい止まってね。かなり混んでたから、僕は座れてたから良かったけど、立ってたら辛かっただろうな」
「駅名が出ましたね!」
東京の赤羽。これはつまり、最寄り駅に向かうのに赤羽を通るということであり、路線を限定することができる。更に放送は続く。
「動き出して、また止まるかなって思ったけどそこからは案外スムーズだったんだ。僕が降りるところはみんなが乗り……降りする駅だから電車も一気に空いたね。まあそんな、ちょっとだけ大変な帰宅でした」
「路線と新宿から三十分って情報を組み合わせれば、候補は数駅に絞り込めそうだね」
海さんがにんまりと笑う横でしかし、俺は表情を崩さない。脳内でさっきの放送を思い出す。そして、それを見落とすような探偵ではなかった。
「何か気になった、オル君?」
「あの、今の部分、もう一度再生してもらっていいですか?」
「もちろん」
十秒戻るボタンを何回かクリックして、虎月さんの帰宅エピソードを聞き直す。俺が疑問に思っていた点を再確認する。
「あの、なんか途中で変な間がありますよね? 赤羽の駅名が出るところと、『乗り降りする』って言ってるところ」
「確かに言われてみれば、ワンテンポくらい間が空いてたな」
「すみません、大したことじゃないかもしれないですけど……」
「いや、オル君のそういう気付きは結構重要だと思ってるんだ。君の過去の経験が活かされてるんだからね。ありがとう」
年下のただの大学生の言葉をこうして素直に聞き入れてくれる、彼の懐の深さが嬉しかった。自分がなりすましで被害を受けたとき、相手を見破れるよう、偽物だとみんなに言えるよう、細かいことに気付けるようになった。それを活かせるなら。
「言葉に詰まったのか、あるいは何か理由があって言い淀んだ……でもそこまで隠そうとしたってことは……」
そう言ったきり、海さんは故障中の人型ロボットのようにフリーズした。手をキーボードに置いたまま、よく見ると目だけがキロリと動いている。しかし、画面を見ているわけではない。脳内に書いた推理を読み返しているかのように、視線が宙を左右に舞っていた。
突然、再起動した体がクッと動く。定位置である自分のデスクに戻り、腕を伸ばして、ものすごい勢いで打鍵を始める。彼の頭には何が浮かんでいて、何を検索しているのだろうか。
やがて、彼は口を開けて大きく深呼吸する。そして自信に溢れた目つきで、顔を俺の方に向けた。
「うん、大体謎が解けたよ。咲菜さんに連絡しよう」
咲菜さんが事務所を訪ねてきたのは、雨もあがったその日の夕方だった。たまたま都合がついたらしく、連絡を受けてすぐに向かってくれたらしい。白のTシャツに少しクリームっぽい色のカーディガン、モノトーンのギンガムチェックのロングスカート。モコモコしたファーの、キャメルカラーのキャスケットが秋らしい。
「もう分かったんですかあ?」
「ええ、僕にかかれば、虎月さんの一人や二人、居場所を突き止めるのはワケないです。といっても、候補が二つありますけどね」
相変わらず気怠そうな話し方をする咲菜さんに、海さんは軽快に言い放つ。虎月さんの一人や二人、という喩えがおかしくて、吹き出しそうになってしまった。
「では、僕たちが彼の居場所を絞り込んだ経緯を聞いてください。まずはこの放送からですね」
ソファーで向かい合って座っている咲菜さんに画面を向けながら、海さんは「とらつきラジオ」を再生していく。新宿駅に近いということから都内近郊と判明し、さらに地震の発言から埼玉だと判断した。
「ああ、なるほどお、確かに組み合わせると埼玉に絞り込めますね。地震からも分かっちゃうのかあ」
「そうなんです、一回一回聞いたり作業しながら聞いたりしてると分からないけど、まとめて聞くと推理の材料になりますね。そしてここからです。九月のこの放送ですね」
続いて、彼が大きな手掛かりを得た放送の該当部分を流した。
『電車で帰るときに事故があったみたいで……赤羽の駅で十分くらい止まってね。かなり混んでたから、僕は座れてたから良かったけど、立ってたら辛かっただろうな』
『動き出して、また止まるかなって思ったけどそこからは案外スムーズだったんだ。僕が降りるところはみんなが乗り……降りする駅だから電車も一気に空いたね。まあそんな、ちょっとだけ大変な帰宅でした』
「コメントを残していたので、もちろん咲菜さんも聞いてたかと思います。覚えてますか?」
「はい、何か事故の話を聞いた覚えがありますね」
パソコンの画面を自分の方に向き直し、海さんは何か検索する。続いて見せたのは、JR京浜東北線の路線図だった。
「さっきので埼玉県内だと絞り込んでいたので、ここからの推理は容易でした。赤羽駅はJR京浜東北線です。『みんなが乗り降りする駅』というところを踏まえるとかなり大きな駅だと予想できます。まず赤羽の隣は川口駅という結構大きい駅ですが、動き出してからは案外スムーズだった、と言ってるから違いそうです。隣駅ならスムーズも何もないですからね」
確かにそうだ。順調に運行してたような口ぶりだったから、少なくとも数駅乗ったということになる。
「であれば大きい駅というのは、終点の大宮駅か、一つ手前のさいたま新都心駅でしょう。この二つから絞り込むのは難しいですが、虎月さんが『ライブ行きたいなあ』というツイートをしていたので、僕はさいたま新都心駅なんじゃないかと思ってます」
「ライブ……あ、アリーナ!」
思わず叫んだ俺の声に、咲菜さんも「ああ!」と反応する。
「そうです、さいたまスーパーアリーナがありますからね。あの駅で乗り降りする人はライブ目当ての人が多いと思います。虎月さんはそれを見てあのツイートをしたんじゃないかな、と推理できるわけです」
「そっかあ、確かにその可能性高そうです。両方の駅で待ってればいつか会えそうです、ありがとうございます!」
お金振り込んでおきますねえ、と咲菜さんはいそいそとバッグの口を閉め、帰り支度を始めた。ずっと探していた人に会えるのだから、期待に満ちた表情も当然だろう。
「いえいえ。もしこれから行くなら一緒に行きましょうか? 僕たちも見落としてるものがあるかもしれないから、最寄り駅を確定させられるかもしれませんよ」
「あ、いえ、本当に大丈夫なんで、お気遣いなく。お世話になりました」
海さんを避けるように、彼女は二回お辞儀をして、事務所を出て行った。前も同じように誘っていたけれど、元カレに会うのに男性も同行するのはどう考えてもおかしいだろう。
断られてしょぼくれているのかと思ったが、海さんはケロリとしていた。そして、ふうと息を吐きながらパソコンを持って立ち上がる。
「さて、これで事件は半分解決かな」
「……え?」
半分? 確かにどっちの駅は分からないけど、もう捜査は終わったんじゃないのか?
「オル君、今日はこの後時間ある?」
「ええ、まだ二十時前だし、大丈夫ですけど……」
「じゃあもう少ししたら出発しよう」
一緒に行けることが嬉しかったのか、彼は微笑を浮かべながら窓の外を見ながら答える。謎を知りたがるように、一匹の蛾がガラスに体当たりしていた。
「出発って……どこにですか?」
「さいたま新都心だよ。そのためには急いでご飯を食べないといけないね」
まるでホームズが事件現場に行くときのような台詞を吐いて、彼は食品棚からイングリッシュマフィンを、冷蔵庫からマーガリンとハムを用意しはじめた。
「寒いですね……」
「寒いね。夏は六月後半から九月後半までたっぷりあるのに、秋はあっという間に終わる気がするよ」
そう言うと海さんは、赤都を探したときにも着ていた薄いコートの前をしっかり閉め、ぶるっと身震いした。
即席のサンドイッチを食べてから京浜東北線に乗り込み二五分。俺たちは二一時前にさいたま新都心駅に着いた。平日ということもあり今日はアリーナでライブはないらしく、駅はかなり空いている。改札を出ると左右にペデストリアンデッキが広がっていて、俺たちは駅前ピアノがあるその奥、左右への分かれ道のところに並んで立っていた。
週末やさっきまでの雨のせいか、先週に比べて一気に気温が下がった。風は吹きっさらしの状態なので、冬を予感させる寒風が体にしっかり当たる。多少厚手のジャンパーを着ている俺も肌寒く感じるので、ペラペラコートの海さんは尚更だろう。長身で痩せ型なので、見てるこっちまで寒さが増してしまう。
「あの、海さん、なんで咲菜さんを待つんですか? 同行が断られてるからって、尾行とかするつもりですか?」
「オル君、僕を完全にストーカーだと思い込んでるね!」
海さんがツッコミを入れるけど、その口元は笑っているように見えた。
「そんなことしないよ。ちょっと、彼女に伝えたいことがあってね」
「でも、今日来るか分かりませんよ? もう駅についてどこかで夕飯とか食べてるかも」
「まあそれでも今日から毎日駅にいれば、いつか会えそうでしょ?」
家から一番近いコンビニに行くような手軽さで、彼は「毎日」と言い放つ。ストーカー気質は十分だと思う。
そのまま待つこと十五分。擦り合わせていた手からそろそろ煙が上がるのでは、というところで、海さんはフッと息を呑んだ。
「来たよ」
改札を抜けて歩いてくるのは、さっきまで事務所で会っていた咲菜さん。薄クリーム色のカーディガンの上に、ライトブラウンのコートを羽織っている。
奥に見える俺たちに気付くことなく、彼女は改札を出た直後に右手に折れ、その場所に待機した。それはちょうど、駅から来る、あるいは駅に向かう誰かを、すぐに見つけられるような位置で。
海さんは彼女に気付かれないよう、大回りしながら近寄っていく。そして、「こんばんは」と言いながら、改札の方を見ていた彼女の背中に声をかけた。
咲菜さんは、ビクッと肩を震わせ、海さんの方を振り返る。それは「おそるおそる」という表現がぴったりで、「探偵さん」と呼んだ声もどこか上ずっていた。
「どうしたんですか? 虎月君を探すのに、同行はしないつもりだったんですけど……」
その言葉を待っていたかのように、海さんはコートに入れていたらしいメガネケースからメガネ拭きを取り出し、手に持ってレンズを拭きながら裸眼で答えた。
「虎月さんは来ませんよ。最寄り駅が違いますから」
「え……?」
彼女と同じくらい驚いたのは俺だった。違う? じゃあなんでここを伝えたんだろう? そしてここに来たんだろう?
俺たちの疑問など全てお見通しの様子で、彼は淡々と言葉を続ける。さっきよりも衝撃的な言葉を。
「だから、彼氏でもなんでもない虎月さんに、アナタが会うことはできません」
「あの、海さん?」
俺は話に割って入る。
「彼女じゃないとしたら、一体何なんですか……?」
「んー、まあその明言は避けておくよ。万が一違っていると悪いし、良い言葉じゃないしね。僕の名前に似てるって意味では好きなんだけど」
何も具体的なことは教えてくれなくても、答えを知るにはそれで十分だった。
「じゃあお金の話は……?」
「さあ、そのあたりは僕には分からないよ。でっち上げなのかもしれないし、本当にお金を送金しているのかもしれない。そのあたりは推理しようがないし、二人の問題だからね」
ということは、海さんに依頼した意味が全く変わってくる。彼女は単純にファンとして、彼を探していた。なんとか直接会いたくて、居場所を突き止めようとしたのだ。
「……ちょっと、何言ってるんですか、探偵さん。冗談やめてくださいよお」
咲菜さんは手を口に当てて苦笑する。しかし、このごまかし方も推理小説では真犯人がよくやる手法だよな、なんて想像が頭に浮かんで、彼女を疑義の目で見てしまう。
「最初に引っかかったのは、彼との別れの話をしていたときです。咲菜さんは『引っ越し先の住所を教えてくれなかった』と言っていた。でも、それはちょっとおかしいんじゃないかと思ったんです。普通怒るのは『勝手に引っ越したこと』なんじゃないかなって。アナタの言い方だと、まるで『こっちにナイショで引っ越したことは仕方ないとしても、住所くらい教えてほしい』という風に聞こえました」
黙って聞いている咲菜さん。その瞳が忙しなく動いているのは、寒さのせいだろうか。動揺のせいだろうか。
「そして、虎月さんのツイートは八月より前は消されていました。彼が意図的にツイートを削除したに違いありません。消した理由は色々考えられます。炎上が多かった、キャラクターを変えようと思った、誰かに情報がバレないよう隠したかった」
「……それだけでアタシが彼女じゃないって言えるんですか?」
「もちろん言えないです。可能性が高いってだけです」
海さんは、自分のスマホを取り出した。ロックを解除すると、Tweeterのアカウントが表示される。それは、咲菜さんに共有してもらった彼女のアカウントだった。
「用事で事務所を出なきゃいけないので、電車に乗ってすぐアカウントを送ってくれることになってましたけど、随分時間がかかってましたよね?」
「それは……忘れちゃっててえ……」
「どうしても虎月さんを探したくて探偵事務所に来たのに、連絡用に使うと言っていたアカウントを送り忘れるなんて随分ちぐはぐですよね」
言い返しても、すぐにロジックで打ち返される。咲菜さんにとっては相当ストレスの溜まる相手に違いない。顔に若干引き攣ってきている。
「なぜ送るのが遅くなったのか。僕はそこに意味があると考えました。送れないということはスマホに問題があるか……あるいはアカウントに問題があるか。そこでツイートを見てみると、随分とツイート数が少なかった。オル君、理由が分かるかい?」
そういえばツイートが少ないと言っていたな、なんて考えていると急に質問を振られて焦る。まずい、なんでもいいから答えないと。ツイートが少ない理由? 閲覧用のアカウントだからじゃなくて? だとすると…………例えば、本当は少なくないのだとしたら……
「ツイートを、消した」
「ご名答」
海さんは両手首をくっつけて、指先だけで小さく拍手した。その表情には余裕があって、どこか楽しそうですらある。
「あくまで僕の想像だけどね。虎月さんに関する、僕たちに見られたらまずいようなツイートがたくさんあって、それを消していたから時間がかかった、ってところかな。もちろん、僕はそれを調べるためにアカウントを聞いたから、作戦は間違ってなかったんだけどね」
「ちょっ、探偵さん、昨日は連絡用って言ってたじゃないですかあ」
「そうだよ。そう言わないと共有してもらえないと思ったからさ」
彼女は真顔で海さんを見つめる。ギリ、と歯ぎしりの音が聞こえた。
「でもね、僕は咲菜さんの気持ちになって考えてみたんだ。すぐに消したいなら専用のツールがあるから全部を一気に消すことだってできたはず。でもそれをやったら、思い出まで消えてしまう。だから個別に選んで削除していったんだ」
「海さん、思い出って……」
俺の問いに、彼はスマホに映っている「ツイートと返信」のタブをタップした。
「返信、リプライだよ。彼女は虎月さんとのリプのやりとりは消したくなかった。虎月さんへの想いを語る一人語りのツイートは消したんだろうけど、虎月さんとのリプは完全に残ってしまっている。
ちゃんと探せば特定の人へのリプだけを残して削除できるツールがあるのかもしれないし、やりとりを全部お気に入りにブックマークしてブックマーク以外消したりできるのかもしれないけど、慌ててたからすぐにはやり方が見つからなかったんだろうね」
海さんにスマホを渡され、返信をスワイプして確認する。「虎月君、ホントに好きだよお笑」「手料理食べてみたい!」といった普通のリプもあれば、「この前、家から通えるオススメのカフェって言ってたお店、探し当てて行ってみた!」「風邪大丈夫? 最寄り駅だけでも教えてくれたら、頑張ってお家まで薬届けるよ!笑」といったやや危ないものまである。
「特に今年の五月くらいが顕著だね。相当粘着している。他のファンと比べても段違いだ。残念だけど、これを見てアナタが虎月さんの彼女だと信じる人は少ないと思うよ」
確かに海さんの言う通りだ。家の近くのカフェまで来られたなんて話、今パッと目にした俺でも少なからず恐怖を覚えてしまう。
「そして当然、虎月さんも参っていた。このままだと本当に住所が特定されかねない。そこで内緒でこっそり引っ越すことを企てた。そして引っ越したという事実だけ知らせることで、自分につきまとうのを諦めさせようとした。探偵に頼むなんて思いもしなかっただろうからね」
心なしか、海さんの口が下に曲がっている。それは、呆れというより怒りに近い表情だった。
「待って待って、探偵さん。じゃあなんで彼はラジオの中でヒントになるようなことを言ったの? 駅名なんて言っちゃってさ。本当に私が怖いなら、言わないようにしたり、動画を消したりするんじゃない?」
咲菜さんの声がさっきより一段階低くなった。睨みつけるような目つきで、敵対心を露わにしている。気まぐれで乱暴な風が通り過ぎて、俺の体を震えさせた。
「まず、動画を消さないのは彼なりの配慮でしょう。アーカイブを残しておけば当日聞けない方にも聞いてもらえる。それに、その動画だけ削除するのはおかしいし、全部消したら自分の思い出も消えてしまう。だから消していない。そして新宿駅から三十分という発言は場所を狭めるには曖昧すぎるし、地震は揺れたのでたまたま言ってしまったのでしょう。つまり、この二つは本人としても仕方ないと考えていた」
ここで海さんは俺たちの周囲をうろうろと歩き始める。寒いのかと思ったものの、人差し指をピンと立てているところを見ると、どうやら往年の探偵の推理披露シーンを真似しているらしい。洋館や被害者の家ならともかく、夜の屋外でやると若干不審さが目立つ。
「問題はアナタが言ったように、赤羽駅のことを言ったところですね。あれだと最寄り駅が割り出せてしまう。そこで彼は話しながら考えた。ちょっとボカすことで、アナタを騙せるんじゃないかと」
騙す、を強調する。「他にも彼につきまとってた人がいたかもしれないしね」と付け加え、ふうと息を吐いた。虎月さんは考えながら発言していた。だから、駅名を言う前に少し変な間があったのだ。
「咲菜さんが新居の場所を調べても、まっすぐには答えに辿り着けないようにした。一度『この駅だ!』と決めたらアナタが毎日のように来る気でいることも分かっていたからこそ、間違えてくれればしばらくは安心だ。そう思ったのでしょう」
海さんの言うことも一理ある。そうやって曖昧にすれば、咲菜さんを騙せるかもしれない。しかし、腑に落ちない点がある。それは彼女も一緒だったらしい。
「探偵さあん、今の話、不思議なところがありますね。なんでそんなまどろっこしいことをしたんですか? アタシが虎月君なら普通に嘘つきますよ? 適当な駅名言えば、それで間違えてくれるわけだし。そういうの、ちゃんと分かって推理してますかあ?」
煽るような発言にも動じず、彼はまっすぐに咲菜さんを見る。そして不意に、頬笑みを浮かべた。それは、哀しさを孕んだ、残念そうな笑み。
「……多分、アナタの方が彼を分かっていないですね」
「どういう、ことです?」
「嘘を言うのは簡単です。でもね、虎月さんのライフワークは何ですか? ラジオなんですよ。もし全く違う駅の話をでっち上げたら、これから先のラジオでも、その嘘を吐き続けきゃいけない。千葉って言ったなら、千葉県民の設定でずっと話さないといけない。アナタ一人を騙すために、みんなに『これは嘘だよ』って思いながらね。
それがパーソナリティーにとって、どれだけしんどいことか分かりますか? その目が曇ってしまっていることこそが、アナタがファンを超えてしまった証なのかもしれませんね」
咲菜さんは下を向いて震えていた。怒りなのか、恥ずかしさなのか、表情は分からない。ただただ、どうしようもない感情を床にぶつけるような強い息の音が聞こえた。
程なくして彼女は顔を起こす。まだ何も諦めてない、不屈で不敵な笑みを湛えながら。そして、俺たち二人にしか聞こえない音量で、「あはっ」と笑った。
「名推理ありがとうございますう。それで、アタシが彼女じゃないって、ストーカーって証拠はあるんですか? 証拠がないと何も動けないですよね? ずいぶん大言壮語吐いてましたけど、他に追加できる説明はあるんですか? ないなら意味ないと思いますけどお?」
完全に敵対態勢に入った咲菜さん。確かに、これまでの海さんの話はあくまで仮説に過ぎない。ラジオしか材料のない俺たちに決定的な証拠を出すことなど不可能で、それが分かっているからこそ、彼女はここまで強気なのだろう。
だが、そんな咲菜さんに対し、海さんはあくまで冷静に「いいえ」と首を振ってみせた。
「証拠はないです。でも、別に要りません」
「…………え?」
聞き返す彼女に、彼はゆっくり俺たちの周囲を周っていた歩みを止めた。
「説明なんか要らないってことです。僕は、おそらく虎月さんはここにいるだろうという本当の最寄り駅の見当がついてます。アナタと一緒にそこに行けばいい。彼女面するからには何回か会っているのでしょう。
これ以上何も推理しなくても、アナタの顔を見た虎月さんのリアクションで全てが分かるはずです。もちろんアナタが行かない場合にも、アカウントを見せれば一発で気付いてもらえますよね?」
その言葉に、咲菜さんは放心状態のように口を開ける。言われてみれば、その通りだ。別に全てロジックを積み上げて立証する必要はない。直接会いに行けるなら、それが一番の近道だ。あまりにも海さんの推理が理路整然としていたので、つい忘れてしまっていた。
「で、どうします? 僕たちと一緒に行きますか?」
生気のない目で彼を見ていた咲菜さんは、項垂れるように肩を落とし、ゆっくりと首を振った。表情が見えない中で、絞り出すような声が聞こえてくる。
「彼が……彼が、振り向いてくれないから……それでどうしても知りたかったの」
そして、急にガバッと上体を起こし、キッと歯をむき出しにする。海さんも俺も、驚きのあまり半歩後ずさりした。
「だってずっと応援してたんだよ! 今みたいにファンが多くなる前からずっと応援してたのに! 昔はリプだって即レスしてくれてたのに、ここ最近は全然だった。他の人とタイムラインで仲良くしてるのも許せなかった。最初の頃みたいに、私のことを古参ファンとして特別扱いしてほしかった。
だから住んでるところを突き止めようとしたの。そしたら少しは意識してくれるでしょ? 昔の関係に戻りたいのよ! アタシの、アタシだけのものだったのに!」
叫ぶというより怒鳴ると言った方が近い、彼女の本音。ヒートアップしている分、夜風も相まって、俺は冷静にそれを聞いている。そして理解しようとしながらも、怒りが込み上げてきた。
こんな一方的な想いで、彼女は彼に付きまとったのか。応援したい気持ちも、昔のような距離感でいられなくなった寂しさも分かる。でも、超えてはいけないラインもある。
海さんはどのように返すのだろうと、隣にいる彼に視線を移す。やや強まった風を防ぐようにコートの前をグッと閉め、ジッと咲菜さんを見ていた。「人間って面白いなあ! 興味深いなあ」といつも楽しそうにしているので、こんな風に真顔で彼女の暴論を聞いているのは意外だった。
そして、鼻からフッと強く息を吐き、「まず」と口を開いた。
「虎月さんはアナタのものではありません。もちろん、他の特定の誰かのものでもない。そして、知る関係にないなら無理に知る必要はない。本当にお付き合いしていない限り、アナタはどこまでいっても虎月さんのファンなんだから、関係性は守らないとですよ」
何も返事をしないのが、正論に対する彼女の精一杯の抵抗なのだろう。「うちでは追加の依頼は受けないので」と一言付け加えて、海さんは改札に向かう。俺も、彼女に一礼してから、慌てて付いていった。
「依頼料はちゃんと払ってもらわないと困るなあ。来なかったら督促状送らないとだね」
上りの京浜東北線に並んで座りながら、海さんはメガネを外して目元を指でマッサージし始めた。
「なんか意外でした。海さん、ああやって怒ることもあるんですね」
「気持ちは理解できないこともないからさ。夢を見られるような疑似世界があるとして、それを現実のように捉えることで陶酔感を味わえたりするからね。咲菜さんは、そういう夢の世界から抜けられなかった」
「それまでずっと親密だった虎月さんを遠くに感じたんでしょうね」
「寂しかったろうし、『特別な自分』をアピールし続けたいのも分かる。でもそれはそれとして、やっぱり悪いことをしてるって部分にはきちんと叱責しなきゃ」
悪いこと、と言い切りながら、裸眼で俺の方に顔を向ける。メガネの上からではなかなか分からない、どこか子犬を彷彿とさせるつぶらな瞳が覗いた。
「まあ、これは探偵というより年上の人間としてだけどね」
「あ、やっぱり海さんの方が上なんですね」
「うん、虎月さんへのリプの中でお互い干支に言及してるのがあってね。二人の年齢が分かったんだ。咲菜さんは虎月さんより下だったらサバ読む必要もないだろうし、多分嘘は言ってないだろうね」
「相変わらず抜け目ない……」
咲菜さんが彼女じゃないと確認するためにリプ欄を見ていたはずなのに、ちゃっかり歳も把握している。さすが検索にかけてはプロだ。
「そういえば、虎月さんの最寄り駅って本当に分かってるんですか?」
「うん、もちろん分かってるよ」
俺は電車のディスプレイで到着時間を確認しながら訊いてみた。すぐに画面が切り替わり、最近よく見る女優によるメイクのワイポイント動画が流れてくる。
「あの時、虎月さんは『赤羽駅』じゃなくて『赤羽の駅』って言い方をした。それ自体がヒントなんだよ。調べてみたけど、あのときJRの京浜東北線に事故は起こっていなかった。ってことは赤羽って名前が付く他の駅ってこと。東京メトロに赤羽岩淵駅、JR埼京線に北赤羽駅があるけど、当時の事故と照らし合わせると北赤羽駅だ」
なるほど、そもそも駅が違っていたということか。当時の事故の状況を調べることくらい、海さんには造作もないことなのだろう。
「そして問題は次の発言だね。『自分以外にも乗り……乗り降りする駅だから、一気に空いた』って言っていた。オル君、なんで『乗り』で止めたんだと思う?」
「えっと……何か別のことを言いかけた……?」
「そう、それを途中で止めて、乗り降りに言い換えたんだ。じゃあ、何を言おうとしたんだろう。電車に関連する言葉で『乗り』から始まるんだ。そこまで分かれば簡単だよね」
俺はすぐに脳をフル回転させる。乗り過ごし、乗り越し……あとは……
「乗り換え、ですかね」
答え合わせをしなくても、メガネをかけ直した彼のにんまりした表情が正答だと教えてくれた。
「乗り換えで人が一気に空く、って言おうとしたんだ。でも途中で止めて、乗り降りにした。その理由は明白だね。乗り換えと言ったら最寄り駅が絞れてしまうからだ」
海さんはスマホを取り出し、JR埼京線の路線図を開いた。
「北赤羽で事故があって、そこから帰ったと言ってたよね。北赤羽から先で乗り換えがあるのは、終点の大宮を除くと武蔵浦和駅だけなんだよ」
「えっ!」
驚いて路線図の乗り換え表を見る。海さんの言う通り、乗り換えができるのは一駅しかなかった。
「もし大宮が最寄りだったとしたら、乗り換えで一気に人が空く、とは言わないだろう。終点だからね。とすると、あそこで乗り換えと言っていたら、彼の最寄り駅が確定してしまう。だから虎月さんは少し迷って変えたんだよ」
なるほど、そういうことだったのか。二ヶ所ボカされたことで、ミスリードできる余白が生まれてしまったというわけだ。
「で、僕はそこに辿り着いたうえで、咲菜さんを誘導するために別の解釈を考えたんだ。さいたま新都心っていう説も結構納得感があっただろ?」
「じゃあ虎月さんのライブ行きたいって発言は何だったんですかね?」
「どういう意図でツイートしたかっていうのは前後のツイートでは分からなかったね。大宮にもソニックシティみたいなホールはあるから埼京線に乗ってるときにライブに向かう人を見かけたのかもしれないし、さいたまスーパーアリーナの近くで遊んでいたのかもしれない。まあいずれにせよ、こじつけに使えたからあの投稿は役に立ったよ」
海さんの推理を聞きながら、俺は赤都を探した時と同じように感心する。ラジオの音声だけで、相手のことをここまで絞り込める。これは、単純に「ラジオを何時間も聞ける」なんて才能だけでは成しえないことだ。僅かなヒントを逃さず、手元の材料から仮説を立てていく洞察力があってこそであり、そういう意味ではやはりこの人は探偵に向いているのかもしれない。
「いやあ、それにしてもストーカーってのは怖いよ。人の情報を勝手に探るっていうのは恐ろしいね、オル君」
「海さんがそれを言う資格はないのでは……」
「まあまあ、それはそれ、これはこれだから」
彼はうはは、と笑って見せる。事件が解決した安堵や清々しさのおかげか、表情から緊張が取れていた。
「今回はこのスキルがあったから、咲菜さんの暴走を止められたしね。虎月君に怖い思いをさせずに済んだんだ」
「うん、それは間違いないです。虎月さんも海さんに感謝ですね」
彼の能力が、誰かを救っている。ネットストーキングも使い方次第でプラスの使い方ができるのだ。
「そろそろ東十条駅だ。オル君は王子だよね? いつか家を当ててみたいなあ」
「お断りします」
くだらないやりとりをした後、「じゃあまた」と海さんは電車を降りていった。残った俺はスマホを取り出し、帰り道に何を聞くか考える。
バタバタした夜だったから、まったりしたラジオでも聞きたい。そんな思いを吸い込んで、手は自然と虎月さんのラジオを探していた。
〈第2章 了〉
▼ 第3章 前編
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
