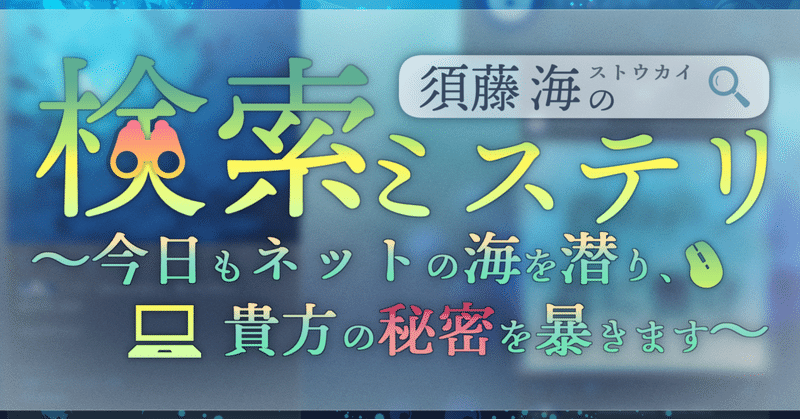
須藤海の検索ミステリ 第3章 ターゲットをフォローして(前編)
「今日めっちゃ寒いな……」
講義棟の三階で二限のチャイムを聞きながら、隣の赤都は机にぐでっと突っ伏し、手で自分自身を抱くようにして腕を擦って温めている。俺もそれを見ながら「分かる、もう冬だよ」と体を揺らした。十一月に入って二日目、過ごしやすい秋の気候はすっかり鳴りを潜めた。冷え込む日が続くので、たまに暖かい日が来ても嬉しいというより体調を崩さないか心配になってしまう。
「あ、何それスマホケース、めっちゃオシャレじゃん」
「だろ? この前鎌倉に行ったときに北欧系の雑貨屋で買ったんだよ」
後ろから男子二人の声が聞こえる。教授が来るのが遅れており、教室の中はちょっと延長した休み時間という感じで隣同士で雑談していた。
「そういえばさ、十条にいる探偵の噂、知ってる?」
「あー、聞いた聞いた。なんか元ストーカーなんだろ?」
「らしいよな」
そのやりとりに飲んでいたホットのレモンティーが気管支に入りそうになり、「んぐっ」と咽てしまう。その様子を見ていた赤都が、クックッと歯の隙間から笑い声を漏らした。
「有名人だな、須藤さん。誤解されてるけど」
「まあ誤解されても仕方ないからな」
今日は水曜日なので、三限、十四時半には終わる。その後に事務所に行く予定なので、海さんに変な噂が立っていると冗談で教えてあげよう。
「じゃあな、織貴!」
「おう、また家来いよ!」
授業が終わり、赤都と別れて、王子駅へ向かう。中央改札の手前で右を見ると、モノレールが視界に入った。山頂までの二十メートル近くを上る、あすかパークレール。白くて丸い車両は、かたつむりに似ていることから、「アスカルゴ」という愛称がついている。地元の群馬と比べたらとんでもない都心だし、上野にも秋葉原にも行きやすいけど、どこか長閑さを残しているこの町が好きだったりする。根が田舎者だから、こういう風景が落ち着くのかもしれない。
「次は、東十条、東十条。お出口は、右側です」
アナウンスを聞きながら一駅で降りる。そこまで遠い距離じゃないはずなのでいつか自転車でここまで来てみようと決意しながら、俺はふと、ある店のことを思い出して、いつもとは反対側の南口で降りた。
公園を左手に見ながら坂を下りていき、大きな交差点に差し掛かる左側にその店はあった。「どら焼き」とのぼりの掲げられた店の中には、五十代、六十代の女性のが数名入って買うものを物色している。十五時のおやつどきだからだろうか。夕方になると、もっと大勢の人が並び、店の外に列をなしているのを目にしたこともある。
俺は目的のものが決まっていたので、他の商品には目もくれず、まっすぐにレジに並んだ。
「あの、黒松を一……あ、いや、二つお願いします」
店員さんが手際よく、紙袋を用意してくれる。これを手土産に、北口の方に戻って商店街に向かおう。
コンッ コンッ
「うわはーい!」
事務所のドアをノックすると、遠くの方から楽しげな声が聞こえていた。まずい、これは依頼者だと勘違いして浮かれている可能性が高い。
「あの、海さん、織貴です」
「あっ、オル君か。今度はノックしながら名前言っていいからね」
若干テンションを落としながら、海さんがドアを開けてくれた。名前を叫びながらドアを叩くのは少し気恥ずかしいし、まず依頼人だからと言ってそんなに浮かれない方がいいと思う。
「あ、珍しいですね。海さんがジャケット着てるの」
「さすがに寒くなってきたからね」
そう言って、くたびれた青いワイシャツの上の、さらに年季の入ったネイビーのジャケットの両脇を持ってパンッと下におろしてみせる。カッコつけたつもりなのだろうけど、よく見ると袖のボタンが両腕一つずつ取れていて、お世辞にもキマっていなかった。
「実はお土産持ってきたんですよ」
「うわほーい! 黒松だ! 食べるの久しぶりだよ!」
俺の紙袋を開けて中を見た瞬間に、彼はさっきと同じような歓喜の声を挙げた。よっぽどお腹が減っていたのか、早速どら焼きのビニールを剝がしている。
一説によると東京三大どら焼きと呼ばれているらしい、草月というお店の「黒松」という名のどら焼き。たまたまこの近くのランチを調べていたら見つけたので、一度食べてみたかった。緊張しながら、その特徴的なまだら模様の焼き色が付いたどら焼きを、そっと口に運んでみる。
「うわっ、これ皮が美味しいですね!」
一口頬張ると、黒糖の香り深い甘さと、はちみつの優しい甘みがうまく溶け混ざって、口の中にじゅわっと広がる。これまで食べてきたどら焼きとは全く違う新鮮な美味しさだった。
「うん、皮のオリジナリティーが突出してるよね。洋菓子のようなふわふわな食感と、和菓子特有のもっちり感が合わさってる。そこに上品な甘みを出すつぶあんが合わさって、絶妙なバランスのお菓子になってるんだね」
「海さん、食レポ上手ですね……」
普段ザラメをボリボリ食べている人とは思えない、意外な特技だ。
「コーヒーとか紅茶飲むかな? あ、新しい紅茶買ったから、そこにあるの飲んでいいよ。僕のも一緒に淹れてくれると嬉しいな!」
「じゃあ、お言葉に甘えていただきますね」
カセットコンロにやかんをかけて、マグカップを用意する。食品棚に置いてあったのは、ちょっと高級そうなティーバッグの紅茶の入った箱。いつの間にこんなのを買ったんだろう。
「そう言えば、今日学校で海さんが噂になってましたよ。元ストーカーの探偵だって」
ティーバッグに当てるようにゆっくりお湯を注ぎ、緑色のマグカップを渡しながらからかうように言うと、海さんは口をへの字にひん曲げてみせた。
「だから僕はストーカーじゃないって言ってるのに、どうしてみんなそれが分からないのかな。一人ひとり家を調べて誤解を解きに行こうかな」
「冗談に聞こえなくて怖いのでやめてください」
本当にやりそうだし、実際に出来そうなのがより恐ろしい。
「まったく、僕はれっきとした探偵なんだよ。今日だってこれから来客があるのに」
「あ、依頼人の方ですか?」
「うん。以前依頼してくれて、今継続して調査中の人が一ヶ月半ぶりに来るんだ。仕事で近くまで足を運ぶから、立ち寄ってくれるらしい」
海さんはいつものデスクに座り、椅子に寄り掛かって体を反らせ、グッと伸びをした。どら焼きとは違う意味でふわふわの髪が、チアガールのポンポンのように揺れる。
「十五時半くらいにって言ってたからそろそろだと思うんだけど……って、虫の知らせもいいところだね」
話している途中にノックの音が聞こえ、海さんは「はいはーい!」と上機嫌でドアを開けに行った。
「お久しぶりです、黒鉢さん」
「どうも、ご無沙汰しています」
黒鉢と呼ばれたグレーのスーツを着た男性は、五十歳くらいに見えた。丸い顔は肌つやも良く年齢の割には若く見えるものの、「中肉中背」というにはお腹周りの主張が激しく、頭頂部の髪の毛もやや心許ない。不安げな表情もあいまって、率直に言って「冴えないおじさん」という印象を受ける。
「紹介します。最近僕の助手になった、安西織貴君です」
俺の方に開いた手を伸ばし、唐突に紹介を始める海さん。助手扱いしてくれるのを喜びつつ「こんにちは」と一礼すると、黒鉢さんは俺よりも深く頭を下げた。
「黒鉢俊之です。家出した娘の居場所を探していて、須藤先生に依頼してます、よろしくお願いします」
「まだ帰ってこないんです。『ちゃんと暮らしてるから大丈夫だよ』って連絡は定期的に妻に来ているので何か事件に巻き込まれたということではないと思うんですが、やっぱり心配ですね……」
「そうですか。連絡を入れてるということは別に家や家族が嫌になったわけではないということかと思いますが……」
そのやりとりを聞きながら、隣の海さんに同調して頷く。彼が中鉢さんの話に相槌を打ちつつ、俺に向けて補足で説明を入れてくれたので、今回の依頼の概要がだいぶ見えてきた。
黒鉢さんは横浜の方に住む五十歳。普段は営業の仕事をしており、今日もクライアント訪問の途中で寄ったとのこと。若いときは誰もが知る上場企業で、全国を飛び回る相当優秀な営業マンだったらしい。今の見た目からはあまり想像がつかなかった。
二十歳になった大学生の娘、仁衣香さんが家出をしたらしく、その調査を依頼したのが九月末だという。定期的に連絡が来るらしいが、どこにいるか全く分からないとのことで、海さんはじっくり居場所を探しているらしい。
「安心してください。だいぶ仕込みも進んだので、今週あたりから動いていこうと思ってたところでした。おそらく見つけられると思いますよ」
「本当ですか、ありがとうございます!」
項垂れていた黒鉢さんは顔を上げ、安堵したような表情を見せた。そして、この後も仕事が入っているらしく、「今度は銀座です」と慌てて黒い大きなビジネスバッグを肩から提げる。
「では、本当によろしくお願いします」
「動きがあったらすぐに教えますね」
海さんの言葉に、彼は玄関先で深くお辞儀をして、事務所を出て行った。
「よし、じゃあ動いていかないとだね」
「あの、海さん」
「ん、どしたの、オル君」
首を傾げる彼に、俺は一番の不安をぶつけた。
「あの、失礼な質問かもしれないですけど、本当に親子なんですよね? その……」
「若い子を狙うストーカーなんじゃないかって?」
察しの良い彼の言葉に、俺は黙って頷いた。
「いや、失礼じゃないよ。むしろそこに気が回るのは優秀な探偵の素質があると思う。今回は大丈夫。初めて来たときに、僕も同じ疑問を抱いたから確認したんだよ。そうしたら、証拠として写真を見せてくれた。幼稚園のお遊戯会と、中学の体育祭と、高校式卒業のときのだったかな。ストーカーに明るい僕の直感も踏まえて、問題ないって判断したんだ」
「明るいというか、同類の匂いみたいなもの——」
「さあ、じゃあ探していくよ!」
俺のツッコミを華麗にスルーして、海さんはパソコンのキーをタンッと軽快に叩いた。
「さっきの言い方だと、全く手がかりがないんですか?」
「いや、SNSは見つけたよ。インステをメインでやってるみたいだね」
Instegram、通称インステ。写真や動画の共有がメインのSNSだ。
「仁衣香って名前も珍しいし、家出しても大学に通ってるってことは都内近郊に住んでるってことでしょ? その辺りの情報で幾つか組み合わせたら、他にやってる実名のSNSからリンクで簡単に辿り着けたんだ」
「そうなんですね。じゃあいつも通り、投稿内容を見れば……」
「いや、それがそうもいかなくてね」
背もたれに寄り掛かった海さんはタバコの煙を吐き出すかのように口を丸くして息を吐いた。
「インステ自体は探し当てたんだけど、完全に人の投稿を読んだり仲の良い人にリプするためだけに使ってるらしい」
「あー、分かります」
これまで海さんと話した中で一番というくらい、同調してみせる。俺も同じだからだ。インステはおもしろ動画や役に立つ生活の知恵みたいな投稿も多いけど、周囲の友人が投稿しているのは専らオシャレな写真だ。こんな美術館に行った、こんなスイーツを食べた、こんなアウターを買った。俺もはじめは適当に写真をアップしていたものの、次第に何を見せればいいか分からなくなり、いつの間にか閲覧してコメントするだけのサイトになってしまった。
「仁衣香さんからの投稿がないから、手掛かりがまったくない状態だね」
ほら見てごらんと言われ、俺は横から彼のパソコンを覗く。黒鉢を文字ったであろう「クローバー」という名のそのアカウントは、何の写真もアップしていなかった。
フォローしている人がアップしている、都内のオススメ喫茶店に関する投稿を拡散したり、オシャレなカフェの紹介に「行ってみたいです!」とリプを返したりしている。彼女のフォローやフォロワーに「紅茶女子」「紅茶大好き垢」といった名前が並んでいるのを見ると、どうやら趣味の情報収集用に使っているらしい。
「この状態からどうやって居場所を調べるんですか? 住所が分かるものを投稿するまで待つとか?」
でも今まで一つも投稿してないのに現実味がないなあ、と思っていると、海さんは首を振った。
「それでうまくいく確率は低いだろうね。万が一投稿してくれるとしても、いつまで待つか分からない。こういう場合は懐に飛び込んだ方が早いんだよ、ほら」
彼は何度かクリックして、得意げに画面を指差す。液晶に映った「うみねこ」というアカウントは、仁衣香さんのクローバーと相互フォローになっていた。
「このうみねこさんがどうかしたんですか?」
「うん、これは僕が作ったアカウントなんだ!」
俺は改めて思い知らされた。この人は、相手を知るためならどんな形でも接近するのだと。
「こうして仲良くなっておけば、DMで直接聞くこともできるしね! ちなみに21歳女子大生って設定だよ。やっぱり大学生同士の方が心開きやすいからさ!」
メガネの奥で、獲物を見つけた肉食動物のように目を光らせている海さんに対し、俺は幾つもの疑問を脳内に浮かべながら呆然とモニタを見ていた。
「え……うみねこっていうのは何ですか?」
「アカウント名だよ。須藤海の『うみ』に、『ねこ』。ほら、僕って犬か猫かって言ったら猫っぽいでしょ」
「いや、分からないですけど」
世界で一番どうでもいい質問だと思いつつ、もう一度フォローの画面に目を遣る。何度見ても、確かにクローバーこと仁衣香さんと相互フォローになっていた。
「あの、どうやって相互フォローになったんですか?」
「仁衣香さんが紅茶やカフェ巡りが好きなのは分かったでしょ? 本人が投稿してないから、こっちからいきなりフォローするのは変だよね。まずは関係性を作らないといけない。だから、まずはアカウントを作って、ちゃんと彼女が好みそうなアカウントに育てたんだ」
「アカウントって育てるものなんですね」
そんな表現は初めて聞いたが、たぶん投稿をして「それっぽい」ものに見せるということなのだろう。
「いきなり幾つも写真をアップするとおかしいからね。一ヶ月かけて日々ちゃんと投稿して、仁衣香さんが好きそうなアカウントにしつつ、彼女がフォローしてる人をフォローした。で、二人がリプしあってるときにいいねを付けて、こっちに気付いてもらえるようにしたんだ。案の定、途中から会話に混ざってくれた。そろそろ僕からフォローしようかなって思ったら、向こうからフォローしてくれたんだよ」
確かに、「うみねこ」のページは紅茶やお菓子の写真で溢れていた。しかも店の感想もしっかり書かれてるし、写真の撮り方も美味い。これなら仁衣香さんは興味を持ってくれるに違いないだろう。
「でも大変でしたね。このカフェの写真とか、いちいちネットから探したんですもんね」
「ちょっとちょっと、オル君。人が撮った写真とか、勝手に引っ張ってきたら犯罪だよ」
「人の情報を勝手に詮索するのはいいんですか……」
海さんの倫理観にツッコミを入れつつ、一つの疑問が脳裏を過った。
「え? あの、ちょっと待ってください。ってことは、これ、海さんが撮ったんですか?」
「そうだよ? わざわざ『トーキョー カフェブック ~紅茶編~』ってのを買って、オル君がいないときに巡ってたんだから」
「えっ! 一人でですか!」
「一人に決まってるじゃないか。このスーツで巡ったんだよ」
都内のカフェに、男性一人で入るだけでも割とハードルが高いのに、こんなよれよれのスーツで入ったとは……お店側も相当びっくりしたに違いない。
「何が良いって、カフェの費用を経費で落としていいって契約になってることだね。おかげで紅茶もケーキもじっくり味わって感想を書くことができたよ」
「ああ、だから食レポが上手くなってたんですね」
いや、そんなことより、俺にはどうしても一言言いたいことがある。
「あの、海さん、今度こそ言わせてもらいますけど……これはホントにストーカーですよね!」
「違うよオル君、これは捜査だよ! それに、ここまで何も投稿せずに隠されたら、逆に興味を持って知りたくなるでしょ!」
「いや、もうそのスタンスが……」
相手のことを知るために、一ヶ月かけてアカウントを捏造する。なんでこの人は、ここまでの情熱を燃やせるのだろう。疑問と感服が一気に押し寄せ、目を細めて首を傾げる。
「でも、本当にそろそろ頃合いだ。本人に連絡を取って情報を探っていこう。この一時間で二件リプを送っているところを見ると、今は暇してるらしい」
俺が隣に来ることを見越して椅子ごと窓側に動き、海さんはDMの画面を開く。彼がチェックすれば、いつどこが空いているかなんて平日のスケジュールも簡単に予測できてしまいそうだ。
「まずは……そうだな、通学してるなら都内近郊に間違いないとは思うけど、大学を休んでるって可能性もなくはないからね。そこを確認していこう」
「確認ってどうするんです? ダイレクトに聞くんですか?」
隣の俺の質問があまりに面白かったのか、海さんはブフッと吹き出した。
「いきなりそんなこと聞いてたら怪しまれるよ。あくまで彼女の興味に寄り添うことが大事だね」
そう言って、キーボードを高速で弾き、文章を打っていく。
『こんにちは! そしてDMでははじめまして、ですね(笑) いつもリプやいいね、ありがとうございます!
そして急に連絡すみません。この前、リプの中で行ってみたいと言っていた恵比寿のカフェ “アナザールーム”なんですが、来週からクリスマスフェアをやるそうです! お住まいが都内近郊か分からないのですが、もしよければと思い、勇気を出して連絡してみました。ぜひ確認してみてください。リンク送っておきますね!』
「こうやって書いておけば、さらっと確認できるでしょ?」
「確かに……」
これで、少なくとも東京近くに住んでいるかどうか、返事で絞ることができそうだ。あと、海さんの『ある程度距離のある女子同士』の文章にほとんど違和感がないのがすごい。
「これで返信を待つんですか?」
俺の問いかけに、海さんは「そうだね」とニッと口角を上げ、食品棚を指差す。
「その間にもう一杯、買ってきた紅茶を飲もうかな。ちょっと渋みがあるから、ザラメを入れてみるよ」
ティータイムで十分経過したが、返事は来ない。不意に訪れた、予期せぬ休憩時間。空気が籠っていたので窓を開けると、待ってましたと自己主張するように秋の風が吹き込み、俺の髪とシャツの襟を揺らした。今ごろ大学の近くで、同じような風が木の葉を舞い落して遊んでいるに違いない。
暇ができてやや退屈しているのか、海さんは軽く首を回す運動をした後、ザラメたっぷりの甘めの紅茶に口をつけながら「ううん」と唸った。
「返事に困ってるのかな。都内じゃない可能性もあるからね。北関東に行ってて、そこから通ってるって可能性もなくはない」
「確かに東京寄りなら通えますもんね」
「僕も群馬にいた頃は、都内に憧れてたからなあ」
「えっ、海さんも群馬なんですか!」
出会って一ヶ月、初めて知る衝撃の事実だ。
「そうだよ、言ってなかったっけ? オル君が群馬ってのは聞いたけど」
「言ってませんよ。うわっ、そうなんですね。なんか急に親近感が湧いてきました」
東京の大学にいると、どうしても東京や千葉、神奈川の知り合いが増えていく。その分、北関東の人間は、なんとなく同志のように感じてしまい結束が強くなる。とはいえ、栃木・茨城・群馬でも北関東ナンバーワンを決める戦いがあったりして固い結束でもないため、真の仲間は群馬県民だけなのだ。
「え、僕は高崎なんですけど、海さんは群馬のどのあたり出身なんですか?」
「赤城山の近くだよ。まあ田舎だよね」
「それは、ええ、まあ」
桐生市や沼田市にかかっている、群馬県ほぼ中央の山。県内でも高崎とはそれなりに差がある。
「まあ自然は綺麗だったけどね。特に赤城山の紅葉の見事さ。群馬全体を華やかに色づかせる、真っ赤なナナカマドの美しさは素晴らしいよ! オシャレな個人経営のカフェはほとんどないけどね!」
「高崎にもそんなになかったからそこは引き分けですよ」
県内のちっちゃなマウント抗争に笑うと、海さんも相好を崩した。
それにしても、海さんが同郷だったなんて驚きだ。大学から東京に来たのだろうか。それとも社会人から? よく考えたら、彼のことを何も知らないことに気付く。探偵ほどの好奇心ではないものの、彼のことをもう少し知りたいと思えた。
「海さ——」
「おっ、返事が来た!」
折り悪く、話を振ろうとしたタイミングで彼は嬉々として画面を食いいるように見つめた。インステにクローバーさんからのDMが来ている。
『こんにちは、はじめまして! ご連絡ありがとうございます! いつも色々な紅茶のお店行ってて羨ましいなあと思ってました。笑 アナザールームの情報、とても嬉しいです。近郊というばっちり都内なんで、今度遊びに行ってみます!』
「まずは一歩前進だね。でも範囲を狭めていくのはここからだよ」
逃がさないよ、と彼は楽しそうな笑みを浮かべる。つり上がった眉が若干怖い。こうして横から見ていると、完全に犯罪者の匂いがする。
「ここからどうするんですか?」
「あくまで紅茶の話題から逸れないようにして、もう少し深掘りしていく感じかな」
言いながら、海さんはまたカタカタとキーボードを打つ。さっきも感じたことだけど、海さんはタッチタイピングが正確で、しかも速い。このスキルで大学のレポートを書いたら、もう少し学期末の作業が楽になるだろう。
『都内なんですね、一緒だ! カフェ好きなJD仲間がいて嬉しいです、これからもやりとりさせてください!笑
ちなみにクローバーさん(って呼んでもいいですか?)はどんなカフェが好きなんですか? 都内でよく行くカフェあれば、いつか行ってインステで紹介してみたいです!』
「これで特定のエリアのカフェが多く出てきたら、そこの近くに住んでる可能性が見えてくるってわけさ」
「さすが……」
スムーズな会話の中で、ヒントを見つけだすテクニックがすごい。仁衣香さんも、まさか住所を推理するためのやりとりだなんて想像もしていないだろう。
「海さん、相手に直接コンタクト取りたいときは、いつもこんな風にアカウントを作ってるんですか?」
「ああ、いや、今回はインステだったからね。Tweeterはもう持ってるんだよ」
「え、専用のアカウントですか?」
彼は食品棚からザラメを取り、「そうだよ」と小皿にジャッと移した。
「今年二三歳の女子、うみねこって名前でね。男性アカウントだと女性に接近しづらいんだけど、女性ならどっちにもアプローチできるから都合がいいんだ。そうだな……もう二年は更新続けてるんだよ。毎日ツイートしてるから、偽物って疑われることもないだろうね」
「それはもはや偽物と呼べないのでは……」
年齢と性別を偽っているだけで、普通に海さんのアカウントな気がする。
「普段忙しいときも、うみねこで投稿するときだけは少し心が穏やかになるんだよね。多分、僕がうみねこちゃんを『人と絡むのは好きだけど、基本はおとなしい』ってキャラとして捉えてるからだと思う。自然と、自分の思ううみねこちゃん通りの振る舞いをしてるっていうか」
「役になりきってる、ってことですね」
陳腐にも思えた俺の合いの手にしかし、海さんは納得したように頷いた。
「心理学者のエリック・バーンが提唱した『人生脚本』に拠ると、僕たちは無意識にそのシナリオ通りに生きてるらしい。オル君の言う通り、役が普段の言動を作るって感じなのかな。だとしたら、うみねこももう一人の僕が作り出した脚本かもしれないね……と、返信が来たよ」
流暢に専門分野について話していたのを止めて、彼は画面を人差し指でコツンと叩いた。
『私も趣味が合いそうな方に出会えてすごく嬉しいです!
好きなカフェ……千駄木にあるHAGA CAFÉって行ったことありますか? 古民家カフェみたいな、古い佇まいのカフェ結構好きなんで、よく行ってます。あとは根津にあるイングリッシュティーホームってお店も、古民家の紅茶専門カフェで、ダージリンとスコーンのセットが特にオススメです!』
「あの辺りか。ってことは……」
海さんはすかさずマップのサイトを開く。お店の名前を打ち込んで広域表示にし、都内のどのあたりかを瞬時に把握する。
「東京の北部、上野方面によくいるみたいだね」
まるでゲームのモンスターの出没場所を分析するように話す彼の顔は、予想通り楽しそうだった。
▼ 第3章 後編
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
