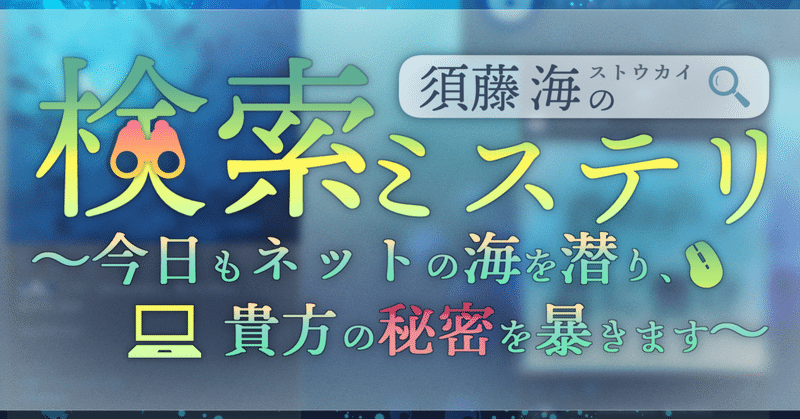
須藤海の検索ミステリ 第3章 ターゲットをフォローして(後編)
「所謂、谷根千エリアか、確かにカフェが多いし、安い店も多いし、学生には重宝する町だね」
「やねせん? そんな駅ありましたっけ?」
海さんはマップを拡大し、上野の少し北部、JRの鶯谷駅付近を中央に映して見せる。
「谷中・根津・千駄木エリアを合わせて谷根千って呼ぶんだ。東京二三区の中心地に近いのに、下町の風情も残してる人気スポットだよ」
「あ、なるほど、頭文字を取ってるんですね。一人散歩のときに何度か歩いた気がします」
歴史と情緒の溢れる町って感じで、散歩にはピッタリだった覚えがある。仁衣香さんが好む、古民家カフェみたいな店が多いのも納得だ。
「確か、霊園とかありましたよね?」
「谷中霊園だね。十五代将軍の徳川慶喜とか、日本画で有名な横山大観とかが眠ってる有名な場所だよ」
すらすらと豆知識が出てくることに軽く感心してしまう。これまで様々な事件でそれぞれの街を調べてきたんだろう。
「さて、ここまでは比較的イージーだったけど、問題はここからだね。そもそもこのあたりに住んでいるかどうかも確定はしてない。メトロで一本で来れる、離れた駅が最寄りってことも十分に考えられるからね。どうやって探っていこうかな……」
腕組みをする海さん。冗談めかした雰囲気はなく、本気で悩んでいるようだ。その迷いを汲み取ったかのように、机からはみ出ていた雑誌が椅子にぶつかり、上下に揺れた。
「海さん、そろそろ『どこに住んでるの?』って聞いちゃダメなんですか? ほら、一緒にカフェに行こう、みたいな名目で」
俺の提案に、彼はお礼を言うように目を細めて頷いた後、「でも」と口を開く。
「仮にそうやってお誘いするにしても、住んでる場所を聞く理由にはならないからね。僕が本物のうみねこさんなら、会ってから帰り道送るって名目で知れたりするけど、生憎僕は大学生じゃないから」
「まず女子じゃないので……」
根本的なところが抜けてる返答に、なんだか笑ってしまった。
「まあ、定石通り行ってみよう。相手のことを知るには、まず自分からだ」
「自分から?」
海さんは組んだ手をグッと前に突き出し、気合いを入れ直してから、パソコンに向かう。俺はマグカップを洗面所で洗い、その隣にあるトイレに行ってからパソコン前に戻ると、彼はすでにDMをほぼ完成させていた。
『あ、どっちも結構前に行きました! っていうか、つい最近まで谷中に住んでたので(笑)
HAGAカフェ、ラム漬けした無花果のチーズケーキがすごく美味しいんですよ! あと、王道メニューなんでみんな頼まないですけど、パフェが美味しいんです。あの店で出してるコーヒーを使ってるんで、コーヒーの苦みとアイスの甘みが相性バッチリです!
イングリッシュティーホーム、窓際の席に行くと庭の緑が見えて綺麗ですよね。キャラウェイシードを使ったちょっとスパイス感のあるケーキを食べながら、何時間も読書していたくなります!
谷根千あたりだと、根津のひみつ園っていうかき氷屋さんがすごく好きなんですけど、クローバーさん知ってます? ひみつって氷と蜜で”ひみつ”って読ませてるのかなって推理してました(笑)』
「すごい、めちゃくちゃ詳しいじゃないですか! 海さん、うみねこの投稿のために行ったんですか?」
「いや、行ってないよ」
何を当たり前のことを、とばかりに彼はけろりと返す。
「検索すればメニューなんかいくらでも出てくるでしょ? それに谷根千のカフェは人気だから特集記事だっていっぱいある。その情報を組み合わせただけだよ」
「ええ……なんか不誠実な……」
「なんてことを!」
俺の言葉に、海さんはメガネの奥の目をカッと見開く。
「いいかい、オル君。知らないことを知らないっていうことも大事だよ? でも雑談だったら、こっちが少し調べれば、同調したり共感したり、新しい話題を振ったりすることができる。その方が相手にとっても嬉しいはずだよ。ある意味誠実だと思わないかい?」
「まあ、それはそうなんですけど……」
なんだろう、うまく言いくるめられてる気がする。
「相手のことを知るためには、自己開示をした方がいい。『相手が教えてくれたなら、自分もお返ししなくちゃ申し訳ない』と思わせることができるかもしれない。前にも話した、返報性の原理だね。それに、こうやってたくさん共感して情報を教えてあげれば、ラポールを築くチャンスにもなる」
「ラポール?」
謎の専門用語に首を傾げていると、海さんは人差し指で自分の胸を差した。
「この人のことは信頼できる、この人になら何でも話せる、っていう信頼関係のことを、心理学でラポールって呼ぶんだ。『橋を架ける』という意味のフランス語だよ」
「なるほど、住所に近い情報も得られるようにしようってことですね」
「そう。うみねこさんはクローバーさんのほぼ親友だからね」
「本体が二八歳男性って知ったらがっかりしそうです」
ネットで性別を偽るのは珍しいことではないけど、ここまで手が込んでるアカウントだとそうそうバレないだろう。
「でも手前味噌だけどかなり良い返信が書けた気がするよ。ちゃんと向こうの情報に反応しつつ、別の店も紹介して仁衣香さんに、『やりとりしてると良いことがある』と思わせる。あと、自分も近くに住んでたってのは正に自己開示だね。こっちから自分のプライベートを晒しにいったんだ」
「なんで過去形にしたんですか? 今住んでるって方が親近感上がるのに」
「今近くにいると思ったら警戒されるかもしれないからね」
海さんは少しだけズレたハーフリムのメガネのフレームをクッと持ち上げる。
「会いたいって言われて困る場合もあるだろうし、普段の姿を見られたらと思うと詳細な情報を教えてもらえなくなる可能性もある。昔住んでたって言えば、話題だけは共通で進められるから何かと都合がいいんだよ」
「なるほど……」
何気ない返信に見えて、ちゃんとテクニックが織り込まれている。やっぱりこの人は相当な策士だし、プロフェッショナルだ。
「さて、仁衣香さんからの返信を待とう。オル君もザラメ食べるかい?」
「いえ、遠慮しときます」
そこからは、海さんはザラメを食べ、俺は冷蔵庫にあった一リットル百円のレモンティーを飲み、少し休息を取る。ここまで順調に家のエリアを絞れてきた俺達にとっては、ヒートアップした熱を冷ます良い機会になった。
やがて時刻は十六時半となり、窓に差し込む西日が少しだけ染まる。ガラスに微かなオレンジ色が溶け込み始めたタイミングで、クローバーさんからDMが返ってきた。
『やっぱりうみねこさん、めっちゃ詳しいですね! HAGAカフェのパフェ、今度食べてみたいと思います!
ひみつ園なら行ったことあります! 私は結構その近くに住んでるので! いちごみるくが美味しいんですよねー!
うみねこさんもこの辺りだったんですね、ぜひ近隣のカフェたくさん教えてください(笑)』
「よし、行こう」
不意に海さんは立ち上がり、薄いターコイズカラーのバッグに財布や携帯、そして黒い謎の棒などをガサガサと詰めだした。
「え、どこへですか?」
「駅だよ。ここからは直接探す」
いつものネイビーのコートを着て、事務所を飛び出す。競走馬が走り出すかのように一気に階段を降りる海さんの後ろを、慌てて付いていった。
「とりあえず、谷根千エリアに住んでるってことは確定したから、ここから現場まで行ってヒントを集めながら見つけていこう。日暮里までは十分くらいだね」
JRの京浜東北線に乗り、ドア近くに並んで立ちながら、海さんは車窓の外を見遣る。谷根千エリアはここから一本の日暮里駅から歩けるらしい。そういえば、大学で散歩しているときに、谷中霊園から日暮里駅まで歩いた気がするな。
「でも、十八時には暗くなりますよ? 調べるなら明日でもいいんじゃ——」
「いや、今のタイミングを逃すわけにはいかない」
俺の言葉を遮る海さん。そのキリッとした真剣な目つきはいつもと様子が違い、普段からその表情で服装もしっかりチョイスすれば女性からも人気が出るのでは、と思わせる。
「今ならDMを続けても問題ないけど、もし会話が終わってしまった場合、明日その続きを再開するのは難しいからね」
「確かに、『もう終わったのに』ってなりますよね」
俺も経験があるから分かる。昨日の話題をもう一度蒸し返すのは、結構難しいし勇気がいるものだ。
「とりあえず、着いたら仁衣香さんに写真も送って連絡しよう。具体的な家まで特定しないといけないからね」
そこからしばし沈黙が続く。目的地まであと十分弱。
せっかくだから海さんのこと聞いてみようと思い、話を振ってみる。さっき彼のことを知らないと考えていた俺にはうってつけの時間だった。
「……大学で群馬から東京に出たんですか?」
いつもの軽いノリで、「おっ、オル君、知りたい?」なんて返してくるかと思ったものの、彼は外を眺めたまま「ん……」と言葉に詰まる。それはまるで、瞳の奥を俺に見せないようにしたまま、どう答えるかを迷っているかのようだった。
やがて彼は、フッと短く息を吸って、口を開いた。
「東京に来たのは大学からだけど、高校で埼玉に行ってるんだ。だから群馬にいたのは十五歳までだね」
「そうなんですね。転勤ですか? あ、その、答えたくなければ無理には」
なんとなく第六感が働き、最後に一言付け加える。しかし彼は、もう覚悟を決めていたのか、「大丈夫だよ」と首を振った。
「転勤は転勤だけど、予期しない形だった。うちの母親は小学校教師をやってたんだけど、僕が中学二年生のときに車で交通事故を起こしてね。小学生の男の子を轢いてしまったんだ」
思いもよらない告白に、息が止まる。頭の中で、救急車のサイレンが響く。
「安心して、奇跡的に子どもにケガはなかったよ。ちょっと擦りむいて出血しただけで、骨も折れてないし、脳にも全く異常はなかった。急に男の子が飛び出してきたらしいけど、ブレーキが間に合ったし、ぶつかって飛ばされた先が植え込みだったのもクッション代わりになって幸運だったらしい。とにかく、事故自体はまったく問題なく終わる……はずだった」
そこで彼は一息つき、中指の部分だけ少し突き出した握りこぶしを窓ガラスにコツコツぶつける。そこには、幾許かの苛立ちが見て取れた。
「ある日ね、中学で友達に言われたんだよ。『お前の母親、子ども轢いたんだって?』誰かがその事故のことを調べて、地元向けのネットニュースにルポ記事みたいな扱いでアップしてたんだ」
「それって……」
「ああ、フリーライターが僕たちのことを探ったんだ。事故のことを聞いて、興味本位で母親のことを調べた。『小学校の教師が小学生を轢いた』なんてネタとしては面白いだろうからね」
今の海さんがやっているようなことを、仕掛けてきた人がいた。小さくても、ネット記事は普通の雑誌や新聞の記事より拡散されやすい。どんな結果になったのか、聞くのが怖かった。
「うちの母親だって必要な罪は償ったはずだけど、ゴシップっていうのはそれ以上の影響力があるからね。田舎だったから噂が回るのも早くて、結局母親は群馬での仕事を辞めた。でも、ちょうど知り合いが埼玉の私立小学校で働いてたみたいで、その紹介もあってすぐに次の仕事が決まったんだ。まだ家も買ってなかったし、父親も埼玉に通勤してたからちょうどいいだろうってことで引っ越すことになったんだよ」
ネットでリサーチして晒した結果、一つの家族が家を移した。文章にしたら大した結果ではないように見えるけど、海さんにも、母親にも、父親にも、みんな居場所があったはずで、それを捨てて新天地に向かうのは辛いことだったはずだ。それはちょうど、俺がなりすましの被害を受けて、部活や友人を失ったように。
「海さんは、どう思ったんですか? やっぱり怒りました?」
「ああ、うん。『人間って面白い』ってなったよ」
「……え?」
予想外の返事に、口をぽかんと開ける。
「だってそうでしょ? そんな、誰にも褒められない、自分の得にもならないことをわざわざ検索したのかって。それは自分が知りたかったからだろうし、他の人もそれを知りたかったから記事を見た。興味がある人のことを知りたいって欲求はすごいんだなって、なんか逆に感銘受けちゃったよ。それが今の仕事にも繋がってるからね」
「そういう見方もあるんですね……」
海さんが変人なのは分かっていたけど、ここまでとは。でも、深く傷ついていないのなら、却って良かったのかもしれない。その結果、彼は今探偵をやって、何人もの人を助けているわけだし。
「あとは……まあ、検索を悪用しない、っていうのはこの事件絡みで誓ったから、そこだけは感謝かな」
「悪用、しようとしたんですか?」
俺の質問に、彼は不敵な笑みを浮かべた。
「大学院で学んで、今みたいに検索の技術も身に付けてさ、相手の名前も確認して、一度だけ復讐を考えたことがあるんだよ。晒してやろうって。でも、母親から止められた。『それをやったら相手の名前がネットに残る。入れ墨と同じくらい、一生消えない傷だから』って諭されてさ」
自分が暴かれて晒されて、傷つけられた側なのに、相手のことを思いやって諫める。海さんのお母さんは本当に人格者だ。
「デジタルタトゥーって言葉も知らないのに、入れ墨に例えるあたりの感性がすごいって感心しちゃって。それで、なんかやめようって思ったんだよ。あれがあったから、後ろめたい思いもないまま、ずっと探偵を続けてられるのかもしれないね」
「それは……良かったですね」
相好を崩す彼につられて、ニッと笑う。思ったより深い話になったけど、少しだけ海さんのことを理解できた気がする。
「よし、ちょうど着いたね」
日暮里駅に着くと、海さんはどんどん西に歩き、御殿坂と呼ばれる坂を進んでいく。五分ほど歩くと、谷中銀座と書かれた大きな商店街に着いた。そこから道を一本外れてマンションが立ち並ぶエリアに来てキョロキョロと周辺を見回し、三階建ての如何にも学生が住んでそうな低層マンションを指差した。
「よし、このマンションから撮った写真を仁衣香さんに送って、向こうからも写真を引き出そう」
「写真って、そんな都合のいい画像、ネットにあります? 下手なもの使うと、この近くじゃないってバレませんかね?」
「オル君、前も行ったけど、僕は画像を無断で使ったりしないよ」
そう言うと、海さんはおもむろにバッグから何かを取り出す。出かけるときに放り込んでいた、五十センチくらいの黒い棒だった。
「それ何ですか?」
俺が訊くのを楽しみに待っていたかのように、彼はニヤリと笑って見せる。そして、棒の先端にスマホを取り付けた。
「セルカ棒だよ」
「セルカ棒って……え、あの自撮り用の?」
「そう。あれの、最大進化版って感じ……だね!」
「うわっ!」
溜めて言い切った「だね!」にタイミングを合わせて、彼はその先端をグイッと引っ張る。内側に入っていた部分がどんどん伸びていき、俺達の身長をあっという間に追い越して、まだ大きくなっていった。
「高さ四メートル、手頃な値段の中じゃ一番長いヤツなんだ。これで撮れば、二階からの写真に見えるからね。それじゃこのBluetoothリモコンのボタンを、と」
海さんは風を気にしつつセルカ棒の向きを変え、手元のボタンを何度も押している。説明してくれたところによると、スマホの音量調節ボタンがシャッターになるのを活かして、Bluetoothで無線接続してシャッターを切っているらしい。
ナイスアイディアだと思うけど、マンションの近くで棒を伸ばして写真を撮っているので、傍から見ると盗撮に間違われる気がする。ストーカーで盗撮、海さんのイメージが危ない。
「うん、これなんか良さそうじゃない?」
セルカ棒からスマホを外して見せてくれた写真にはチェーン店の屋根や道路標識が映っていて、確かにマンションの二階あたりから撮ったように見える。
「じゃあこれを送ろう」
続いて彼はインステのアプリを開き、DMを打ち始めた。海さん、スマホで文字を打つのが女子高生並に速い。
『ホントですか! ひみつ堂の近くってことは、前に私が住んでた家からもめっちゃ近いですね笑 ちなみに、前のマンションのベランダから撮った写真です!笑』
「うまくいけば、向こうからも写真なり家の情報なり貰えるはずだ。仲良くなりたい人と共通点があれば、共有したくなるからね」
「貰えなかったらどうするんですか?」
俺の質問に、彼は具問だとでも言いたげにチッチッチと指を振った。
「今日は諦めて、次回チャンスを狙って聞き出そう。毎回そんなにうまくいくわけじゃないよ。ストーカーは一日にして成らず、だね」
「ストーカーって言っちゃってるじゃないですか!」
「まあ今のは言葉の綾だよ。おっ、返信が来たよ」
彼がスマホを俺の方に傾けたので、覗き込んでみる。そこには低層階からの写真が添付されていた。
『わっ、ありがとうございます! 映ってる薬局、よく行くところです(笑) せっかくなので私も、ベランダからの写真お見せしますね!(笑)』
「よし!」
海さんが胸元で小さくガッツポーズする。少しずつ陽が沈んできているけど、まだ景色がはっきり判別できるので助かった。とはいえ。
「よく見ると、特徴的なものは映ってないな。ここから探すのは至難の業だ」
さっきまでのテンションとは打って変わって、彼は細く長く息を吐く。写真には店などが映っておらず、標識や幾つかの建物が映っているだけだった。
「この辺りを歩いて見つけていくと暗くなりそうだし、最悪続きの捜査は明日以降に回すか……」
落胆する海さん。今日で完結しないとすると、さっき話していた通り、明日DMを再開しなければならない。連日執拗に住所に関わることを訊いていたら怪しまれるだろう。彼の気落ちももっともだった。
「……あれ? 海さん、その写真、よく見せてください」
俺はスマホを借り、ジッと見つめる。奥に見える、少し大きめの戸建てらしき建物。その入り口に付けてある変な看板に、見覚えがある。
「この看板、前にこの辺りを散歩したときに見つけた気がします」
「オル君、ホント?」
頷きながら記憶を遡る。高校のなりすましの事件以来、人と関わることを避けて始めた散歩や一人旅。その経験を役立てられるかもしれない。
「これ、ウサギっぽいけど、確か……」
やや暗いからシルエットしか分からない看板。異常に尻尾が垂れ下がってるウサギに見える。でも、あの時も同じことを思っていたはずだ。
「耳に見える部分は……クワガタ! そう、クワガタのハサミだ! これ、ファーブル昆虫館ですよ!」
「あっ、僕も名前は聞いたことあるよ。ありがと、オル君、助かった!」
フランスの学者であり「昆虫記」があまりにも有名なファーブルに由来した、昆虫の魅力を学べる博物館。その建物だった。
「これは……千駄木にあるね。行ってみよう」
千駄木の、この建物が見えるマンション。だいぶ候補は絞られた。
「あの三つが候補だね」
谷中から歩くこと十分。俺たちは千駄木のファーブル昆虫館近くに来ていた。クワガタと虫を探している男性のシルエットが目立つ看板を背にマンションを探すと、三棟のマンションが見える。このどれかに、仁衣香さんはいるはずだ。
「どうします? 海さん、写真で仁衣香さんの顔分かってるんですよね? ここで見張ってたらいつか出てくるんじゃないですかね?」
「オル君、ちょっと待って。それじゃ本当にストーカーだよ!」
「これまでのは何なんですか」
ダメだ、彼のオッケーの基準がよく分からない。
「こういう時は、ドンピシャで当てに行くしかないんだ。まずはこの三つのマンションを調べよう」
そして海さんは、何食わぬ顔でそれぞれのマンションを覗いていく。どれもエントランスがオートロックになっているから建物の中には入れないものの、宅配ボックスや駐輪場、ゴミ捨て場などを念入りにチェックしていた。
そして全て確認し終えると、満足気な表情を浮かべ、スマホのロックを解除する。
「ほいじゃ、DM送ろっか」
そう言って、彼は恐ろしいほど速い指捌きで文章を作っていった。
『わあ、ファーブル昆虫館ですね! 一度も行ったことないですけど笑 千駄木のあの辺りって、新しいマンション多くていいですよね。友達も近くに住んでるけど、宅配ボックスあったり二四時間ゴミ出しできたりしてすごく羨ましいです。通販で紅茶買うこともあるので、受け取ったり捨てたりが便利な方がいいなって。クローバーさん、家でも紅茶飲むなら、オススメのお取り寄せティー教えますよ!』
「これで分かるんですか?」
「うん、一応絞り込めるようにはしたつもり。あとはうまい返事が来るのを祈るだけだね」
ふうっと大きな息を吐く海さんに、俺は「あの」と声をかける。
「今回の件でずっと気になってたことがあるんですけど……」
そして、自分の考えていたことを話す。探偵でもない、ただの大学生の俺の話を、彼は真剣に聞いてくれた。
「どうですかね?」
全部聞き終えた海さんは、やがてニッと笑い、ゆっくりと首肯した。
「オル君、鋭いね。僕も同じこと考えてたよ」
「え、じゃあ……」
「最後に言うつもりさ。おっ、返事が来たよ」
通知音をオンにしていたらしく、ポンッという音がスマホから響く。
『そうです、昆虫館です! 私は大学の友達と一回だけ行きました。もう行かなくていいかな……笑 うちのマンションはやや古いので、ゴミはいつでも出せますけど宅配ボックスはないんですよね(涙) お取り寄せティー、気になります! ぜひ教えてください!』
「よし、ベストな返事だ! マンションは確定だね」
海さんは一番近い「アーバンエステート」という三階建てマンションのエントランスに向かいながらホッとしたように溜息をついた。
「いつでも使えるゴミ出し場があって宅配ボックスがないのは、このマンションだけだ。後は……」
オートロック手前のエントランスを入り、右手にある集合郵便受けを指差しながら確認する。
「ポストに黒鉢の名前はない。名前が空欄なのは二部屋だけど、さっきのベランダからの写真を見るに一階はなさそう。ってことは多分この部屋だね」
二○六という部屋番号を写真に撮り、スマホを薄いコートのポケットにしまう。
「すごい、本当に特定できた」
「まあ、部屋まで分かったのは運が良かったね。どうしてもの場合はDMで階数とか聞こうと思ってたよ」
じゃあ黒鉢さんに報告だね、と彼は笑い、寒そうに手を擦り合わせた。
「すみません、連絡もらってすぐに来れず」
「いえいえ、お仕事お忙しいんですから仕方ないですよ」
十一月四日、金曜日。仁衣香さんの家を特定してから二日後、ちょうどバイトで入っている日の夕方に、依頼人の黒鉢さんが事務所にやってきた。この前より若干濃い、ダークグレーのスーツを着ているけど、お腹のワイシャツ生地がグッと伸びている。知りたがっていた娘の居場所を教えてもらえるからかもしれないが落ち着きがなく、表情も不安げだった。
「早速ですが、仁衣香さんは千駄木駅のこのマンションに住んでいますね。部屋番号も書いてます」
応接用のソファーで向かい合って座る黒鉢さんに、海さんは不動産のサイトから印刷したマンションの紹介ページを渡す。右下の余白に、サインペンで二〇六と書いてあった。
「ありがとうございます。早速会いに行って連れ戻せるよう説得しないと」
それを聞いた海さんは、子どもの気持ちを全て理解して話す母親のように、柔らかく微笑んだ。
「娘さん、会えるといいですね。数年ぶり……なんですかね」
瞬間、黒鉢さんはビクッと体を震わせる。黒目がキロリキロリと泳ぎ、明らかな動揺を見せた。そして、今の態度のままでは誤魔化しきれないと判断したのだろう。小さく息を吐いて、口を開いた。
「あの……なんで分かったんですか」
「これは僕の助手の安西君も気付いたことなんですけどね」
彼は、俺のことを持ち上げてから、推理を披露し始める。
「僕が調査依頼を受けたとき、ストーカーとかじゃないかという確認の意味で本当の親子か訊きましたよね。失礼なことをしてしまってすみません。でも、そのとき黒鉢さんは証拠として写真を見せてくれたんです。写真って、データさえ手に入ればいくらでもプリントできる。親子だと証明するには、戸籍などを出すのが一般的、というか確実です。それを出せないのは、何か理由があるんじゃないかと思ったんです」
依頼人は頷きながら静かに聞いている。口を湿らすように海さんがマグカップのコーヒーを飲むと、湯気がメガネを曇らせた。
「で、あのとき見せてもらったのは三枚です。幼稚園のお遊戯会、中学の体育祭。ここまでは日常の学校行事の写真でした。でも、高校のは卒業式、しかも正門前でのかっちりした写真だった。一人で映ってるから、黒鉢さんが仁衣香さんとお母さんを撮ったわけでもない。
これをもとに、仮説が成り立ちます。彼女が中学のときまでは気軽に撮れる環境にあったけど、高校では入学や卒業の大事なポイントだけ写真をもらっていたのではないか。まあ養育費は二十歳まで払うのが通例なので、ひょっとしたら成人式の写真も持ってるかもしれませんけどね」
謎解きを小休止した海さんは白い陶器の小瓶を開けて、口の広いスプーンでザラメを救う。それをコーヒーに入れるでもなく、手のひらに乗せて普通のお菓子のように口へ運んだ。
「その仮説は今回ここに来てもらってかなり確信に近づきました。そもそも一ヶ月半も家出してるなら、普通ならもっと焦ったり怒ったりして良いタイミングですけど、アナタからはそんな雰囲気が見られなかった。
そして、水曜に報告して、今日は金曜。僕の探偵経験からしても、娘さんを本当に心配しているなら、すぐに飛んできたり、電話でどの辺りに住んでるかだけでも聞こうとするのが一般的な反応だと思います。多分、そこまで急ぎではない。ということは、仁衣香さんが娘なのは本当だし、居場所を知りたいのも事実だけど、家出というのは嘘。違いますか?」
最後まで聞いた黒鉢さんはがっくり項垂れた後、ぽつりぽつりと語り始めた。
「仕事が忙しくて、なんてありきたりな理由ですけど、本当に忙しかったんです。新しい営業支店の立ち上げ担当に抜擢されて、毎日調整ごとと打ち合わせの連続で。で、無事に終わったと思ったらその実績を買ってもらってまた別の支店の立ち上げになりました。認めてもらっているなんていうのはありがたいことで、断るなんて選択肢はない。
でも、そのしわ寄せは家庭に来るんですよね。余裕がなくて妻とのケンカも多くなったし、仁衣香と話す機会も減っていった。結局、仁衣香が高校に入ったときに離婚しました」
仕事と家庭どっちが大事かなんて話、ドラマでもすっかりありふれたものになっている。でも、こうして現実でも度々起こるからメディアにも出てくるのだろう。家庭も大事なのは当たり前で、でも仕事を蔑ろにするわけにもいかなくて、徐々に綻びが生じていく。
「そこから仁衣香さんには会ってないんですか?」
海さんが尋ねると、彼は黙って頷く。
「ええ、もう四年会ってないです。離婚した後も仕事に忙殺されていて家族と頻繁に取れるような状態ではありませんでした。須藤さんの推理通り、高校卒業の写真だけはもらいましたけど、妻にも娘にも会えていません。仁衣香からも会いたいって話は出てないようですしね」
ははは、と力なく笑う黒鉢さん。その目に、一方通行な想いの寂しさが映る。
「最近一人暮らしを始めたということは妻から聞きました。で、私もようやく仕事が落ち着いてきた。でも、『今更父親面しようとして』と思われるのが怖くて、妻から住所を聞くのが憚られたんですよね」
「お会いするんですか?」
「いえ、別に向こうがその気がないのに会う気はありません。でも、手紙を出してみようと思います。言い訳のない謝罪とか、近況を書いてみようかと思って。そこで、万が一連絡を取りたいと思ってくれたらその時は、という感じです」
居住地の紙をバッグの中のクリアファイルに大事そうに入れ、「本当にありがとうございました」と深々一礼して、黒鉢さんは事務所のドアに向かう。こちらを振り返ったときに、海さんが声をかけた。
「うまくいくよう、祈ってます。もしうまくいかなくても、何の連絡も来なくても、想いは届くはずなので」
黒鉢さんはもう一度お辞儀をして、事務所を出て行った。
「仁衣香さんと会えますかね?」
マグカップを洗面所に片付けに行く海さんに訊いてみると、彼は少し斜め上を向いて考えた後、少し微笑みながら首を横に振った。
「それは僕には分からないよ。でも、希望を持って生きられるなら、それで十分なんだと思う。毎日、今日は連絡が来るかなって待つことができる」
「確かに、そうですね」
日々の楽しみが一つ増える。それだけで、人生は今より少しだけ上向くのかもしれない。
「それじゃオル君、事件解決の打ち上げってことで、たまには外に紅茶を飲みに行こうよ。東十条にも良いカフェはあるからね」
すっかり詳しくなった海さんは、近くのカフェについて説明しながら、出かける準備を始めたのだった。
〈第3章 了〉
▼ 第4章 前編
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
