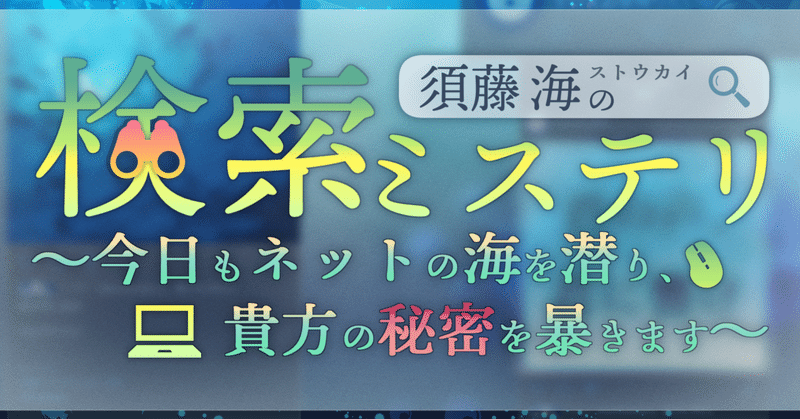
須藤海の検索ミステリ 第4章 鍵は動画の中にある(後編) ※最終話
「海さん、どうしますか? 香帆さんに連絡取ります?」
「いや、和沙さんがこれ以上送るのは危険だね。下手なことを送ったら、さっきの動画が疑われてしまう。そうしたらどんな危害が及ぶか分からない。こんな時は……」
「こんな時は?」
彼は右手のピースサインを左頬にくっつける形で答えた。
「うみねこアカウントの出番だね!」
「……はい?」
陽気に答えると、海さんは今月上旬に仁衣香さんの事件で使用していた紅茶大好きなアカウント「うみねこ」にログインする。
「これで動画にコメントをつけよう。急ごしらえのアカウントじゃない方が、黒須にも疑いを持たれる心配が少ないだろうからね」
どこか上機嫌な海さん。こういう時にも気を張りすぎずに振舞えるのは大人の余裕というヤツなのだろうか。少し羨ましくなる。
「他の人も投稿休みだったのを心配するコメントをつけてる。これなら僕たちがコメントしても怪しまれることもないね」
そう言って彼はカタカタとキーボードを打つ。
『(いつもと動画の雰囲気が違うけど、再生数伸びるのかな……私が再生すれば支援になるかな……)助けてあげますね! 次の動画も期待してます!』
「今まで挨拶したこともない人からこういうコメントがくれば、気付いてもらえるかもしれない」
なるほど、括弧を飛ばして読めば、助けにきた、そしてまた動画を送ってほしいというのが分かるようになっている。
伝わるかどうか。その答え合わせに五分もかからなかった。
「あっ、海さん、通知来ました!」
すぐにリプライがつく。香帆さんも待っていたのかもしれない。
『ありがとうございます! 助けてもらえると嬉しいです!』
「よし、これで次の動画を待とう。といっても、もう二一時近いから、次の動画は明日になるだろうね。オル君、今日はもう帰っていいよ」
「分かりました。あの、海さん。土曜だけど、明日も来ていいですか?」
俺の質問に、海さんはやや驚いたような表情を見せた後、微笑みながら頷く。
「待ってるよ。今日より寒いらしいから、気を付けておいで」
次の日。俺は九時から事務所に来た。俺が朝から来ることを予見していたからか、鍵が開いている。
「海さん、おはようございます」
案の定、彼は夢の中だった。眠りを妨げるものには容赦しない、という感じで聳え立つ二つの本棚の間を抜け、ベッドに寝ている探偵を思いっきり揺さぶる。
「起きてください! 香帆さんが何か動画アップしてるかもしれないですよ!」
「ううん……分かったよ……仕方ない……」
始めこそ布団を被って抵抗していたものの、無理だと悟ったらしい。「早いよ」と文句を言いながら、彼はしぶしぶ起きて青いワイシャツとチノパンに着替えた。
「オル君、気合い入ってるね」
「……まあ、相手が相手ですから」
かつて高校のときに俺を陥れた人間。自分自身の敵討ち、のようなものかもしれない。
「待ってると時間が長く感じられるからね。香帆さんだけ、投稿のお知らせをオンにしておいたから、何かアップされたら音が鳴る。それまではゆっくりするといいよ。果報は寝て待て、ってね」
そして海さんのアドバイス通り、しばらく動画が上がらず、俺も海さんも思い思いにスマホをいじったり本を読んだりして過ごすことになった。
やきもきしてしまい、スマホで読むニュースも頭に入らなくなって、俺は海さんに話を振る。
「香帆さんたち、どこにいるんですかね? 都内で会ってるって言ってたから、東京にいることは間違いないんですよね?」
「ううん、残念だけど、断定はできないね。どこかに移動した可能性もなくはない。黒須の家がどこにあるか分からない以上、千葉でも埼玉でも神奈川でも、それこそ群馬だってあり得るからね」
そうか……たまたま香帆さんが都内にいるから都内で面会した、というケースも考えられるのか。
「何で閉じ込めてるんでしょう? フォロワーもたくさんいるから一発でバレそうなのに……」
「いや、逆だよ」
彼は、椅子を九十度回転させて、ソファーに座っていた俺の方に体ごと向ける。
「フォロワーがいたって、所詮ネットの繋がりだ。大学で一人暮らしなら、授業に出なくても『体調悪いのかな』って特に気に留めない人が多いだろう。会社だと無断欠勤は難しいからね。現に、和沙さんがここに来てなかったら、今まで誰もこの件を調べようなんて思わなかったはず。住んでる家も大学から離れてるところみたいだし、実家の両親にさえ知られなきゃバレるリスクは低いと思う」
言われてみればその通りだ。赤都のときだって、俺以外は特に気に留めていなかった。
「でも、昨日動画のアップを許可したところを見ると、別に暴力を振るったりしてるわけじゃなさそうだね。ただ恋愛感情で軟禁してるのかもしれない」
「恋愛? でもこれまで会ったこともないはずなのに——」
「ないって言い切れる? 香帆さんはずっとネットで顔を出してる。全く面識がなくても、一方的に恋心を抱く可能性だってあるからね」
俺の言葉を遮って話した海さんに、俺は「そう、ですよね」と黙って頷いた。何の縁もない人を閉じ込める。外傷はつかなくても、立派な暴力だ。
「とりあえず、香帆さんの更新を待とう。こっちからは、もっと動画を欲しいってことは『次の動画期待してます』ってコメントで送ってある。チャンスがあれば、彼女からまた動画の投稿があるはずだよ」
果たして、海さんの予想通りに事件は動いていく。十一時、「女子大生リトミーの宅飲み部屋」に新たな動画が投稿された。昨日より長尺の、四分弱のムービーだ。
まずは香帆さんのアップから始まる。急に顔が出てきてびっくりしたものの、顔を出せる状況であることに安心もした。外のようなので、場所はベランダだろうか、茶色い柵が見える。晴天だけど、顔を映しているせいで全くといっていいほど外の景色は見えない。
「口に注目!」
そう叫ぶと、口をアップにし、ビールを飲んで口の周りに泡をつける。
「友人の家のベランダからお届けしまーす。場所は内緒ですね」
完全に香帆さんの鼻から下しか映っていない状態で、彼女は話し始めた。
「いやあ、正直インステも大変ですよね。他のインステライバーさんも台頭してるし……編集の高等テクも持ってるから、強いです。今はお酒好き女子大生界隈では中央のポジションにいるけど、仲の良い子というかタイプが近い子も増えてきたんで、様子見だなんて言ってられないんですよね。負けないようにしたいなって思います」
宣言を終えた後、香帆さんはグッとカメラを離す。一瞬だけ、画面の下側に川が見えたと思ったら、すぐに画面が真っ黒になり、今度は彼女の背中越しに窓ガラスが映る。ベランダのドアを背景に撮っているに違いない。そのまま景色を映したらバレてしまうから、と犯人から忠告が入ったのだろうか。
香帆さんは、窓ガラスを映したままベランダから真下を見つつ持っていたビールを飲み、小さく溜息をついた。
「明日は全国的に雨になるかも、って天気予報で見ました。雨は嫌ですね、川が怖いです。傘持ってきてないしなあ」
そして「最後に」と顔をアップにした。
「これからまた友達と話したりするので、しばらく更新は難しいと思います。待っててくださいね、よろしくお願いします!」
動画はそこで終わった。最後の「しばらく更新は難しいと思います」というのは、俺達に向けたメッセージだろう、と予想がつく。犯人が「これで当面更新しなくて良いだろう」と判断したのかもしれない。つまり、彼女からもらえるヒントはこれが最後、というわけだ。
「さて、ここからどう推理するかだね」
海さんは、左手の指を右手にグッと押し当てる。パキパキっと骨の音がした。
「今のところ、川が近いってことしか分からないね。今日は関東全域で天気は良いみたいだから、東京かどうかも確証は持てない。あとは……川を見下ろす形で映ってたからおそらくマンションだってことくらいかな」
「この動画から推理するのはかなり厳しいですね」
「でも、香帆さんからしたら川を映してくれたのもギリギリのラインだったのかもしれない。あの一瞬なら犯人が見逃してくれると踏んだ、とかね」
そう、川が映ったのは本当に一瞬だった。それだけでも何らかのヒントにはなるはず、とカメラの視点を切り替える中で撮影してくれたに違いない。
「海さん、一応確認ですけど、DMで香帆さんに直接聞くって選択肢はやっぱりないですかね……?」
「ないね。スマホを香帆さんがずっと持っているとは限らない。オル君もそれが心配だったんでしょ? 万が一黒須が保管していて逐一チェックしていたら僕たちの存在がバレる。そこで場所を移動されたりしたらアウトだからね」
「ですよね……」
仕方ない、ここは地道に推理していこう。
「まずは場所を絞り込もうか。もう一度動画を見よう」
こうして、動画とにらめっこする時間が始まった。もう一度、なんて言ったものの、海さんは「もう一回」「また始めから見るね」と再生を繰り返す。短い動画と言えど、四分のものを十回以上見ると、あっという間に一時間が経過した。台詞を一部覚えるほど聞いたけど、特に収穫はない。
「オル君、ザラメ食べる?」
「……いただきます」
小皿に盛ったザラメをティースプーンで掬い、二人で並んでボリボリと食べる。こんな変な光景はそうそう見られないだろう。
噛み砕く食感が心地よく、砂糖の甘さがダイレクトに頭に回っていく感じがする。「糖分は頭脳労働には大事だからね」という海さんの言葉を思い出した。
「動画の中で気になるところあるかい?」
海さんに聞かれ、俺は唸りながら頷いた。
「最初にインステライブが大変って語ってる部分、ですかね。かなり急な話題なので、何か伝えたいメッセージがあるんだと思うんですけど、それが分からないんです。特に……」
「特に?」
「『今はお酒好き女子大生界隈では中央のポジションにいる』って部分ですかね。普通なら『トップクラス』とか『上位にいる』って言うところだと思うんですけど、中央って珍しいなあって。まあアイドルとかはセンターって呼ぶのが変ってことはないんですけど……」
「中央って使わなきゃいけない理由があったんじゃないかってことか。僕も『様子見』って言葉が引っかかってる。なんでここでこんな言葉使ったんだろう……中央……中央……様子見……」
海さんは立ち上がり、再び悩みだす。うろうろと歩きながら考え込んでいるのは、ホームズをリスペクトしてのことだろうか。彼もよくこんな風に歩き回っていた。
「そういえば、香帆さんと黒須はどこであったんでしょうね。大学は駒込って言ってたからその辺りですかね」
「どうだろうね、同じ豊島区なら池袋の方が会いやすい——」
そこまで言った海さんが話すのを止める。メガネの奥の目だけが、ギラギラと動いていた。そして、嬉しそうに口をググっと曲げる。
「香帆さんはホントに頭のキレる子だね」
「謎、解けたんですか?」
「うん、語り出した部分だね。見事な言葉遊びだよ」
そう言って、彼はグーにした手を前に出し、一本ずつ指を立てていく。
「他のインステライバーさんも『台頭』、編集の『高等』テク、『中央』のポジション、『仲の』良い子、様『子見だ』なんて。全部、二三区の名称だ」
「あっ!」
台東区、江東区、中央区、中野区、墨田区。だから中央って単語を使ったんだ。
「別にこの中のどこかにいるってわけではないと思う。だったら紛らわしく五つも並べないだろうからね。多分、都内にいるってことを伝えたかったんだ」
「確かに、都内にいるかどうか、確定してなかったですもんね」
そうだとすれば俺の知識や記憶が役に立つかもしれない。
「具体的な場所でいうと、多分さっきの川が……海さん、さっきの映像見せてください」
画面とキーボードを借りて、一瞬だけ映った川を見ていく。関東全域くらい広い範囲だと見当のつかなかった場所も、都内なら記憶にある映像と対比できる。黒須のせいで人と関わるのがイヤになり、黒須のおかげで始めた一人散歩で、この川を見ていないか脳内の思い出を引っ掻き回す。
やがて、曖昧ではあるものの、一つの結論に至った。
「これ……荒川です」
「オル君、覚えてるの?」
「はい、近くを歩いたはずです。といってもすみません。どこで見たのかまではちょっと思い出せないんですけど……」
「いや、それだけでも大分絞れるよ」
海さんはブラウザ上でマップを開く。そして、東京都の部分を拡大した。
「この東十条のある北区とか江戸川区を通って東京湾まで流れ出てる、かなり大きな川だ。それでもこの流域に絞れるなら儲けものだよ。オル君、ナイス手柄だ!」
拍手する海さん。しかし、実際には解決までの道のりはまだまだ遠い。荒川沿いにあるマンションなんて幾らでもあるはず。もっとヒントがないと減らせない。でも、しばらく香帆さんからの更新は期待できない。だとしたら、やはりあの動画からヒントを探すしかないのだ。
「大丈夫だよ、オル君。僕のネットストーキング知識をフル活用するからね」
「なんかそう言われると逆にちょっと心配になりますね……」
パソコンのモニタをずっと見ていた探偵は、その動画をデスクトップに保存する。そのまま操作を続け、見たことのないアプリを立ち上げた。
「動画編集ソフトだよ。ここに音声編集のツールも入ってる」
「音をいじるんですか?」
「小さくて聞こえない音を拾うんだ。映像自体はイヤというほど見たからね」
カチカチとクリックし、さっきの動画を読み込んだかと思うと、音の波形が表示される。範囲指定をしながらパラメータを打ち込み、香帆さんが喋っていないシーンの波を著しく大きくした。
そして改めて再生してみる。すると、今まで聞こえていなかった部分のボリュームが上がり、今まで聞こえていなかった音を発見した。
カキンッ
調整したところで大きいとは言えない音。それでも、確かに聞こえている。聞き覚えがあるけど、あと一歩のところで思い出せない。
「何でしょう、この音」
彼の方を見ると、にんまりと笑みを浮かべている。もう既に解けているのが明らかな表情だ。
「オル君、川沿いということは河川敷があるんだよ? そして今の、金属で何かを叩くような音だ」
「……野球!」
「正解。画面の下に川が映ったから、川の手前にあった野球場に気が付かなかったんだ」
そうか、金属バットで打った音だ。中学や高校でサッカーをしているときに同じグラウンドでさんざん聞いた音、記憶に残っていて当たり前だ。
「荒川で、近くに野球場がある場所。北区、足立区、葛飾区あたりが多そうだね。ただ、さすが荒川、流域が広いな。もう少し場所を絞り込めないと、直接行って調べるのも難しいよ」
頭を掻く海さんの横で、余っている少し大きめのノートパソコンを借りて、香帆さんの動画を再生する。
何か、何かもっとヒントがあるはずだ。確証はない、でもあると信じて今は映像を流す、食い入るように見る。
絶対に香帆さんのいる場所を見つけたい。俺も海さんも被害に遭った。黒須を、今度こそ止める。
「明日は全国的に雨になるかも、って天気予報で見ました。雨は嫌ですね、川が怖いです。傘持ってきてないしなあ」
香帆さんが茶色い柵のベランダから真下を見つつ、ぼやいていたシーンを見返す。せめてもう少し川をしっかり見て、特徴でも言ってくれたらいいのに。全国的に雨だとしたら、東京都内の区を絞り込むなんて夢のまた夢だ。増水する川が怖いのはよく分かるけど……
「…………あれ?」
動画を思い出し、どこか違和感を感じた。「何かあった?」と訊く海さんに返事する余裕もないまま、もう一度再生する。もう一度。もう一度。何度も見返す。
そして、遂にその違和感の正体を突き止めた。
「海さん、見てくださいこの場面!」
「ベランダから川を覗いてるシーンだよね」
「いえ、よく考えたら違うんです。一瞬映った荒川は画面の奥に位置してましたよね。でも、ここで香帆さんは真下を見てるんです。つまり別のものを見ている」
「何だって?」
海さんはもう一度動画を見る。そして、香帆さんが下を覗き込むシーンを数度見返した。
「本当だ。でもこうして下を見ながら、雨だと川が怖いって言ってる。ということは……真下にも川があるってことだ」
「恐らくそうだと思います」
「お手柄だよ、オル君!」
俺の手を急にギュッと握り、ブンブンと腕を振り回す。力任せのお礼が、なんだか嬉しい。
「まあ、分かったのはそれだけなんですけどね」
「いや、それだけでもかなり推理は進むよ」
ブラウザのタブを右に移動し、東京の地図を再度表示した。
「香帆さんの映像を見ると、昼前に撮ったはずなのに逆光になってない。ということは南から北に向けて撮影してるってことだ。奥に荒川、真下に別の川があるのだとすれば、その別の川は荒川の南に位置してるってことになる。そうなると……足立区の隅田川と、北区の新河岸川しかなさそうだ。この近くにある野球場は全部で十五ヶ所くらいだから、あとは特定すればいい」
「特定できるんですか?」
返事の代わりに、海さんはザラメの乗ったスプーンをパクッと咥え、スマホの影響をコンコンと叩く。
「野球場の管理番号に電話してみるよ。幸いもう寒くなってきた時期だ。今日の午前中に野球をやってた場所は限られるかもしれないからね」
そして、リストアップした野球場に片っ端から電話をしていく。電話が繋がらないところは、Tweeterで「草野球 荒川」などのキーワードで検索して情報収集。単調で地味な作業。一ヶ所の確認に短くても三分、検索が入れば十五分、全部調べるのに優に一時間半はかかる。
しかし、それはストーカーも顔負けの根気強さである海さんが最も得意とするところでもあった。
そして、その努力は今回、幸運な結果に結びつく。
「よし、午前に使ってたのは新河岸川の二ヶ所だけだ!」
結局二時間かけて最後の電話を切った海さんが小躍りする。時間は十四時半。気が付くと俺も海さんも、お昼など完全に忘れて調査に没頭していた。お腹が減らなかったのは、ザラメのおかげだろう。
「北区にある新荒川大橋少年野球場ってところだね。オル君が見たのもこの辺りかな?」
海さんが画像検索で画面を出した瞬間、「あっ、こんな感じです!」と叫び声が出た。以前一人で散歩したときに、確かにこんな風景を見た気がする。
「埼玉と東京の境目あたりにある野球場だね。アルファベットでエリアが区切られてるんだけど、BとCが使われてたみたいだ」
東京の地図を思いっきりズームアップする海さん。北部で埼玉県と隣接している野球場が表示された。その北には荒川が、南には新河岸川が見えている。
「ここが見えるマンションは十軒ちょっとだ。ベランダの柵の色が茶色だったから、マンションの外観で探していこう」
今度は住宅サイトに行って、マンションを片っ端から探していく。空き部屋がないマンションでも、細かく探していけば過去の掲載情報などが見られるものだ。こんな風にどんどん候補を狭めていけるのは、正直面白かった。
「ここまでで残ったのは三軒だね」
「あとは現地に行かないと分からないですかね」
「いや、オル君。住宅サイトでまだ確認できることがあるよ」
海さんは昨日投稿された動画を再生してくれる。おせんべいを机の上に乗せているシーンだ。
「これは和室で撮られてる。つまり、全部洋室のマンションは対象外ってことさ」
「確かに! 間取りを調べましょう!」
そしてサイトでマンションの間取りを調べていく。三軒のうち、全部洋室の間取りが二軒、残り一軒だけが、和室もある2LDKだった。
「このマンションだね。六階建てだけど、割と高いところから川を見てたから、三階から六階って感じかな」
言いながら、彼はスマホを持って立ち上がる。そして、いい加減それでは寒いだろうというペラペラのコートを羽織った。
「出ますか?」
「うん、出よう」
それだけでこれからやることが分かる。完全に以心伝心。
現地に行って、香帆さん、そして黒須を直接探しに行く。
東十条駅から目的地の最寄り駅である赤羽はJR京浜東北線で一駅。東京湾に近い場所だと移動が大変だったので、近場で良かった。
駅の東口を出て、赤羽一番街と名のついた商店街を歩いていく。北方向へ四、五百メートル続く通りは、「赤羽と言えば安くて美味しい居酒屋」というイメージ通り飲み屋が多いものの、焼き肉屋や寿司屋、薬局や呉服屋も入っているメインストリートだ。
休日の夕方前ということもあって、グループで歩く大学生や三十代らしきカップルなど、大勢の人々で賑わっている。昼から開いている居酒屋では、既に酒盛りが始まっていた。
「そういえばお腹減ったな……僕たち、昼食べてないもんね。夕飯は美味しいものにありつこう」
「そうですね、口の中がザラメで甘ったるいです」
「まああの甘ったるさも、慣れると良いもんだよ。あ、オル君、ここを左だ」
線路の下をくぐって西側に渡る。交差点を川に向かうように右折すると、川の手前にマンションが見えた。
仁衣香さんの事件のときと同じように、郵便受けを確かめる。四階の405だけポストに宛名がなかった。
「これですかね? 海さん、ちょっと隙間から覗いて、黒須宛に来たものか確認しましょうよ」
「オル君、それはダメだよ。それじゃ立派なストーカーだよ!」
「だから海さんの中でストーカーの基準って何なんですか」
ここまでどれだけ検索をしてここに辿り着いたのか。
「でもホントに、今のままだとこの部屋で合ってるか確認できませんよ」
「ああ、それなら心配には及ばないよ。あとオル君、ちょっとスマホ借りてもいいかな」
「いいですよ。何に使うんですか?」
スマホを渡すと、彼は「ちょっとね」と楽しそうにはぐらかす。そしてワイシャツの胸ポケットに入れた後、エントランスのドアの前に行き、横のインターホンで406と押す。呼び出しのボタンを押すとピンポーンと可愛げな音が鳴った。しばらく待ったものの、出る気配はない。
「留守、ですかね?」
「居留守ってこともあるから。ここは根競べだね」
海さんはその後も何度もインターホンを押す。もしこれが人違いで、何かあって出てないとしたら、怒って応対するかもしれない。でも、海さんはそんなことは気にも留めないだろう。それは俺も同じ気持ちだ。今は目的のために手段を選んでいられない。
六回目か七回目のインターホンで、遂にガチャッと通話の音がする。気怠そうな声が、スピーカーを通じてエントランスに響き、天井に反響した。
「何だよ、何回もかけてきやがって」
向こうからはこっちの顔が見えているはずだ。宅配便の格好でもないスーツの男性と、大学生の俺。どう考えても普通の用事ではなさそうに見える。受け答えによっては、まともに取り合ってもらえず、すぐに切られてしまうだろう。それ以上しつこく呼び出したら、逆に俺たちが警察を呼ばれる可能性もある。
海さんはどう対応するのだろうと見ていると、ものすごく腰の低い態度で、カメラで見えるようにペコペコとお辞儀しだした。
「あの、すみません何度も。ちょっとお尋ねしたいことがありまして……そんなにお時間取らせませんので」
警戒心を解こうとしているに違いない。しかし次の瞬間、彼はメガネのブリッジに指をかけてクイッと持ち上げ、不敵に微笑んだ。
「黒須浩二さん、だよね?」
「……誰だ?」
突然名前を言い当てられたからか、黒須はかなり動揺しているように声を揺らす。
「君は僕のことを何も知らないと思うけど、僕は君のことをそれなりに知っているよ」
海さんはスマホも開かず、何も見ないまま話し始めた。
「黒須浩二、今年で三四歳。身長は一七二センチ、体型はやや痩せ型。都内を転々としているうえに漫画喫茶暮らしのような生活をしている時期もあるので住所を特定しにくい。視力は悪いのでコンタクトをつけている。以前はハードコンタクトだったけど、強風で飛ばされたことがあり、そこからはワンデーのものに変えた。好物は牛丼、つゆだく。甘いもの、特にあんこ系が苦手なので群馬の高崎にいたときも親族からもらった和菓子はほとんど食べてない。お酒は好きだけどそこまで強くなくて、もっぱら発泡酒を買っている。
仕事はフリーのライターで、群馬では地元のニュースを独自取材していた。それをネットニュースに買い取ってもらっていたけど、プライバシーに踏み込みすぎた記事も多く、ニュースのサイトに何度も苦情が来ている。三十歳くらいの上京前は、仕事がなかったのかバイトとして依頼された人物の家や素性、行動パターンをSNSなどをもとに調査するっていうストーカーのようなことをやっていて、被害にあった学生も多い。僕の友人含めてね」
これまで調べてきたであろう、恐ろしいほど細かな情報を立て板に水で伝えていく。友人、のところで、海さんは僕をちらりと見た。
スピーカーからは何の声も聞こえてこない。突然自分自身のことを詳らかに暴露されたことに驚いているのかもしれない。
やがて、黒須の叫び声が聞こえてきた。
「何だよ……何なんだよお前は!」
その質問を待っていたかのように、海さんはにやりと笑ってみせた。
「ストーカー、なんてね。ただの探偵だよ」
「それで、ストーカーが何の用だ?」
「いや、そこに利富香帆さんを匿っているんじゃないかと思ってさ。この前、インタビューってことで彼女と会ってるでしょ?」
俺は驚いて彼の方に体を向ける。そんなストレートに聞いても、絶対に黒須は教えてくれない。どころか、インターホンを切ってしまうのではないだろうか。もっと少しずつ話を詰めていって、ヒントを集めていくのだと思ったのに。
「残念だったな。彼女はここにはいないよ」
自分が有利な立場にいるのが可笑しかったのか、黒須はクックックと笑い声を漏らす。
「大体、いたとして、どう証明するんだ? そっちからは俺の顔も見られない、彼女の顔だって確認できない。もし今ここで女の声が聞こえたとして、それが彼女だと確認できるか? そもそも部屋にも入れないし、誰か通らなきゃエントランスも開かないんだぜ? 探偵はな、ここでは無力だよ」
悔しいけど、彼の言う通りだ。今の俺達では、どうやっても彼女を助けることはできな——
「別に無力でいいよ、僕たちはね。力のある人に任せればいい」
海さんは冷静に、しかしどこか力強く叫んだ。そしてスマホを取り出し、何か操作をする。
次の瞬間。
~♪~♪~♪
インターホンの向こう、つまり黒須のいる部屋から着信音が流れる。黒須は「うおっ」と軽く叫んだあと、かけている主に気付いたからか、すぐに着信拒否した。
「香帆さんの友人から依頼を受けていたからね。もちろん番号は控えてた。そして何か連絡があったときに気付けるよう、君がマナーモードにしていないことも予想がついていた。それは香帆さんのスマホだね。そして……」
彼はワイシャツからもう一つのスマホを取り出す。俺が貸したそのスマホは、何かが動いていた。そして、俺たちの背後に、二人の人影を感じる。
「ボイスメモを録らせてもらっているよ。僕が発信した番号と時間は履歴から分かるし、そっちの部屋で携帯が鳴った時間はボイスメモから分かる。つまり、これを組み合わせれば、少なくとも君の部屋に香帆さんの携帯があることは立証できる。後は、今ちょうど後ろに到着した警察がそこに踏み込むから、少しだけ待ってて」
「警察……だと……」
明らかに動揺しているようだ。二の句が告げないでいる。
「先に呼んでおいたんだよ。管理人ももうすぐ来るから、エントランスも開けられる」
「ふざけるな! 待ってろ! 今そこに行くから!」
「いいや、いいよ。僕は別に、君の顔を見ようとは思わないからさ。時間取らないとか言って、しっかり取っちゃって悪かったね。あと、最後に……」
スマホをしまいながら、海さんは振り返る。その目は、これまで見た中で一番冷酷だった。
「他人の情報を悪用したり、余計な詮索したりするのはやめた方がいい。その年になっても分かってないみたいだから、一度だけ忠告しておくよ。次にやったら、また僕がどこまでも探して捕まえに行くから」
黒須が「おい、待て!」と叫ぶ中、海さんと俺は警察官二人に「あとはよろしくお願いします」と伝え、足早にマンションを出た。
「よし、これで完了! ふう、疲れた!」
時間は一五時の昼下がり。海さんは伸びをしながら歩く。少し肌寒くはあるものの、日も照っていて、荒川沿いを散歩するにはちょうどいい天気だった。遠くで野球少年たちが目一杯拍手と声援を送りながら試合をしている。
「なんかあっけない幕切れでしたね……あれで俺達が部屋まで踏み込めたらヒーローだったんですけど」
「ヒーローじゃなくていいよ別に」
数歩前を歩く海さんは、俺の方を振り向いてフフッと鼻を鳴らす。
「僕は物理的にも権力的にも力があるわけじゃないからね。できるのは根気よく調べることだけだから。それで誰かが助かるなら、ヒーローは他の人がやればいい」
「……ですね」
悪用されて俺の人生を狂わされたネットストーキングの技術も、こうやって使えば人を活かすことに使える。それを再確認した瞬間、探偵、須藤海も十分ヒーローに見えた。
***
「黒須、ちゃんと逮捕されたらしい」
月曜日、探偵事務所にバイトに行くと、海さんが二つのマグカップにドリップコーヒーを淹れながら話してくれた。
「監禁罪だとすると、軽くでも三ヶ月以上の懲役かな。まあこれまで犯罪スレスレとはいえ逮捕はなかったみたいだから、執行猶予がつきそうだけどね」
そこから彼は、動機についても話してくれた。
Instegramで彼女の動画を見て興味を持ったまではいいが、調べていくうちに好意を抱いたらしい。インタビューという名目で会い、そのままカフェから誘い出して自宅に軟禁状態にしたようだ。もっとも、乱暴しようとしたわけではなく、憔悴させて交際をOKしてもらおうとしていたとのことだ。
そんな状態でOKをもらって本当に嬉しいのか、交際が続くと思っているのだろうか。盲目状態になった人の発想はよく分からない。
「海さん、あんまり興味ないんですか?」
因縁の相手が逮捕されたというニュースにも、彼はあまり興味を示していない。理由を聞いてみると、ぼさぼさの髪を揺らして苦笑した。
「もともと黒須の情報を晒す気はなかったけど、たくさん調べたからさ。インターホン越しに『お前が憎くてこんなに調べたんだぞ』って感じで話したら、なんかスッキリしちゃった」
「なるほど、それなら良かったです」
ソファーに座って得心して頷く俺に、海さんは折った紙切れを渡そうと自分の机から腕を伸ばす。
「黒須の個人情報、色々教えてもらったよ。どうする? 何かに使うかい?」
俺は一瞬考えたものの、すぐに首を横に振った。
「いいえ、やめておきます。悪用したら、アイツと一緒だから」
「そっか」
彼は、少し嬉しそうにその紙をクシャッと丸めてゴミ箱に捨てた。
「そういえばオル君、今月のバイト代と仕送りで、依頼料は返せるんだよね?」
はい、と返事する。赤都の事件のときに立て替えてもらっていた依頼料が、ようやく払える。払えるけど。
「でも、もう少し働いてもいいですか? ここのバイト、暇なときは楽だし……忙しいときは楽しいです」
もう少しこの場所で、このストーカーもどきの探偵のもとで、色んな事件に触れてみたい。
「もちろんいいよ! オル君の家の家賃も、王子駅の周辺だとそんなに安い方じゃなかったし、足しにしてよ」
「ありがとうござい……え、待ってください、何で知ってるんですか? ひょっとして海さん、調べました?」
「まあまあ、細かいことは気にしないで。悪用したわけじゃないから」
「調べましたね! やっぱりストーカーだ!」
「だから僕はストーカーじゃないって!」
二人で笑いながら、海さんと俺は同時にコーヒーを啜った。
〈須藤海の検索ミステリ 了〉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
