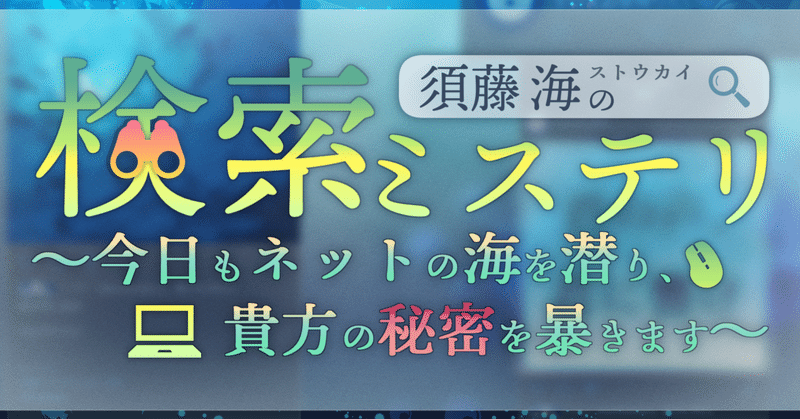
須藤海の検索ミステリ 第1章 行方知れずの友人(後編)
「え、裏アカ?」
表に出していないアカウント。赤都がそれを持っていると、彼は推理した。
「須藤さん、なんでですか?」
「ツイート見てごらん。日常のことしか書いてないでしょ?」
ほら、と顎で促された画面には最近の赤都のツイートが出ている。食事の写真、サッカーの話題、秋空の写真、本屋に行ったこと……確かに日常を切り取った呟きだった。
「でも、別に普通じゃないですか? 俺だってこんな感じですし」
「いや、織貴君のとは違うよ。これは綺麗すぎる」
綺麗、を強調する須藤さんに、思わずビクッと体が反応した。
「日々生きていれば何らか文句や愚痴も出るさ。織貴君のツイートだって直近のはほとんど読んだけど、結構大学の教務課への愚痴とかもあったでしょ? でも赤都君のにはそれがない。全部楽しいこと、明るいことばっかりだ。楽しいことしか書かないってポリシーでやってるのかもしれないけど……」
「不満や愚痴を吐き出す専用のアカウントを持ってる可能性もあるんじゃないか、ってことですね」
俺の言葉に、彼はご明察と言わんばかりにニッと微笑んで見せた。そして、親指と人差し指で「ちょっと」のサインを作る。
「また少し時間もらうよ。ここまでくれば、案外すんなり見つかると思う」
そして肩を回しながら、再び画面に向かう。カーテンの隙間から陽光が漏れ、キーボードの左側に白色のマークを作った。
探偵といえば現場をうろうろしたり怪しい人を尾けたりするイメージがあったし、安楽椅子探偵なら事件を聞いただけで謎を解いてしまうけど、須藤さんの場合はどちらとも違う。ひたすら画面に向き合い、キータッチとクリックの音だけが、カタカタカチカチと響いていた。
十五分後、メガネを外して目頭をぐりぐりと押しながら、「見つかったよ!」とモニタを見せてくれた。
「この『おたかさん』ってアカウントですか?」
さっきのアカウントと違い、自己紹介には「雑記用」と書いてあるだけ。アイコンも適当な写真で、確かに裏アカウントっぽい。
「裏アカウントって、大体メインのアカウントと繋がってるんだよ。だから、メインアカウントのフォロワーを見ていったんだ。フォローやフォロワー数が少なくて自己紹介が雑なものがないかってね」
「見ていった……って一人ずつですか? フォロワー1000超えてませんでしたっけ?」
「まあ一覧で見ればそんなに時間はかからないよ。明らかに表のアカウントは細かく見なくても分かるし」
大したことではないように言ってのけるけど、そんなに多数のアカウントをなめてチェックしようなんて、やっぱりなかなかできることじゃない。
「でも須藤さん、フォローやフォロワー数だけなら、同じようなアカウントいっぱいありませんか?」
「そう、だからこの名前がヒントになったんだ。赤都って名前は珍しいし、表の名前のベースにもしてるから、何らかの形で残してると思った。赤都をローマ字にして逆から読むとOTAKA、このアカウントに一致するんだ」
「あっ!」
言われてみて初めて気が付く。なるほど、こんなことがヒントになるのか。
「書いてる内容も講義の話とか入ってるし、まあ間違いないだろうね」
「それにしても、裏アカって鍵かけないもんなんですね」
「人間の承認欲求ってのは結構強いから、たとえこういう雑記のアカウントでも知らない誰かに見てほしいって思いが出てくる。だから初めて見た人にもツイートの中身が分かるように鍵はかけない人も多いんだ。その代わり、表の人に見えないように分けてるって感じかな」
承認欲求。自分を見てほしいから、何でもツイートする、記録に残す。赤都の裏アカウントには、どんなことが呟かれているだろうか。
「さて、ようやく出発点だ。大事なことが書いてあるといいんだけど。織貴君、一緒に見るかい?」
無言で頷き、スツールごと机の前に移動する。須藤さんは少しだけ左にズレてくれた。
「一番ポイントになりそうなものはこの写真だね」
そう言って、彼はスクロールしていた手を止める。それを見た瞬間、心臓がきゅっと締まる。
上から見下ろした海の写真が二枚セットでアップされていた。一枚は砂浜と海が映ったもの。そしてもう一枚は、崖状になっていて、真下にはごつごつした岩肌を捉えているもの。ツイートの本文は『このあたりがいいな』という一言だけ。投稿日は昨日だ。
「このあたりって……まさか……」
最後までは口にしたくなくて、「飛び降りたのでは」という続きは飲み込む。しかし、それを察してくれた須藤さんは首を振った。
「いや、違う。ほら、今日の朝になって『体が痛い』って投稿してる。少なくともまだいるはずだよ。他のツイートも見てみよう」
そして過去に遡っていく。「さっきの海、実家の静岡ですかね?」と訊くと、彼は返事の代わりに画面を指差した。
「いや、多分実家じゃないね。原因もこれの可能性が高い」
そこには、ちょうど赤都を学校で見なくなった日の前々日、十月一日のツイートが表示されていた。
『実家帰ったら両親がまた喧嘩してるんだけど、どっちからも相手の文句を聞かされるの、めちゃくちゃしんどい。俺と妹が出ていってからはずっとこんな感じだよな』
「これを見る限り、実家のことは嫌いになってるはず。だから別の離れた場所にいるんじゃないかな……自殺を考えたから」
その単語に、全身の毛が逆立ったような気分になる。
「自殺って……」
「織貴君、わざわざ崖の写真を撮って『このあたりがいいかな』って投稿してるんだよ。他に解釈がない」
「でも、親が喧嘩したって、そんなことで死ぬなんて——」
「そんなこと、で死ぬんだよ」
俺の言葉を遮る須藤さんに、小さく唾を飲み込む。
「その重さは、辛さは人によって違うからね。もちろん、それだけの理由じゃないかもしれない。何か別の辛いことが積み重なっていて、表面張力ギリギリの状態で、自分の両親からお互いの悪口を聞かされたら、グラスから溢れる可能性はあるさ」
「そう、ですね……」
言っていることはもっともだった。でも、そうだとしたら時間がない。一刻も早く、赤都を探さないと。
「あっ、新しい写真が上がった!」
「ホントですか!」
正に今、アップされたのは黒い床の狭い部屋の写真で、パソコンや漫画の新刊が映っている。どうやら、漫画喫茶にいるらしい。今朝の体が痛いというツイートは、この個室に寝泊まりしたからかもしれない。
「まずはここがどこだか探さないと……」
言いながら、俺は絶望していた。日本全国、海も漫画喫茶もどこでもある。目的の場所を探すなど不可能に近かった。場所のヒントがないかと思ったものの「さて、行くか」というツイートがあるくらいで、あとは「お腹減った」「コーヒー高いな」「寒いな」など、何の情報も掴めなそうな投稿だけだった。
「ううん……」
食い入るように画面を見つめていた須藤さんは、やがて口を開く。
「多分東日本にいると思う」
「なんで分かるんですか?」
「それぞれのツイートを見ると、なんとなく予想できるよ」
ページダウンのボタンを押して画面を下まで動かしながら、彼は推理を説明しだした。
「まずここで『うなぎパイ買った』ってツイートがあるでしょ? これはお土産、多分織貴君たちに配ろうとしたんじゃないかな。で、これは両親のケンカの投稿の後だ。ってことは、ケンカを受けて衝動的に飛び出したってことじゃなくて、いったん東京に戻ってこようとしたってことだ。つまり、おそらく赤都君は一度こっちに帰ってきてるんだよ」
「授業に出ようとして戻ってきて、やっぱりイヤになってどこかに行ったってことですね」
「そうだね。東京でまた両親から不仲の話を聞かされたのかもしれないし、思い返して気が沈んだのかもしれない」
一つのツイートでここまで可能性を追求する。須藤さんの「探偵らしさ」を垣間見た。
「じゃあどこに行ったのか。そのヒントが『さて、行くか』ってツイートだよ。多分この時に出発したんだね。で、そのあと三十分もせずに『コーヒー高いな』ってツイートが出てくる。つまり移動中にコーヒーを買ったか、コーヒーの値段を知ったんだ」
「移動中にコーヒーを買える乗り物?」
首を傾げていた俺に、須藤さんは棚にあった常温のペットボトルコーヒーをちらと見た後、こちらに向き直った。
「新幹線だよ。車内販売で売ってるんだ」
「そうか! 確かにワゴンで売ってますね!」
確か三、四百円した気がする。俺でも高いと感じてしまう。
「そして、しばらくしてから『寒いな』って投稿がある。あくまで仮説だけど、『さて、行くか』が新幹線に乗るタイミング、そして『寒いな』ってのが新幹線を降りたタイミングなんじゃないかな。この二つのツイートの間は一時間半だ。赤都君は王子近くに住んでるの?」
「そうですね、アイツも俺と一緒で王子駅です」
「ってことは京浜東北線で東京駅まで二十分。新幹線は東京駅から乗ったと考えてみよう。新幹線で一時間半で海沿いの寒いところへ行ったとなると、北上して仙台駅や新潟駅の方に行ってるんじゃないかな。どっちも九十分くらいのはずだ」
新幹線の乗車時間を調べる須藤さんの横顔を見ながら、俺は素直に感心していた。かなり変わった捜査方法だけど、ただの短文のツイートから今いるであろうエリアを絞り込めたのは、彼の推理力の賜物だと思う。
「うん、やっぱり新潟か仙台かな。でもツイートから分かるのはここまでだね。それに……ひょっとしたら特急に乗ったのかもしれない。特急ってコーヒーの販売あったかな。茨城の日立まで一時間半くらいだった気がする」
ブラウザの別タブを開いて検索を始める須藤さんを見ながら、俺はさっきの写真を思い出していた。そして、ハッと気づき、彼に声をかける。
「すみません、さっきのツイート、もう一回見せてくれませんか? 行ったことある場所かもしれません」
「織貴君、本当かい? ツイート、見てみてよ」
パソコンを借り、Tweeterの画面を上にスクロールする。赤都が投稿していた海と砂浜の写真をじっくり見て、記憶と重ね合わせた。
「これ……去年一人旅で行ったことあります。多分、新潟です」
「間違いない?」
「はい。崖の方は分からないですけど砂浜の方は。新潟駅から越後線に乗っていくと、十分くらいで青山とか小針って駅に着くんですよ。確か小針浜海水浴場がこんな感じだったはずです。このベンチ、見覚えがあるので」
「ベンチ?」
目を細める彼に拡大した写真を見せる。左端に、ほぼ見切れる形で背もたれのない木製の何かが映っている。
「これ、ベンチだと思うんです」
「ああ、なるほど、よく気付いたね。何だろうと思ってたんだけど、散歩の途中で休めるようになってるんだ。お手柄だよ、織貴君!」
すごいすごいと連呼しながら、マップで新潟駅周辺を検索し、ストリートビューを立ち上げる。実際の写真を写して、海沿いを丹念に探していく。
「バスで移動するにしても、そんなに遠くには行かないだろうから、この辺りで探していけば崖も見つかるはずだ」
ストリートビューで少し先に進んでは海の方に視点を変え、また道路に視点を戻して先に進む。根気のいる作業を延々と続ける。
「時間かかりますね……」
「いや、新潟って絞りこめただけで大分楽だよ。候補になる地域全部やろうと思ってたからね」
とんでもないことを言い出したけど、この人ならやりかねない。画面に向き合っている彼は、どこか活き活きとしていた。
ネット上で捜査すること二十分。ついに彼は「よしっ」と小さな叫び声をあげた。
「おそらくこのエリアの崖じゃないかな。ここに映ってるでしょ? この奥にも更に崖っぽいところがあるから、どっちかだと思う」
ストリートビューの画像を見る。さっき見た小針の海水浴場から国道四〇二号線を南西に進んだ場所に、崖っぽい場所があった。夜なら人目につかずに来れそうだと思うと、ふらふらと深夜にこの場所に来ている赤都を想像してぞくりと寒気がした。
「後はこの近くの漫画喫茶だ。軒数的にはそんなにないはず……」
須藤さんは恐ろしく速くて正確なキータッチで近隣の漫画喫茶を検索し、サイトを開いていく。フラットシート席と呼ばれる、部屋状になっている個室の内装写真を見て、さっき赤都がツイートした写真と見比べていく。
「うん、ここだろうね。確かめてみよう」
あるチェーンの店舗サイトを開きながら、須藤さんは机の上のスマホに手を伸ばす。
「確かめる……ってどうやってですか?」
「そりゃあ、店に聞くのが一番だよ」
ニッと笑って、彼は画面左側に表示されている番号にかけ始めた。
電話でって……いきなり知らない人が聞いて教えてくれると思えないけど……。
何コールか鳴った後、「お待たせしました」と若そうな男性店員の声が彼の耳元から漏れ聞こえる。
「ああ、すみません。お恥ずかしい話なんですが、ちょっと孫が家出みたいな状態になってましてね。家の近くのお宅みたいな店に行ってるんじゃないかと思って電話をかけた次第です」
これまでの声からかなりトーンを落とし、しわがれた声で低い声でゆっくり話す須藤さん。赤都の祖父になりきっているらしい。
「そちらに、北藤赤都という人は入ってますかね? 会員証の名前で分かるようなら、替わってもらいたいと思ったんですが……ああ、いや、やっぱりいいです。いきなり呼ばれたら息子もびっくりするでしょうから。あの、じゃあせめて、いるかどうかだけでも教えてもらえますか? いると分かれば、妻も安心します。色々あって二人で育ててきたものでね……」
電話口に何やら返事を聞いた彼は、俺に向かってピースサインを送りながら「本当に感謝します」とお礼を言って電話を切った。
「縁もゆかりもないところに行ったから、おそらく偽名までは使ってないだろうと考えてたけど、想定通りだったね。火曜から泊まりこんでるらしい」
「電話替わらなくて良かったんですか?」
「ああ、うん。そもそも替わる気はなかったし。居場所が分かれば十分だったから」
予想外の答えに驚いていると、彼は人差し指で俺の眉間をまっすぐに指差した。
「ドア・イン・ザ・フェイスっていう心理学の初歩のテクニックだよ。断られそうな大きな要求を最初に出して、断られたら小さな要求に変える。こっちが譲歩したら向こうも譲歩した方がいいかなって気持ちになる。返報性の原理ってやつだね。普通はいるかどうかなんて情報教えちゃダメなんだろうけど、老人相手ならしれっと教えてくれるんじゃないかって期待してたしね」
表のアカウントを見つけ、裏のアカウントを見つけ、俺の記憶も参考にツイートからエリアを割り出して、居場所を突き止めた。この探偵、若干恐ろしい。
「さて、どうする、織貴君? 帰るまで待つ?」
「いや、行きます……帰ってくるかどうか分からないし」
「そう言うと思ったよ。僕も行こう……と言いたいところだけど、僕一人の力では無理だ」
「何かあるんですか?」
ザラメをティースプーンでジョリッと頬張りながら、彼はなぜか自慢げに首を振る。
「いや、逆だよ。お金がない。往復で二万円は大金だからね」
そんな気はしていた。お金があったら絶対に別の方法で糖分補給している。
「……分かりました。じゃあお金出しますから、付いてきてください」
「ありがとう、織貴君!」
彼は俺の手を取ってぶんぶんと振る。クレジットカードの支払いをミスして止められている、と余計な情報まで教えてもらいながら、俺と須藤さんは急いで準備をして事務所を出た。
***
「ここからだと新潟まで七五分。東京から行くより近いけど、大宮からの新幹線は基本的には北にしかいかない。もし赤都君が東京駅から乗ったとすれば、東西どこに行くのか迷っていたのかもしれないね」
「ですね」
埼玉で最大の駅、大宮から新幹線に乗り込み、二列シートに並んで座って須藤さんの話に相槌を打つ。平日の十五時、スキーやスノボには少し早いこの十月に新潟に向かう人は少なく、車内の客はまばらだった。
お金を出してもらったから、という理由で窓側を譲ってもらったので、車窓から風景を見る。信じられないスピードで後ろに走っていく景色は、徐々にビルが減り、塗料独特の白色の住宅地と茶色の田畑が増えていった。
「織貴君」
車内に流れる電光掲示板と、どんどん田舎になっていく景色を交互に見て数十分が経ったとき、不意に須藤さんは俺に話しかけてきた。後ろに誰もいないのをいいことに、思いっきりリクライニングしている。
「赤都君、大丈夫だと思うよ」
「……はい、俺もそう思います」
「そっか。何か根拠はある?」
当たっているか不安だったので言うかどうか迷ったものの、俺は考えを話してみることにした。鼻の頭を掻きながら口を開く。
「さっきの漫画喫茶の個室の写真、漫画が置かれてたと思うんですけど、連載中の新刊が幾つかありました。これから自殺するって人が、続きが気になるはずの漫画を読むとは思えなくて……」
「織貴君、探偵に向いてるよ。何かの弾みで考えが変わるのは怖いけど、今の時点ではそれほど追い詰められてるわけではなさそうだ」
僕も同じ推理をしてたよ、と言って、彼は後ろに突っ張るようにして伸びをした。
「ついでに一つ聞いていいかい? 答えにくいことかもしれないけど」
「はい、話せることなら」
「過去にネットストーキングか何か、受けたことがある?」
その質問は、自分なりの推理が当たって安堵していた俺を再び硬直させるには十分すぎる威力だった。どう答えればいいか、どう誤魔化すか、急に脳が高速回転を始める。
「検索で人探しするって言ったときに忌避するようなトーンだったでしょ? それに一人旅で新潟行ったって言ってたけど、一人旅って悩んでたり回りと距離を置きたいときにすることも多いからさ」
「ん……」
今の自分の強張った表情とこの空白の時間で、本当の答えはバレているだろう。それなら、教えてみてもいいかもしれない。須藤さんは変人だけど、土足で自分の領域を汚しに来るような人には見えなかった。
「高校一年生のとき、サッカー部入ってたんですよ。まあ別にサッカーがめちゃくちゃ強い高校ってわけではなかったですけど、その中では結構上手い方だったんで、一年でレギュラー取れたんですよね」
じゃあモテたね、と眉を上げた須藤さんがからかうような表情で訊いてきたので、「割と、はい」と頷いた。
「でも、その結果妬まれたりしたんでしょうね。二年生のときにネットで『なりすまし』に遭いました」
「なりすまし? 誰かが織貴君のふりをしてSNSやってたってこと?」
「はい。インステグラムやってなかったんですけど、急にアカウントができて、落書きしてる動画とか、川にゴミ捨ててる動画とか、いろいろ投稿されたり、女子にDM送りつけたりもしたみたいです。Tweeterはやってたんで、その情報をもとに住所や家族構成とかも把握してたらしくて」
あの頃を思い出して口の中に苦い唾が溜まる。自分の投稿から全て割り出された。自宅の外観も撮られ、過去に行ってた店も特定され、大急ぎでツイートを消した。自分の過去そのものまで消されたような気がした。
何もツイートできなくなって、それでもデータを保存していたら、いつ何の情報を特定されるか分からないと、ただただ怖かった。SNSは新しいアカウントを作り直した。
「部員や友達も何人か偽アカウントのこと信じてましたね。部内やクラス内で拡散されたりして、ちょっともうやっていけないなって精神的に参っちゃって……それで部活を辞めたんです。あの時、みんなに自分のじゃないって説得しようと思って偽アカウントが投稿する画像を何度も注意深く見てたんで、いろいろ細かいこと気付くようになったのかもしれないですね」
だからこそ、未だにネットの嫌がらせのニュースを見ると、加害者への怒りはもちろん、被害者にも「もっと気を付けないと」という説教めいた心が沸き上がってしまう。俺と同じようにならないようにと。
「なるほど、海のベンチとか、漫画喫茶の漫画とか、観察眼はそのときに養われたんだね。一人旅は大学生になってから?」
「高校までは群馬だったんで、北関東とかは行ってました。大学で東京に来てから、二三区を回ったり新潟まで足伸ばしたりしましたね。部活なくて暇になったんで、平日バイトして、週末試合してた時間で電車乗るって感じで」
須藤さんは黙って聞いていてくれる。余計な口を挟まず、メガネのフレームを少し触りながらゆっくり「うん」と相槌を打ってくれる傾聴の高さに、探偵としての資質と大人としての余裕を感じた。
「友達とも距離置いてたんですよ。信じてくれてる人も、またいつ信じてもらえなくなるか分からないなと思ったりして……。だから一人で旅行してました。といっても、電車乗って窓の外を見たり散歩したりしてただけですけど……おかげで町並みとかはだいぶ覚えてますね。今回はそれが役に立って良かったです」
なんて言われるだろうか。それは辛かったね、と慰められる? そんなことで離れる友達は友達じゃないから気にしなくていい、とアドバイスされる? どちらも何回もされてきた。自分には響かないけど、そんな風に想ってくれるだけでもありがたい。
「残念だったね」
座席背面のテーブルに溜息をぶつけながら、須藤さんがぼさついた髪の毛を撫でつけた。
「織貴君の力量があれば、なりすましの相手を特定できたかもしれないよ? そして晒し上げることができた」
「いや、そこまでしなくても……」
「まあ、それは言い過ぎかもしれないけどさ。でも織貴君はそれだけのことをされたんだから!」
思わず彼の方に顔を向ける。
「なりすましってことは君の情報を相当掴まれて悪用されたんでしょ? あることないこと噂が出回って、誰かに何か話したらその情報も漏れそうで、毎日しんどかったでしょ? ネットストーキングってのは、僕みたいな使い方をしなければ、相手を知りすぎることも相手もフリをすることもできるひどいスキルだよ。だから、良くないことだって分かってるけど、復讐の一つも許したくなるね」
初めてだった。友達が離れていったことや孤立したことに同情するのではなく、なりすましそのものにこんなに怒ってくれる人は。
今更復讐なんてする気はないけど、あの頃の俺はストレスと同時に途方もない怒りが込み上げてきていて、だからこそ、その怖さを十二分に知っているからこそ、こんな風に同調してくれるのが嬉しかった。
「さあて、少し寝ようかな。ここまで倒せると、ぐっすり眠れそうだ」
自宅かと思うほどリクライニングシートでくつろぎ、須藤さんは外したメガネをよれよれのワイシャツのポケットに入れてすうすうと眠り始める。
空の色はだんだん正午の明るさから午後の明るさに変わっていき、電車に乗ったときとこれから降りるときの気温差が想像できて小さく身震いした。
「到着! 寒いね、織貴君!」
乗車からほぼピッタリ九十分後、新幹線は新潟駅に着く。まだ残暑の面影の残るはずの十月だというのに、風は涼しいというより冷たいという表現の方が適切で、偶然とはいえ厚手のジャケットを着ておいて正解だった。
一方の須藤さんはワイシャツの上にペラペラなコートを着ており、仕事があまり儲かっていないことが見た目にも分かるようになってしまっている。
「とりあえず目的地に向かおう。行き方覚えてる?」
「小針の方ですよね、こっちです」
先頭に立ち、新幹線からJR越後線に乗り換える。吉田行きと表示された電車に揺られること十五分。小針駅に辿り着いた。そこから歩き、漫画喫茶を目指す。
急に心音が加速し始めた。さっきまであの場所にいたことはツイートで分かっている。でも、今いるとは限らない。もう店を出ていたら? 海に向かっていたら? 今この瞬間にでも身を投げていたら? 不安を募らせた自分にできることは、マップのアプリで迷うことなく最短ルートで店に向かうことだけだった。
「いらっしゃいませ」
店に入ってすぐ、須藤さんは店員に、事前に準備してきたと分かるくらいすらすらと告げる。
「基本料金、二人入れるフラットシートでお願いします。あと、会員じゃないので登録させてください」
「では、会員登録用紙をお書きください」
渡された用紙に名前を書き殴る須藤さん。どうやって店内を探すのかと思ったけど、そこまで強引ではなさそうだ。
「三八番の席をご利用ください」
「ありがとうございます」
言うが早いか、彼はサッと角の部屋へ移動し、いきなりドアをノックし始めた。なんて強引なんだ。
「何だよ?」
明らかに不機嫌そうな四十代の男性客が出てくる。漫画喫茶でノックされたら、誰だってそうだろう。
須藤さんは、小声で説明する。
「すみません、この部屋、僕が押さえてる席だと思うんですけど……」
「はあ? よく見ろよ、ここ二二番だろ? お前の三八じゃねえか」
「あ、ここ二二番なんですね、見間違えてました、すみません」
およそ間違えないだろうというめちゃくちゃな理由を引っ提げて、彼は個室を片っ端から開けていく。連続でやっているとバレないよう、隣の席に聞こえないようなボリュームで話しているのが巧い。
そして、ちょうど一○部屋目、三一番の部屋をノックしたときだった。
「はい」
聞き覚えのある声。そしてすぐに、ぱっちりした目とさらさらの黒髪が印象的な見覚えのある男子の顔が、暗い部屋のドアの隙間から覗く。その顔を見て、俺は努めて普通のトーンで挨拶した。
「よう、赤都」
「織貴……なんでここが……」
「ちょっと、探偵に頼んでね」
横にいたストーカー探偵が気取ってぺこりと挨拶する。
久しぶりに会う顔は、いつも見ていたはずなのになんだか随分懐かしくて、俺はほんの少しだけ泣くのを我慢した。
「いやあ、良かったね。これにて一件落着!」
「はい、ありがとうございます」
帰りの新幹線で、少しずつ濃紺に塗り潰されていく景色を見ながら、窓側に座る須藤さんは嬉しそうに体を揺らす。クレジットカードは持っていないので、ATMで現金を引き出し、切符代に充てた。もちろん二人分。この代金はどこかでちゃんと返してもらおう……。
「でも大丈夫ですかね? 赤都をそのまま残してきちゃって」
「大丈夫でしょ。少し観光して帰るって言ってたわけだし、明日からの土日過ごしたら帰ってくるよ」
確かに。せっかく新潟に行ったのだから、旅行してもいいだろう。俺も明日出かける用事がなければ泊まったかもしれない。
赤都と再会した後、店を一時抜けして彼と話した。
最終的なきっかけは俺たちが想像していた通り、家族の不仲だった。帰省して高校時代の友人と同窓会をしたときにケンカになってグループを外れてしまい、追い打ちをかけるように両親が離婚が話題にのぼるほどの言い合いをして、自分の行いが悪いのではと責め続けて相当しんどかったようだ。本当に死ぬことも考えて新潟に行ったものの、どうにもその気になれずにずるずると今日まで来てしまったらしい。
少し恥ずかしそうに「織貴が会いに来てくれたら、帰らないわけに行かないもんな」と笑って、漫画喫茶で深夜に観たサッカースペインリーグの話をしてくれた。
「実際、あの崖の写真を見た時点で、多分死なないでいるだろうとは思ってたんだ」
「そうなんですか?」
須藤さんは車窓に顔を近づけて話す。友人のセンシティブな話題なので、敢えて直接顔を見ないようにしているのかもしれない。
「あの時点で何の未練もないんだったら、写真と一緒に『お世話になりました。さようなら』ってツイートにして、それで終わってるはずだよ。それができないってことは、勇気が足りなかったとか、何か後悔が残りそうだったってこと。それが三、四日で払拭されるなんてあんまりないからね」
言われてみればそうかもしれない。そして、そうであって本当に良かった。
「あ、そうだ。これ、簡単だけど」
須藤さんは思い出したとばかりに、手持ちの小さなカバンからクリアファイルを取り出した。中には二つ折りにした白い紙が入っている。
「なんですか、これ」
「請求書だよ」
「請求……あっ」
完全に忘れていた。これは仕事で依頼していたんだった。契約書に料金の話も書いてあったはずだけど、あの時は赤都のことが気になりすぎてあんまり記憶にない。おそるおそる紙を開くと、手書きで金額が書かれていた。それを見ながら思わず手を震わせ、紙がガシャガシャと音を立てる。
「二○万と交通費などの実費! 高い!」
「高くない! 今日丸一日仕事したんだから相場通りだよ! 値段だって、ちゃんと契約書に書いてあった通りなんだから!」
くそ……不覚だった……完全に勢いで契約してしまった……そんな大金は……
「すみません、お金持ってないんで、毎月返済とかでもいいですか……?」
「おっと。じゃあさ、うちで働かない?」
「え?」
予想外の返事に、数回瞬きを繰り返す。
「今シフトでやってるバイトはあるの?」
「いえ、ちょうど九月で辞めたところですけど……」
なら良かった、と須藤さんはパチンと指を鳴らす。
「町並みにも詳しいって言うし、細かいところに気が付けそうだから、助手やってもらえると、依頼の解決がもっとスピーディーになって助かるんだよね。それに書類管理とか電話対応とか掃除とかザラメの用意とかお願いできること結構あるんだ」
「後半は完全に雑用ですけどね……」
週二、三で良いという話と、気になるバイト代を聞かされる。隣駅というのはちょっと面倒だけど、そこまでキツくなさそうな労働でそれだけ貰えたら十分、という額だった。
もちろん仕事内容には少し抵抗がある。自分がされて嫌だったネットストーキングを仕事にするなんて。でも、やり口を知るチャンスかもしれない。もう俺がターゲットになることはないだろうけど、いつか誰かを救うことに役立てられるなら。
「じゃあ、せっかくなのでしばらく働かせてもらいます」
「オッケー。じゃあ愛称を決めよう。織貴だから……オル君でいいかな! よろしくね、オル君。僕のことは海さんでいいよ!」
「よろしくお願いします、海さん」
こうして事件は解決し、俺はこの事務所に雇われることになった。
愚痴を書き込むために鍵アカを用意した方がいいだろうか。どうせすぐ見つかってしまいそうだけど。
〈第1章 了〉
▼ 第2章 前編
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
