
【サポート事例】企業の定点観測(モニタリング)
本日は、サポート事例のシリーズとして、企業の定点観測(モニタリング)についてお話します!!!新規取引時に審査して、その後、特に見直し等することなく取引を続けていたりしませんか?
企業の状況は良いときもあれば、悪い時もあります。企業の定点観測(モニタリング)について実際にサポートした事例をご紹介します!
こんにちは、佐々木正人です!
是非、最後まで読んで持って帰って下さい!!
フォロー✅・スキ💗・コメント📝大歓迎です!特に記事についてのコメント頂けると、今後の記事作成の励みになります。100%返答します( ´艸`)
そもそも企業の定点観測(モニタリング)とは、なんでしょうか。
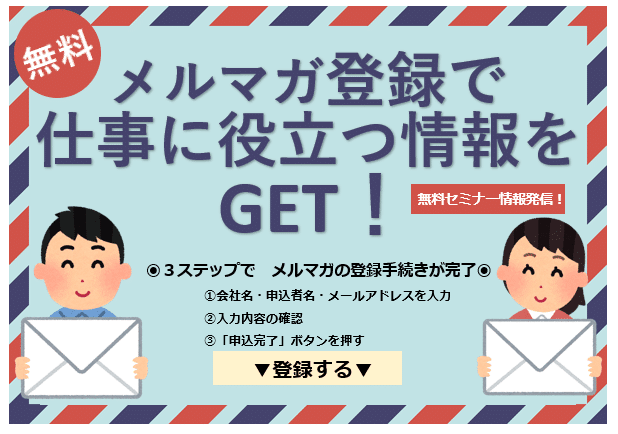
(1)【定点観測(モニタリング)とは】
定点観測でWEB検索をすると次のような言葉がでてきます。
「変化のある事象について、一定期間、観察や調査を続けること。」
…今ひとつ、ピンとこない方が多いと思います。。
与信管理での定点観測(モニタリング)とは、企業の動向を監視し、何か変化があった場合にその情報をキャッチできるように情報収集することを指します。
なぜ、与信管理に定点観測(モニタリング)が必要かと言うと、新規取引時には問題無くても、その後状況が悪化して、気づかない内に債権が回収できないということが発生する可能性があるためです。
例えば、2020年5月に倒産した(株)レナウンの事例をあげさせていただきます。
(2)【(株)レナウンの倒産事例】
(株)レナウンはもともと業績が良かったわけではないですが、次の理由で一般的にあまり不安視されていませんでした。
・東証一部上場企業でかつ大手企業
・1902年創業の老舗
・過去の利益の蓄積もあり自己資本比率も50%程
しかし、アパレル業界の競争激化やEC展開の遅れにより、徐々に業績が悪化していく中で、2019年~2020年になって次のようなことがおきました。
・山東如意グループの香港企業に対する多額の回収遅延が発生
・新型コロナウイルスによる営業自粛
この多額の回収遅延、コロナウイルスによる営業自粛が同時期に来ましたので、急激に資金繰りが悪化し、倒産にいたってしまいました。
この変化は急激におきましたので、驚かれた方も多いと思います。
(株)レナウンは東証一部上場企業、大手ということもありニュースとなりみんなが知ることになりましたが、実は中堅、中小企業でもこういったことは頻発しております。
そして、与信管理、特に債権回収においては、いかに情報を早くキャッチして、素早く債権回収の行動にうつすことが非常に重要になってきます。
なぜ、債権回収において早く行動を起こす必要があるのでしょうか。
(3)【債権回収は早い者勝ち!?】
まず、取引先が倒産手続きに入ってしまうと、債権者平等の原則が働き抜け駆けできなくなります。つまり先方の弁護士から倒産する旨の通知が来た時点で、ほとんど何もできなくなってしまいますので、手遅れです。
ですので、倒産手続きに入る前までに対応する必要があります。
そして、倒産手続き前の対応においては、まさに早い者勝ちです。
債権者はあなただけではなく、他にもたくさんの債権者がいます。
そして債権者達は、様々な方法で債権回収、債権保存を行ってきます。
比較的ライトなものであれば、次のようなものがあります。
①回収サイトの短縮、前金対応の要求等
②保険会社、保証会社への保険、保証依頼
①については相手の資金繰りを圧迫しますので、早く対応しないと相手に限界がきます。
②についても保険会社、保証会社にも引き受けできる金額に限界がありますので、早い者勝ちになります。
更に厳しくなってくると次のような対応方法がでてきます。
・財産の差押え、抵当権の設定等
これらに対応ついては、相手の財産には限りがありますので、早い者勝ちになります。
このようにいずれの対応をとるにしても、他の債権者よりも早く対応をしないと回収することがどんどん難しくなります。他の債権者より、早く対応するために、早く情報をキャッチ、つまり定点観測(モニタリング)が必要になります。
(4)【定点観測(モニタリング)のサポート事例】
ここから先は、実際の定点観測(モニタリング)のサポート事例をご案内します。まず、先方の状況です。
(状況)
・定点観測の重要性は理解しており、要注意先の定点観測を行っている。
・定点観測の方法は以下の通り。
①半年に一度、営業からの要注意先の報告書を上げさせている。
②管理部で半年に一度、複数の調査機関から情報を取得し、変化がないか確認
このような状況に対して、次のような課題を抱えていました。
(課題)
・営業現場からの報告書が形骸化しており、毎回報告書の内容がほぼ同じ。
また、悪い兆候があっても、根拠もなく大丈夫と軽視しがち。
・複数の期間から情報を収集するのが手間。また、それらの情報を持ってどう判断したらいいかわからない。
・半年に一度の対応なので、情報キャッチまで最大半年のタイムラグがある。
ここで私が提案したのは、弊社で扱っているモニタリングというサービスです。モニタリングの特徴は次の通りです。
(提案内容)
〇モニタリングサービスの特徴
・30社超の情報機関からデイリーで情報を収集
・審査会社としてのノウハウを活かして、収集した情報から1つの格付を算出
・倒産した企業の90%超が、E-F格なので、E-F格がでたら要確認先と設定
このモニタリングサービスを使うことで次のようなメリットでありました。
・30社超の情報期間からデイリーで情報収集するため一早く情報入手可能で、何より楽。
・倒産企業は、E-F格から出ているという実績から、E-F格が出た場合は営業現場でも警戒するようになった。
・E-F格に保険をかけるというルールにすることで、運用が非常にシンプルでわかりやすいものになった。また、E-F格からの倒産が大半のため、焦付きリスクもほぼ0に近くなった。
引き続き、様々企業様のお役立ちができるように頑張っていきたいと思います。
本日の内容は以上になります。
次回もお楽しみに!では!
○メルマガ登録は▼コチラから▼○

Twitterやってます!フォローお待ちしてます
ハッピーバレンタイン🌞
— 佐々木正人|格付会社の営業部長【人生は楽しんだ者が勝ち】 (@rismon_sasaki) February 13, 2022
ウキウキする年齢じゃないけどイベントは好き。弊社では本命とキープ君以外へのチョコ受渡しは推奨されていないが、男性からの逆チョコやホワイトデーは制限されていない謎のルールがある😓毎年社長からチュッパチャップスが配られるのが恒例だけど、これって飴だよなぁ🥺 pic.twitter.com/v7to95BydN
#最近の学び
#とは
#note
#ビジネス
#コラム
#エッセイ
#ブログ
#仕事
#学び
#営業
#経営
#しゃかせん
#定点観測
#モニタリング
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
