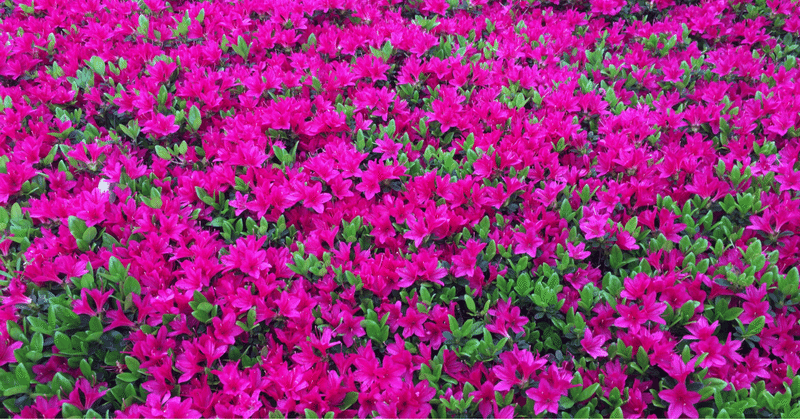#伝統芸能
伝統文化② 歌舞伎メイク 隈取り
こんにちは。通訳ガイドのぶんちょうです。
今日も私の視点で、初心者さん向けに歌舞伎について紹介します。前回の記事はこちらで、歌舞伎がどのように生まれたのかについて書いてあります。
皆さんは歌舞伎の演目に、どちらのイメージをお持ちですか?
1 二枚目の役者さんがなよっとした感じで演じる
2 すごい形相で顔に模様のついた役者さんが「てやんでぇ」風に演じる
1に近いイメージの方は「和事」2の場合は「
伝統文化③ 江戸時代の歌舞伎の楽しみ方
通訳ガイドのぶんちょうです。今日も私の視点で歌舞伎を知らない方に向けて書いていきます。前回は「見得」という独特の演出方法について触れました。
見得はクライマックス、感情が最高潮に達したときに役者が首を少し回してからにらみを効かせるのですが、この瞬間に合わせて、舞台の右手に置いたツケ板が拍子木で勢いよく打たれます。この音で場に緊張感が走り、観客は今まで以上に役者の表情に釘付けになります。
また、
伝統文化④歌舞伎 今を生きる江戸庶民
通訳ガイドのぶんちょうです。
今日も初心者向け、歌舞伎について私の視点で紹介していきます。
テレビも映画もなかった江戸の庶民は、歌舞伎が最高の娯楽だったわけですが、なぜそんなにハマっちゃたのでしょうか。
きのうの記事に書いたように、舞台演出の面白さがあります。でも、それだけではありませんでした。
歌舞伎のストーリーは大雑把に分けると以下の二つがあります。
時代物 (江戸時代から見た歴史物で