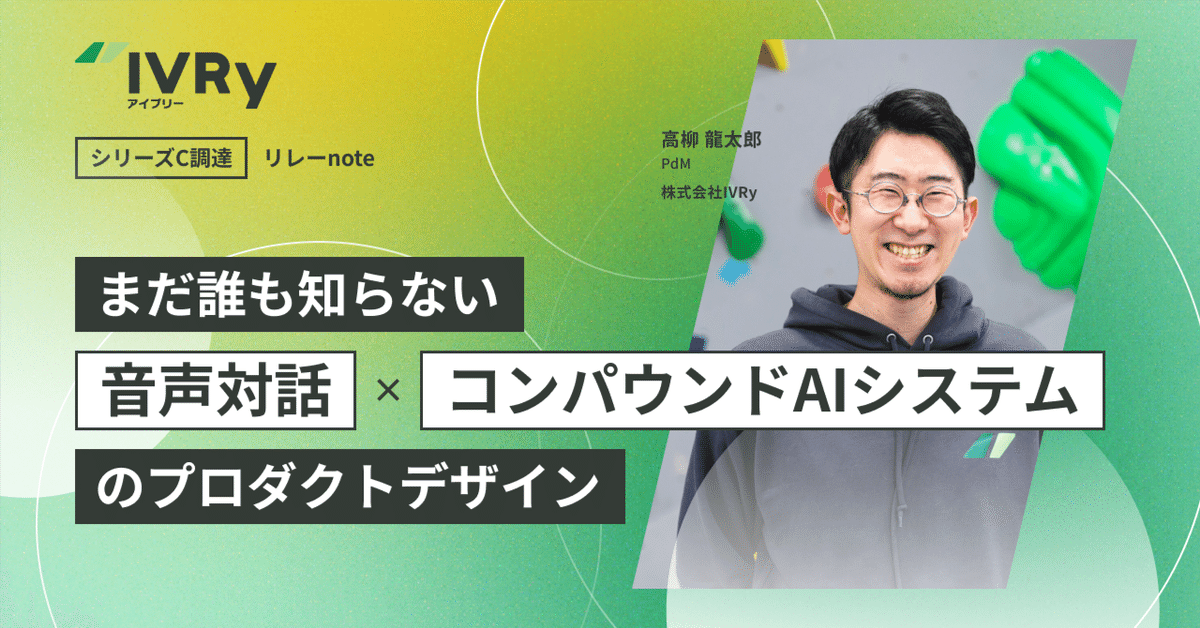
【30億円調達】IVRyがチャレンジするまだ誰も知らない”音声対話”×”コンパウンドAIシステム”のプロダクトデザイン
はじめに
未来を予測する最も良い方法は、それを発明することだ。
こんにちは、対話型音声AI SaaS IVRy(アイブリー)でプロダクトマネージャーをやっています高柳(@neveryanagi)です。
この度、IVRyはシリーズC30億円の調達を実施いたしました。
累計14,000を超えるクライアントにご利用いただき、T2D3を超えるスピードでプロダクトが力強く成長している点をご評価いただき嬉しい限りです。
私はシリーズA手前(2021年頃)からIVRyに関わっているのですが、個人的にも本当に一生に一度の貴重な経験をできているなと感じています。

現在シリーズC調達を記念してブログリレーを実施中です。
今回は30億円を調達したIVRyの、
プロダクトのこれまでとこれから
これからを支えるプロダクトチーム
IVRyのプロダクトデザインが秘める魅力
について書いていきたいと思います。
こんな人向けです
主にプロダクトマネージャーやプロダクトデザイナー
話題のIVRyさんは結局何をやっているのって人
電話のサービスってやっぱちょっと古臭く感じますって人
採用順調だからもうやることなくなってきてない?今入って何ができるの?って思ってる人
IVRyプロダクトのこれまでとこれから
2023年前半はボタンプッシュ型の電話自動応対サービスのみを主軸サービスにしていましたが、現在はAI電話代行サービスを当たり前のように提供しており、この1年でIVRyは「電話自動応対サービス」から「対話型音声AI SaaSサービス」へと進化を遂げて来ました。

2023年のプロダクトの詳しい歩みについてはこちらのnoteをご覧ください。
これからのIVRyが目指しているのは、電話だけに留まらないフロントオフィス業務を解決するための「マルチプロダクト」の展開、そして「コンパウンドAIシステム」の実現です。
コンパウンドAIシステムについては代表・奥西のnoteで詳しく紹介していますが、
単一のAIだけに頼らず、複数のAIモデルや伝統的な処理システムを組み合わせて
クライアントとユーザーの課題解決をするための最適なプロダクトを提供する
という考え方です。
過去の電話データを活用し、任意の店舗や事業所に適したAIを生成したり、予約や注文システムとの連携を増やすことで、様々な業務ユースケースを自動化していきたいと考えており、既に各セグメントでのプロダクト検証も同時並行で進行しています。
一例として飲食店向けの予約業務において、リクルート社とのAI電話予約の実証実験を開始しています。
「マルチプロダクト」×「コンパウンドAIシステム」でIVRyが狙う市場は15兆規模。

プロダクト構想レベルではかなり詳細な全体像を描いていますが、外向けに見えているIVRyはプロダクト構想全体からするとまだまだほんの一部分です。
(noteに書けない部分も知りたい方は、ぜひカジュアル面談にお越し下さい笑!)
IVRyプロダクトチームってどうなっているの?
そんなプロダクト構想を実現するIVRyプロダクトチーム(正社員)は 2024年6月現在、
プロダクトマネージャー(PdM):6名
デザイナー:0名
エンジニア:17名
で構成されています。
PdMはイシューごとにミニチームとして、エンジニア・デザイナーはワンチームで横断的にイシューに取り組んでいます。

どんなカルチャーですか?
経営とプロダクトチームが”超”近い
代表の奥西がプロダクトマネージャー出身のため、会社全体にプロダクトデザインの思想が深く浸透しています。

ボードメンバーがプロダクトやデザインの重要性を理解してくれているのはプロダクトに関わる立場としては本当にありがたい限りです。
体制上も代表とプロダクトマネージャー・デザイナーがかなり近い位置で働くことができるため、経営視点から「なぜこのデザインにこだわるべきか」「なぜ中長期的にこのプロダクトイシューを進めるべきか」といった議論を日々行うことができています。
(逆にいうと最初はちょっと面食らう部分かもしれません笑)
そのため、中期的な負債解消を見越してかなり早いタイミングでプロダクトの大規模デザインリニューアルを実施したり、

会社の今後のロードマップから逆算したタイミングで戦略的にロゴをリニューアルしたり、
時にはRubyKaigiといったカンファレンス用のノベルティなどもIVRyを伝える手段としてプロダクトデザインと同じぐらい全力で取り組んでいます。


先ほど触れた奥西以外にも
プロダクトマネージャーを経験
宮田(VP of Corporate):リクルート
片岡(VP of Growth):GREE、メルカリ
ブランドデザインマネージャーを経験
西尾(VP of HR):Chatwork
といったプロダクトデザインバックグラウンドを持っているボードメンバーが多くいます。

まさにこれからがデザイン組織の立ち上げフェーズですが、UXやプロダクトデザインについて深い思考がある経営チームと事業戦略とのバランスを取りながらデザイン組織はどうあるべきか?を考えていけるのはユニークなポイントかもしれません。
Keep on Groovin'なモノづくり
Keep on Groovin'はIVRyのバリューの1つです。
IVRyは誰か特定の人が考えたことをそのまま形にするのではなく、多様な観点・視点を持つ人が協働してモノづくりをする文化を持っています。

特にプロダクト開発においては下図にあるように上流部分からデザイナー・エンジニアと一緒にプロダクトのあるべき姿を考えていっています。
(ただし本来はもっと上流部分からタッグ組んで進めていきたいと思っており、ここも伸びしろポイントです!)
プロトタイピングしながらエンジニアとコミュニケーションして、最適なHowを固めていくプロセスはかなりスピード感を感じてもらえると思います。

デザイナー少なくない?
その通り。少ないです。とっても少ないです!
現在正社員デザイナーが0名(業務委託が3名)で、先ほどのプロダクト構想を実現しようとした場合にはどう考えても足りていません笑
「IVRyさんプロダクトもだいぶ出来上がってきてるし、どんどんやることなくなってるんじゃない?」ってたまに聞かれるんですけど、全くそんなことないです。
各セクション(プロダクト、マーケ、ブランディング/HR)のデザイン組織立ち上げ・拡張
組織化を前提としたデザインシステムの構築〜本格運用
マーケコンテンツへのデザイン組織の関与強化
バリュー浸透のためのデザイン活用
IVRyプロダクトデザインの面白さの外部発信
など、プロダクトデザインに限らず、コミュニケーションデザインも含めた全方位で助けてほしい気持ちしかありません!
逆にプロダクトマネージャー多くない?やることない?
一般的に1プロダクトマネージャー:5エンジニアぐらいと言われたりするのを考えるとめっちゃ多く見えますが全然「少ない」です。
IVRyのプロダクトマネージャーの職能は他の組織と比べてもかなり広く、プロダクト開発における責任だけではなく
プロダクトポジショニングの検討や競合サービス理解・リサーチ
顧客へのヒアリング/課題発掘、新プロダクトのプリセールス
社内/外のオペレーション設計
プロダクトGTM(リード獲得〜契約)における事業数値コミット・改善
などプロダクトマネジメントトライアングルのすべてをやる、を地でやっています。

より事業そのものへの責任が強いロールなので「プロダクトの成功のためにやれることを全部やる」方にはうってつけですし、「マルチプロダクト」×「コンパウンドAIシステム」を実現しようとしているIVRyにはプロダクトマネージャーがまだまだ必要です。
これからのIVRyプロダクトデザインの可能性
プロダクトとチームの話をした上で、これからのIVRyのプロダクトデザインについてお話したいと思います。
音声対話デザイン
これまで電話は莫大なコール数がありながらも、全くデータ化されていない領域でした。
IVRyはSaaSサービスを通してこれらの電話データをサーバーに蓄積することにより、GoogleのようなBigTechですら持っていない価値あるデータの分析・活用を実現しています。
そもそもこれまで分析することすらできなかった音声対話データを分析していると、
AI音声の最初の案内で離脱してしまう人が多い
ユーザーの発話タイミングがなぜかAI音声に被ってしまう
など「なぜそれが起きているか」経験則では全く解けない問題ばかりに直面します。
長年Webサービスをやってきていると、ページのファネル改善などはある種「経験」でできてしまう側面があると思うんですが、電話という音声対話デザインは「全く未知」のことがめちゃくちゃ多いです。
(本当に面白くて「0.5秒だけAI音声の返答速度を早める」とユーザー体験が劇的に変わるなんてこともあります)
クライアントの設定画面を考える際に「ユーザーにとってベストな音声対話体験」を迷わず簡単に設定できるようにする必要があり「利用するクライアントとその先のユーザー」を想像したプロダクトデザインは他にはない醍醐味だなと感じます。
誰もが使えるホリゾンタルSaaSのデザイン
IVRyはホリゾンタルなSaaSサービスとして47都道府県、80業界で利用されています。
日本にある業界の総数は99なので、なんと80%以上の業界をカバーしています。

使っているクライアント・ユースケースも
鹿児島の100年続くお茶屋さんのEC対応
業界1位のビジネスホテルチェーンさんの窓口対応
スタートアップの代表電話対応
と多種多様で
「店舗や事業所など実際に電話が使われるシーンや業務のユースケース」を考えたうえで
「幅広い業種」の「誰もが簡単に使える」ユーザー体験
を作っていくのはかなり難易度が高いです。「鹿児島の100年続くお茶屋さんの注文担当者」と「東京のITスタートアップの担当者」がどちらも簡単に使えるプロダクトデザイン、聞いただけでも骨が折れそうですよね(折れてます)
ありがたいことにIVRyにはそんな難易度の高いプロダクトデザインをサービス改善に快くご協力いただけるクライアントと一緒に取り組むことができる環境があります。
店舗や事業所に行って使い方を横で見せてもらったり、電話の通信速度を計測をさせてもらいながらクライアントの業務フローにDeep Diveすることで、局所的/部分的ではない本質的なユーザー体験のデザインに向き合っています。
※余談
実はIVRyはグッドデザイン賞も受賞しており、本質的なユーザー体験を追求していることを受賞理由の1つとしてご評価いただきました。
AIコンパウンド(融合)したプロダクトデザイン
compoundは「複合する」といった意味ですがここではあえて意訳しています。
コンパウントAIシステムにおいて必要なのは、AIが自然とサービスに融合された状態の実現です。
IVRyって「結局レガシーな電話のサービスでは?」「電話にデザインなんているの?」って思う方もいらっしゃるかもしれないのですが、「音声対話」と「LLM」を融合させているプロダクトとして見ると、実は最先端のことをやっているんですよね。
これまでAIを使ったことがない人たちに対して、
電話をかけたユーザーが戸惑うことなくAI対話で目的を完了できる
設定画面上でAIでの音声対応ルールを一瞬で設定できる
ボタンをワンクリックするだけで、AIが問い合わせデータを分析し重要な示唆を導き出してくれる
ことを実現しようとしています。
ちょうど米国を代表するVC・Andreessen Horowitz (アンドリーセン・ホロウィッツ、a16z)が音声対話×LLMについての記事を公開し話題になっていましたが、世界のビッグプレイヤーが注目しているイシューにIVRyはいち早く取り組んでいます。
まだ答えが無いものに対して自分たちが10年後当たり前になる体験を作りにいけるなんて、めちゃくちゃエキサイティングだと思いませんか?
弊社ではChatGPT API触り始めて2日目くらいで「これ、end-to-endで使うのは厳しくない?」という結論に至り、そこからコンパウンドAIの方針に全振りしたので割と社内にノウハウがたまっており、かつ一緒にLLMを社会実装するAIエンジニアを大募集しています☺️ https://t.co/mXh3fKb3CH
— べいえりあ (@mr_bay_area) February 20, 2024
グローバルなホリゾンタルSaaSプロダクトへの挑戦
「店舗や事業所など実際に電話が使われるシーンや業務のユースケース」を考えたうえで
「幅広い業種」の「誰もが簡単に使える」ユーザー体験
という点はIVRyのプロダクトデザインの(難しくもあり)面白いポイントですが、事業グロースを担っているShinyaさんのポストにもあるとおり、私達はIVRyをグローバルでも使われるサービスへと進化させにいこうとしています。
入社エントリーで勝手に、グローバル行くぞ!と言っていたんですけど、オフィシャルに会社として検討し始めています!
— Shinya KATAOKA / 対話型音声AI SaaSのIVRy(アイブリー) (@shinyakataoka) May 26, 2024
一緒に0から海外で勝ち切りたい方募集します。(↓のリンクからカジュアルにお話ししましょう)https://t.co/gUC7mMd61n…
音声対話の切り口からグローバルを見ると、日本では日本語で読み書きできることが当たり前で日常のテキストコミュニケーションに困ることがほぼありませんが、
他の国では言語を話せる人の割合は高いが読み書きできる人の割合は低いといったケースがまだまだ存在しており、音声対話の重要性は高いと言えます。

またGPT-4oのデモであったように、社会実装可能なレベルでのリアルタイム翻訳を実現する難易度が大幅に下がったことで、言語の壁を超えてグローバルへ進出するチャンスも高まっています。
SlackやNotionのようなレベルで「国や言語の壁を超えて直感的に使えるToB SaaS」を自分たちで実現できるなんて想像しただけでワクワクしますね。
向こう数年を見据えたとき、グローバルで本当に使われるプロダクトデザインに取り組みたい人にはかなりおすすめできるんじゃないかなと思っています。
おわりに
未来を予測する最も良い方法は、それを発明することだ。
冒頭引用したのは、パーソナルコンピューターという概念を提唱したアラン・ケイの言葉です。
当時誰も想像すらできていなかった「誰もがコンピューターを持つ世界」にパーソナルコンピューターという名前を持たせ「アルト(Alto)」を生み出しました。
そのアルトを見たスティーブ・ジョブズが開発したのが、その後世界を席巻する「マッキントッシュ(Macintosh)」です。
アラン・ケイは先程の言葉のあとに続けて以下のように語っています。
未来は、あらかじめ引かれた線路の延長上にあるのではない。
それは、われわれ自身が決定できるようなものであり、
宇宙の法則に逸脱しない範囲で、われわれが望むような方向に作り上げることもできるのである。
まだ誰も見たことがないものでも、それを信じて形にすることで未来を自分で作り上げていくことができます。
そして、IVRyにはこれまでの経験だけでは解けない「まだ誰も見たことがないもの」がたくさん広がっています。
デザインやプロダクトへの熱量を武器に、一緒に新しい未来を形にしていきませんか?
お読みいただきありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
