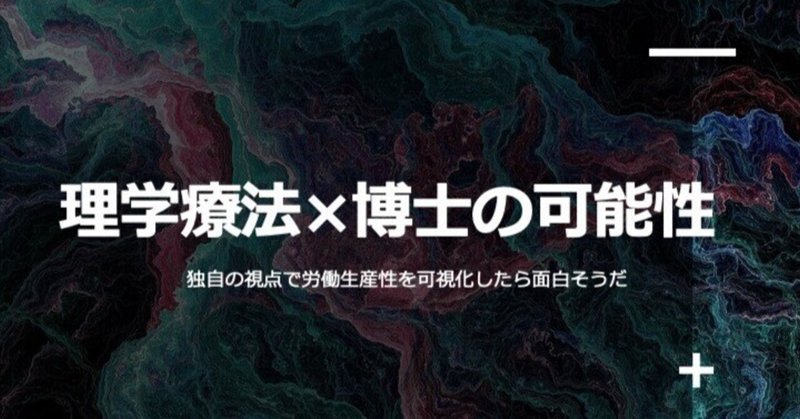
博士人材活躍プランに注目中
はじめに
本日は、文科省の博士人材活躍プランに大学院教授が注目している理由を短く共有します。
博士人材活躍プランとは
文部科学省が令和6年3月26日に打ち出した博士号の取得者を増やし、博士号取得者の就職率を改善し、人口100万人あたりの博士号取得者数を世界トップレベルに引き上げることを目標に様々な取り組みを実施するというものです。
注目ポイント
リハビリテーション専門職(理学療法士)で大学院教授の私は、博士人材活躍プランの資料に、注目しています。「労働生産性(USD)」に注目しています。
普段、理学療法士は、病院や施設で働きながら大学院に通う社会人大学院生がほとんどを占めています。すでに職場があります。
つまり、「臨床家にとっては博士号を取得する意味が不明瞭である」という課題を業界全体で抱えています。一方、博士号取得者は博士号を取得して良かったと言います。 私も博士号を取得して良かったと思っています。
ただし、社会人大学院生の経験が無い理学療法士の中には、「大学教員や研究者等のアカデミックキャリアに切り替えるのであれば大学院に通うだろうが、臨床現場で働き続けるのであればほとんど意味がない」と思っている方もいるかもしれません。 なぜか、社会人と大学院生の二足の草鞋で頑張って、修士号や博士号を取得しても、職場で昇給がほとんど無いからです。
経済的な評価が期待できない状況では、「自己研鑽」の一言で片付けられてしまうこともあります。 理学療法士は専門職ですので、管理職にある理学療法士は各々の職場で何を指標に博士号取得者のパフォーマンスを評価すれば良いか、研究して欲しいんです。
なぜか、私が注目している労働生産性(USD)は、博士号を取得して臨床現場で活躍する理学療法士と、そうでない理学療法士を経験的に分類してみると、”大差あり”と思うからです。
理学療法士×博士号取得者が職場に在籍する強み
臨床現場で博士号取得者が何%程度いるのでしょうか。職場における博士号取得率と職場内パフォーマンスについての研究は、非常に興味がある研究テーマです。もし、このような研究を実施したい理学療法士の方がいましたら、ぜひ、私のところの大学院をご検討ください。
その強みについていくつかあげてみます
優れた思考力により、同僚が悩む業務を相談にのり、課題解決できる。
臨床推論(クリニカルリーズニング)ができるので、考え方のルールを周知することができるために、中期・長期的に職場内の水準が向上する。
思考力×行動力を掛け合わせ、臨床研究論文などをわかりやすく発信・共有できるので、職場内研修会の水準が引き上げられることにより、職場内の研修費を別のミッションに向けて使用することができるようになる。
思考力×臨床推論×行動力の組み合わせにより、中・長期的に知恵(wisdom)が向上していくので、チーム医療の水準が向上するまたは、新規事業や新規分野への参入を目指した人的資源を保有できる。
知恵がある理学療法士は、模範的なリーダーに育つ可能性が高く、優れたリーダーが所属する職場では、離職率が低く、また、新入職員などから頼られ、憧れる良いメンターになれる可能性があり、時代の変化に合わせて仕事内容を変えられる職場になる可能性がある。
管理学を学ばずに管理職にある理学療法士の存在に危機感を感じることができ、思考力×臨床推論×行動力×知恵×リーダ意識によって、管理学を正しい学修プロセスに基づき知識とスキルを身につけることができ、新たに適切な管理職像を職場で構築できる可能性がある。
これらの強みは、今後の研究により可視化することが可能であると推測しています。研究により可視化することに成功すれば、理学療法の業界においても労働生産性が違うということを明確に提示することができます。明確に提示できる状況を一緒に作りませんか?
まとめ
理学療法士×博士号取得者の組み合わせにより、労働生産性が異なるということは博士号取得者は知っているが、それを定量的に示した研究が乏しい状況であるので、理学療法士が博士号を取得しても経済的な評価を受けることが難しいと述べました。それを解決するために、何がどのぐらい労働生産性が違うのかという独自の視点で研究活動を通して解決したら「面白い」というお話でした。 最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
