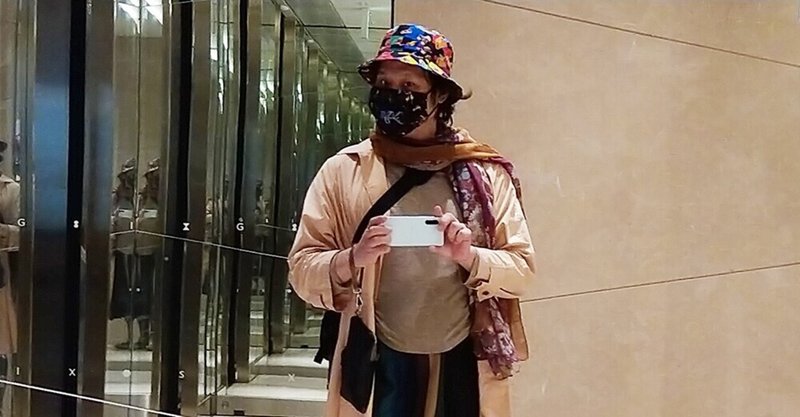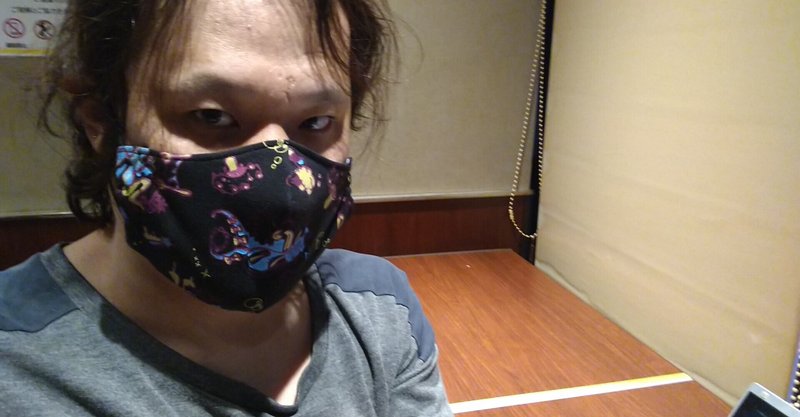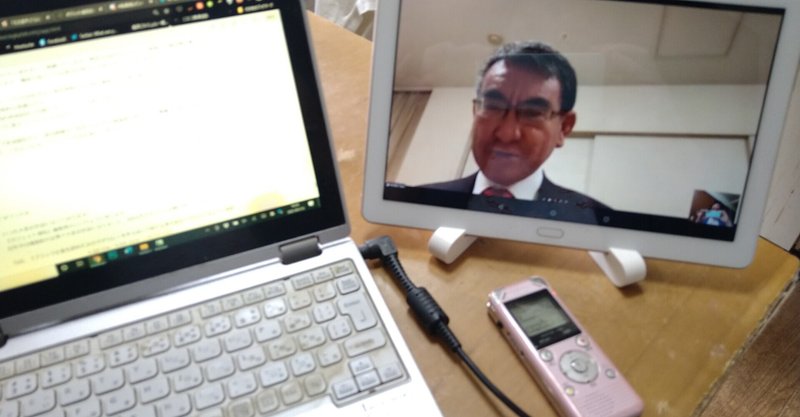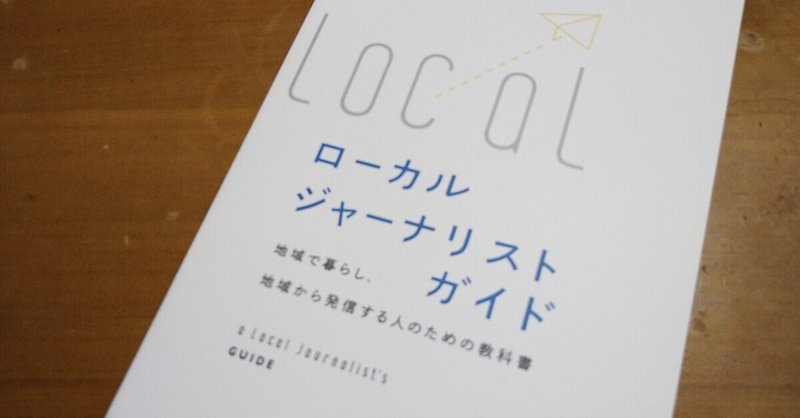#ライター
ワーケーションをする上で絶対に避けるべきこと
旅工房が運営するウェブメディア『たびポケット』から、「ワーケーションに関する記事にツイート引用させて」とご連絡があって、「著作権法とTwitter利用規約に沿っているのならばご自由に」とお答えしていたのだけれど、先ごろ記事が公開された模様。
ここで、私のツイートは「反対派」とされているのだけど。申し訳ないけれど、自分は「ワーケーション」という言葉ができるおそらく6年くらい前から旅先で首都圏にい
しんどいけど止めてはいけないこと
ちょっと思うところがあって、できるだけ毎日この『note』を更新してみることにした。自分の気持ちやら考えていることやら、できるだけ公開していくというのが、ホームページ→ブログを書いているうちに、「書いて、伝える」ことが本業となってしまった、自分の本分であり「業」なのだと、改めて身体に刻み込む作業が必要だろうと感じた、というのがわかりやすいだろうか。いや、わかりにくいね!(笑)
竹村俊助さんの