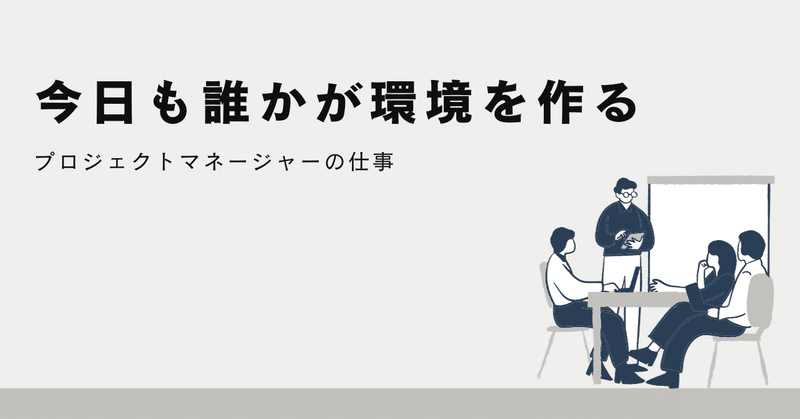
今日も誰かが環境を作る
Sun Asteriskという会社でプロジェクトマネージャー(以下、PM)をやっているおぬりーです。日本酒が好きで色々飲んだり調べたりしてます。Sun Asteriskでは主にシステム開発を通じて、クライアントが解決したい課題や、世に生み出したい価値を実現するためのプロジェクトを推進する立場として仕事をしています。
この記事はSun* Advent Calendar 2023 24日目の記事です。12月1日から始まったAdvent Calendarもいよいよ大詰めです。24時間テレビでいうところの「サライ」を歌っている頃です。今回はPM関連の記事を書くように指令があったので自分の体験をベースにつらつらと書いていく。
読んでほしい人
PMのお仕事に興味がある人
PMの存在価値について言語化したい人、できる人
日本酒が好きな人、興味ある人
はじめに
ある日参画しているプロジェクトで仕様決定、タスク・スケジュール管理、関係者との交渉などを実施していると、これPMじゃなくても対応できるんじゃないか?PMじゃないとできないことはなんだろうか?と、ふと自分(PM)のプロジェクトにおける存在価値について思索する場面があった。
PMを生業としていると他人から「何をやる仕事なの?」と聞かれた時に「なんでもやる万屋だよ」と答えた経験がある方は少なくないはずだ。実際に働いていて思うが、プロジェクトの推進に必要なことはなんでもやると思う。
スキルとして明確に定義することが難しい営みを日々行っているPMだが、改めて自身のプロジェクトにおける働きの価値を言語化するために内省してみることにした。
内省を進めていく中で、たまたま同時期に趣味として調べていた日本酒造りに携わる人の働きと紐付けて考えるとPMの存在価値について妙に腹落ちできたので今回はITシステム開発におけるPMと日本酒造りに携わる人の働きについて拙文ではあるが一筆したためる。
本記事がPMの存在価値について認知するための補助となることを心より願う。そしてあわよくば日本酒に興味を持っていただけると幸いだ。
「PM」と「日本酒造りに携わる人」が目指すもの
言わずもがなITシステム開発におけるPMはプロジェクトの成功を目指している。プロジェクトによって多少差はあるが、品質(Quality)/費用(Cost)/納期(Delivery)(以下、QCD)の3つの指標それぞれを計画通り達成したかによって評価されることが多い。
そして日本酒造りに携わる人たちは決められた原料と様々な技法を駆使して美味しい日本酒を造ることを前提に「狙った味わいの日本酒」となることを目指して取り組んでいる。
かなり抽象的に共通点を見出すとどちらも「ある特定の状態」を目指しているということは一致していそうだ。これらを踏まえてそれぞれの業務の解像度をもう少し上げてみる。
PMの営み
クライアントが実現したい世界の翻訳
一般的にシステム開発を進めるにあたって、クライアントがシステムによって何を実現したいか?という議論が最初に行われる。
実現したいことの例
従業員のシフトを管理したい
紙ベースの稟議をやめたい
製品を販売するための自社サイトがほしい
しかし、実現したいことをエンジニアやデザイナーにそのまま伝えてもコーディングやデザイン作成のタスクに落とし込むまでに当然時間がかかる。人によっては実現したいことからどのような機能が必要か分解し、コーディングやデザインに落とし込むアクションまで取ってくれるが本業以外の部分で体力を使わせてしまうのも勿体無いし申し訳ない。せっかくなのでエンジニア、デザイナーとしての価値を十二分に発揮してもらいたい。そのためにPMはクライアントから要求・要望を各メンバーがタスクとして動けるように引き出し、翻訳して伝え、プロジェクトメンバーがそれぞれの得意分野で最大限のパフォーマンスを発揮しやすい状況となるよう尽力する。
プロジェクトを取り巻く不確実性
実現したいことに対して必要なタスクの洗い出しをクライアント、プロジェクトメンバーとで協力してある程度進めていくと「これらのタスクを実行すればクライアントが実現したいことを叶えるものが作れそうだ」という状況になる。その後プロジェクトメンバーと一緒にタスクにかかる時間を見積り、スケジュールを作成する。これでタスクを実行する準備は万端だ。あとはスケジュール通りにタスクを実行すれば実現したいことを叶えるものが完成しそうなのだが、現実はなかなかそれを許してくれない。頼むから許してほしい。
この状況はあくまでスケジュールが見えた状態にすぎない。プロジェクトは推進状況に影響を与える想定外の事象が発生し得る不確実性の高い状況に常に晒されているのでそれらに対応する必要がある。プロジェクト推進に影響を与えそうな一例としては下記の通り。
プロジェクト推進に影響を与える要因の一例
想定していた技術での実装に課題があり時間がかかる
新たな機能追加や変更が発生する
機能に対するクライアントとの認識の齟齬の発生
権力を持った人による無慈悲な要望
外部のシステムとの連携調整
メンバーのモチベーション変化
あくまで一例なのだが既に多い。特にプロジェクトが始まったばかりの頃は影響を与える要因が顕在化していない物も含めて多数ある状況なので注意深く進める。この時ほど予知能力がほしいと思うことはない。
仮にこれらが発生した際には、情報の整理や関係者間での方針検討・合意形成などの対応などが発生する。発生した事象に対して「このタスクを実施すれば解決できる」という状態まで導いていく。実際に対応していて思うが事象を解決するための必要な情報を各メンバーから集め、それらを整理した上で関係者間での合意形成まで実施するのはぼちぼち気力を持っていかれる。気力ゲージが満タンの状態でお仕事をスタートするとしたら、徐々にこのゲージが減っていくイメージだ。この気力を持ってかれる対応をエンジニアやデザイナーにさせたら彼らの本業で消費してほしい気力を奪うことになりそうなのでPMが率先してして捌くのが良さそうだ。やはりメンバーにはそれぞれが得意な分野で価値を発揮してほしい。
このような事象が発生する状況下で、PMはプロジェクトの成功を目指してQCDを計画通り達成するために、メンバーがそれぞれの得意分野で価値を発揮できるようにしゃかりきになって動く。
日本酒造りに携わる人の営み
ざっくり日本酒の造り方
日本酒は米を原料に微生物の力を借りてアルコール発酵をすることで造られる。日本酒の原料が米であることは大抵の方は予想がつくと思うが、どのような工程を経て米から日本酒が造られるのか知っている人はそこまで多くないはずだ。実際に私も調べるまで知らなかった。
日本酒造りの工程についてあまり細かく伝えても本筋からかけ離れてしまうので、本記事では大幅に簡略化した内容を記載する。詳細な行程について興味のある方は是非調べてみてほしい。
大前提としてアルコール発酵時のアルコール生成原理は下記の通りだ。微生物が糖分を分解してアルコールと炭酸ガスを生成してくれるとのこと。私は糖分を摂取しても太ることしかできないのに微生物はすごい。この生成反応はおそらく学生時代に学んでいるはずだが忘却の彼方だったので、調べた時は十数年ぶりに化学反応式を見て若干の眩暈がした。
糖分 → アルコール + 炭酸ガス
この原理を前提に日本酒は下記の通り米から糖分を生成して、その糖分を分解してアルコールを生成するという2ステップを踏んでいる。ちなみに米は勝手に糖化しないのでステップ1でも微生物の力を借りている。
米を糖化して糖分を生成する
糖分からアルコールを生成する
微生物に働いてもらうための環境作り
このステップで日本酒を造ることはできるが、微生物の力を借りるといっても放置しているだけでは当然狙った味にはならない。さらに当然の如く微生物と人間の言語でコミュニケーションを取ることができるような特異人材はおそらくいない。微生物に人間にとって都合の良いように営みをしてもらい、狙った味にするための最適な環境となるための対応をする必要がある。具体的な対応の一例として下記を挙げる。
米の下処理
微生物の活動をコントロールするための温度調整
原料を適切なタイミングで投入
外的要因(雑菌など)の排除
当然これらは微生物だけでは対応ができない。人間が対応し続けることで微生物が働きやすい環境を作り、狙った味を目指すことが日本酒造りに携わる人たちの仕事とのことらしい。言語が伝わらない相手との共同作業によって造り出されている日本酒すごい。改めて日本酒を大切に味わおうと心に誓った。
日本酒造りに携わる人たちにPMの働きを重ねてみると類似している点があるように思えてきた。
PMはプロジェクトに必要か?
PMと日本酒造りに携わる人の働きを並べてみると、どちらも目標(QCDの達成 or 狙った味わいの日本酒造り)を達成するために、メンバー(人間 or 微生物)が得意分野で価値を発揮するための環境を作り出すプロフェッショナルであると私は認識した。
生物が何か営みをする環境では不確実性への対処は不可避であり、それらに対処して環境を守り続けることに特化した役割は価値ある存在なのだと他職種とならべてみることで認知することができた。環境作りのためのアクションが存在価値として他職種で立証されているのだから、PMとしてメンバーのための環境作りに必要なアクション(情報整理、関係者との合意形成など)を実施している自分も胸を張って存在価値を見出しても良さそうだ。
今回の内省をする前に「PMじゃなくても対応できるんじゃないか?」と考えていた仕様の決定、タスク・スケジュール管理、関係者との交渉などの働きはプロジェクトを目標達成に導くためには誰かがやらなければいけないし、それをやることで救われている人が少なからずいることを再認知し、PMとしての自己肯定感がほんのり上昇した。
内省の果てに
PMの存在価値の1つはメンバーが得意分野で価値を発揮するための環境作り
プロジェクト内で不確実な要素は必ず存在するので対応する人が必要
一見すると不確実性への対応は誰でもできそうな地味なタスクに見えるがその積み重ねがプロジェクトを成功へ導く
微生物と協力して美味しい日本酒を造る蔵の人たちすごい
今回の内省はそもそもガッツリとエンジニアをやってこなかった自分がPMとしてプロジェクトに参画していることへの仄かな劣等感と不安がきっかけで始まった。内省を経て、自分のPMとしての働きがプロジェクトにおいて少し価値があることは認識できた。これからもプロジェクトに携わる全ての方への畏敬と尊敬の念を抱きつつ、メンバーが気持ちよく動ける環境を提供し続けることに従事していこうと思う。
もし私と似たような経歴でPMをやっている方がいれば、その方達を少しでも勇気付ける記事となれば幸いだ。
Sun* Advent Calendar 2023 の次の記事もお楽しみに。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
