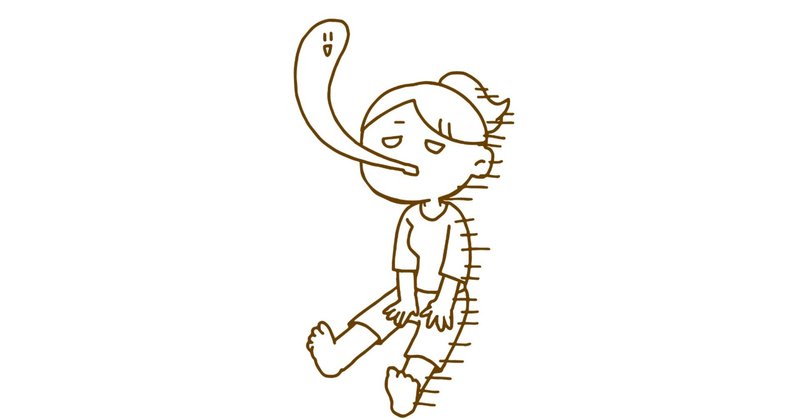
明石家さんまの主張「努力が報われると思う人はダメ」を、「ホンマでっかTV」出演の脳科学者が解説する。『努力不要論』中野信子 著
本書は、フジテレビ「ホンマでっかTV」に出演する医学博士/脳科学者である中野信子さんが、日本社会におけるブラック企業・やりがい搾取・同質化圧力の根底にある物を、脳科学と遺伝子の観点から解説します。
本書を読むと、日本人がイノベーションを苦手とする一方で、改善が得意な理由も、科学的に納得できます。欧米人とは異なる脳の日本人が、世界の中でどう生きていくべきかにまで話が及びます。
素晴らしい本なので、すべての日本人に一読をおすすめします。
<本書メモ(意訳込)>
・明石家さんま 主張
「努力は必ず報われる。努力をしていれば必ず誰かが見てくれていて、報われる」という考え方は、早くやめた方がええね。努力は報われると思う人はダメ。好きだからやってるだけよ、で終わっといた方がええね。報われるんだと思うと、こんだけ努力してるのに何でっと腹が立つ。人は見返り求めるとろくなことない。見返りなしでできる人が一番素敵な人やね。
・努力している状態にあるとき、脳の内側前頭前野が「自分は良いことをしている」と判断して快感を生み出します。また、ストレスや睡眠不足などの条件が揃うと、判断能力が低下して、いいように使われる危険性を増大させます。努力という言葉は、人を長時間酷使するブラック・レトニックに繋がる可能性があるのです。
・真の努力とは、本当に目的を達成したいのであれば、適切に目的を設定し、戦略を立て、実行することです。目的を達成するためには、睡眠・栄養をしっかりとり、ストレスをためない生活を送り、冷静な判断力を保ち続けることが必要不可欠です。その事を忘れ、努力そのものが楽しい状態は、正しい努力ではありません。
日本以外の国では、努力とは目的をスムーズに達成するためにやるものだという考え方があり、無意味に努力する人を見て「間抜け」と言う人たちまでいます。
・自己犠牲的な滅私奉公や、寝てない自慢、病気自慢をしたり、それらを他者に強制する事は、努力中毒の典型です。何十年もの時間を搾取されたあとに、取り返しがつかなくなったあとに気付いても、遅いのです。これを回避するためには、「自分は今どういう状態なのか」とメタ的な視点で自分を顧みる事がポイントです。信頼できるメンターから、第三差的な気付きアドバイスをしてもらう手段も有効です。
・アメリカ社会は、日本人が思うよりもセーフティネットはしっかりしています。地域共同体が、とくに都市部ではほとんど壊滅状態の日本と比べると、キリスト教コミュニティが存在する分だけセーフティネットが機能しています。日本では「クビを切られたあの人はダメ人間」と熔印が押されるが、アメリカでは「ああ、あの会社とは合わなかったんだね」と認知されるだけです。
・欧米では、滅私奉公せよと圧力があっても、意に介しない人が多い。その理由は、日本人と欧米人では、心の安定性に関わる遺伝子が違うためです。具体的には、日本人は欧米人と比べてセロトニントランスポーターが少ない為、周囲から非難されると不安になり、自分の主張を貫けず流され易くなります。
<セロトニントランスポーターの遺伝子比較>
・少ないタイプ:日本人7割、欧米人2割以下
・多いタイプ :日本人2%、欧米人30%
・アメリカは、セロトニントランスポーターが多いタイプがたくさんいる国です。とても陽気で楽しい人たちの反面、「自分の考え方が間違っているかも」というフィードバックはあまりしません。セロトニンがたくさんなので、さして不安になることはなく、リスクを過小評価気味に行動して、失敗してもへこたれません。
・アメリカ人はリスクを恐れないので、0から1をつくるのがとても得意です。周囲の批判が耳に入ってきてもスルーして、冗談みたいな発想からイノベーションを起こすことが得意です。
逆に日本人は、セロトニントランスポーターが少なく、批判されると不安になり主張を貫けないので、0から1を生むイノベーションは苦手です。心配性で、今あるものの弱点を見つけることに長けている日本人は、今すでにある種を見つけて、1から100まで育てる作業をした方が、世界一の仕事に繋がり易いのです。
欧米人と日本人は、遺伝子傾向(セロトニントランスポーター)が違うので、その適正に合った努力戦略をとる必要があります。
・人間の脳には、1人だけ突出して優秀な個体を、集団から排除しようとする機構があります。人間は、単体ではそれほど強くない生物であり、集団で生きることによって発展きました。1人だけ突出して優秀な個体がいると、既存の集団協力構造にタダ乗り出来てしまいます。それを見て、他の仲間たちまでもがタダ乗りしようとして、集団内の協力構造が壊れてしまいます。だから、協力構造を守るために、逸脱した個体の排除機能を、構成員が備えている必要があるのです。
・突出した才能を周囲に潰されない為には、「私なんか大したことないですよ」「結構つらいんですよ」という姿を見せることが有効。アンダードッグ効果と言いますが、同情の余地のある何かを提示することで、相手は溜飲を下げて応援してくれるようになります。ただし、見せた弱みを広められてしまうリスクもあるので、広まっても差し支えない話題を慎重に選んでください。
※日本は、集団が協力し合う村文化の遺伝子が、適者生存で強く残ってきた為、このアンダードック効果(謙遜)が必要不可欠なのでしょうね...
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
