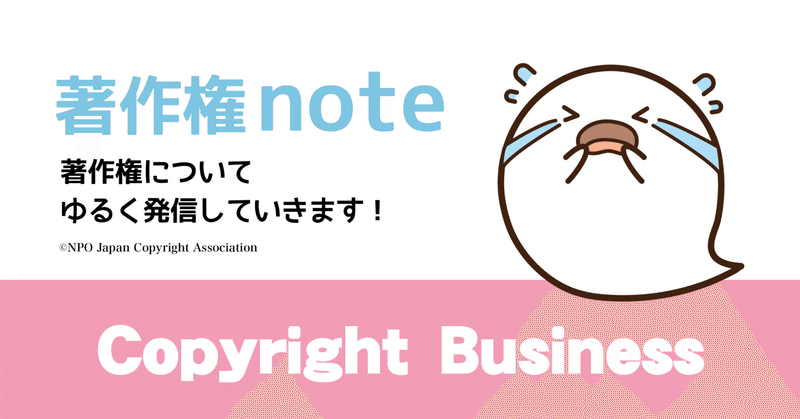
59.マネをするのは悪ではない!
1.他人のレイアウトをマネする場合
まず、「レイアウト」とは一体何なんでしょう?
レイアウトとは、一定のスペースにおける各素材のことをいいます。
たとえば、写真・イラスト・コピー・キャッチフレーズ等の配列のことをいう。他人のレイアウトをマネする場合の注意点には、著作権の問題と不正競争の問題の二つがあります。
著作権に関しては、レイアウト自体は著作権法では保護されません。
たとえば出版物の場合、各頁の部分や出版物背全体のレイアウトはかなり重要な部分としての要素だが、それでも保護されません。
ただし、私見ですが本来はレイアウトも立派な著作物です。
なぜならば、消費者の商品の購入動機は、その中身よりもその表現によって左右されてしまっているからです。
つまり、デザインや色彩、見やすいバランスのとれたレイアウト表現は、かなり重要性を帯びているといえます。
さらに、一つのレイアウトを制作したり、まとめたりする労力は大変なことのひとつで、どんなに商品が素晴らしくても、その文章や写真が美しくとも、最終的にはレイアウト調整でまとまるからです。
たしかに現在は著作権法ではレイアウトは保護されていません。だから誰もが自由に利用できます。
しかし、注意する部分もあります。
それは、レイアウトに基づいて各素材が特定され、その全体が編集著作物の要件を満たしている場合には、編集著作物として保護される場合があり、各素材の選択については注意しなければなりません。
次に、不正競争に関しても注意が必要。
もし、そのレイアウトが出版物や商品印刷物等の形態が一般に広く認識されているとしたら、逆に商品の混同を生じてしまい、不正競争に基づいて、差止請求権を行使される恐れもあります。
このように著作権と不正競争防止法の二点は注意しなければなりませんが、基本的にレイアウトには著作権がありません。
だから誰もが自由に利用できるのは間違いないでしょう。
しかし、わたしは、ソックリそのまんまのマネはおすすめしたくはありません。むしろ、素敵なレイアウトならば、それを参考にして、さらに自分らしく加工し、オリジナル性を高める努力が欲しい。それならば何も問題はありませんね。
このように法律には必ずスキマがあり、完全な法律などあり得ません。
最近は、違法コピーソフトマニュアルなどの書物が出回っていますが、たとえ違法性があっても、なくとも、そんなものを利用しないで自分のオリジナルティ(創作性)が欲しい。
また、著作権法の定義にあてはまるレイアウト(創作性のあるもの)ならば、著作権法でもレイアウトは保護されることを忘れてはなりません。
アイデアも著作権法では保護されない、発明的なことも著作権法では保護されません。
しかし、著作権法の定義にあてはまる考え方、作り方であれば、アイデアも、発明も、レイアウトも著作権によって保護されることを忘れてはなりません。
では、自分の企画した商品や著作物が、たまたま他人の商品と似ていた場合はどうなるのでしょう?
もちろんこの場合はデッドコピーにはあたりません。
不正競争防止法が禁止するところの「模倣」は、完全なパクリ、完全なるモノマネをいうのであって、他人の商品を知らずに、参考にすることなく、偶然に形態が似てしまった場合には「模倣」にあたりません。
もし、模倣だと指摘された場合には、「独立開発の抗弁」を主張することができます。これは著作権法においても、既存の著作物を参考にしないで独自に創作したものは著作権侵害とはならないと認められているからです。
これらは両商品、両著作物の類似性を比較判断することで、単なるイメージや雰囲気が似ている程度では侵害したとはいえないからです。ただし、誰が見ても同一に見える、感じるものは認められません。
2.他人の作品を参考にして創作する場合の注意点
他人の作品を利用する場合に、著作権法の解釈として次の三つがあります。
⑴「複製」
⑵「翻案」
⑶「別個の創作」
まず、著作権侵害になってしまう「複製」にあたるとはどんなことをいうのでしょう。
複製といえば丸写しすることが典型的なものです。
「複写」も同じです。
ならば少しだけ手を加えればいいのか、もっとさらに手を加えればいいのかという問題もありますが、どんなに手を加えようが他人の作品と同一と考えられる場合は複製になります。
これはひとつの作品から誰が見ても異なる、違った作品に見えたり、感じたりすればよいが、部分的な「修正増減」の範囲内であれば複製と考えられてしまいます。
このように著作権は表現を重視するものだから、表現を若干変えたくらいでは複製となってしまいます。
次に「翻案」の場合、既存の小説から脚本を作ったり、既存の音楽から編曲したり、既存の絵画を変形したり、既存の論文を要約したりする場合のことをいいます。
これは、既存の小説や音楽の表現そのものをそのまま利用しているわけではなく、小説のストーリー、音楽のメロディなどの基本的な特徴を利用している。そしてその基本的な特徴を利用しながら、さらに創作性が加えられ、新たな作品(著作物)が生まれていることになります。
このようにして創作された作品を「二次的著作物」といい、二次的著作物を作成した作者は著作権者となります。
しかし、二次的著作物を作成する場合は原作者の許諾が必要となります。
「完全に別個の創作」。これは、他人の作品を利用したが、あくまでも参考にした程度のもので、既存の作品で明らかにされた事実のみの利用だけで、表現そのものはまったく似ていないし、基本的な特徴も異なります。
この場合はまったく別個の創作物として、侵害にはなりません。
さて、これらのことを注意しながら考えてみると、他人の作品を参考にして創作する場合の注意点が見えてきたはずです。
つまり、他人の作品を参考にしながら、その内容を理解し、自分なりに消化して、自分独自の考え方や感じ方に基づいて表現した場合には、完全にその他人の作品の著作権とは無関係になる。
ここが重要なポイントになります。

特非) 著作権協会です。みなさん、お読みくださりましてありがとうございます。
人間の頭の想像には限界がありますね。
それは自分が知っているわずかな情報だけを頼りにして想像力を駆使するわけですからおのずと限界が生じます。
また「無から有を生む」という考え方もありますが、現実には無からは何も生み出すことができません。
そこで人間は、過去の歴史から学んだり、調査、分析、資料収集、情報の収集が必要になりますね。
その情報量によってインプットしたものを表現としてアウトプットするわけですから、無から有はありえないことがわかります。
4.どんどんマネをしよう!
今は情報がネットによって簡単に手に入る時代ですからこんなに情報収集、参考資料等が集めやすくなっているので、「有から有を生む時代」ともいわれていますが、あまりにも膨大な無限な情報のため、次に必要な能力は、「選ぶ」「選定」という力が必要になります。
そこに必要なことは、その情報に対するアイデア化、表現化にするための「感性」なるものが必要になります。ここでいう「感性」とは〈選ぶ目〉です。ここにマネの仕方のコツが隠されているような気がします。
ただのマネは模倣であり、盗作、著作権侵害となりますが、そこにわずかなアレンジをするだけでその参考にしたアイデアとはパクリでない限り、異質なものが出来上がるはずです。
つまり、新たなるオリジナルを登場させることができるからです。
ですからおもろいアイデア、イラストなどでいえはレイアウト、描き方、表現の仕方などは良い部分をマネて自分独自の世界観を創る、それがオリジナル作品となるはずです。
他人のものを参考にする、マネする、利用することによって自分の作品はさらに深みを増して、独自性を表現するのですから、他人の良い部分はどんどんと取り入れてマネをする。
マネをするのは悪じゃあない。
自分だけの考え、自分だけの想像には限界があるわけですから、いかに上手くマネをするか、がこれからの創作の世界かもしれません。
※特非)著作権協会の電子書籍のご案内「~無料・無断で使用できる著作権活用法④~「無断OK!著作権」全4巻発売中!下記にて検索してください。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
