
ゲーム開発者は人の幸せを作れるのか
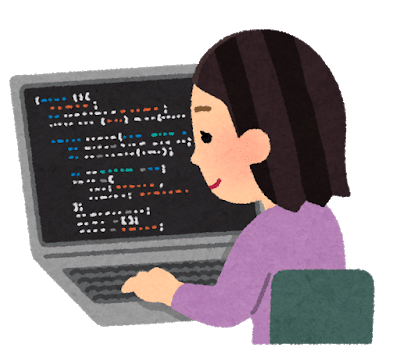
小さい時から音楽にのめり込み、進学校に潜り込んだところで、今の生活が決まってしまったのかもしれません。
高校で
「理系から文系には転向できるが、逆は無理」
というシンプルな理由で理系クラスに。
そこから進学した先も理系でした。
そして、音楽属性の理系風味、という人格が誕生しました。
特に目指さなかったがなぜかこの分野
非常階段の手すりに点字の階数表示シール
フルフラットな点字ブロック
いつでも最新ニュースが聴けるアプリ
聴覚障害を持つ人に日本語字幕
視覚障害を持つ人に音声ガイド
足が動かない人が動かせる車椅子
視覚に障害がある人が晴眼者を指導する仕事
手話ワイプ付き動画
声を失う人の声のデータを残す
ちょうど仕事の棚卸しをする機会があり、振り返ってみると、結構このような仕事もやらせてもらってました。特に福祉分野での仕事を目指したわけでもありません。流れで関わった感じです。
一見やってる内容はバラバラに見えます。でも、根幹は同じ、と同時に気付きました。
その根幹とは。
「利用者が利益を得るためにテクノロジーを活かす」
という視点です。
そのような感覚がどのように作られ、今の仕事に活かされてきたか、を整理すると、今回のテーマが見えてきました。
子供のお小遣いを巻き上げる

ストレートに読むとあまりよろしくない見出しです。でも、ある時期、こんな思いを持っていました。
社会人になって進んだ先はゲーム開発者。もちろん真面目な理系風味の担当者として、一生懸命仕事してました。実際に自分の仕事の成果が、子供たちの間で遊ばれてる様子も見えて、やりがいもあります。
しかし、ゲームカルチャーが流行れば流行るほど、ゲームやり過ぎ問題が出てきたり、学校での話題もそればっかりになってる感じも見えてきました。なんとなく世間に申し訳ないような気持ちも出てきたのは、少し仕事に疲れてきた頃かもしれません。
その時に、「自分は子供のお小遣いを巻き上げている」というこの表現が芽生えました。
勉強をしたり、幅広い知識を得なくてはいけない子供たちに、ゲームという大人でもハマる商品を提供すること、のネガティブな側面が自分にのしかかった…は大袈裟な表現ですが、近いものはあります。
一方、息抜きがあるから生きていける

実際の生活で「必要な事だけ」で生きていけるか?と哲学的な問いを発したとします。せっかくお読みいただいているので、皆さんにも聞いてみたい。
多分、リラックス、息抜き、ご褒美、余暇、といった、「必要不可欠とは言えないがでも必要」みたいな存在も必要、と多くの人が答えるのではないでしょうか。
自分も、そのような考えに至ることができ、疑問を持った自分の仕事に、もう一度モチベーションを取り戻す事はできました。
似たような話を思い出しました。
3.11で被災した友人に不便を尋ねたらそれこそ山のように出てきました。何が欲しい?と尋ねたら最終的に「タバコ」。色々なところから温かい支援はいただいていて、十分ではないけど、生きていける。でも、ちょっと現実逃避したい、という時の友人の「生きるのには不要だがでも必要なもの」がそれだったようです。
多少の不便を忘れる瞬間があれば、大変なことを乗り切る力にもなる、ということです。
今で言うゲーミフィケーションに
そんな葛藤を経て、まずは本線に戻れた自分ですが、新しいチャレンジをしました。
純粋なエンタメ作品を作っていた時代からだいぶ経って、「全くゲームを作らない部隊」の立ち上げへの参加です。元々色々な事に興味はあったので、すんなりと移行。
ゲームは「必要不可欠ではないもの」ですから、面白くなければ当然見向きもされませんし、面白くても
「面倒くさい」
「習得が難しい」
「操作が覚えられない」
「説明書を見て理解しないと始められない」
といった事があれば二度と手に取ってくれないこともあります。
このような状況にならないように、ゲームは開発されます。上のようにならないようにする、というのは絶対に落とせない要素です。
対して、と例にすると語弊があるかもしれませんが、公的な手続きや義務教育は、「必要不可欠」なもの。もちろん快適に進められるような工夫もされてますが、ゲームに比べれば「多少不便でもやらなくてはいけないからやる」という側面もあります。
必要不可欠でも、手続きは簡素で迷わずできた方がいい。さらにあらゆるサービスでゲームが目指してきたものはプラスになります。
活きることに必要のないものに興味を持ってもらうためにゲーム業界が培ってきたノウハウを他の分野に活かせば、さまざまな事がより快適になる、とゲーミフィケーションの考えは発生した、と考えています。
そんな領域へ入っていきました。
改めてゲームが守ってきた事をまとめる

先ほどの避けるべき要素、を反対に書きます。
「面倒くさくない」
「習得が難しくない」
「操作を覚える必要がない」
「説明書を見る必要がない」
これにより何を実現したのでしょうか。
それは
脱落させない
ことです。
偏差値、という評価軸を教育界では使っています。中央が高く、成績の低い人、高い人の割合が減っていく山のようなグラフ。つまり、その分布を通常状態としているなら「履修が100%ではない状況を容認している」という事になります。
自分が小学生の時、主要教科じゃないからこの教科の5は他人に譲れ、という事を言われた事がありました。5の割合があらかじめ決められている故の調整です。小学生ながら、しっかりとこの考え方に疑問と不満を持つ事に。
ゲームでは、上手な人も初心者も、なんとか全員をエンドロールを見てもらうまで、あの手この手の工夫をしています。そうでなければ、自分の会社の他のゲームや続編を遊んでくれません。死活問題ですので、それはもうありとあらゆる手を考え、検証し、改良し、が毎日続きます。
上手な人は簡単すぎると意欲をなくします。ビギナーは難しすぎると投げ出します。さらにどちらのユーザーも遊びながら上達します。これを一つのゲームで受け止めなければいけないのです。
偏差値で言えば、全員が右に寄った形を目指すことになります。もちろん、学校の授業のように同一時間軸で全員を進めさせるという縛りはありません。それでも、学校のカリキュラムにも活用できる考え方はたくさんあります。
一般サービスのユーザに対しても
非ゲーム分野の仕事をゲーム開発者が行う会社を立ち上げて、そこからの仕事の対象範囲は広がりました。
一見、新しいチャレンジに見えます。でもやる事は基本は同じです。脱落させず、いただいた利用料を得したと思ってもらう設計をする。これはゲーム開発と同じです。モンスターを倒す操作が、タスクを効率的にこなす操作に変わっただけです。
その会社としても、非ゲーム専門の部隊を持つのは初めてではありましたが、蓋を開けてみれば中で行っていた作業に大きな違いはありませんでした。
改めて気付いたのは、ゲーム開発の仕事の要素を取り出してみれば「利用者の快適な時間軸体験の設計」だったのです。
福祉分野での出会い

自分が扱ってきた分野は、ざっくり言えば
テクノロジーでサービスを作る
です。
これを魔王を倒す事にまとめればゲーム。生活の不便を解消する形にすればゲームのノウハウを活用したサービス。
そんな業務をこなしていたときに、たまたま視覚障害で全盲の部下と一緒に働く事がありました。いっしょに仕事をする中で、本当に様々な未知の世界を体験できました。
既に彼らは、テクノロジーによって不便を減らす事を当たり前に体験していた、という事実は、他の障害を持っている人はどうだろう?という考えが当たり前のように広がります。
あとはフットワークです。ここからは比較的簡単に様々な方と知り合えて、結果、先に書いたような色々な仕事に携われたのです。
障害を持つ人へのサービスで気付き
様々な方と知り合う中で、当事者たちはもちろんですが、支える側の人たちともコミュニケーションができました。皆さん、真剣に障害を持つ人たちの助けになる事に真摯に向き合い、頑張ってらっしゃいます。そんな姿を見て。
感動しました、感服しました、感心しました
ではない印象を持ちました。皆さん、自分の時間や技術を費やし、場合によっては私財も投入されてる方も。
非常に素晴らしい事なのですが、この状態を普通にしてしまうと、後に続く人が産まれにくいと考えられます。
そこで、ある程度の賛同者を募り、持続するサポートのあり方を共有、その方針で様々な企画を進めよう、となりました。
その「あり方」はシンプルです。ビジネスとしてしっかり利益を出す事。利用者は便利をその割合に応じて対価を払っていただく事。もちろん、補助金なども使えるようにはします。
これにより、たとえ立ち上げた人がどこかで力尽きても、そのサービスを受け継ぐ人が出やすくなり、結果としてサービスは継続できます。
良く考え、緻密に作り、確実に利益を出し、粛々と継続する、という普通の商売の形を目指したわけです。
そのようなビジネスの雛形を横展開する、という流れができれば最高です。
ゲーム開発者ならできる

ゲーム開発者は、遊びをカジュアルな格好で作ってる、という幻想があります。いや、幻想ではなく、結構な割合でそうかもしれません。
しかし、その作業内容はカジュアルと反対、非常に論理的で緻密です。作っている商品はエンタメですが、作業を単純化して言えば、
破綻しないシステムのルール作り
ユーザーの体験の時間軸の設計
を、先に述べたように様々な「脱落させない工夫」を駆使して形にしています。もう一度確認してみます。
「面倒くさくない」
「習得が難しくない」
「操作を覚える必要がない」
「説明書を見る必要がない」
特にゲームに関わらず、様々な事が便利になる、という事はご理解いただけると思います。
つまり、優秀なゲーム開発者は、優秀な一般サービス開発もできる可能性があるわけです。ゲーム開発で得たノウハウは、将来、いろんな意味で使える学びがあります。どんどんゲーム開発者を若い人にも目指して欲しいと思います。
自分にとって大切なこと
エンタメの世界で頑張ってきて、たくさんの子供たちの大切なお小遣いから、給料をもらってきました。
今、会社には属さずにフリーで色々な方と仕事をさせてもらってますので、この考え方を若い連中に(年寄りくさい言い方ですが)伝えることができていません。でも、今回のこのテーマを設定してもらったことで、世の中に伝える機会をもらえました。
自分にとって大切なことは二つです。
ゲームを楽しんだ人たちから育ててもらった。これからは社会に貢献しつつしっかりと利益を出すこと!
ゲーム開発者のスキルは必ず世の中の役に立つ、だから世の中に目を向けよう!と声を上げること!
です。
最後にひょっとしたらもっと大切なこと
とにかく思いついてしまうのです。街を歩くだけでも、こんなことすれば便利なのに、とか、家電量販店に行けば、こうすれば目の見えない人が使えるんじゃないか、など。
しかも、障害のある人向け、という仕立てではなく、外国人にも、土地に慣れない旅行者にも、高齢者にも、さらに障害を感じてない全ての人にも、より便利を提供できる可能性を感じています。
死ぬまでに全部を消化できる分量ではないアイデアがたまりまくってます。
この考え方に賛同いただける仲間を増やすこともしていきたいと思います。

スマホで書く分量じゃない文字数になってしまいました。お読みいただき、ありがとうございます。
まだまだ色々と書きたい記事もあります。金銭的なサポートをいただけたら、全額自分の活動に使います!そしたら、もっと面白い記事を書く時間が増えます!全額自分のため!
