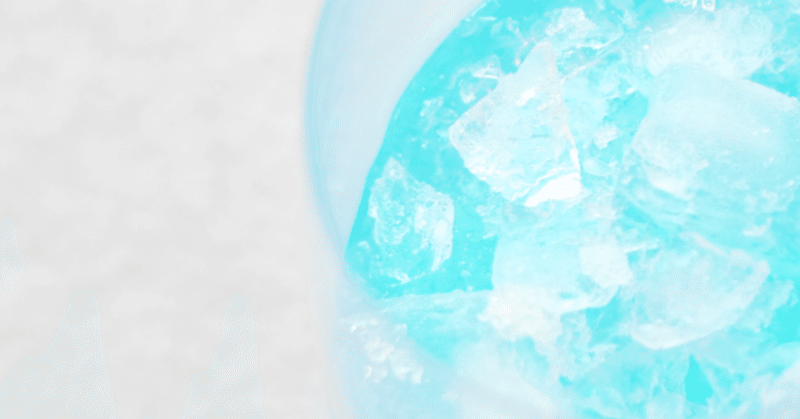
小説?|ブルーハワイ・フロート
前置き
文学的な問題は一切孕んでいません。
本編
午後一時半の中心業務地区は酷暑と言っても差支えがないほどに大気が煮えていて、アスファルトの照り返しが私の脚をストッキング越しに刺す。何故こうも高層ビルばかり空を埋め尽くすように建っているのか――それは地価が高い以上そうせざるを得ないのだ、そんなことわかってるのに――ただ、これではまるでコンクリートの雑木林と形容せざるを得ない。植林地でもいい。とにかく蒸すし蒸れるし蒸し暑い。日はもちろんさっき南中したばかりだから傾いてはくれないし、残念ながら今の季節は日照時間が長いから、彼の支配は比較的長く続く。歩道の鳩がタバコ屋の前の溝をつついている、美味しそうに。首筋に汗が走った。デオドラントスプレーはしたはず。大丈夫……
別に私は会社勤めでもないし、外にいなければいけない身分でもない。タクシーの前で右手を挙げるだけでこの地獄から開放される。しかし我が小さき財政にはそれを諦めざる深い深い理由、すなわち明日の飯があるため、やはり私は外に投げ出されたままである。変にスーツなんて来てくるんじゃあなかった。サラリーマンと肩がぶつかった。お互いになにも言いはしない。暑いからそれどころじゃない。禿頭をお天道様に曝し申し上げなさって、大層なことだ。心の中で毒づくだけだ。靴の中も蒸れてるし。汗は滝のように流れるし。一瞬冷静になってあたりを見回してみたが、おおかた私と同じようなことしか考えていない社会人の辛気臭い顔だった。私が社会人かは、わからないけれども。
嗚呼、なにか冷たいものを。
生憎私は洒落たカフェや人気のデザートチェーンなどとは無縁でありまさか一人で入店するなんてことは出来ない……というか、そうは言ってみたものの本当の本当に知らないからたとえ看板を見ても判別不可能で――ただ、なんというか、男子トイレを見る気分というか、私と関係ないけど、あるなぁ、みたいな。そういう存在。しかし喉の渇きは、今回ばかりはそれで許してはくれなかったのである。
結果から言って、私は日なたから逃げるように、一つのカフェのようなものに敢行したのであった。もとより羞恥心などないが、居心地が良いかと言われると微妙だ。店の雰囲気自体はシックに大人な印象設計がなされているらしいのに、利用客が頭の悪そうな女子高生気取りなどでは、当惑もするというものだろう。しかしながら、別にそれを気にする必要はない。私はサムシング・コールド・トゥ・ドリンクと冷房の効いた腰掛け、机があればそれで良いのだ。足るを知っている。多分。
まずレジに向かうようなので、それに倣う――メニューを渡されたが、よくわからなかった。期間限定のライムがなんたら。ヘーゼルナッツシロップがなんたら。目に入ってくる外来語は、でもれっきとした日本語の文字列のはずにも関わらず私の頭のスポンジには吸収されない。まずい、受付が次の次だ、早く決めなければ――
依然としてシステムと商品名が示すものの照合がとれず、あたふたとしていた私だったが――ひとつ、見覚えのある名前があった。
「フロート」
故郷の喫茶店で飲んだことがある。
「ブルーハワイ・フロートをください」
主にグラスに入った炭酸飲料にアイスクリームを浮かべたものを、フロートという。コーヒーフロートやコーラフロートがメジャーな部類かもしれないが、私はあえて(文字通り)異色のそれを選んだ。とかく涼みたかったから。青色の涼しさに惹かれた。
商品を受け取ると堪らず首元を扇ぎながら雪崩込むように個人席へ座り込んだ。何となくアイスクリームを食べるのは勿体ぶって、ちびちびと青色の沸いた炭酸水を飲む。ストローでかき混ぜる。
鮮やかな色彩を伴った液体が店の窓から尚も侵入しようとした陽光に透かされて、空色に輝いた。からんころんと音を立てて。やがてアイスクリームは漸次溶解を始める……最初、空に対する雲に、入道雲に見えたそれだったが、段々と私自身が涼んでくると、実際にはそれは、名前通りの浮いている氷――流氷とか、氷山とかに連鎖するようだった。先程まではカンヅメのサクランボは太陽だったが、じゃあ今度は何になるんだろう――そんなことをつらつらと考えながら、私はパソコンを開く。
ガラス一枚挟んだ向こうの熱帯都市に思いを馳せて。
文字を打ち込む。
✱
私は、大きな白い氷山の端っこで寝ていた
空も海も遮るものがないほどに青く、つまりこの氷山を除いて海には海しかなかった
白熊の親子が私を見ている
決して近づいては来ない
決して逃げてはゆかない
ただじいと、私を見ている
ごお、お、お、お、お、お、ん、ん……
青空に白竜が咆哮す
わざとかどうか、口から溢れる煙を撒き散らして
大空を我が物顔で横断す
天球の中心を軸に旋回す
白熊の親子も私も、それを見ていた
白い無数の影が、竜を追った
それは海鳥だった
空を返せ。
海鳥は言う
海を返せ。
竜の尾を啄む
あの大地に、静けさを返せ。
竜の目をくり抜かんとす
ごお、お、お、お、お、お、ん、ん……
竜が吐く不可視の煙は小さな白い影を一羽、また一羽と海に溶かしていった
溶けてしまえば飴細工
怒って溶けて、また怒る
天気雨がぼとり、ぼとりと降ってきた
かわいそうに。
私はそれを拾って食べた
白熊親子はそれを見ていた
いつしか登った灼熱の星
透かして輝く飴細工
それでも彼らの追及はやまぬ
風を返せ。
海鳥は鳴く
波を返せ。
その翼膜を裂く
この天蓋の、冷えきった過去を返せ。
竜の肺を穿たんとす
ごお、お、お、お、お、お、ん、ん……
透明でしかし厚ぼったくて、それでいて暑苦しい、淀むスクリーンに影が歪む
形を改め槍と成る
海鳥は決して許さなかった
灼熱の下に甘露を垂らし続けても
かわいそうに。
私はそれを拾って食べた
白熊親子は見ていた
しかし
一つの影がついにやった!
腹を食い破った
はらわたが飛びでて、黒い、物凄く黒い、黒い、黒い何かが落ちてくる
竜は耐えかねて
喉を鳴らし、身体をくねらせ
この空は、この海は吾輩のものだ、誰にも渡しはしない!
一層に煙を噴かしながら、乱回転で堕ちていく
ごお、お、お、お、お、お、ん、ん……
そこで私は立ち上がり、意気揚々と筒を脇に構える
そこで私は立ち上がり、見ていろよと親子に告げる
直径二・七五インチ、全長五フィート、重量三四・五ポンド、有効射程四〇〇〇メートル――のそれを、私は掲げ、その下部にてのひら大の円柱をねじ込める。そして左手をそのまま添え、スイッチをオンに入れ、目標――白竜の頭、つまり熱源を補足する。
そして引き金を引いた。
ばしゅっ。
筒から発射されたミサイルは、十メートルほど空を進んだのち、突如としてその尻から火を吹き出して、超音速で白竜に向かう――
しゅ、う、う、う、う、う、ん、ん……
ごお、お、お、お、お、お、ん、ん……
遠くの遠くで、だいだい色の火球が生まれた
音はしない、ただ波の立つだけだった
■■■■!■■■■■■■!■!■■■!■■!
白竜は咆哮す
過去に見ない正義の鉄槌に
そして、小さな火球は消えた
しかし、すぐに光を取り戻す
■■■■■■!■!■■■!■!■■■■■■!
白竜は戦慄す
過去を見ない平等な優しさに
裏切りに。
白竜は既に白竜ではなかった
絶望の色を浮かべるそれには、もはや気高き空の支配者たる威厳はない
頭から尾まで、連鎖的爆発が、続く
光る
青空は既に青空ではなかった
人差し指が引き起こした爆発は、空を西から東まで終末的黒煙で覆う
生ける爆弾と化した王の形骸は
しかし、今まででいちばんに輝いていた
私と白熊の親子はそれを見ていた
やがて、その閃光も絶えた
そして、雲は過ぎ去った
鈍く燻った遺灰が、ゆっくりと大洋に舞い降りてゆく
元の青空に、黒い蝿が飛んでいるように見えた
でもこれで、ひと安心。
ようやく空は、平穏さ。
静かな海は、守られた。
私は振り返る
守るべき命を
守るべきなにかを
愛しむべき親子を
愛しむべき静寂を
慈しむべきこの青色を
慈しむべきかの関係性を
志すべき正義を――
どんっ
えっ。
ざばん
振り向いたとき、そこにあったのは青い海洋それのみだった
水中から水面を通して辛うじて見えたのは、白熊の母
なぜ!
私はあなたたちを助けたのに!
氷山の岸が醸す海中蜃気楼が私の視界を遮っていく
止まらない、止まってない――知らない!
私はやったのに、あいつを、白竜を倒したのに、なぜ私を突き落とした!
歪んで見づらい母の顔は、しかしなにも言わなかった
決して擦り寄っては来ない
決して背を向けたりしない
ただじいと、私を見ている
じいと
ざばざばざば
いつか溶けた海鳥たちが、今、水面を突き破って私の周りを取り囲む
水泡が煌めく世界は、さほど美しくはなかった
飴細工は私の体を包み出す
べとべとと、重く、沈み込むように
引き落としてゆく
やめろ!
水の中で声なんて出なかった
もがくことも出来なかった
飴細工は私だった――
白熊の親子はもう見えない
きっとあの岸でまだ私を見ている
でももう見えない
私に許されたのは、とうに光の届かない海中を臨み
そこのグラスの底まで自動的にたどり着くのを待つこと
水泡が見えた
上ではなく、下から
このグラスの底の方からわきあがって来る、泡
ぶくぶくぶくぶくぶくぶくぶくぶくぶくぶくぶくぶくぶく
瞬間
私の目に映るは、赤き妖星
熱源だ。
ここは、沸いている
黒煙を吹き出している
海底火山が怒っている
彼らは、私を待ち受けていた
いつの間にかその熱で飴細工は溶けていた
でも、関係ない
怒りに晒されてしまったから
もう、仕方ない
ようやく会えた、大地の怒りに
燒ける、灼ける、妬ける、焚けるように熱い、暑い、厚い、あつい!
だからどうした!
グラス底の発泡海嶺帯
そこで私は、尽きる運命
そこで私と、尽きる運命。
さようなら。母よ。
私は
黒煙を噴す案内人に導かれ
多少咳き込みながら
妖星の断層へと
しず
んで
いっ
✱
気がつくと、私はカフェの一角で寝ていた。
一瞬、何故こんなところにいるのかすらわからなかったけれど、すぐに思い出した。寝過ごしたからと言って急がねばならない身分でもないから、幾分その点に関しては他人よりも寛容になれたが――しかし、当たり前というか、半分まで飲んでいたフロートは既に全て、溶け切ってしまっていた。
後に残ったのは、灰色みたいな不透明の液体。
陽光がなかった。
さっきまで見ていた夢を今更思い出したような気分になって、それもあまり後味が良くなかったので、私はもう不味そうなそれをえいやっと飲み干した。ストローは使わなかった。急がなくてもよかったけれど、こんなところで寝ていたことに羞恥心はあった。
なんのために入店したのか――若干火照った顔を伏せて、トレイにグラスを載せ、トレイを持ち、立ち上がり、返却台へ置き、化粧室に入り、身だしなみを整え、そそくさと店をあとにしようと思った。店の出入口は自動ドアではなかった。私がそのドアに向かおうとしたとき、一人のスーツ姿の男性客が、半ばずぶ濡れのような状態で入店してくるのと、すれ違った。そこで私は初めて、その大きい窓から店外を凝視出来た。外は豪雨だった。傘は持っていない。変に立ち止まることも出来ず、とりあえずドアを開ける――途端、雨にも関わらずドアの隙間から店内に向けて熱風が吹き込み、水蒸気で飽和したそれは私の頬を滑った。雨脚はかなり激しい。どうもゲリラ豪雨というやつらしい。今日はつくづく天気に恵まれていないなあと思い、目を側める。
カフェの室外機が雨音に負けないくらい唸っているのを、しかし私は聞こえないふりをして――仕方のないふりをして、一番近いコンビニまでビニール傘を買いに向かうのだった……
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
