
【詩人の読書記録日記】栞の代わりに 5月8日~5月14日
はじめに
こんにちは。長尾早苗です。
長い休みが平日も続くとペースを崩してしまうこともあり、自分でなんとかできた先週。今週からは普通の生活に戻るので、ちょっとだけうれしいです。
少しずつ近づいてくるZoomオープンマイクやスラム。そして文学フリマ。頑張っていこうと思います。
5月8日
今日は少し持病が再発し、体が痛かったり悲しくなったりしましたが、なんとか生活リズムを取り直せる日となりました。夜には実家に母の日の花束を届いておくように注文しておいたのだけど、なんと昼前に届き、両親がとても喜んでくれたらしく、とってもうれしいメッセージをもらいました。
5月9日
よかった、いつもの日常の平日がやってきました。始業時刻までは体の痛みと戦い、始業してからは椅子に座っていられなくなったらスマホでソファベッドで作業していました。本当に便利です。
テレビ、休日は友人が担当する番組がある時にしか見ないのですが、平日は朝ドラ以外見ないんです。でも、すごくいいなと思うのは、朝ドラ前に気象情報があることでした。万年筆も書き味が悪く、寒暖差や気圧で書き味が悪くなってしまうこともあるそうです。このつらさは寒暖差や気圧で体が参っているんだ! と今更気がつき、エアコンを入れたら元気になりました。ご心配をおかけしてしまってごめんなさい。5月中旬になったら、また何かとせわしなくなりそうなので、今はゆったりとした今を楽しみたいと思います。
月曜日はがんばってはいけない。昔の同僚に言われました。ゆるゆると進んでいくつもりです。今週は今週末に向けて、体調を整えていく期間。ラジオをたくさん聞いていて、元気が出ました! デスクワークなので、スタンドにスマホを置いて、ラジオや双子のライオン堂さんの開店9周年のイベントアーカイブなど。双子のライオン堂さんのイベントアーカイブは何本かあるので、ちょっとずつ。大好きな赤坂ノンブル交差点もありました! 見ながら、聴きながら作業ができるので、この仕事の仕方でよかったなと思います。とても楽しい一日となりました。今週末は土曜に連句会、その他もろもろエントリー、日曜日にアーカイブですが、オンラインイベントを見ます。楽しみ!
・出久根達郎『東京歳時記 今が一番いい時』河出書房新社
大学生の時から、連句の会にお誘いいただき、出ていました。
その頃から、「連句仲間」というものができ、今は時折になってしまっているけれど、歳時記をひらいたりします。
連句会が近づくと、句を作りたくなりますし、連句仲間の近況を聞きたくもあります。
このエッセイは、俳句に合わせて歳時記をめくるように季節ごとに書かれたものです。そうだよなあ、季節と共にわたしたちはまわっていますし、季節や暦と共に生きている気がする。そういうすべての事象が「季節を表す」ことができる。名前って、なんて素敵なんでしょう。そういう意味で、色々なものに季節を感じていたいです。
・なだ いなだ『とりあえず今日を生き、明日もまた今日を生きよう』青萠堂
当時82歳だった著者。自らの「死」を見つめながら、自分の生きていく道をもう一度発見する。
今日を生きたら、明日がやってきます。
しかし、明日という日になると、明日は今日になります。治らない病気と告知されても、それでももっと書いていたかったという情熱。わたしは本当に幼いころに手術をしましたが、そういう時にことばがあったおかげで生き抜くことができました。病気というものは常にわたしや、そして長く生きているとついてまわるものです。
それでも、新刊の準備をして、三十三冊準備中の話はグッときました。
・森谷明子『南風吹く』光文社
再読になります。週末に向けて、俳句というものや短詩というものを考えてみたくて。
俳句甲子園。青春ですね。それでも、高校生には高校生なりの悩みがあります。悩みがあるからこそ、書けるものがあります。悩む。それでも作品を創る。句作ということに関することだけではなく、詩作もそうです。
自分のすべてを客観的に冷静に見つめ、そして季節の中で生きていくと決めることが、句作の中で重要になってくるような気さえします。
主人公の男の子も、そんな「俳句を作る」ということにおいて、そういう決意があったとわたしは思いました。
・荻上直子『川っぺりムコリッタ』講談社
荻上直子監督の映画作品、『かもめ食堂』『めがね』は大好きな映画です。
あのような日常と非日常が、映画として伝わってくる描写が好きでした。
今回は小説として初めて読みましたが、やっぱり映像的なんですね、ことばの選び方を上手に操っている。この主人公の男性の絶望とこれからが、映像として伝わってくるんです。映画でしかできないこと・小説でしかできないこと。情景描写がとてもよかったです。情景を人や風景に対して与えて、それをことばにしていくこと。それはすてきだと思う小説にはよくあります。
母の長い爪、マニキュア、口紅の描写がすごく好きでした。それに対してどう暗闇の中で生きている主人公がどんな怒りを抱いているのかも。
家族、というものと、人と人とのつながりをきちんと表していると思います。
・大島真寿美『三月』光文社
幼いころに知り合った友達が不思議な縁で語っていく物語のアンソロジーになります。
わたしも今度の夏あたり、小学校の同窓会があります。少し落ち着いてきたし、行けるかなと思います。
なんだろう、この本を読んで思い出しましたが、今までみんなが同じ「小学校」という場所にいたのに、全然違う道のりを進んで。
わたしも結婚したし、出版もしたし、「本が好きな泣き虫の早苗ちゃん」だけではなくなりました。
時折みんなのグループメッセージをのぞくのですが、海外勤務をしている友達、パパになった友達、たっくさん色々な生き方をしてきたみんなが、います。そのごちゃごちゃした感じ、いいなあと思うのですが、改めてそういうみんなと出会ってきっと、また書けるものも変ってくるのかなと思います。
多分、この小説はそれを言語化してくれているから、心地よかったんでしょう。
・太田治子『星空のおくりもの』新潮社
女性も、いつだって色々な悩みを「ライフイベント」として持っているような気がします。これは、そんな女性たちの物語。
結婚、出産、子育て、就活、恋愛……
みんなそれぞれ悩んでいて、でもそれは、「贈り物」でもあるんです。
わたしは女子校に長く通っていたためもありますが、そこで出会った友達、一緒に勉強してきた友達がそれぞれの生き方をしながら、その「ライフイベント」を楽しんでいるようで、全然違う問題で悩んでいたりするんです。
わたし自身、そういう女性の友達が多く、みんながSNSに書き込んでいったりするのを時折見ています。そういう意味で、わたしとは違う生き方をしているみんながいることに苦しくなった時もありましたが、最近は慣れてきました。読書をして、そしてそれを紹介するエッセイを書き続けたことが大きかったように思います。読んでくださるみなさまに本当に感謝いたします。そういう意味でも、彼女たちのSNSは勉強材料になったし、彼女たちにいつかまた会えたら話したいことも、すべて原稿にぶつけているというか。いつか、自分の悩みも「贈り物」というものになると、わたしは信じています。
5月10日
今日は朝からほてっていたので、また寒暖差と気圧かなと思い、じぶんで本をデザインする双子のライオン堂さんのYouTubeを見ながら、インデザインの作業を少しだけ学ばせていただきました。
自分の本がどのように組版されて本になっていくのかを他の著者さんの文章を使った映像で知る過程は、本当に楽しいものでもあります。
韓国パンデミックSFの『最後のライオニ』がやっと手に入るようになりました。楽しみです。
色々と楽しいことが待っているのに、季節についていけない体……なんとかしよう。今週末の連句会では歌仙を巻くのだけど、その後の夜にエントリーとスラムの対戦相手発表……! なんとまあ。歌仙自体も久々。半歌仙の倍なので、今回は多くとられるといいな。
今日は午後に少し気圧の変化についていけたので、移動図書館に行っていました。やっぱり新しくなって、よかった。読書で元気になるって、いいな。句作15句。
・ナーズム・ヒクメット 石井啓一郎編訳『ナーズム・ヒクメット詩選 タランタ・バブへの手紙』公益財団法人 大同生命国際文化基金
わたしは囚われている
ということばが、こんなに響くとは思いませんでした。トルコの詩人の詩集で、その土地の文化が現れていますが、どうしようにもなくなった時、詩人は声を上げ続けるか、沈黙せざるをえないか、そのどちらかでもあります。
本当に極限状態になっても詩を書くということは、非常にエネルギーを使います。
それでも、伝えたいことがあるなら人は詩を書きます。
それは、わたしたち日本語を使う人も、トルコのことばを使う人もそうであると知りました。
伝えたいことをきちんと整理して、ことばにできないことほど詩人として苦しいことはありません。
わたしも少しずつ休憩を入れて、がんばりたいと思います。
・村上春樹『めくらやなぎと眠る女』新潮社
最近、メリーポピンズをパフィンブックスで読んで、舞台を観に行ってから、よくロンドンキャストのメリーポピンズのサウンドトラックを聴くんですね。そして、自分自身の詩を翻訳ソフトで英語訳してみたり、去年から始めたラジオ英会話で、毎日英語に触れているんです。
なんのこっちゃと言われるかもしれないんですが、村上春樹さんの文章は「英語として聞こえてくる」んです。わたしは人より少しだけ、視覚と聴覚が敏感です。最近は視覚に対する刺激に強くなり、聴覚は視覚から入ってくる情報を具現化してくれる。そんな要素があったからこそで、ラジオを聞いているんです。
わたしが読んでいる文章は、ここのところリーディングを再開したのもあって、非常に聴覚に働きかける。だからこそ、合評会で詩人の皆さまにリーディングしていただきます。自分自身の詩も、音声データとして保存して、聴きなおして推敲したりします。
そんなようなこともあって、村上春樹さんの短編小説(特に短編小説です)を読んでいると、自然とジャズが浮かんできて、ジャズと共に読める小説になっていると感じます。他の詩人の方でも作家の方でも、音楽を感じるものはその音楽を思いながら聞くことが多くなりました。
短編小説を書くのは「喜び」。かっこいいですね。「造園に近い」ということも、なんだか最近ほほうと思ったことでした。
・益田ミリ『47都道府県女ひとりで行ってみよう』幻冬舎文庫
益田ミリさんは友人におすすめされたエッセイが本当に面白く、彼女のゆるやかな文章や何かと鋭い観察眼が好きです。
ちょっと頭が疲れてきたなという時に、手軽にさくっと読めるのも魅力かもしれません。
月に一度、一か所を女一人で巡る旅。いいなあ、わたしもやってみたい。
ここのところ、週末を一人でどこかに行って、レポートを書いて、平日がんばる、週末一人旅、というリズムがGWで逆に崩れてしまって……なんだか心配をおかけしているのですが、なんだかこの本を読んで元気になりました。平日に平和な日々を過ごすことも、すごく重要だし、ウォーキングしていてたまに会う地元の個人店の方々なんかもすごく好きです。
でも、知らない街にも行ってみたいし、知らない人とも会いたい。もう一度行きたいところに、もう一度会いたい人とも会いたい。そんな気持ちを高めさせてくれました。
・伊藤比呂美『ショローの女』中央公論新社
伊藤比呂美先生にはお会いしたことがあるからか、何かと近しく感じます。先生が早稲田で教えていらっしゃった頃のことを、大変な日々とはいえちゃんと原稿にしているというところにまずわたしは感激しました。
最近、「詩人は体力」ということを常に感じていまして、どれだけ一編の詩や詩的言語に触れたエッセイを書くかというところで、ちょっと元気をなくしていたんですね。体力が切れてしまったのかもしれません。
インカレポエトリの発起人の一人の伊藤比呂美先生。伊藤比呂美先生が早稲田の子たちを教えていて、彼ら彼女たちに対する友情のような愛情のようなものは、実際に会って、一緒に連詩を作るのを見てもらって、彼らと一緒に踊りながら詩を読んで感じていました。「長尾です!」と言っておいて、ご存じで本当にうれしかったです。
だからこそ、伊藤先生の最近の著書に触れてよかったなと思います。大変な日々、心に余裕がなかった時でも、ちゃんと原稿を書く。すごい体力です。わたしもそんな詩人でありますように。がんばろう! と思えました。
・村田沙耶香『コンビニ人間』文春文庫
最近、小川洋子さんの読書ラジオで取り上げられていたので、文庫でも読んでみました。中村文則さんの解説も刺激的でした。
主人公の古倉さんという女性はオーディブルで聞いていただくとわかりやすいと思うのですが、すっごく「ファニーな」女性なんです。
一般的な「価値観」を「演じている」。マニュアルとされていることから逸脱することを嫌い、「マニュアル通りに動く」ことに快楽を見出す。
村田さんご自身がロバートキャンベルさんのポッドキャストで仰っていたことですが、ある種「コンビニ」という場所は光り輝いています。宗教っぽいと言えば宗教っぽいですね。24時間開いていて、飲み物も食べ物も衣服も雑誌もすべて手に入る。そして、古倉さんにとっては、生きるための居場所でもあったのかもしれない。
どんな人間になろうとも、「個」ということは非常に大事です。自分がオリジナリティを持った何者かであることを立証するために、自分自身が自分をきちんと見つめ、受け止め、「個」であることを自覚する。
わたし、思うんですけど、「社会の歯車になりたくない」って思うことがあったりしました。すっごく社会人になりたての頃。でも、今になってわかるんです。誰もがみな歯車で、社会というものはまわっていかなければ「みんな」が困る。だからこそ、やりがいのない仕事でも、その仕事をしていくうちに、いつか天職というものが見えてくる。わたしはそういったことを思いながら、在宅フリーランス主婦を「演じて」いるのかもしれません。
5月11日
昨日、本で元気を本当の意味で復活させ、早朝ウォーク。リーディング用のテキストを2編追加しました。もうそろそろスラムシーズン、ですが、まずは今週末のために本を読んだり句作したりします。句作55句。今週は定型詩しか考えられないのかもしれません。今年初ゴーヤチャンプルとなりました。お惣菜を買ってきました。なかなかゴーヤから作るのは難しいので、うれしいです。
・ほしおさなえ『言葉の園のお菓子番 見えない花』だいわ文庫
連句というものに、思いを馳せます。
わたしの居場所だった場所、そして一巻まき終えた後の達成感というか、みんなで巻く「場」としての詩。
いつもは「何かぽっかりとなくしてしまったもの」が、不思議なご縁でつながっていくこともあるんですね。その喪失と共存することももちろんできるのだけど、「一緒に一編の作品を創る」ということに関して、ある意味スタジオワークのような、遊びのような場所だなと思っています。
わたしも大学生の頃から参加させていただいた連句会、何かを満ち溢れるように持っていた時。許されていた時。それでも支え続けてくれたのが連句仲間でした。この主人公の一葉も、きっと何かを取り戻すために、句を詠んでいるのだと。
・ほしおさなえ『言葉の園のお菓子番 孤独な月』だいわ文庫
ぼうっと、石垣りんさんの「くらし」という詩を思い出します。
ことばでこんなことが、という衝撃を与えるものですが、人が生きて暮らすって、すごくドラマチックだったり。
わたしはまだまだ、若すぎるんでしょうか。勢いだけで突っ走っている、そんな気持ちもするのですが、以前よりは地に足がついているのかな。
第二巻となるこの本では、それぞれのキャラクターのそれぞれの原体験が明かされつつ、一葉自身が仕事を見つけ、そして生き生きと暮らし、そこでまた連句仲間のなかの知らなかった暗がりをも見出していきます。
海月ちゃんがナイスキャラでした。何度読んでも好きなんです。
・瀬尾まいこ『強運の持ち主』文春文庫
わたしも結構「何か(タイミングを)持ってる」とか、「強運の持ち主」って呼ばれることあるんですけど、この瀬尾まいこさんの本に触れると、ちょっと悩みも晴れるような気もしています。
今日は朝から「明日」についての捉え方の違いについて悩んでいました。
わたしはすごく自分でも不思議と、今とか過去のことについては衝動的になってしまったりするんですけど、今日一晩寝て、朝がくれば世界は美しい、だから明日はすごく素晴らしい、という考え方なんです。前向きなだけなんでしょうか。他の方の歌謡曲などを聞いていると、「明日」についての捉え方が人それぞれで、本当にびっくりしました。
この主人公は占い師なのですが、本当はいんちきです。でも、彼女自身が出会っていく悩む人たちを見ていると、みんな「運」を自分で切り開いていく。占いはそのきっかけになっていくようなもので。
ご縁や何か、「自ら動く」ってすごく大事だなと思うんです。そういうことで、強運って生まれるのかもしれませんね。
・住野よる『この気持ちもいつか忘れる』新潮社
いつだって、きっと明日をみつめて今日を生きれば、そのうちに終わりがやってくる。だから、毎日生きてる。
すごくね、「こんな意味もない場所」って思っていた教室とか、思い出すんです。熱中できるものって、そうたやすく見つかるものじゃないんですけど、それを見つけられて、ずーっとそれを持ち続けることがどんなに素晴らしいか。
青春って、それを探すために勉強したり、悩んだりする時間なのかなと思います。
その真っただ中にいると「普通のやつ」を演じたくて、でも「なんか違う」と違和感を覚えて。そこでもがいたり、苦しくなったりする。
でも、真っただ中を過ぎて、「なんとなく生きたくない!」という強い信念に変わると、それはすごいエネルギーになるんです。
よく朝ドラでも、前向きに助ける役目を多くの「さなえ」ちゃんがしているのですが、この中の「沙苗」ちゃんもそうで。やっぱり名付けってすごいなって思います。わたしもそういう立場なのかな。
・窪美澄『じっと手を見る』幻冬舎
よく思うのが、身体的な関係と心。
すごく切実に、この人との結びつきを離れたくないと思う人に出会えることと、その人のことを愛することは、わたしにとっては同値でした。
心と体はケンカするそうですが、わたしにとってはいっしょくたです。だからこそ、愛しい人を愛しぬきたいし、その人と命がいつかまじりあうまで一緒にいたいと思います。なんか、そうじゃなくちゃいけないと思う。
色々な親密な結びつきはあります。そして、関係性をなんとなく続けてしまう人もいるのかもしれない。焦ってしまって、この人と決めたのに、ということも多々、あるようです。
心と体はケンカしちゃいけない。一緒くたになって、いつか死ぬ時まで生きること。そういう意味で、ずっと求めていた誰かを愛しぬくことって、すごく尊くて、命がけなんです。
・髙樹のぶ子『私が愛したトマト』潮出版社
日常のなかのことには、時折非日常が混ざってきたりします。
それだから人生ってたくさんの物語にあふれていて、人は物語がないと生きていられない生き物になってしまいました。
自分というものについての不思議は、本当に不可解です。一番びっくりするのは自分かもしれない。それでも、どこか奇妙だと思っているうちに、だんだんとそれに「慣れていってしまう」。それはとても日常を送るうえで危険なことだったりします。
だからこそ、自分の原体験を日々立ち返って見直さなければいけないし、このなかで「私」という登場人物たちは書き手と一部分重なる所はあるのですが、一緒にするのはちょっと違う読みかたかなと思います。
小説とか詩において、ある種書き手を連想させられたらそれはそれで成功だと思うのですが、それ以上に、「知らない誰かに自分の『すべて』を見てもらう」というのが書き手としてとても有意義な時間だと思うし、そういう職業でもあります。
長尾さんは日々元気ですね、とよく言われます。はいと答えます。
それは生きにくい日常を共にする人や家族、近しい友人や町の人々によって支えられているからこそでもあったりします。弱い体でしたが、わたしのエネルギーもきっと誰かの生きるエネルギーになっていると信じて。
・川口俊和『さよならも言えないうちに』サンマーク出版
人生をやり直すことはできません。それでも、未来を変えることはできます。誰かにずっと言いたかったのに言えなかったこと。ふとなんらかの拍子に、いつかどこかでその人やその人の近しい人につたえられるかもしれない。
いつかやってみたかったこんなこと、あんなこと。生きていればいつだって、精神のしなやかさは取り戻すことができます。いつだって歩き出していい時間です。
この小説内で書かれる「過去に戻る」ことは多くの作品で言われているけれど、その中でもこの小説で面白いのは「現在は変えられない」ということです。現在は変えられない。けれど、過去に戻ることによって、知りたかった真相を見つけ出したり、大切なことに気づけたりする。
それってなかなかできない体験だけれど、わたしは日々書いている記録を、空いている時間に読み直して、こういう日があったからこういうことになったんだと良くも悪くも(笑)分析しています。
そういった意味で、生きていくってとっても面白いことです。だから、いつか終わりが来るまで生き続けなければならない。大事なことです。難しいことです。でも、大事なことです。
・キムチョヨプほか 斎藤真理子ほか訳『最後のライオニ 韓国パンデミックSF小説集』河出書房新社
そうか、この流行病について、あまりにも非現実的なことが起こり続けているから、あまりにも物語を書きにくい時代になってしまったのかもしれません。でも、この作者たちはそれぞれがそれぞれの視点で、未来に行ったり、この時代を反映する形で海に航海に出たり、箱を開けてしまったりする、そんな人々を描き出しています。
韓国の小説自体は最初は翻訳者の皆さまの情報源より仕入れて読んでいましたが、ここ最近は毎週ラジオで聞く「空飛び猫たち」というPodcastに頼り切りです。そうか、なんだかこの非現実を現実として生きていると、なぜか心が疲れてしまって、体は疲れていなくて。それだから心と体が一致せずに、何か言えないフラストレーションがたまるんだとおもいます。でも、それをもし、発散することができたなら。もう一度、人間としての生活を手に入れることができたなら。
わたしたちは語り続け、わたしたちは書き続け、誰かと会いたいと願い、いつか会える日まで待ち望んでいる。
わたしは、会いたい。会いたい人に、会いに行きたい。そして、語り合いたいことを語り合いたい。オンラインでのつながりなどは、その期間や距離を埋めるものだと思っていました。
だからこそ、今色々な価値観があるけれど、イベントがまた開催されるようになったり、オンラインでしかないつながりからオフラインへ発展させていけるようになったのが今わたしがここに生きる所なんだと思います。それはとても祝福されていることでもあり、望めなかったことが望めるようになったのかもしれません。
本当は、当たり前のこと、だったけれど。
あなたに会いたい、という思いから、たぶん語るべきことは始まっていると思うのです。
5月12日
今日は今週走り過ぎないように、執筆のペースを整えていました。
仕事として執筆することも、何も言われなくても次の詩集へ向けて執筆することもあるのですが、今日は朝ドラのように「感じたままに」動いてみました。高校生の時に、卒業する前に現代文の先生に、「書き続けて! あきらめてはいけないわ」と強く言われて、レターセットをいただいたのを本当によく覚えています。新作2編。
5月13日
定期検診の日でした。
これからの執筆のことなどとリーディング、その他もろもろイベントや新刊準備について考えるなど。シェアオフィス・コワーキングスペースのことを考えています。
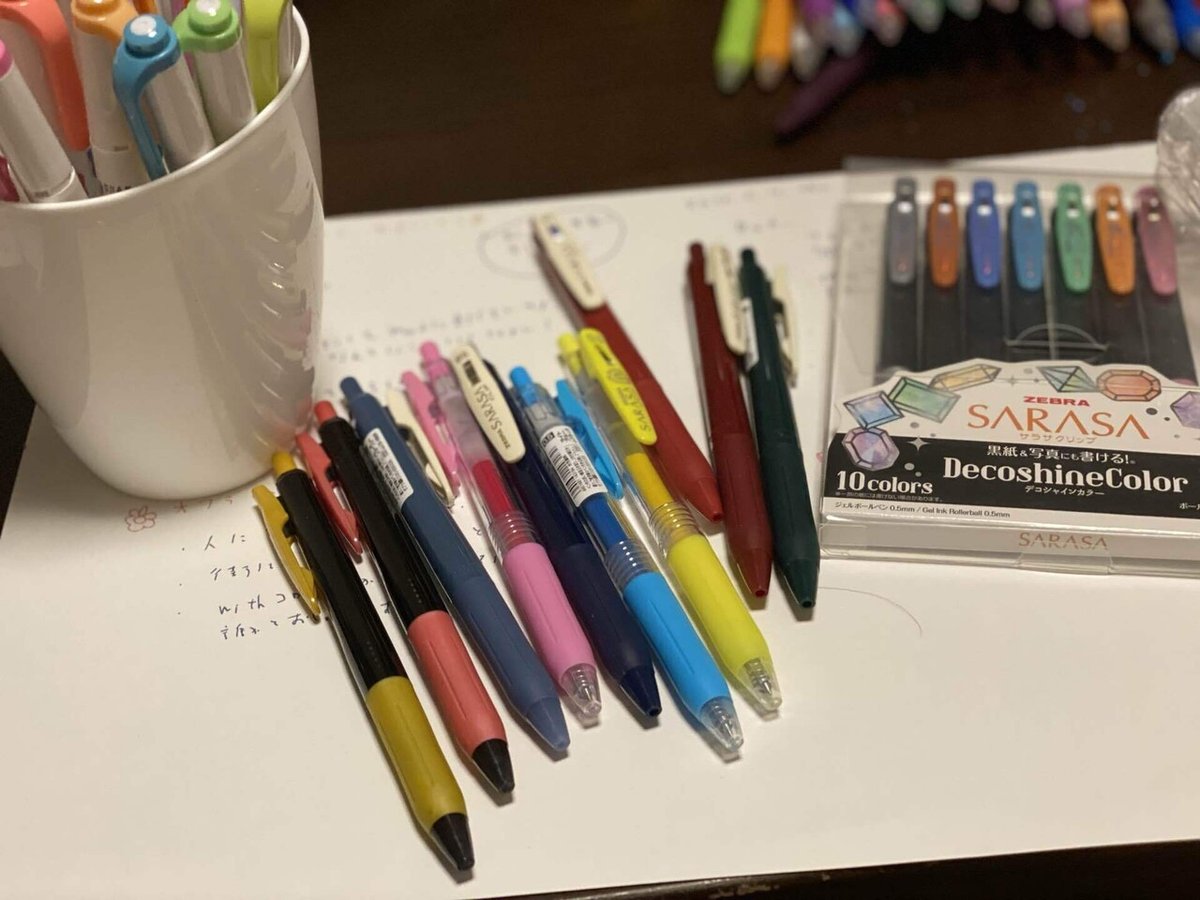
5月14日
今日は連句会です!
昨日ももろもろ楽しそうな詩のイベントが入ってきたので、とっても楽しみ。不思議と、イベント当日の方が「わくわく」が「不安」より勝って、体調もよくなったりします。なじみの仲間たちに久々に会えて、ほんとうにうれしかった。9時間、本当にお疲れさまでした!
*お知らせ
いつも、詩人の読書記録日記にお付き合いいただき、誠にありがとうございます。
この度、本業としての新刊準備と、チャレンジしたいリーディングの準備諸々で、本が手に入りづらくなってしまう可能性が出てきました。
そのため、6月中旬まで、この日記は毎週ではなく、不定期に更新する予定です。
いつも長文になってしまっても、お付き合いくださる皆様、本当にありがとうございます。
読書はわたしの栄養剤でもあります。それでも、その感想をエッセイ形式にして発表するには、作者の方の意図などをきちんと汲み取り、皆様に伝えることが大事と思っています。そのためには、他に色々な何かを奪ってしまうかもしれないし、今まで以上に時間をかけないといけないこともあります。
少しの充電期間となりますが、よろしくおねがいいたします。また会おうね!
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
