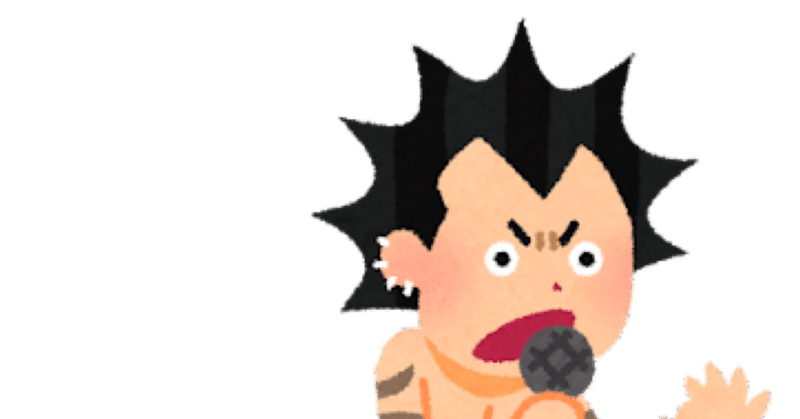
《連載小説》おじいちゃんはパンクロッカー 第二十三回:黄ばんだ紙
「俺はあん時本当にバンドを辞めてカタギになるつもりだった。俺がこんなくだらねえことしてるからアイツは死んじまったんだって本気で思った。そんな罪の意識から逃げたくて女だの酒だのクスリだのやりまくったけどそれでもダメだった。恥の上塗りで罪の上に蜜まで塗ったようなどうしようもない状態でもう今までやってきた事が全部バカバカしくなった。それで俺はもう真人間になろうって思ったんだ。せめてアイツの供養のために真面目に働こうってな。それでお前らにバンドやめるって言ったんだ」
垂蔵はそう言うと口を閉じて再び天井を見た。露都はその垂蔵を見て母が亡くなってから家を出るまで垂蔵と暮らしをしていた日々思い出した。母が死んだというのに平気で女を連れ込んでいた垂蔵。いつも酔っ払い、度々女を連れ込んで来てその度に追い出していた。ああ!思い出すたびに腸が煮えくり返ってくる。
「だけどな」と垂蔵が再び口を開き、枕元を探り出した。そして彼は枕元から出した黄ばみきった紙の束を広げて言った。
「俺はコイツを読んじまったんだよ!」
その黄ばんだ紙を見て露都は衝撃のあまり倒れそうになった。自分が依然見たあれとはすっかり似ても似つかなくなってしまったが、だけどあれである事はもう火を見るより明らかだった。垂蔵の奴ずっとこれを持っていたのか。とっくにどこかに捨ててしまったと思っていたのに!
「露都、これお前がくれたんだぜ。覚えてるだろ?」
「ああ、忘れるはずねえよ。アンタずっと持ってたんだな……とっくに捨てちまったと思ってたよ」
「バカやろ、いくら俺がバカでもアイツの形見を捨てるはずねえだろ!へっ、しょっちゅう読み返していたせいでこんなに黄ばんじまったけどよ。読みすぎてもうインクなんか全部飛んじまって、もうまともに読めやしねえや。だけど中身は全部覚えているぜ。この身に入れ墨見てえに刻んでいるぜ」
それは間違いなく母の遺書であった。すっかり黄ばみ、さらに垂蔵が酒がなんかこぼしたせいで水跡とシワが出来てしまい、字なんかも垂蔵が言うようにすっかり薄くなってしまっているが、それでも母の遺書だった。よく見ると便箋のあちこちが黒く汚れていた。きっとそれは垂蔵の手あかに違いない。母さんの大事な遺書をよくもここまで汚くしてくれたな。そんなになるぐらいずっと読んでいたっていうのか。露都は垂蔵をまじまじと見た。
「正直に言うと俺、お前にアイツの遺書を貰ってからずっと読まずにいたんだ。あの借家から出てアパートで暮らし始めてからも、ずっと出してはしまって、出してはしまっての繰り返しだった。怖かったんだよ俺は。アイツに一番酷えことをしたのは俺だってわかってるから、どんな事が書いてあるのか見るのがずっと怖かったんだ。ぜってえありえねえけどアイツが恨みつらみなんか書いてたらどうしようってそんなことまで考えた。でも恨みつらみでなくちょっとしたお説教じみたものは書いてあるかもしれねえとは思った。アイツが生きているときだったらそんな説教いくらだって聞いてやったさ。だけどアイツは俺がくだらねえことばかりやっていたせいで死んだんだ。遺言でそんな説教かまされちゃもう俺耐えられねえよ。死んで詫びするしかなくなっちまう。だから俺ずっと遺書を放っておいた。だけどこのクソ垂れどもにボコボコにされてアパートでやけ酒かっ食らってた時、ふとバッグにしまったまんまだったアイツの遺書を思い出したんだよ!」
ここまで言うと垂蔵は顔を顰めた。露都はその垂蔵の方へ思わず歩み寄った。垂蔵の言うことをもっとはっきりと聞きたかったのだ。
「それで俺は引き出しからアイツの遺書出した。そして勢いで読んだんだよ。もう何が書いてあろうがどうでもよかった。俺自身完全に終わりだと思ってたしな。だけどよ、読んでも恨み事どころか説教一つ書いてねえじゃねえか。思わずバカ野郎って口に出したね。アイツは最期まで俺を全肯定して逝っちまったんだ!こんなクズ以下の俺をさ!」
そう震える声で言うと垂蔵は声をあげて泣いた。その涙が母の遺書にポタポタと落ちてあちこちに黒ずんだシミを作った。露都は泣いている垂蔵を見て目頭が熱くなった。今までこんな事は始めてだった。生まれてからずっと軽蔑と憎しみしか感じていなかった父。母に苦労を全て押し付けて遊び呆けていた父。そのクズ以下の人生を歩んで来た父の悔恨の言葉にどうしてこんなに心が動くのか。その父がシワだらけの泣き腫らした顔を上げて彼をじっと見た。
「露都、お前母ちゃんの遺書読んだか?」
父の問いに嘘をつく事は露都には出来なかった。彼は額に手を当てて正直に答えた。
「読んだよ。アンタには悪いとは思ったけど、読ませてもらった」
「そうか。じゃあ話は早いや。俺は母ちゃんの遺言に従わなきゃいけねえ。お前がどんなにまともに働かないクズだと罵ろうが、俺はサーチ&デストロイのボーカル大口垂蔵なんだ。だから最期まで母ちゃんの望んだように大口垂蔵として生きていかなきゃいけねえんだ。だから頼むよ!俺にライブを演らせてくれよ!そうじゃなきゃ俺は母ちゃんに申し訳がたたねえんだよ!」
垂蔵はその痩せ切った体を折り曲げてベッドがめり込むほど深く露都に頭を下げた。サーチ&デストロイのメンバーや家時もまた露都に向かって頭を下げた。露都は周りの連中を見回してそれから再び垂蔵を見つめた。ベッドでライブに出るために必死に息子に懇願しているのは余命が一年、いやそれよりずっと短いかも言われている末期がんの患者だった。こんな人間にライブなんかまともに出来るはずがない。大体痛み止めにモルヒネ使っているような人間にライブなんか出来るはずがない。無理だ、いくら母さんがそれを望んでいたとしても絶対に無理だ。
「坊主頼むよ。親父がこんなに頼み込んでいるんだぜ」
そう口にしたのはイギーだった。彼は泣いていた。ジョニーもトミーも泣いていた。イギーの言葉にただ頷いて露都をじっと見た。
「露都さん、僕からもお願いします。確かに垂蔵さんの体調は絶対に気をつけなきゃいけません。だけど僕垂蔵さんがどれだけライブにかけていたかを考えるとやっぱりライブをやらせてあげたいんです。それは事務所とかそういうの関係なくて僕個人の正直な思いなんです」
サーチ&デストロイの所属事務所の次期社長家時未来は涙ながらにこう語った。今、垂蔵とサーチ&デストロイのメンバー、それに家時は露都を一心に見つめただ彼の言葉を待った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
