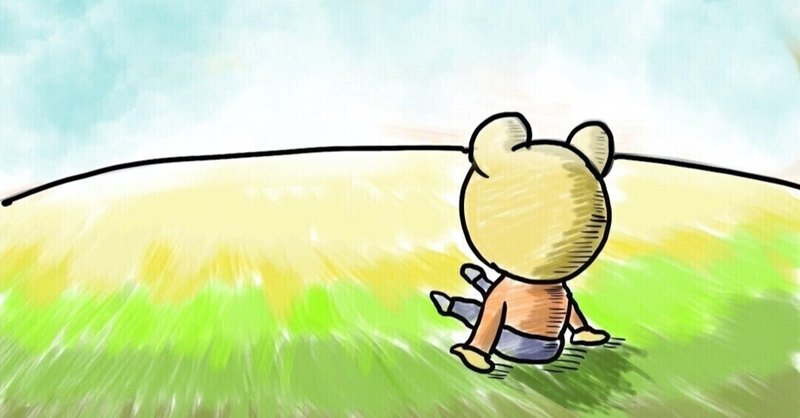
やりがいは与えられるものではなく、自分で見つけるもの
病院の待合席にて、先日のことを思い出しながら、隣の親子を見る。いや、隣の親子を見て、先日の出来事を思い出したのかもしれない。
前職の方と久しぶりにお会いする機会があって、いろいろとお話しを聞いた。
私にとってはもう、見知らぬ後輩の話しではあったものの、話しの中でとても気になることがあった。
その話しの細部は正直どうでもいいことであるし、伝えたいことから離れていることでもあるので割愛するが、そのときに私が思ったことは、
やりがいは与えられるものではなく、見つけるものなのでは?
ということだ。
話しを聞く限りでしかないけれど、その方はすべてが受け身であり、自分から働きかけることも少なく、やりがいを与えなければ(?)自分はここでは必要もないと感じてしまっており、それでいてプライドも高い。という、印象だ。
私は、
なんでだろう、と。
そんなことを感じてしまった。
なぜ、そうなってしまうのだろう、と。
そんなときに目に映るのは、隣の親子であった。
まだ小さいその子はタブレットを使ってゲームーーいや、勉強といったほうがいいかもしれない。数字を当てはめていくもので、自分なりに一所懸命に考えている様子だった。
けれど、隣の母は「どうしてこうなるの?」や「ほら、もっとよく見て」と、その子のタイミングを待つわけでもなく、過干渉気味に答えを導き出そうとしていた。
その子はそれを聞いてかえって戸惑っている様子もあり、焦りもあり、うまくいかない様子が見えた。
明らかに母親は不機嫌そうな空気を醸し出し、それによって子は萎縮している……けれど、
もう少し待つことで、子ども自身も答えを導けるのではないだろうか? もう少し踏みこむと、正直なところ
必要なのは、答えを導くことではなく、その問題に対してどう感じ、どう考え、どうしていくか、ではないだろうか。
答えだけを知りたい、答えさえ導ければいい、では、自分で考える力を喪ってしまうのでは?
私はその場面を見て、先日の話しに妙につながった。
きっとそういう経験の積み重ねの中で、獲得された無力感のような、そんな状態に陥ってしまったのではないか、と。
そうして諦めていくうちに、意固地な気持ちも表れ、凝り固まり、どうせ自分なんか、という感覚に陥ってしまったのかもしれない。
やりがいは、与えるものではなく、自分で見つけ出すもの。
それは自分自身がどう思い、どう考え、その結果、こう決断し、こう行動する、という、自分の感性と判断を信じる、ということにもつながる。そうして、その自信(自身)がつくために、どう考える、というのが大事になる。
やりがいを自分で見つけられなければ、そこに踏みこむ気持ちも成長も、望めはしない。……けれど、
私は待合席で自分が呼ばれる番を待ちながら、あぁ、でも、たしかに。
待つことは、難しい。叶うことなら、自分で済ませられることなら、動いてしまいたい。自分のやりがいのために。
そんな気持ちもまた、切に感じるのであった。
そうして考えているうちに、上司から見る「私」という視点から考えた「私」のやりがいのために、相手にやりがいを与えられるように働きかける、という、先ほど私が考えていたこととは矛盾してしまうことが、成立してしまう、という不思議を体感した。
私は答えを見出せぬまま、それでも、やりがいは与えられるものではなく自分で見つけ出すもの、という気持ちの中。矛盾を肌で感じながら、呼ばれるがままに診察室へと入っていった。
いつも、ありがとうございます。 何か少しでも、感じるものがありましたら幸いです。
