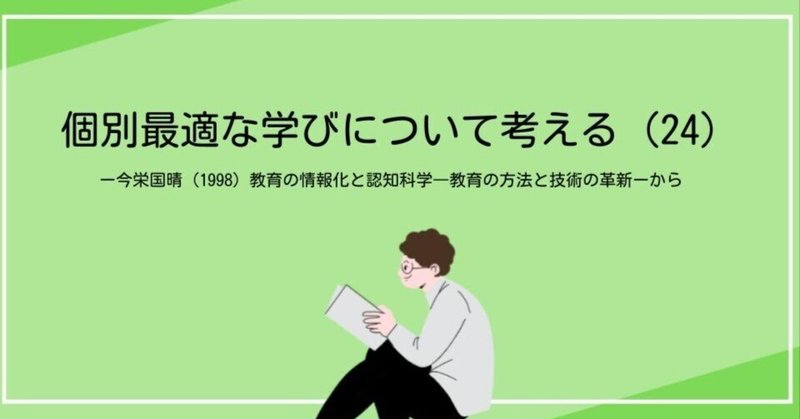
個別最適な学びについて考える(24)ー今栄国晴(1998)教育の情報化と認知科学-教育の方法と技術の革新-ーから
おはようございます!
今回は,今栄国晴氏による1998年の著書『教育の情報化と認知科学-教育の方法と技術の革新-』をテーマに,個別最適な学びについて考えていきたいと思います。
時代はますます進化し,教育も例外ではありません。
デジタル技術や認知科学の進展により,新たな教育の可能性が広がっています。
それに伴い,自分たち教師や児童生徒はどのように対応すべきなのでしょうか?
さて,この興味深いテーマについて一緒に考え,今後の教育における変革の兆しと個別最適な学びについて探っていきましょう。お付き合いいただければ嬉しいです!
2つの学習法があって,全ての学習者にとって,その一方の学習法が他方の学習法に比較して学習の効率が良いとといえる場合もあるが,必ずしもそうはいえない場合もある。
すなわち,ある特性を持った学習者にはある学習法がより効率の良い学習法であるが,それ以外の学習者にとってはもう一方の学習法の方がより効率的であることがある。
このような現象をATI(Aptitude Treatment Interaction:適正処遇交互作用)とよぶが,このことは,すべての学習者について,一方の学習方法(指導方法)が,他方の方法よりもより優れた方法とはならないことを示しており,したがって,個人差に対応した学習方法が考えられるべきであることを示唆している。
ATIに関しては以前も取り扱ったことがあったと思います。
人によって適切な学習方法は異なるということですね。だからこそ,個別最適な学びにおいて学習方法を選択してもらう機会を与えるのかもしれません。
文部科学省の資料を確認すると,個人差に対応するという場面で実際に適正処遇交互作用の話は考慮されているはずです。
この後の具体例でも書いてありましたが,子どもの主体性を持った授業よりも教師が主導で進める授業の方が,非常に高い知能を持っている子供からしたら,効率がいいという可能性もあるそうです。
この点は,教師の調整も難しくなっていくことだと思います。
しかし,最終的には個人差に応じた学習方法が考えられることが大切です。
最初は教師が伝えていくのかもしれませんが,徐々に子どもが振り返り,メタ認知していくようになると,子ども自身で学習方法を調整していくようになるのかもしれませんね。
前回の記事と被っているようなことを伝えていたらすみません!
認知科学の面から考えられているので,情報機器と絡めてとても面白い一冊でした!
本日はここまで!また次回の記事でお会いしましょう!
よかったらサポートもお願いします!
よろしければサポートお願いします! いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!
