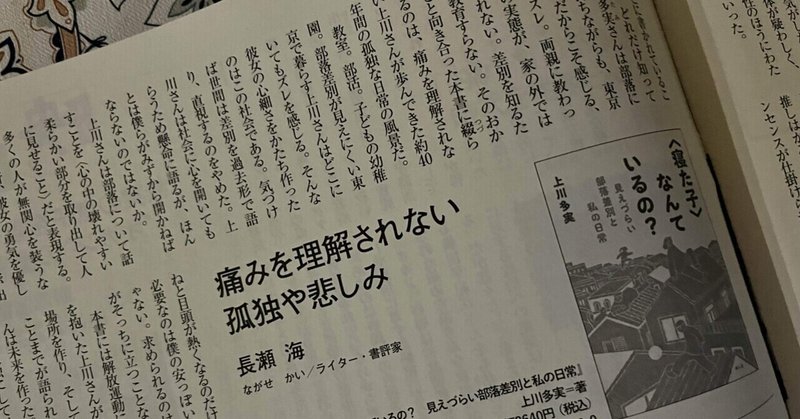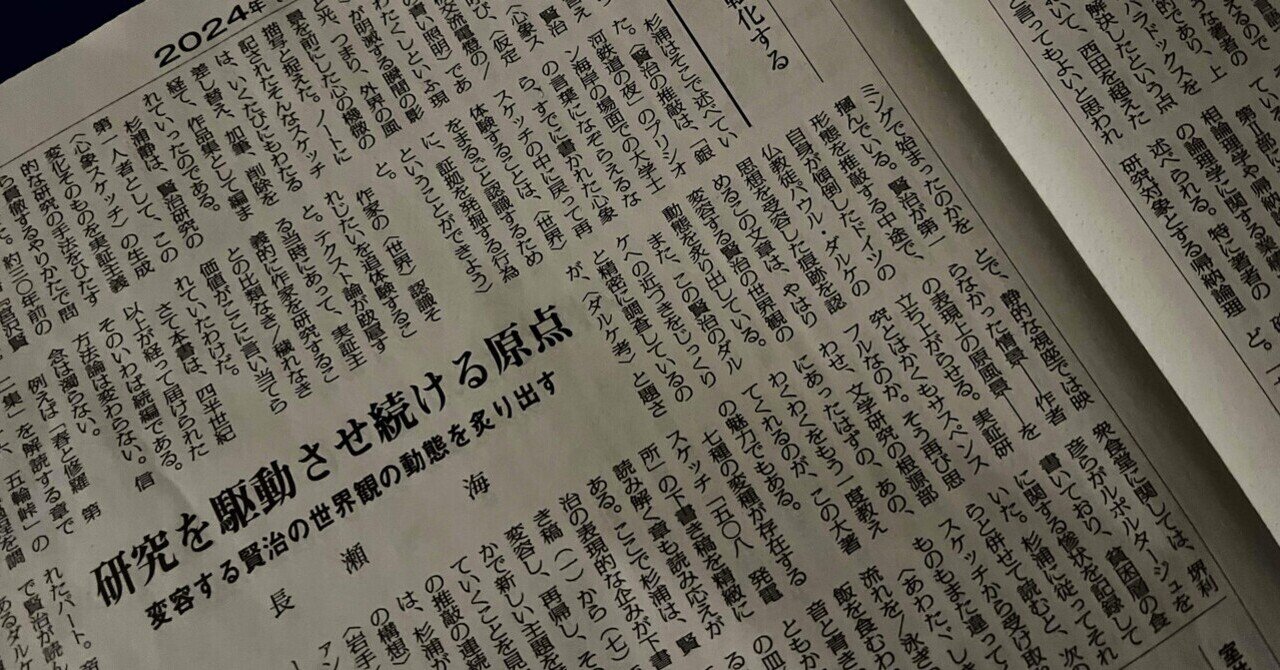最近の記事
- 固定された記事

「週刊読書人」(2024年8月30日号)に申京淑『父のところに行ってきた』(姜信子・趙倫子訳、アストラハウス)の書評を書きました。
申京淑さんと言えば『母をお願い』が有名ですが、今作は父について書くことで誰も知り得なかった社会の痛みを探る物語。父と久しぶりに暮らすことになった〈私〉が、ひと知れず夜中に涙を流している彼の人生を辿りなおしながら、堰き止められていた涙の根源にあるものを見つめていくんですね。 ただ書評では、父の物語であるのと同時に、現代の韓国社会で娘を喪失した母としての〈私〉の回復の物語でもある、と読みました。 というのも、語り手の〈私〉が娘を失った過去を持つのは早々に語られるのですが、慎重

「週刊金曜日」(2024年8月23日号)に前川仁之『人類一万年の歩みに学ぶ 平和道』(集英社インターナショナル新書)の書評を書きました。
平和論でも、学でも、考でもなく、〈平和道〉。人類が平和を構想してきた一万年の歴史をたどりながら、博愛の理想を追求するための一本の道を作る。材料とするのは、それぞれの時代で平和思想を唱えた思想家たちの書物。それら万巻の本を読みほどき、現在に向けて蘇生する本書は、博覧強記な著者ならではの考える力の波打つ思想書です。 史上初めて平和条約が結ばれたエジプト文明から、古代ギリシャのアテナイやキリスト教が公認の宗教となった帝政ローマを通り、コロンブスが先住民の地を侵略した大航海時代やフ
マガジン
記事

「週刊金曜日」(2024年7月19日号)にサマル・ヤズベク『歩き娘 シリア・2013年』(柳谷あゆみ訳、白水社)の書評を書きました。
サマル・ヤズベクは複雑な世界の語りがたさ、描きづらさを熟知し、けれども、絶望と諦念の淵に落ち込むことなく、現実と釣り合う言葉を探してきた作家です。以前、僕はこの小説家のノンフィクション・ノベル『無の国の門』を読み、打ちのめされたのをおぼえています。シリアという国の現実を物語として再構築し、その惨状をありありと、そこに生きる人々をいきいきと描いたこの小説家は、これからの世界にとって必要な人物なんじゃないかと思いました。(この小説についてはこちらでも触れています。) わから

「週刊金曜日」(2024年7月5日号)に黒川創・瀧口夕美『生きる場所をどうつくるか』(編集グループSURE)の書評を書きました。
編集グループSUREの本を読んだのは、鶴見俊輔『たまたま、この世界に生まれて』が先だったか、瀧口夕美『民族衣装を着なかったアイヌ』が先だったか、忘れてしまいましたが、とにかくどちらかの本かが最初でした。この出版社は従来の流通制度で本を売っていません。本屋には流通を通しておろすことがなく、注文をした読者に、一つひとつ丁寧に手渡すようにして販売をしているのです。 『生きる場所をどうつくるか』によると、この出版社は元々、黒川の父親、北沢恒彦が一人で運営する編集グループだったようで

「週刊金曜日」(2024年5月24日号)に『戦争は、』(ジョゼ・ジョルジェ・レトリア 文、アンドレ・レトリア 絵、木下眞穂 訳、岩波書店)の書評を書きました。
この不穏な時代を忘れないために、いつまでも、ずっとずっと大切にしたい絵本です。 作者のジョゼ・ジョルジェ・レトリアとアンドレ・レトリアは父と息子です。父親が詩を書き、息子が絵を描く。そんな彼らの作品には例えば、宇野和美さん訳の『もしぼくが本だったら』があるのでご存知の方もいるかもしれません。 今回の本は、表紙をめくると、薄い黒を基調とした紙に蛇のような細長い、軟体の物体がいくつか描かれていることにまず気が付くでしょう。生き物のようにも見えるし、抽象的な、何かの概念そのもの

「週刊金曜日」(2024年4月12日号)にカラー二・ピックハート『わたしは異国で死ぬ』(髙山祥子訳、集英社)の書評を書きました。
この小説が描くのは2014年にウクライナで起きたユーロマイダンという革命。当時のヤヌコビッチ大統領による親ロシア的な政策に抗議する人々が治安部隊と衝突し、おびただしい数の死者が生まれたあの革命に取材したアメリカ人の作者は、キーウにあるマイダン広場を中心に、一つの大きな悲しみの物語を紡ぎます。現在の世界に生きる〈わたし〉たちならみんなが共有しうる、痛みや喪失としての悲しみの物語を。 語り手のまなざしの先にいるのは、三人の男女。 ひとりは、広場付近の修道院で働く医者のカーチャ

「週刊金曜日」2024年3月15日号に中井亜佐子『エドワード・サイード ある批評家の残響』(書肆侃侃房)の書評を書きました。
今回の書評では、いま、なぜエドワード・サイードなのか、という問いを立てて、本書を評しました。端的に言えば、この本が試みているのは、サイードとともに、批評の力を取り戻すことです。だから、著者はサイードと真摯に対峙しながら、彼にとって批評とは何だったのかを追跡するわけです。 著者の中井亜佐子さんは言います。 そして、次の文章が続くのですが、ここはこの本のこころざしが最も明確に表れている箇所です。 サイードの批評意識とは何だったのか。たとえば、それは、理論を机上で形骸化させな