
僕らはみんな漫画が好きだった/貸本漫画
イラストエッセイ「僕の昭和スケッチ」78枚目

あなたは貸本屋って知っていますか?
読んで字のごとく本を貸す本屋さんです。
古くは江戸時代からあったのですが、1940年代末頃から月刊漫画雑誌を扱うようになり、間もなく厚表紙の豪華な単行本(月刊漫画雑誌に連載された漫画の単行本化されたもの)に加え、貸本専用漫画(大阪、名古屋等で生まれた貸本専門の漫画出版社から大量に発刊された厚手の雑誌/単行本)を取り扱うようになると、貸本ブームは一気に花開いたのです。
子ども達は「立ち読みお断り」の張り紙をものともせず貸本屋に集まり、店主との攻防戦も見物でした。

中「墓場鬼太郎」水木しげる 貸本専門漫画単行本(復刻版/角川文庫)
右「さすらいの少女」ちばてつや 貸本専門漫画単行本/あかしや書房>
貸出料は漫画単行本一冊で10円から20円程。
当時、少年月刊誌の販売価格が120円程、漫画単行本が150円程で、子供のお小遣いでは買うにはまだまだ高価でした。そのため、皆貸本を借りては読んでいたのです(テレビは未だ一般家庭に普及していません)。
一方でこの貸本漫画は、子ども達だけではなく高度成長期に金の卵と呼ばれた中卒で社会に出た若者達にとっても安価で楽しめる身近な娯楽でした。そして、この新しいマーケットは思いもかけぬ副産物を漫画にもたらします。それまでの子供向けの丸みを帯びた(手塚治虫風の)絵ではなく、シャープで頭身の長いリアルな作風がより年齢層の高い世代をターゲットにして生まれたのです。それが、劇画と呼ばれる新しいジャンルでした。
つまり、劇画は漫画の中から偶然生まれたのではなく、それを産む社会的土壌があって初めて生まれて来たのです。後に「ゴルゴ13」で有名になるさいとうたかおを始め、「墓場鬼太郎」(『ゲゲゲの鬼太郎』の原型/水木しげる)、「忍者武芸長」(白土三平)などの傑作がここから生まれました。いずれも劇画作品です。
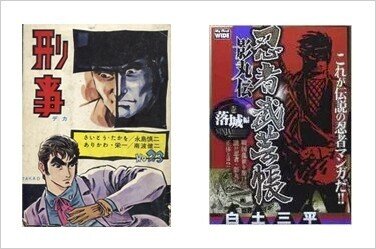
右/ 名作「忍者武芸長」白土三平 貸本専門漫画単行本(復刻版/小学館)>
他にも、後に「ベルサイユの薔薇」を発表する池田理代子や少女雑誌で活躍する矢代まさ子も貸本漫画の出身です。こうして、後に活躍する多くの漫画家がここから巣立っていったのでした。
けれど、一方でグロテスクな怪奇もの等も多く、又全体的な作品の質の低さも拭いがたく(何しろ描いていたのは、十代半ばから二十歳そこそこの若い漫画家だったのですから無理もありません)…
次第に「低俗/劣悪」の社会的誹りを受けるようになっていきます。
加えて、1960年代になるとテレビの普及と「少年漫画週刊誌(少年サンデー、少年マガジン等)」の発刊により貸本は急激に人気を失い、貸本専門の地方出版社も次々と倒産、貸本屋も廃業に追い込まれていったのでした。
こうして貸本業は、わずか7年程で全盛期を終え、その後日本から次第に姿を消して行きました。けれど、この貸本文化はファンの間で昭和レトロとして懐かしく語られ、現在ではその当時発刊された貸本漫画本に思わぬ高値がつく物も多々あるのです。
大繁栄した現代マンガの黎明と言えるこの貸本マンガを支えた有名無名の漫画家達に心からオマージュを捧げます。 もりおゆう

この記事はnote公式マガジン「今日の注目記事」に選ばれました.

この記事はnote編集部の「今日の注目記事」にも選ばれました.
<© 2021 もりおゆうの著作は全て著作権によって守られています>
(© 2021 All of Morio Yu's works are protected by copyright.)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
