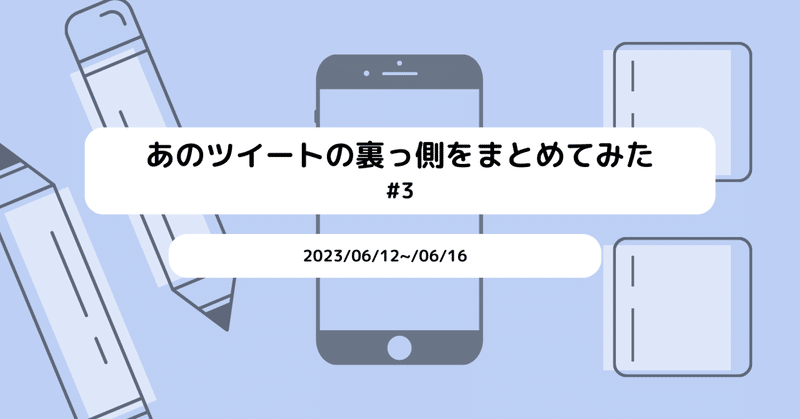
#3 あのツイートの裏っ側をまとめてみた
#3を投稿しました
こんにちは。ムーさんと申します。
『あのツイートの裏っ側をまとめてみた』の#3となります。
この記事は、私がTwitterで日々呟いているツイートについて、少し掘り下げたり、どんな考えが含まれているのかだったりをあーだこーだ書いてみる、というものになっています。
インプットよりは、「読み物」としてご覧いただければと思います。
日記の感覚で投稿していて、そこまで大袈裟に考える?というレベルのものもあるので、少しでも暇つぶしになれば嬉しいです!
※構成や書き方などに不慣れなところがあるかと思いますので、ご了承くださいませ・・・
※1週間全てのツイートではなく、いくつかをピックアップしたものになります(プライベートなものを深掘りしてもしょうがないので)
◎1%でもポジティブ要素を増やして1日を終えよう
おはようございます☀
— ムーさん(26)@Webディレクター4年目 (@yattoshussya) June 11, 2023
起こるであろう面倒なことを先に想定しておけば、そこを乗り切った時の達成感があったり、他のことで面倒だったことを相殺しちゃおうという考え方を作れる。今日の僕で言えば、出社日なのに夕方から天気が悪くなりそうということ。明日は在宅だからさっさと終わらせて帰ります😆
普段、在宅勤務をしており、出社は面倒だと思っている派の私が、久しぶりの出社日をどのように気持ちよく乗り越えようか、ということを考えた時のツイートです。
久しぶりの出社日でしたが、この日は運悪く雨でした。
雨が降っていることを窓から確認し、準備をして、傘を差して駅まで歩いて、満員電車に乗って、降りた駅で人混みにまみれて、駅から会社までまた傘を差して歩いて・・・、といった感じで。
これだけ見て、「ヒャッホー!!」ってテンションを上げられる人はそうそういないですよね。
でも、普段の生活でネガティブなイメージや思考をなるべく持ちたくないのが人間です。
逆に言えば、ポジティブがネガティブを上回れば、結果として良い1日として片付けられるのではないかと思っています。
「久しぶりの出社が雨だった」がネガティブでも、「雨の中出社した自分頑張った」はポジティブです。
それぞれ書き出したらわかりやすいかもしれませんが、「ポジティブ:51」VS「ネガティブ:49」だったらポジティブの勝ちですよね。
少し面倒なことがありそうな予感がしても、ポジティブなこと、良かったことに目を向ける瞬間が多い日々を過ごしたいですね。
◎欲はルールで押さえつける
おはようございます☀
— ムーさん(26)@Webディレクター4年目 (@yattoshussya) June 12, 2023
たかがゲームであれど冷静さは保ちたい。連敗したりしょーもないミスを重ねるとコントローラーをぶん投げたくなる。なので5回勝つか5回負けたら何がなんでも終わりにするルールを設けました。つまりは勝ちたい欲が強すぎると人は冷静さを失います。これスマブラの話です😂
負けず嫌いなので、ゲームであっても全力で戦います。
でも負けることがあるのも勝負の内で、それを受け入れる、または耐えるためにはどうすれば良いかを考えたツイートです。
スマブラのオンライン対戦は、同じレベル帯の人と対戦できるのですが、レベルで見れば紙一重なので、勝てるチャンスは十分にあるはずなのです。
それなのに、一度負けると、次こそ勝つ!→また負ける→イライラする→次こそ勝つ!→また負ける→さらにイライラする・・・、という悪循環を生んでしまいます。
そして、ちゃんと勝てない自分に怒りをぶつけたくて、しまいにはコントローラーをぶん投げたくなってしまいます。自暴自棄で危ないですね。
勝てるであろう相手に勝てないからこそ、とても悔しくなります。
これで本当にコントローラーをぶん投げてしまったらやばいので、色々考えたところ、負け続けると大体その先に勝つ確率が低くなっていくということに気づきました。
なので、勝負の回数に制限を設けて、負ける数が増えるのを防ぐことに。
負ける数が減れば、相対的に勝つ数を増やすことにもなります。
こうすることで、自分がイライラする時間も削減できましたし、健全に楽しむ心の余裕も生まれました。
もし欲に負けてしまって後悔をしたり、悪い方向に行きそうだなと思ったらルールを設けると改善できるかもしれませんね。
最もそれに思い通りに従うのも難しい話ではありますが。。
◎インプットの効率を紐解く
わからない状態にいることがわかっていると、Wikiとかマニュアルの情報って入ってきやすいけど、そもそもわからないにたどり着いてない真っさらな状態だと、インプット
— ムーさん(26)@Webディレクター4年目 (@yattoshussya) June 13, 2023
の効率って圧倒的に変わる気がする。知る目的が明確かそうでないかの違い。とりあえず見たり読むのって非効率なのかもしれない🤔
色々な情報をインプットしていく中で、「何も知らない」(真っさらな状態)と「わからない」って違うなと思ったツイートです。
そもそも「何も知らない」というのは、知るという段階をまだ踏んでいないので、「わかる」「わからない」が存在しておらず、どちらも全く別物だと思います。
「わからない」「わかる」が発生するまでにはまずこの知るという段階があるのではと思います。
そして「何も知らない」状態から、例えばマニュアルや参考資料を読むといった知るという段階を踏む中で、知ろうとする意思や目的を介在させることができるか否かで、インプットの効率が変わってくると思います。
知ろうとする意思と目的を介在させることができていると、読み始めのタイミングから、その意思に従い、定められた目的を達成する方向に向かうので、インプットが効率的に進められると思うんですね。
そして、「わかる」が生まれ、「わからない」が自ずと定義され、わかったこととわからないことがそれぞれ明確になっていくはずです。
ここで「わからない」を作ることができ、次にこの「わからない」を解消するということが意思や目的となり、また同じようなやり方でインプットを進められます。
しかし、逆に意思も目的もなく、とりあえず読む姿勢になるとどうなるか。
どこに向かえば良いのかわからないですし、最終的には「読み終わる」ということが達成されれば良いということになる気がします。
その結果、知る目的がないからそれも達成されず、「わかる」「わからない」が定義されず、何がわからないのかわからないという状態が生まれるのではないかと思います。
「何も知らない」という状態から大して差がない状態だと思います。
じゃあ、それからどうなるかというと、結局何がわかっているのかを確かめるべく、また同じものを読むことになる気がします。
こうしてみると、これはとても非効率な行為だと思いますし、前者と比較すると、意思と目的の有無によってここに効率の差が生まれてくるのではないかなと思います。
結論としては、インプットにおいて意思と目的の有無が、効率に影響するということです。
なので、普段から意思と目的を明確にしてインプットは実践していきたいものですね。
◎現地の実態をとにかく知ることが大事
おはようございます☀
— ムーさん(26)@Webディレクター4年目 (@yattoshussya) June 14, 2023
そういえば先日、こちらの本を読んで部署のチーム内で紹介しました。海外市場に事業展開してる人向けで、実践例もかなりハードですが、面白い本です。発表も好評でした。カンボジア人向けに現地に即したWebサイトを作った事例が特に勉強になりました🤔https://t.co/Z50nGDq8RX
会社の部署のチーム内で、読書発表会の担当となったので、『クロスカルチャー・マーケティング 日本から世界中の顧客をつかむ方法』という本を読みました。
ちょっとした本紹介になります。
「クロスカルチャー・マーケティング」とは学術的な用語ではなく、著者が経験則を基に下記のように定義しています。
企業や組織が自国で培ってきた文化やサービスの特長を活かしながら、大正市場(海外)の現地特性に合わせたマーケティング戦略を立案し、多様性に富んだチームの潜在的な能力を用いて最適化していくこと
実際のプロジェクトの事例もありますし、マインドセット、チーム作り、コミュニケーション、リーダーシップ、マーケティングなどなど、内容は豊富です。
事例で言うと、特にツイート内にあるカンボジア人向けのWebサイトの事例は面白かったです。
プロジェクトとしては、JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)の認知拡大と受験者増加を目的に、現地のクメール語に対応した情報サイトを制作するというもので、ポイントで言うと、①カンボジアの文化に配慮して制作、②現地の特性に合わせた広告運用という点です。
①について、カンボジアには曜日によって関連する色のものを身に着けることで、幸運や成功、健康がもたらされるという慣習が古くからあるそうです。
また、現地サイトを調査してどの色がよく使用されているのかを特定しつつ、デザインパターンを開発してカラーコントロールを実施したそうです。
加えて、政治的背景から教育普及率が低いため、カンボジア人の識字率にも配慮して、JFT-Basicの存在と興味関心を持ってもらうことに主眼を置き、重要な情報以外のテキスト情報は大幅に削減したサイト作りをしたそうです。
②ですが、公用語のクメール語はGoogle検索に対応しておらず、代わりにFacebookを使用して検索や情報取得を完結させる実態があることに目をつけ、Facebook広告を活用したそうです。
そのため、日本で配信するよりもコメントやリアクションが多く、ワンクリックあたりの費用を日本の平均的な金額よりも10分の1まで抑えることができたそうです。
①②を踏まえると、外国人の実態を色々な観点から目を付けて、とにかく細かく知ることから始めないと、海外向けの事業展開というのはうまくいかないと思いました。
曜日によって関連する色があるなんて、日本に住んでいたら占いとかでない限り意識しないですよね。
とても面白い本でしたし、日本の企業の成功事例もいくつか紹介されていたので、興味のある方はぜひ。
特に下記の方にはピッタリだと思います。
・海外市場への展開を考えている方
・チームメンバーに外国人がいる方
・日本向けと海外向けのマーケティングとの違いを知りたい方
◎どうやってボールの受け渡しをしたら良いか
おはようございます☀
— ムーさん(26)@Webディレクター4年目 (@yattoshussya) June 15, 2023
来たボールを反射的にすぐ返す行為は注意が必要。確認事項とか修正依頼はポンポン出すのでなく、なるべく1回に集約した方が良い。五月雨式だったり重ねて色々やり取りするのはお互い疲れる。進めやすい流れへとコントロールするのはディレクターが持つべきスキルですね🤔
Webディレクターをやっているとよく目にする、あるタスクを処理するまでの間、その担当者がボールを持っていると表現されますが、このボールの渡し方や受け取り方に関するツイートです。
結局どうやってコミュニケーションを取るのが一番お互いにとって気持ちが良いか、を考えることがとても大事だということです。
実際のボールをカゴに入れて交換し合う様子をイメージするとわかりやすいかもしれないので、簡単にイメージ図を作りました。

例えばボールが10個あるとして、上側は1つのカゴに対して1つのボールを入れています。
ボールのやり取りをすることに変わりはないですが、最低でも10回はやり取りが発生しますし、抜け漏れが発生したりするなど、ボールの管理がとても煩雑で大変です。
さらにやり取りを進めていくと、まだ渡していないボールと既に相手から返ってきたボールの区別も難しくなりますし、渡したボールが誤ってそのまま返ってきてしまうケースもあります。
では、下側を見ると、1つのカゴに対して10個全てのボールが入っていますが、こちらは一度ボールを渡すだけで済みます。
扱うカゴが明確なので抜け漏れも起こりにくいですし、このやり取りが定着するとボールの管理も簡単になります(ボールがなぜか増えるケースもありますが笑)
仕事を進めている中で、上側のイメージになっていることに気づけたら、下側の形に置き換えて、コミュニケーションコストをなるべく削減することを心がけたいですね。
最後に
#3 、いかがでしたでしょうか?
毎週投稿予定ですので、来週もぜひご購読いただければと思います!
もしよければ、私のTwitterアカウントもフォローしていただけると幸いです!
また、noteや記事作成に詳しい方、アドバイス等いただけると嬉しいです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
