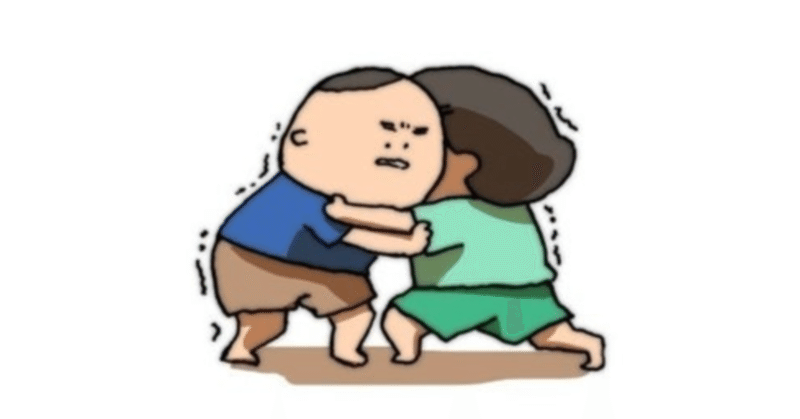
あの日の小錦と同じ現場にいた記者から学んだ。伝える事の素晴らしさと表現の在り方。
Yahoo!ニュースから流れて来たこの日刊スポーツの記事を何度も読み返している。とてもいい記事だ。
2300文字ほどのこのコラムは、大関(KONISHIKI)の事をすごく愛情を持って書いてある。何より読んでいる人にそれが伝わってコメント欄がそれぞれの読者の大関との思い出、相撲についてと、すごく好意的に受け入れられているのを読み、やはり文章は、人の心を動かせると再認識している。
現役時代、相撲界に思うこと、現在の心境、これからのこと。
同じ日に同じ場所にいた私は、私の言葉で伝えることしか出来なかったが、同じ事を体感して書いている記者の凄さを知れた。
私は、この記事の感想が書きたいワケではなく、自分の表現を見つけたいと日々推敲しながら書くことを挑戦している中で「記事」にするということのスゴさを知れた事を残しておきたい。
コラム記事を新聞に書くというのは、どれだけ神経をすり減らしているのだろうか。想像するだけで緊張する。
この記事は、全く知らない第三者が読んでも大関の相撲界での歴史と心境の変化、その日何が行われたか、そして記者の視点や大関との接点が、散りばめられていて楽しませてくれている。
たぶん、スタートから違うのだと思った。
「事実をきちんと伝える」
これを分かりやすく、人に届くようにだ。
無駄なく伝えるからリズムが生まれて読んでいて気持ちがいい。
私は、私の書きたい事を書いて表現を見つけようとしているが、
伝える、伝わる事を意識していない。
独りよがりの表現は、読む人を時に置いていくのかも知れない。もちろん、書く上でそれでいいと思って書いている人もいっぱいいるだろう。
だけど、私はもっと伝えるということを考えないといけないと思った。わかりやすく状況を伝える事は読者の想像力を助ける事になる。
それが表現としてつまらない淡白なものになるのなら、それは単なる私の力量不足だ。
こんなタイミングで、同じ日に、同じ空間にいた人のプロの記事を読めるなんてとんでもなくラッキーだ。
この記事は、本当に愛を感じるし人の興味を大関や相撲界へと読者の裾野を広げている。
こういう応援の仕方もあるのか。
この記事を読んでそれに気付いた時に、
文章に技術が存在するのなら、書く事と考えることを続け、わかりやすく伝える事を常に意識しながら、そこに自分の表現を出していくこと。と思った。
もっと一言一句を大事にだ。
より明確に自分の向かう方向性が見えてきた気がする。
なんのはなしですか
日刊スポーツの渡辺佳彦記者。
こういう文章は、意外とスラスラ出てきて苦労しないで書けたりするのだろうか。あまりにも自然な流れで角がない。
伝えるということをどういう風に捉えているのだろうか。
文章の奥の人間を感じる。それが書き手としていいことなのか悪いことなのか。
話しを聞いてみたいなぁ。
ついでに、noteの皆様の中でもし、私に興味のある方いたら連絡してみてください。
あと何人と出会うかなんて、逆算したら恐ろしく少ない。
今年何人に出会ったか。人に出会いたくないと考えるようには、なるべくしたくない。
もっともっとと思っていた事に、より輪郭がついてくる出来事に触れて本当にラッキーだ。
つまるところ、私はラッキー文学中年だということをただお知らせしたかった記事である。
同じ日の、私の記録はこちら。
まどろっこしい表現だなぁ。
だけど、noteはそれを肯定出来る場所だと思っている。
いいよ。もっと自分らしく上手くなってやる。
40歳からでも遅くない。圧倒的にこの一年で自分の文章は変化し上手くなっている。
真正面からぶつかるスタイルでいい。
それを見てきたはずだ。
プロとプロのぶつかり合いは、それをお互いに昇華させる事を学んだ。
私も、その土俵に上がるべきだ。
そうしないと、ハッキリと自分の姿を認識することは叶いそうにない。
まずは序ノ口からだ。
私が幕内に上がる頃、文学女子は私をほっとかないだろう。10年かけて成し遂げよう。
10年後文学女子を口説く目標を、10年後文学女子に口説かれることに変更する。
より、ハードルが上がったが、ハードボイルドな50歳を迎えられそうだ。
10年経過したら、子供成人か。
バレてハードボイルドな暮らしを迎えたくはないな。
連載コラム「木ノ子のこの子」vol.14
著コニシ 木ノ子(土俵際からのスタート)
自分に何が書けるか、何を求めているか、探している途中ですが、サポートいただいたお気持ちは、忘れずに活かしたいと思っています。
