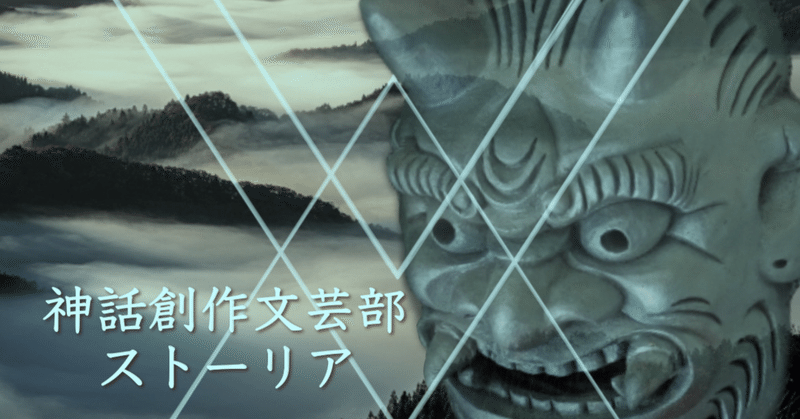#エッセイ
え、そこで完結ですが
正直、唐突過ぎるのだ。
神話部に寄せるコラムや論考もどきの記事が。
当のわたし自身がそう思っている。それを何とかしてくれているのが神話部の存在だ。
部長の矢口さんが覚え書きを出された。これは神話というモチーフであるがゆえ、非常にデリケートに扱うべきという信念の現れだと思っている。
宗教性や信仰性と切り離す事が難しく、思想の誘導を促しかねないからだ。
エッセイ、コラムの類いを書く時に気を付けてい
フラワーアレンジメント
先に言う。
わたしが挿した訳じゃない。
花を仕事にしている娘が作ったものだ。
この秋娘は転職した。今まではプリザーブドやドライも扱っていたが、今は生花専門だ。
そこで意外だったのは、仏花が非常に多いと言う事だったようだ。娘は元々婚礼装花から花に入ったので、余計そう感じるのかも知れない。
お盆やお彼岸以外にも、仏壇があるお宅は花を添える。
日本では実は婚礼よりも葬儀の方が、礼を尽くすと言う意味
民族性だからこそ言葉を変えてみる
「同調圧力」この一年、どれ程聞いただろうか。
様々な推測や仮説に決着をつけるもののひとつに「発掘」がある。
埋まっていた地層から年代を測定し、解析を加え証拠として提示されてきたものの中には人骨もある。
国家としての体裁を整えてから現代までより遥かに長い年月をかけて積み上げられた民族性は、島国であったことから外敵による転覆を逃れてきたこの国の中では、むしろ上書きされても、否定する事は容易ではなく