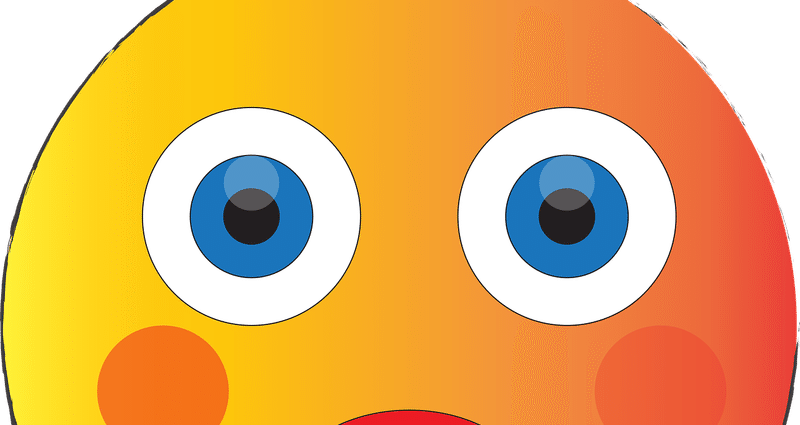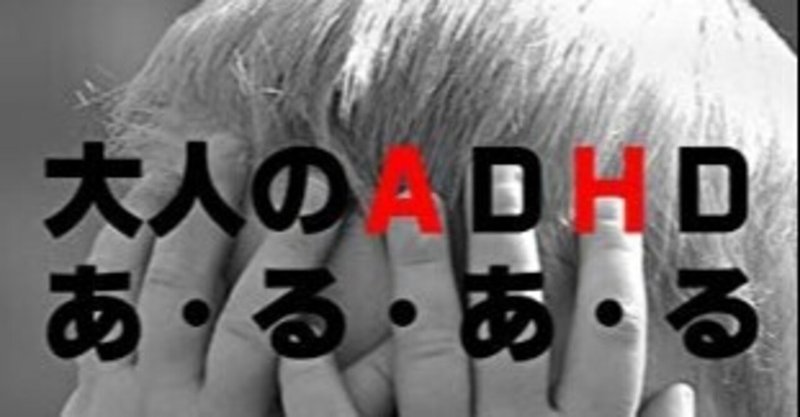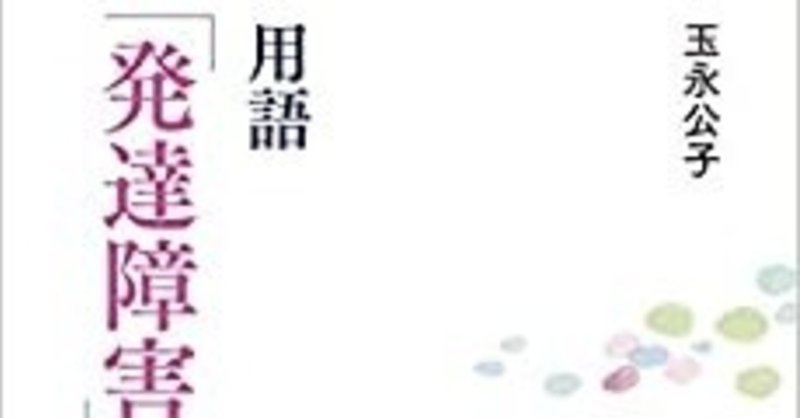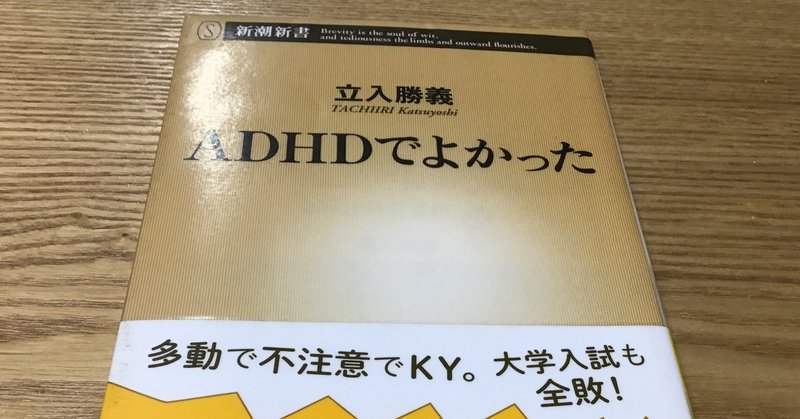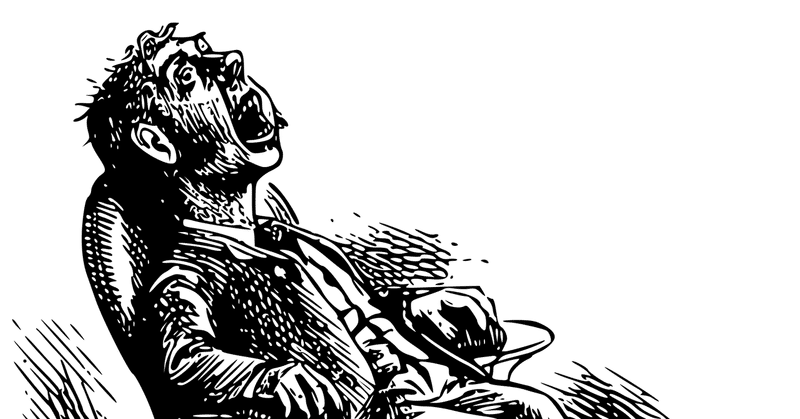#発達障害
kindle出版10作目「大人のADHDあるある」制作秘話。
ずっと構想はあったのだけれど、とりかかるまで半年かかった。本当は年末までにリリースしたかったのだが、間に合わず。なんとか、かんとかリリースできた。この本は、NOTEのADHDあるあるを編集して一冊に仕上げたものだ。NOTE1000記事を入れた意味があった。とにかく適当に書きまくり、あとから編集して一冊にする作戦の第一弾だ。
文字数は7万5000文字を超える力作だ。普通のkindle本は2~3万文
そんな自分がちょっと好きだったりする(書評)ADHDでよかった 立入勝義
ADHDでなければ、どれだけ生活が楽だっただろうと思うことはあるけれど、ADHDでない自分のことを想像することができないのも事実だ。ADHDは自分そのものなのだ。だから、今ある自分がいるのも、たどっていけばADHDのおかげだとも思える。このなんだか、わけのわからない感覚を自伝の形で書き表した本を見つけた。
アメリカ在住20年の起業家・コンサルタントの立入氏だ。彼がADHDの診断を受けたのは34歳
発達障害(ADHD)=「ワーキングメモリー障害」と理解すると対処法が見えてくる。
日々、ADHDのお勉強に励んでいるのだけれど、ADHDについて正確な知識が分かれば分かるほど、その症状にどう対処してよいか見えるようになってくる。
ADHDという言葉に出会ったのは、15年くらい前だけど、あの頃は「なんだ、そんなもん。そんなラベルを付ければ、誰でも障害じゃないか」というくらいの認識しかなかった。あの頃からちゃんと向き合っていれば、もっと生きやすかった気がする。
さて、ADHDと
#ADHDあるある:発達障害は睡眠障害になる可能性が高い?眠りの質が低くて、寝起きが悪い。
毎日、スマートウォッチで睡眠時間を計測しているが、なかなか深い眠りが少ない。基本的にはロングスリーパーなのだが寝ている時間の割には、目ざめのスッキリ感は乏しい。いつも寝足りない、グロッキー、憂うつな目ざめとなる。目が覚めだしてから、確実に動けるようになるまでは30分はかかる。スッキリ起きることができた朝は、人生の中でも数えるほどしかない。
睡眠の質を高めることには、こだわって、いろいろな実験をし
ADHDには「ランドセルサイクル」が通じない。「普通」の人には理解できない感覚なんだろうな。
前もってちゃんと準備をしていれば、忘れ物が減るだろう。きちんとチェックすれば、失くし物が減るだろう。こんな論理は、ADHDには通用しない。私は、小学生の時に、学校からもらったプリントをまともに家に持って帰ったことがなかった。だいたいランドセルの中でくちゃくちゃになっているか、学校の机の中でくちゃくちゃになっているかだった。
ADHDと「普通」の人は、驚くほど感覚が違うのだ。最近、コンサルタントの
#ADHDあるある:突進する癖・追突癖
ADHDは、黙っていられないのだ。私は今でも落ち着いていられないので、座っていても体が上下左右に揺れ動き続けているらしい(自分ではあまり自覚していない)。先日、ZOOM会議の録画を見たが、自分一人がひたすら揺れているのを見て、ちょっと悲しかった。まさに多動児なのだ。
発達障害に関しての、温かな目線での本を出している杉山氏も、ADHD気味で多動傾向があるらしい。「多動メンバー」という、自分の周囲の
#ADHDあるある:致命的に時間の逆算ができない。時間通りに家を出るための3つの方法。
ADHDの大きな特徴は「衝動性」だ。普通の人は、そこでしないだろうというところでブレーキがきかないのだ。精神科医の備瀬氏は、夏目漱石の「坊ちゃん」が、まさにADHDの特性を持っていると分析している。
私は、坊ちゃんほど、衝動性が高くないけれど、思いついていきなり行動し始めることがあり、その動きは家族に迷惑をかけている。時間の逆算が致命的なまでにできないのだ。不思議なんだけれども。まあ、いわゆる遅