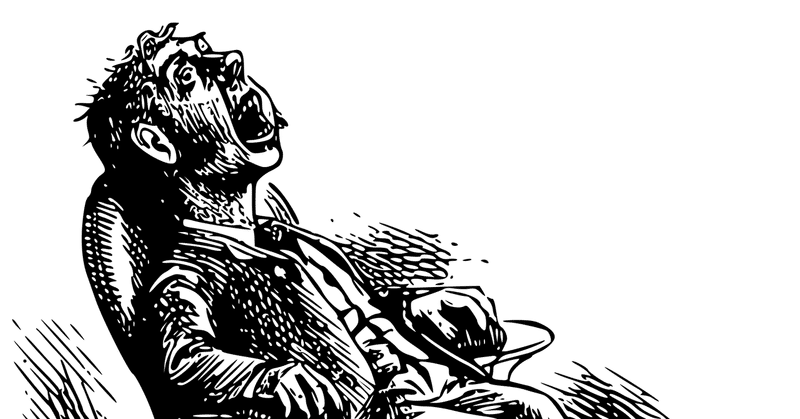
#ADHDあるある:発達障害の二次障害「不安障害」との戦い。
ADHD傾向が激しい私の悩みは、二次障害ですっかりブルーになってしまう時間が多いことだ。これまでは、あまり発達障害と結びつけて考えてこなかったのだが、日常生活が遅れるかどうかの微妙なラインに悩んだ時に、改めて、発達障害という「根っこ」に戻ってきた。
参考:#ADHDあるある:発達障害の二次障害は、かくも苦しい。
参考:「隠れADHD」の苦悩、注意すべきは二次障害。【書評】精神科医が伝えたい「発達障がい」でもだいじょうぶ! 端谷 毅
特に深刻なのが「不安障害」だ。それまで長年続いてきた過敏性腸症候群(IBS)の症状が好転すると同時に表れたのが不安障害だった。
発達障害(ADHD)は不安障害になりやすい
いくつかの調査では、ADHDの人の45~50%以上が何らかの不安障害を併発しているという報告がなされているそうだ。一般の人の不安障害の発生率は4~5%だから、実に10倍だ。
自身もADHDである精神科医の星野氏によると・・
「大人のADHDにしばしば全般性不安障害が合併するのは、彼らが不注意傾向や衝動性などのために自分の言動をコントロールできず、いつも漠然としたふんを抱えて生きているためとみられる」(発達障害に気づかない大人たち 星野仁彦 祥伝社 P143)
とのこと。これはわかりすぎる。
ADHDの生活では、できないことが多くて、本当に日常でもビクビクすることが多い。財布がなくなったり、カギがなくなったり、切符を落としたり、慌てふためくことが多いため、絶えず何か失敗しているようなビクビクした気持ちがする。
個人的な分析では、こんな夢をしょっちゅう見るのも、きっとADHDの特性ゆえじゃないかなと思っている。
参考:冷や汗ダラダラ。頻繁に繰り返される「裸で外を歩いている」悪夢。
さらに、ADHDは脳機能障害も相まって、ネガティブな感情の影響を長い間受けやすいのだという。
「自尊心をつかさどる前頭葉から基底核・線条体に至る「報酬系(ドーパミンを分泌して快感を高める神経系)」という部位が未発達で、自己像・自尊心が低くなりやすいと考えられている」(発達障害に気づかない大人たち 星野仁彦 祥伝社 P71)
まさに踏んだり蹴ったりである。
ただ、私の場合は、かなりラッキーなことに、精神科領域では「発達障害が万病のもと」であることを知っていたのがよかった。多くの人の発達障害は、うつ病や不安障害のような二次障害の陰に隠れている。その結果として、二次障害を引き起こしている本丸にたどり着けないことが多く、治療は困難を極める。
自分自身に発達障害の傾向があることを知っておくのは大事なことだ。まずは原因を知ることで、自分を冷静に見ることができる。
自己効力感が大切
ADHDには、自己効力感(自分をコントロールできているという実感)が非常に欠けているのが普通だ。しかし、一度、発達障害の自分を受け止めると、そこを起点に工夫することができる。
大人の場合、発達障害を受け入れると、自分なりに生活を工夫して(時には環境を変えたり、仕事を変えたり)もっと生きやすくなるように調整を図ったり、自律スキルで対処できたりする。そして、その工夫が不安障害にはダイレクトに効く。
だんだん、自分をコントロールできていることが分かってくるにつれて、不安は少なくなっていく。私の場合は、認知療法的に行っている日記の習慣や、論理療法(REBT)でのセルフトークの書き換え、交流分析でのエゴグラムなどが役に立った。
もちろん、完ぺきではないので、今でも不安になったり「今日はメンタルのコンディション悪いな」と思う時はある。でも、そういう時には、不安に抗うのをやめるようにしている。不安を何とかしようともがけばもがくほど、おぼれそうになるのだが、「うむ、残念ながら、これもADHDあるあるだな」と理解できることで、冷静になることができるのだ。
特効薬ではないけれど、少しずつ自分をコントロールすることに取り組む日々だ。ちょっとずつ強くなっている。
#ADHD #大人のADHD #発達障害 #大人の発達障害 #不安障害 #二次障害 #ADHDあるある
大人のADHDグレーゾーンの片隅でひっそりと生活しています。メンタルを強くするために、睡眠至上主義・糖質制限プロテイン生活で生きています。プチkindle作家です(出品一覧:https://amzn.to/3oOl8tq)
