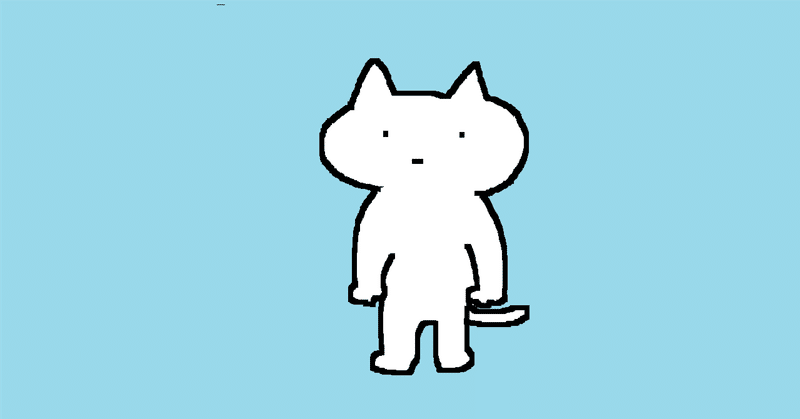
「ぼっち」はそんなに悪いのか
現在の学校は様々なことに怯えている。
それは、学校に物を申す「利害関係者(ステイクホルダー)」が多いことに起因する。
学力を上げろ、働き方改革をしろ、いじめを見過ごすな、子どもの主体性を認めろ、〇〇教育を推進しろ、などなど挙げ出したらキリがない。これらは、保護者、教育委員会、文部科学省、研究者、メディア、教育評論家の方々が学校に盛んに要求してくる言説である。
おかげで、学校はすっかり小動物のようになってしまった。
それはつまり「各方面から文句を言われないようにアリバイ作りをする」という学校の所作に現れている。言い返すことなどできないので、何とか「やり過ごす」ための処世術にかかるコストを引き受けるのは現場の教師たちである。
結果、アンケートやテストを繰り返して、それを集計した結果を蓄積することで「説明責任」を果たそうとするのだ。そもそも教育の成果という可視化できないものを可視化しようとするのだから、それは「無限の営み」になる。どこまで行っても「まだ足りない」という無限地獄に現場は悲鳴をあげているのだ。
さて、今回のテーマも、そうした学校への圧力の中で生まれた「学校教育の悲しき習性」の一つである。それは「ぼっち撲滅運動」である。いや、そんな運動などは無いと感じる先生もいるだろう。しかし、そんなことはない。それは、教師の中であまりにも内面化し過ぎている価値観のため、気づけていないだけなのだろう。
ここで実例を一つ述べよう。
それは遠足の時のことである。遠足に恒例の「お弁当の時間」に、ある先生は、自身の食事も食べずにずっとウロウロしている。
「どうされました?」と聞くと「一人でお弁当を食べている子がいないか探していました」という。私が「一人で食べたい気分の子どももいるんじゃないですか?」と聞き返すと「いじめを見過ごすことはできません」と返された。
どうも、その先生に言わせると、クラスで1人ぼっちの子を助けることができないクラスは「いじめクラス」ということになるらしいらしい。
もう一つ事例を述べよう。
先ほどの先生のクラスには「みんな遊び」という時間が存在する。これは、休み時間に「みんなで遊ぶ」という活動である。
その目的を先生に尋ねると「休み時間にひとりぼっちの子でも、みんなと遊べる機会を作ってあげたいので」とおっしゃっていた。その先生には、「休み時間に一人で読書をしている子」は「みんなから遊びに誘ってもらえない寂しい思いをしている子」に映るらしい。
いずれもバカバカしい話である。
でも、このバカバカしさに気づけないほど、学校現場には子どもの「ぼっち」を恐れる。その理由はわかりやすい。学校現場は「いじめ」を恐れているのだ。
いじめというのは「IJIME」と表記されるくらい、「日本語独自」の言葉である。「TSUNAMI」や「KENDAMA」と同じなのだろう。その独自の理由としては「いじめ」のもつ「豊かなイメージ」であろう。暴行も窃盗も恐喝も、陰口も仲間はずれもモノ隠しもプロレスごっこも。犯罪行為から悪戯行為までその全てを「いじめ」という言葉は内包している。
その理由は「いじめの定義」に由来する。
現在の文科省による「いじめの定義」を以下に記す。
「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍してい る等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な 影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該 行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/06/26/1400030_003.pdf
つまり、「当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」という定義に照らせば、先ほどの事例は全て「いじめ」に定義されてしまうのだ。もちろん、犯罪行為を「いじめ」にしてしまうのは問題があるということで、先ほどの引用の下には注意書きのように、以下のような文章が添えられている。
「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察 に相談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生 じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについて は、教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談・通報の上、 警察と連携した対応を取ることが必要である。
しかし、これを根拠に学校が警察に連絡することは極めて稀であろう。
「直ちに警察に通報することが必要」と「早期に警察に相談・通報」の間にある「教育的配慮」という言葉が、学校に警察への通報を躊躇わせるのだ。加害者も児童生徒である。日本においては、警察に通報されるというのは、その人の人生に多大なる「社会的影響」を与えることになる。そんな決断を学校レベルで行うのには、かなりの勇気がいる。加害児童の保護者から訴えられることもあるかもしれない。結果「いじめ」という言葉は「犯罪行為」をも内包して、学校現場の外側には隠されることになる。
現代の学校においては「いじめ」は絶対にあってはならないことなのである。なぜなら、起こったことが一度でもバレて仕舞えば、その学校の社会的信用は地に落ちてしまうからだ。だから、学校は「いじめはなかった」とか「認知していなかった」と述べるしかなくなる。これは「わざとじゃないもん」という子どもにそっくりである。でも、そればかりだと社会も学校を責めれなくなってしまうので、いじめアンケートが頻繁に行われるようになる。
そこで「いじめられた」という子どもがいれば、先生は即対応が義務付けられ、その事案の「即解決」が求められる。こうして、学校からは「いじめ」がなくなるのだった。
さて、「ぼっち」に話を戻そう。
以上のような事情から学校は「いじめ」を恐れるあまりに、そこへの対応策として「なかよし作戦」を実行していくことになる。
その成果が「ぼっち飯の排除」と「みんな遊びの推奨」なのである。
しかし、これはあまりに浅はかな対応である。
人間形成としての知見にあまりに欠けていると言わざるを得ない。
『人間の条件』や『エルサレムのアイヒマン』などで知られるハンナ・アーレントはその著書の中で「ぼっちでいること」について、それを3つの容態に分けて分析ているので、興味深い。
以下は、東京大学大学院の石神真悠子の研究論文「ハンナ・アレントにおける”一人であること”の多層性 政治的主体化に向けて」という論文から引用しながら、「ぼっち」について考察していこう。なお、論文は以下のリンクより閲覧可能である。読みやすいので、おすすめだ。
https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/record/52171/files/4511.pdf
まず、アレントは「ぼっち」を以下の3つに分けた。
孤独(solitude)
孤立(isolation)
寂しさ(lonliness)※石神はこれを「見捨てられていること」としている
孤独とは、物理的には一人である状態ではあるが、内面では世界とつながっている状態であるという。これは、我々が「思考をしているとき」を思い浮かべてもらえればいいだろう。
思考は言葉によって行われる。これは自明なことであるが、よく考えるとおかしなことでもある。なぜなら、伝えるべき相手などいないのに「言葉」を用いているからである。自分だけがわかればいいなら、そこに言葉は必要ない。実際、我々は言葉に表せないような「感情」をたくさん持っている。
しかし、思考には言葉を用いる。というか、言葉がないと思考ができない。
これはつまり、我々の思考は「一人の営み」ではなく「対話」であると考えることができる。では、我々は思考を通じて誰と対話をしているのか。それはアレントの言葉を借りれば「世界」ということになる。これまでに出会って来た人たちと共に作り上げた世界と対話をして思考をしているのだ。
つまり、孤独は「ぼっち」ではない。世界と繋がる対話ができる思考状態は、決して「ぼっち」ではないのだ。
孤立とは、思考をしている状態ではない。そういう意味では「世界」とは繋がれていない。物理的にも一人である。
しかし、これは悪いことばかりではない。例えば、読書や生産活動を思い浮かべてみよう。このような時は、時間があっという間に過ぎ去る。そのような状態を「没頭」ともいう。そして、人間には「没頭」できる状態が必要なのである。
子どもたちは没頭の達人である。すごい集中力で、すごい仕事量をこなしてしまうこともある。そんな時は「思考(孤独)」とは違う「没頭(孤立)」なのである。なお、没頭についても過去に論じているので、以下の論考をご覧いただきたい。
つまり、孤立は「ぼっち」ではない。一人きりになれないと捗らない活動というのは決して「ぼっち」ではないのだ。
では、寂しさはどうであろう。
これは、もう全くの「ぼっち」である。この状態では、世界からも見捨てられ思考もままならず、自分自身への信頼も見失い、活動する気力もない。これをアレントは「世界に現れていない」と表現した。
これは「思考(孤独)」とも「没頭(孤立)」とも違い「ぼっち(寂しさ)」である。教師としてはすぐに救い出して、その子を世界へ連れ戻さないとならない。
このように、石神の議論を参照しながらアレントの「ぼっち論」を見てみると、やはり、学校の対応は愚策にも程があると言わざるを得ないのである。
教育は「人間形成」の営みである、と最近は考えている。
教育哲学者であるガート・ビースタは「教育の学習化」を憂いているが、これは教育という営みの矮小化を嘆いているのだ。
教師は勉強だけを教えたらいいというのは間違っている。
子どもたちの人間形成に深く介入する営みだからこそ、そこには深い人間洞察が求められることは自明だろう。
そういう意味で、私は教師の素養としての「教育哲学」を学ぶことを薦めている。
ミシェル・フーコーを読めば自分の権威性についてもう少し自覚的になれるし、デリダを読めば教育の手法を大きく刷新することができる。アリストテレスの「中庸」には納得させられるし、東洋哲学の持つ「内面へのベクトル」は感心させられる。
教師は教科教育法や学級経営手法だけを学べばいい時代は終わったのだ。
