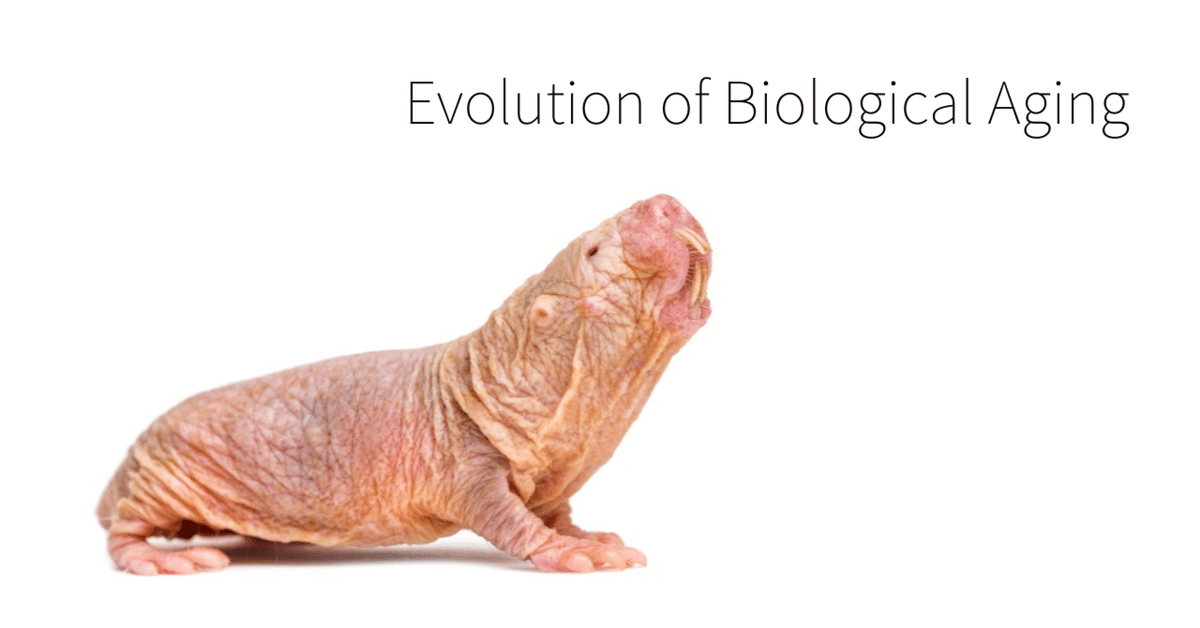
老化の進化:なぜ老化しない生物がいるのか?
生物はなぜ老化し、死ぬように進化したのだろうか? 現在まで、進化学の分野では、老化の進化に関しての理論的研究やその実証研究などが行われてきた。しかし、「老化の進化や死の進化」についての解説には誤解が多い。最近、老化しない生物に関する論文が複数出版されており、「老化しない生物はなぜ進化したのか」という問題と同時に議論する必要がある。本稿では、それらの研究を紹介するとともに、なぜある生物は早く老化し短命であるのに対し、ある生物は老化せずに長寿なのか?という「老化と死」の進化的要因について解説する。
なぜ生物は老化し、死ぬのか
老化(Senescence)あるいは生物学的加齢(biological aging)とは、年齢を経るにつれて死亡率が増大するような生物の生理的状態の変化のことだ。多くの生物は、年を取るにつれて、次第に体の状態が衰え、最終的に死に至る。年齢とともに病気に罹りやすくなったり病気で死亡しやすくなるすることは、老化が原因である。一方、生物は、偶然の事故や自然環境の変化で死亡したり、捕食者に食べられたりして死亡することもある。このような年齢とは独立した外的要因による死は、老化による死としては考えない。
「生物はなぜ老化し、死ぬのか」という問いには、2つの異なる側面がある。一つは、「老化を引き起こすメカニズムはなにか?」(老化機構)という問いであり、もうひとつは、「なぜ生物は老化し、死ぬように進化したのか?」(進化要因)という問いである。
たとえば、NAD+(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)は、年齢と伴に減少していく補酵素で、老化と関連しているといわれている。NAD+はSir(サーチュイン)遺伝子を活性化する(注1)。それにより、ミトコンドリアの機能調節、ゲノムの安定化、細胞周期の調節、DNAや細胞の修復を通して、老化が遅れると考えられている(1)。Sir遺伝子の活性化と老化との関係は、老化に関わるメカニズムであり、最初の問いの答えの一部である。
一方、たとえば、ある生物のSir遺伝子に突然変異が生じ、より長寿な個体が生じたとしよう。その長寿な個体は、その生物の集団内でより多くの子孫を残し、集団内での頻度を増大させていくだろうか。Sir遺伝子の例ではないが、寿命が長くなる遺伝的変異(hx546)をもった線虫と普通の線虫を同じ環境で飼育した実験がある(21)。実験の結果、餌が不足した環境では、寿命の長い線虫はその長寿の遺伝的変異を伝えていくことができず、淘汰されてしまった(21)。つまり、線虫では、長寿は進化できなかったということになる。
Sir遺伝子の例でみてみよう。ハツカネズミ、ラット、ハムスターなど短命の種からハダカデバネズミなど長命のげっ歯類18種を調べた研究では、長寿の種では、Sir6遺伝子のDNA修復などの機能がより高くなっており、より強固なDNA修復が長寿と関係していることが示されている(2)。
このことは、遺伝子が進化することにより、長寿になったり、短命になったりする可能性を示唆している。進化とは、ゲノムなどの遺伝情報が世代を超えて変化していくとによって生じる現象である。生物は、それぞれの生息条件のなかでの進化した結果、寿命が延長されたり、短縮されたりするように遺伝子や老化に関わる性質が進化した。その進化をもたらした原因に対する問いが2番目の進化要因に関する問いである。
注1. NMN(ニコチンモノアミドモノヌクレオチド)は、健康寿命を延伸するサプリとして販売されている。これは、NMNが体内でNAD+に変換され、体内でのNAD+の濃度が高まるからである。ヒトでの実証研究でも、NMNの摂取で、糖代謝が高まるなどの有効性が示されている(22)。しかし、NMNは、癌を抑制する場合と、すでに癌が存在する場合は、その増殖を助ける場合があることが指摘されている(1,23)。NMNがすべての人で癌を抑制し、老化を防ぐかどうかは確実にはわかっていないようだ。
老化しない生物
細胞分裂で増殖している大腸菌のような生物においても、細胞が分裂後、一方の細胞系列は老化しないで分裂が繰り返されるが、他方の細胞系列では増殖とともに老化していく(25)。多細胞からなる生物では、遺伝情報を次世代に引き継いでいく生殖系列は老化しないが、体の様々な部分を構成している体細胞の系列は、次第に老化し、個体は死亡する。少なくとも多細胞生物では、個体が加齢とともに死亡率が増大する老化は生物の普遍的な特性であると認識する研究者は多かった(3)。
しかし、加齢ともに死亡率が増加しない生物は、例外的でないことが報告されるようになってきた。Jonesらは(3), 46種の様々な生物の成熟した後の死亡率と加齢との関係を調べた。たとえば、ヒト、チンパンジやショウジョウバエでは、加齢とともに死亡率は増加し、繁殖率は低下しているが、ヤドカリやヒドラは死亡率がほぼ一定である(図1)。実験室のヒドラでは、その制御された条件下で1400年後に成体の5%がまだ生存していると推定される(3)。また、アカネアワビのように、繁殖率が加齢と共に上昇する種もみられる。

最近、爬虫類と両生類の加齢と死亡率の関係が報告された(4,5)。52種のカメとリクガメを調べた研究では、約75%が加齢に伴うゆっくりとした死亡率の増大(老化)がみられ、3〜4%の種は、無視できるほどの老化しか示さなかった(4)。また77種の爬虫類と両生類のうち23種は老化しないか、無視できるほど低い値であった(老化率が0.001より小さい種)(5)。
老化しない脊椎動物は、爬虫類や両生類だけではない。120種の鳥類と哺乳類をみてみると、そのうち8種は、マイナスの値の老化率が推定されている(文献5のSupplementary Data 1) 。また、ハダカデバネズミ(Heterocephalus glaber)は長寿として有名であるが(本記事のトップ画像)、生存率を詳細に調べた研究では、性や繁殖個体かどうかにかかわらず、加齢とともに死亡率が上昇しないことが示されている(6)。また、後述するが、魚類でも、ロックフィッシュ(Sebastes属)の中には200年以上の寿命をもつがいる(7) 。
老化と死の進化
多くの生物は加齢するにつれて、細胞やDNAの修復や維持機構が低下したり、異常なタンパク質の増加やミトコンドリアの機能が低下する。またミトコドリアで発生する活性酸素を処理しきれなくなる。このような機能低下や正常な構造が維持できなくなるのは、エントロピーが増大していくのと同様に不可避であり、生物が老化し、死ぬというのは必然的帰結であると考えるかもしれない。しかし、前項で紹介したように、老化しない、あるいは、ほとんど老化しない生物が例外的でない。つまり、生物によっては、加齢に伴う様々な体内の機能低下による老化を食い止めるような進化が可能であるということだ。
まず、「生物はなぜ老化し、死ぬように進化したのか」という問題についてみていこう。しばしば、生物学者でもよくある誤解が「集団や種が絶滅しないように個体は死ぬように進化した」(8,9)という誤解である(注2) 。この「絶滅しなように個体に不利な性質が進化する」という考えが妥当でない理由は「「種の保存のための進化」はどこが誤りなのか」で説明したので、そちらを参照してほしい。
「生物はなぜ老化し、死にいたるのか」については、古くから議論され、複数の説が提唱されてきた。以下は、その主要な説である。
使い捨て体仮説 (10): 生物個体は、次世代に遺伝情報を伝える生殖系列細胞と、生命活動を行う体細胞系列の細胞からなっている(図2)。生物個体は、常に体(soma)を維持し、修復するためにコストを払わなければいけない。しかし、次世代に遺伝情報を引き継いでいくのに必要なのは生殖細胞系列である。得られたエネルギーを繁殖(生殖細胞系列)に費やすときには、体細胞系列へ振り分けられるエネルギーが少なくなり、体の維持や修復が充分にできなくなって、次第に生存していくことができなくなる。

拮抗的多面発現説(11,12): 年齢の若い時期に、生存率を高めるのに有利な遺伝子に、自然選択は強く働く。そのため、若い時に機能を向上させる遺伝子は、同時に高齢になると生存に不利に働くことがある。たとえば、骨へのカルシウム沈着を促す遺伝子は、若年期の生存を促進させるが、老年期には、同じ遺伝子が動脈へのカルシウム沈着を促進するので、動脈硬化の悪影響が生じる(9)。このように、年齢の初期に生存や生殖活動を増加させる遺伝子は,加齢後の生殖や生存にマイナスな影響を与える可能性が高い。このために加齢とともに生存率は低下する。(同じ遺伝子が複数の性質に影響するよう場合を多面発現という)。
生殖細胞系列に有利に働く遺伝子は、体細胞維持に不利に働くことで、体細胞維持と生殖細胞維持とのトレードオフが成り立つとも考えられる。これは使い捨て体仮説の考え方である。そのため、使い捨て体仮説は、拮抗的多面発現説中の一つとみなされる場合もある(13)。
有害変異蓄積説(14, 15): 自然選択は一生に残した子どもの数が多い個体に有利に働く。そのため、生物にとって、次世代の子どもを残した後の生存は重要ではないため、加齢後に現れる有害な性質を持つ個体は自然選択によって淘汰されづらい。その結果、繁殖後に有害性を引き起こすような有害遺伝子が蓄積され、加齢後の生存率は低下し、死にいたる。
死の幇助説[Assisted death](16): 過剰な生存や繁殖は、近縁な個体の集団にとって有害になる 。そこで、他個体に有利になるように、自ら早く死ぬという説である。集団の個体数が増えすぎないように生物は死ぬという説(注2)とは異なり、局所的な血縁集団に有利に働くという、血縁選択説の一つである。 たとえば、ニホンミツバチのワーカーは、捕食者であるオオスズメバチに対して、高温で焼き殺す熱殺蜂球を形成する。一度熱殺蜂球形成に参加した個体は、生存率が低下し、再度熱殺蜂球形成に参加しやすくなるという(17)。これは、ワーカーが自ら死亡率を上げて、巣を防衛することで、血縁者である女王の繁殖を助けるという利他行動である。
注2. よくある誤解である「個体が死ぬことで、過剰な個体数の増殖が抑制され、集団の絶滅を防ぐ」という考えについてみてみよう。多くの生物は、個体数が増大すると、餌やすみ場所が不足したり、競争が激化したり、捕食されやすくなったりして、死亡率が増大する。これは、外的要因による密度依存的な死亡である。また、時折経験する気候の悪化など外的環境変化でも個体数は減少する。多くの生物の個体数は、このようなメカニズムで維持されている。
このような生物集団内に、死を早めて個体数の増加を抑制するような遺伝的性質をもった個体が生じたとしても、すぐに集団中から淘汰され、進化することはできない。
また、「集団中に新たな遺伝的変異の供給を助け、環境に適応しやすくなる」のために個体は死ぬように進化した、といわれることがある。たとえば、大腸菌の実験では、極度のストレスを与えて、進化させると、高い突然変異率をもった株が進化する(26)。このとき、細胞(個体)の死が自然選択の効率を高め、突然変異率の急速な進化を促すと考えれている。しかし、死ぬこと自体は、高い突然変異によって有害な効果を蓄積する結果である。死自体が急速な適応を促すために進化したわけではない。また、ストレス環境下で、突然変異率の高い個体が進化するのは、集団の絶滅を防ぐためではない。突然変異率の高い個体の多くは死ぬが、たまたまストレス環境下で生き延びる個体が出現することで、平均的な生存率が高まるからである。
老化理論が成り立つ条件
上記の老化理論のうち、死の幇助説は、限られた場合のみ成立すると考えられるので、最初の3つの説(使い捨て体仮説、拮抗的多面発現説、有害変異蓄積説)が主要な理論と考えられている(18)。そこで、この3つの説についてももう少し詳しくみてみよう。
生物は老化が原因で死亡することがなくても、様々な外的要因(捕食、災害、事故、資源の枯渇、年齢に依存しない捕食や病気など)で死亡する。以下のような仮想生物を考えてみよう(図3)。ある生物は、老化以外の外的要因での死亡率が毎年50%である。老化しない個体では(図3a)では、1年生き延びる確率は0.5で、生き残った個体は2個体の子どもを産む。2年目は、さらにその半分が生き残り2個体の子どもを産む。3年目も同様だが、4年目には、生き残る個体はいなくなる。1個体が生涯に残せる子どもの数は1.75となる。同様に老化しない個体の場合(図3b)、2年目、3年目で子どもを産まなくても、1年目で4個体の子どもを産めば、生涯2個体の子どもを持つことが期待できる。
一方、図3cの個体は、同様の外的要因での死亡率は同じだが、老化によって、2年目まで生存することはない。しかし、1年目に生き残った個体は4個体の子どもを産むので、一生涯に残せる子どもの数は2となる。老化しない個体(図3b)と同じ数の子どもを残せる。

この例のように、老化による死亡がない生物でも、外的要因で個体が死亡するとき、一生涯の早い時期により多くの子どもを産めば、一生の後半では、繁殖を終えても、一生涯に残せる子どもの数(適応度)は下がることはなく、自然選択で有利になる(自然選択は、他個体と比べて相対的に多くの子どもを残せるような性質に有利に働く)。そのため、2年目、3年目で、生存率を維持するような性質には自然選択が働きづらくなり、高齢になって生存率を低下させるような有害遺伝子が遺伝的浮動により蓄積することになる。その結果、図3cのような老化が生じる個体が進化する。これが有害突然変異蓄積の説である。
一方、図3aの個体が図3bの個体のように、生涯の若い時期により多くの繁殖をする性質は自然選択に有利になる。その結果、若い時期の繁殖に有利に働く遺伝子が、年老いてからは有害な効果を示す場合、図3cのように老化が進化する。これが拮抗的多面発現説である。また、生涯の早い時期に生殖にエネルギー投資をしたために、体細胞への投資が低下し、老化するというのが使い捨て体仮説となる。特に、生殖の機能を維持する遺伝子への選択が、体細胞維持では有害になると考えると、使い捨て体仮説は、拮抗的多面発現説の特殊例といえる(13)。
これらの老化理論が成り立つためには、外的要因による死亡率がある程度存在し、加齢に伴って繁殖成功(生存率を考慮した子どもの数)が低下する、という条件が必要である。
老化理論の検証
これらの老化説のうち有害突然変異蓄積説と拮抗的多面発現説に関しては、それぞれの理論からの予測を検証するという形で、ショウジョウバエ、魚類など、いくつかの生物を対象に検証が行われてきた。拮抗的多面発現説を支持する研究や、どちらの説も支持する研究が発表されてきたが、どちらの理論にも反する研究結果もあり、まだ確実にこれらの説が確かめられたわけではない(老化理論の説明や理論検証を含めた詳しい解説は、文献18の補足情報「加齢研究の基本的背景」に詳しい) 。
ここでは、ヒトについての検証研究を一つ紹介したい。
Rodríguezらは(18)、ヒトの120の疾患に影響するゲノム上の2559箇所のSNP(一塩基多型;一塩基が異なっている遺伝的多様性。SNPの説明については進化的視点からみる人間の「多様性の意味と尊重」の図1と2を参照)を利用して、老化理論を検証した。閾値年齢を決め、それら120の疾患を、その閾値年齢より前で発症する疾患と後に発症する疾患に分けた。たとえば、10才を閾値年齢とすると、10才以前で発症する疾患と10才後に発症する疾患にわけ、それぞれの疾患に関わるSNPの遺伝的多様性(遺伝的変異)を調べた。閾値年齢を変化させ(10才から60才まで)、それぞれの場合の遺伝的多様性を示したのが図4aである。
36歳より低い年齢を早期発症と晩期発症を分ける閾値として用いると、早期発症疾患の遺伝的多様性が後期発症疾患の遺伝的多様性より統計的に有意に小さいことが示された。遺伝的多様性が小さいということは、疾患を引き起こす変異に対して自然選択が働き、低い頻度に抑えられているということだ。逆に、遺伝的多様性が高いということは、自然選択が緩和され、疾患が有害であるにも関わらず、高い頻度で維持されているということである。つまり、この結果は、有害突然変異蓄積説を支持する結果といえる。
次に、拮抗的多面発現遺伝子の影響をみるために、一つの変異箇所が、異なる疾患に影響している266のSNPを調べた。たとえば、あるゲノム上のSNP箇所は、DNAの塩基がGとAのどちらかの多型となっているとする(AあるいはGアレルという) 。Gは、一つの疾患(疾患G)のリスクを高めるアレルとなっているのに対し、Aが別の疾患(疾患A)のリスクを高めるという場合がある。この場合、アレルAをもっている個体は、疾患Aにはなりやすいが、疾患Bにはなりづらいために、拮抗的多面発現変異といえる。
前述の解析と同様に、閾値年齢をきめ、同じ変異箇所の一方のアレルが、早期発症疾患のリスクアレルであり、別のアレルが後期発症疾患のリスクアレルとなる拮抗的多面発現遺伝子が、期待されるより高い頻度でみられるかを調べた。図4bはその結果である。閾値年齢が40才から50才の時、拮抗的多面発現効果を示す変異が有意に多くみられた。年齢40~50歳より若いときに、ある疾患リスクを下げるアレルが、より高齢で他の疾患のリスクを高める傾向があったという事だ。
Rodríguezら(18)の結果は、加齢に伴って自然選択による淘汰が弱まることによる有害突然変異の蓄積説と、若年での発症を低下させると、老齢での別の疾患に罹るリスクが増大するような遺伝子が有利になっているという拮抗的多面発現説の両方を支持する結果となっている。

なぜ老化しない生物がいるのか?
有害変異蓄積説の理論構築を行ったハミルトン(15)は「老化は普遍的」であると考え、老化理論を考えていた。しかし、上述したように、年齢とともに死亡率が上昇しない種や場合によっては低下する種もいる。
Vaupelら(19)は、理論的解析から、(i)サイズが大きくなると死亡率が低下する、(ii)サイズが大きくなると繁殖力が増大する、(iii)個体の修復能力が高い、といった種は、老化がみられないか、あるいは負の老化(加齢とともに死亡率が下がる)が生じることを予測した。外的要因による死亡率が小さく、高齢になっても高い繁殖率を維持したり、増加させるような種は、長寿であり、老化が生じないように進化するというのだ。
図3と同様の生命表で考えて見ると、外的要因による死亡が少ない場合、年齢を経てから子どもを産むことの不利益は減少はする。たとえば、加齢とともに体サイズが大きくなり、出生数が増加していく場合、生物個体にとって、老化を防ぎ、寿命を延長させる方が、より多くの子どもを残せることになる。
北太平洋沿岸に生息するロックフィッシュ(Sebastes属)の寿命は、11年から200年以上であるという。Koloraら(7)は、88種のロックフィッシュ(Sebastes属)のゲノム配列を調べ、寿命に関係する遺伝子を検出した。さらに、短命種と長命種で正の自然選択をうけた遺伝子(有利に働いた遺伝子)を検出した。その結果、長寿の種では、免疫遺伝子(炎症を制御)やDNA修復関連の遺伝子が自然選択をうけ、進化していることがわかった。
さらに、生活史形質との関連を調べたところ、体の大きい種ほど最大寿命は長い傾向にあった。繁殖力は体サイズが大きいほど増加するため、加齢とともに繁殖率は増加する傾向にあった。極端な例では(S. ruberrimus)、150歳の個体が1シーズンあたり100万匹以上の子供を産むこともあるという。
短命のロックフィッシュは、長命のロックフィッシュに比べて小型で浅い海域に生息している。そのため、競争相手や捕食者、病原体などの危険に直面することが多く、外的要因による死亡率が高い。それに対して、長寿のロックフィッシュは体サイズが大きく、より深い海域に生息している。そして、年齢とともに体が大きくなり、繁殖力が増大する。このような長寿種の性質や生息する環境が、高齢でも老化しないように、DNA修復などに関わる遺伝子が自然選択を受けることで、長寿へ進化したと考えられる(20)。(注3)
77種の爬虫類と両生類の加齢と死亡率を調べた前述した研究(5)は、長寿にかかわる複数の仮説を検証した。最初の仮説は、保護的表現型仮説である。これは、硬い甲羅などの物理的な防御性質や、毒などの化学的防御をする生物は、捕食されるなどの外的要因による死亡率が低下するために、長寿に進化するという仮説である。結果は、この仮説を支持するように、防御性質をもってる種の方が寿命が長かった。
次に、Reinkeらは(5)、初生殖年齢と老化の関係を調べた。老化理論の項でも触れたように、早い年齢で繁殖するほど、その後の生存に対する自然選択が緩和され、有害な遺伝子が蓄積しやすくなったり、初期の繁殖に投資するほど、後期の生存に不利になる。解析結果は、初生殖年齢が早くなるほど、老化率は大きくなり、最大寿命は短くなった。これは、有害突然変異蓄積説や拮抗的多面発現説を支持する結果である。
さらに、外温性の種の温度環境と老化の関係を調べ結果、外温性生物種の温度環境と老化率に関して、一貫した傾向はみられなかった。環境温度や体温が上昇すると、代謝率が上昇し、活性酸素生成、炎症の悪化、DNA損傷などの複数のプロセスを通じて分子損傷の蓄積が促進されると考えられている。おそらく、このような老化の要因を食い止めるには、ならんかのコストが必要だと思われるが、生物種によっては、進化的変化によって、それらのコストが回避できるのかもしれない。
これらの研究結果は、外的要因による死亡率と高齢にともなうサイズの増大や繁殖率の維持・増加が重要であるとする理論的予測を支持するものになっている。
注3. もし生物が、個体数が増えすぎて絶滅しないように、あるいは集団中により多様性を生じるために、死が進化したという仮説が仮に正しいなら、安定した環境で個体が外的要因で死ぬことなく、増えていくような種ほど、死は進化しやすいと予測できる。しかし、実際には、安定した環境で外的死亡率が低いほど長寿になったり、老化が起こらなかったりする。
老化と寿命の進化
この記事でみてきたように、生物の老化とそれによる死は、不可避的な生物現象ではなく、進化によって変更可能な性質といえる。老化に関わる様々な遺伝子に自然選択が働いたり、緩和(働かなくなる)したりすることで、老化を早めたり、遅らせたりする生物が進化することが可能なのだろう。
生物の生息環境やその生物が持っている性質(たとえば成長や繁殖様式、形態などの保護形質、代謝生理機構)などが、老化を早めたり、遅らせたりする進化的要因として働くのだと考えられる。
現在、多くの研究者が、老化メカニズムについての研究を行っており、多くのことが解明されつつある。そのような老化機構は、ある生物がどのように老化するのか、という回答を提供してくれるが、なぜ、そのような老化機構によって早く老化するように進化したのか?あるいは、老化速度が低下し、長寿に進化したのか、という問いには、答えてくれない。
しかし、老化機構を解明することは、老化の進化要因を探る上でも重要である。たとえば、知られている老化機構を抑制するには、どのような制約やコストが掛かっているのか、という知見は、ある生物が長寿に進化できない避けられないコストはあるのか?といった問題に繋がる。
代謝率が上昇し、酸素消費量の大きい生物は短命であるという大まかな傾向が示されている。しかし、両生類では、代謝が増大すると考えられる高温環境で生息する種の方が老化が遅かった(5) 。また、飛翔する鳥類は飛翔できなくなった鳥類に比べ、代謝は高いが、寿命は長くなっている(24)。代謝の上昇は、老化を早め、それを抑制するにはコストがかかっていると思われる。しかし、ある種の生物では、そのコストを克服するような進化が生じている。その具体的な生理的・分子メカニズムを解明することは、老化の進化研究にも重要である。
また、老化に関わるどのような遺伝子に自然選択が働くことで、老化が遅れるのか、という問題についても、老化機構の理解と進化的理解の両者を必要とする。老化に関わる遺伝子のうち、生物で選択を受けやすい遺伝子、あるいは受けづらい遺伝子があるのかという進化の問題は、老化機構の研究にも重要だろう。
現在、人の老化を遅らせる研究が盛んに行われている。しかし、もし人の寿命が高齢での有害突然変異の蓄積によって進化したとすると、それら多数の有害変異に対応するのは、難しいだろう。
今後、進化的視点を含んだ老化研究がさらに必要となってくると思われる。
進化の仕組みについては以下の新書を参照してください。
以下は、関連記事です
- 人類の進化史と病気の進化
- 食生活の変化による脂肪酸代謝の進化:植物性脂肪か動物性脂肪か
文献
1.:Demarest, T. G. et al. (2018) NAD+ Metabolism in Aging and Cancer. Annual Review of Cancer Biology, 3, 1–26 .
2. Tian, X. et al. (2019) SIRT6 Is Responsible for More Efficient DNA Double-Strand Break Repair in Long-Lived Species. Cell, 177, 622-638.e22.
3. Jones, O. R. et al. (2014) Diversity of ageing across the tree of life. Nature 505, 169–173.
4. Silva, R. da, et al. (2022) Slow and negligible senescence among testudines challenges evolutionary theories of senescence. Science 376, 1466–1470.
5. Reinke, B. A. et al. (2022)Diverse aging rates in ectothermic tetrapods provide insights for the evolution of aging and longevity. Science 376, 1459–1466.
6. Ruby, J. G. et al.(2018) Naked mole-rat mortality rates defy Gompertzian laws by not increasing with age. eLife 1–18. doi:10.7554/elife.31157.001.
7. Kolora, S. R. R. et al.(2021) Origins and evolution of extreme life span in Pacific Ocean rockfishes. Science 374, 842–847.
8. 小林武彦 (2021) 生物はなぜ死ぬのか。講談社
9. 吉森保 (2020) LIFE SCIENCE:長生きせざるをえない時代の生命科学講義. 日経BP.(進化についての記述部位については、次版で修正していただけるそうです。)
10. Kirkwood, T. B. L. (1977) Evolution of ageing. Nature 270, 301–304.
11. Williams, G. C. (1957). Pleiotropy, natural selection, and the evolution of senescence. Evolution, 11, 398-411.
12. Charlesworth, B. (1994) Evolution in Age-Structured Populations. Cambridge University Press, 1994.
13. Kirkwood, T. B. & Holliday, R. (1979)The evolution of ageing and longevity. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 205, 531–546.
14. Medawar, P. B. (1952) An Unsolved Problem of Biology. H. K. Lewis, London.
15. Hamilton, W. D. (1966) The moulding of senescence by natural selection. Journal of Theoretical Biology 12, 12–45.
16. Bourke, A. F. G. (2007). Kin selection and the evolutionary theory of aging. Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics 38, 103–128.
17. Yamaguchi, Y. et al. (2018) Double-edged heat: honeybee participation in a hot defensive bee ball reduces life expectancy with an increased likelihood of engaging in future defense. Behavoral Ecology Sociobiology, 72, 123.
18. Rodríguez, J. A. et al. (2017)Antagonistic pleiotropy and mutation accumulation influence human senescence and disease. Nature Ecology & Evolution, 1, 1–5.
19. Vaupel, J. W., et al. (2004)The case for negative senescence. Theoretical Population Biology, 65, 339–351.
20. Lu, J. Y., et al. (2021) Long-lived fish in a big pond. Science, 374, 824–825.
21. Walker, D. W., et al. (2000) Evolution of lifespan in C. elegans. Nature, 405, 296–297 .
22. Yoshino, M. et al. (2021)Nicotinamide mononucleotide increases muscle insulin sensitivity in prediabetic women. Science, 372, 1224–1229.
23. Nacarelli, T. et al. (2019) NAD+ metabolism governs the proinflammatory senescence-associated secretome. Nature Cell Biology ,21, 397–407.
24. Ikemoto, A., et al. (2020) Genetic factors for short life span associated with evolution of the loss of flight ability. Ecology and Evolution, 10, 6020–6029.
25. Steiner, U. K. (2021) Senescence in Bacteria and Its Underlying Mechanisms. Frontiers in Cell and Developmental Biology9, 668915.
26. Swings, T. et al. (2017)Adaptive tuning of mutation rates allows fast response to lethal stress in Escherichia coli. eLife 6, e22939.
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
