
ひとつ前の『風の時代』・鎌倉時代の「宋銭」と「電子マネーや仮想通貨」 〜風の時代を会計から読み解いてみよう④〜
風の時代と土の時代
今回も、ひとつ前の「風の時代」に起きた出来事から、これからの「風の時代」について考えていきたいと思います。
ひとつ前の風の時代は
ひとつ前(前回)の「風の時代」は1185年頃~1425年頃だそうです。
日本では、ちょうど鎌倉幕府が始まった頃ですね。
第②回は「鎌倉時代の始まりとAI」、第③回は「御成敗式目とAI」です。
上記の2回では、政治や法的な側面を確認しました。
ではなぜ、これから先の「風の時代」をずっと昔の歴史から確認していくのか。
理由はこちらです。
歴史は人間にとって無限のコンテンツの宝庫であって面白い。
今回は、経済的な側面を確認していきたいと思っています。
テーマは「宋銭と電子マネーや仮想通貨(ビットコイン)」です。
歴史的に必ずしも正確ではない文章になっているかもしれません。
正確な歴史については教科書や本などでご確認くださいね。
荘園公領制の発展
承久の乱によって、朝廷側の荘園が鎌倉幕府に没収されました。
没収された荘園は鎌倉幕府の御家人に分け与えられ、地頭が置かれました。
地頭は、荘園の治安の維持と徴税(年貢)の管理を行いました。
荘園の一部は地頭給田という取扱いになりました。
地頭は、地頭給田から徴収した年貢を給料として与えられることになります。
地頭は、毎年、地頭給田からの年貢を受け取ることができるようになります。
私が地頭なら、農地からの収穫量を少しでも増やしたいと思うことでしょう。(経済的な動機の一つです)
このようなことから鎌倉時代には、農地からの収穫量を増やすために、
農業技術が大きく発達しました。
鎌倉時代に発達した農業技術の例としては、
灌漑技術(給排水の技術)や農耕具(鍬や鎌など)の開発があります。
また、農耕牛馬の利用が始まりました。
さらに、二毛作が行われるようになりました。

産業の発展と市と座
農業技術の発達によって、農作物の収穫量が増えるようになります。
収穫量の増加は、日常生活で消費する分量の残りの部分、余剰分が生まれます。
この余剰分は蓄えられて富となります。
富は、物品の購買力へとつながります。
また、農業技術の発達により、手工業の原材料の収穫量も増えていきました。
たくさんの原材料があることで、手工業では大量生産が可能となり、
製品の種類や生産量が増加します。
そして、出来上がった製品の売買のために、流通や取引が活発になります。
このようなことから、農作物や手工業の製品を売買する「市(市場)」が各地で開催されるようになりました。
また、商工業者の同業組合として「座」が広まっていきます。
市
1 毎日、または一定の日に物を持ち寄り売買・交換すること。また、その場所。市場。「—が立つ」「朝顔—」
2 多くの人が集まる所。原始社会や古代社会では、歌垣 (うたがき) ・祭祀・会合・物品交換などに用いられた場所。
座
1~7 省略
8 中世、朝廷・貴族・寺社などの保護を受け、座役を納める代わりに種々の特権を有した商工業者や芸能者の同業組合。
貨幣経済の発展
「市」などで、農作物や手工業製品がたくさん取引されるようになりました。
そうすると、取引を行うための貨幣の役割が大きくなります。
貨幣については、奈良時代の頃から、和同開珎(わどうかいちん・わどうかいほう)などの貨幣が鋳造されていました。

しかし、鋳造技術が低かったことなどから、日本で鋳造された貨幣は、
商人の間でも、あまり流通することとがありませんでした。
実際の商取引では、
交換ニーズの高い「米」や「絹、綿布」などを用いた物々交換が中心でした。

貨幣は、商取引においては、農作物と比べて保存ができる点(腐らない)や
持ち運びが容易である点などから重宝されます。
鎌倉時代には、各地で「市」が開かれて、地方での商取引が活発になりました。
商取引が活発になると、商人間では、取引に貨幣を用いるニーズが高まっていきます。
その一方で、
当時の日本国内の貨幣の鋳造技術は高くありません。
そこで、中国の宋から輸入した「宋銭」が商人の間で重宝されて、
広く用いられるようになりました。
「宗銭」の流通によって貨幣経済が大きく発展しました。
物々交換から貨幣による交換への変化
商取引において、物々交換から貨幣による交換への変化は、
農村などでの富の増加が背景にあることでしょう。
荘園公領制における農業技術の発展により、農作物の収穫量が増えて、
生活必要量を上回る余剰分を生み出せるようになったことが大きいと言えます。
逆に、富がない、すなわち余剰分がない状態では、
貨幣を使って取引する必要はあまり多くありません。
自分が食べるだけの量しか生産できないとなると、
人には他の品との交換する余裕はありません。
このような状況では、生活に必要な必需品を手に入れるには、
必需品と必需品を物々交換で行うことで足りてしまいます。
無人島では、お金を持っていても意味をなさないことに近いですね。
農村では、生産物に余剰分がないため、商品の購買力もあまりありません。
平安時代の貨幣があまり重宝されませんでした。
これは、鋳造技術の低さだけでなく、「市」での取引量の少なさから、
貨幣のニーズがあまり高まらなかった点もあることでしょう。
鎌倉時代なって、農村にも生産物の余剰分ができることで、
余剰分を「市」で売却することができるようになりました。
そして、余剰分を売却して得た貨幣でさらに別のモノを購入するという、
取引の循環が行われるようになります。
取引が活発になり、どんどんと循環していくようになると、貨幣の流通量がさらに増えていくことになります。
物価の存在
鎌倉時代には、「市」を中心に、貨幣を用いた取引が主になってきました。
貨幣での取引では、商品と貨幣とを交換するために、
商品の交換価値を貨幣の単位で測定(評価)することになります。
ここで、「物」の値段、価格(物価)が生まれます。
「物」に物価が存在するようになると、物価が変動したり、
貨幣の価値が変動するという影響が出るようになります。
宋銭の特徴
鎌倉時代に流通した「宋銭」の特徴には、下のようなものが挙げられます。
「宋銭」は、平清盛が日宋貿易を開始したことにより、日本への流入が始まった。
しかし、平清盛の没後、「宋銭」の流通はいったん廃止された。「宋銭」は宋から輸入した貨幣であり、朝廷が鋳造させた通貨ではなかった。
「宋銭」は、商人が取引の利便性から広く用いるようになった。
都市部だけでなく地方の「市」でも貨幣としての価値が受け入れられた。「宋銭」は、広く流通するようになったことから、公式な貨幣として取り扱われるようになった。
宋銭と電子マネー(○○ペイ)
これからの「風の時代」の貨幣経済を考える時には、
ひとつ前の「風の時代」の鎌倉時代の「宋銭」の流通の経緯や広がりが
参考になるかもしれません。
「宋銭」は、平安時代の終わり頃から日本での流通が始まりました。
「風の時代」の少し前、「土の時代」の終盤です。
そこで、「宋銭」を、
今の「風の時代」の少し前の「土の時代」の終盤に起きた出来事に
置き換えてみました。
「土の時代」の終盤の2010年代後半から、
大きく流通が始まったものに「電子マネー」があります。

電子マネーの特徴
電子マネーの特性を考えてみました。
宋銭と同じように箇条書きしてみます。
「電子マネー」は、土の時代の終盤、平成の終わり頃から流通が始まった。
「電子マネー」は、国や政府が鋳造した法定通貨ではない。
「電子マネー」は、大変多くの取引の決済に利用できるようになっている。
「電子マネー」での取引の安全や安定性を確保できるように環境整備が進められている。
「宋銭」と「電子マネー」を比較すると大変良く似ている印象があります。
中国からの電子マネー
宋銭のように、中国から入ってくる「電子マネー」を考えてみましょう。
私は、アリペイ(Alipay)が最初に浮かんできます。
アリペイの中国でのシェアは、50%を超えるということです。
5億人以上が利用していることになります。なんと多いことでしょう。
アリペイは、日本では、PayPayと連携しています。
PayPayのホームページには、「PayPayが使えるお店では、アリペイでのQRコード決済ができる」との案内がされています。
また、日経新聞(6.5.24朝刊)に、面白い記事を見つけました。
フィリピンの電子マネーである「Gキャッシュ」は、アリペイと提携しており、海外の各地で「Gキャッシュ」が利用できると記載されています。
海外に旅行するフィリピン人にも重宝されている。中国アント・グループが手掛ける「アリペイ」やVisaカードなどと提携し、海外の各地でGキャッシュが使える。
日経新聞の記事によると
「Gキャッシュ」の利用者は9000万人に上ります。
「Gキャッシュ」を利用する際に、アリペイを経由させることで、
日本国内のPayPay加盟店でのQRコード決済が可能になるということでしょうか。
(正しい情報は、「PayPay」や「アリペイ」、「Gキャッシュ」のホームページ等でご確認をお願いします)
海外旅行での決済手段
これまでは、海外で買い物をする場合には、現金やクレジットカードが主な決済手段でした。
現金なら外貨への両替が必要になります。また、現金を持ち歩く点でのリスクもあります。
クレジットカードを利用する場合には、例えば、学生であれば、クレジットカードを持つこと自体に1つのハードルがあります。
さらに、利用限度額も設定されています。
海外でも、自分のスマホの電子マネーで決済ができることは、
利便性がとても高いと感じられます。
利便性が高ければ、利用量はどんどんと増えていくことになります。
世界中の電子マネーが、提携の形で、つながっていくというのは、
貨幣経済にとっては、非常に大きな出来事であると感じます。
中国のアリペイは、鎌倉時代の宋銭のような役割を持つのかもしれません。
これから、世界中の電子マネーの提携が、貨幣経済の変化に大きな影響を与えていくのかもしれませんね。
宋銭とビットコイン(仮想通貨)
電子マネーと同じように、「土の時代」の終盤から広がりを見せたものに、
「仮想通貨」があります。
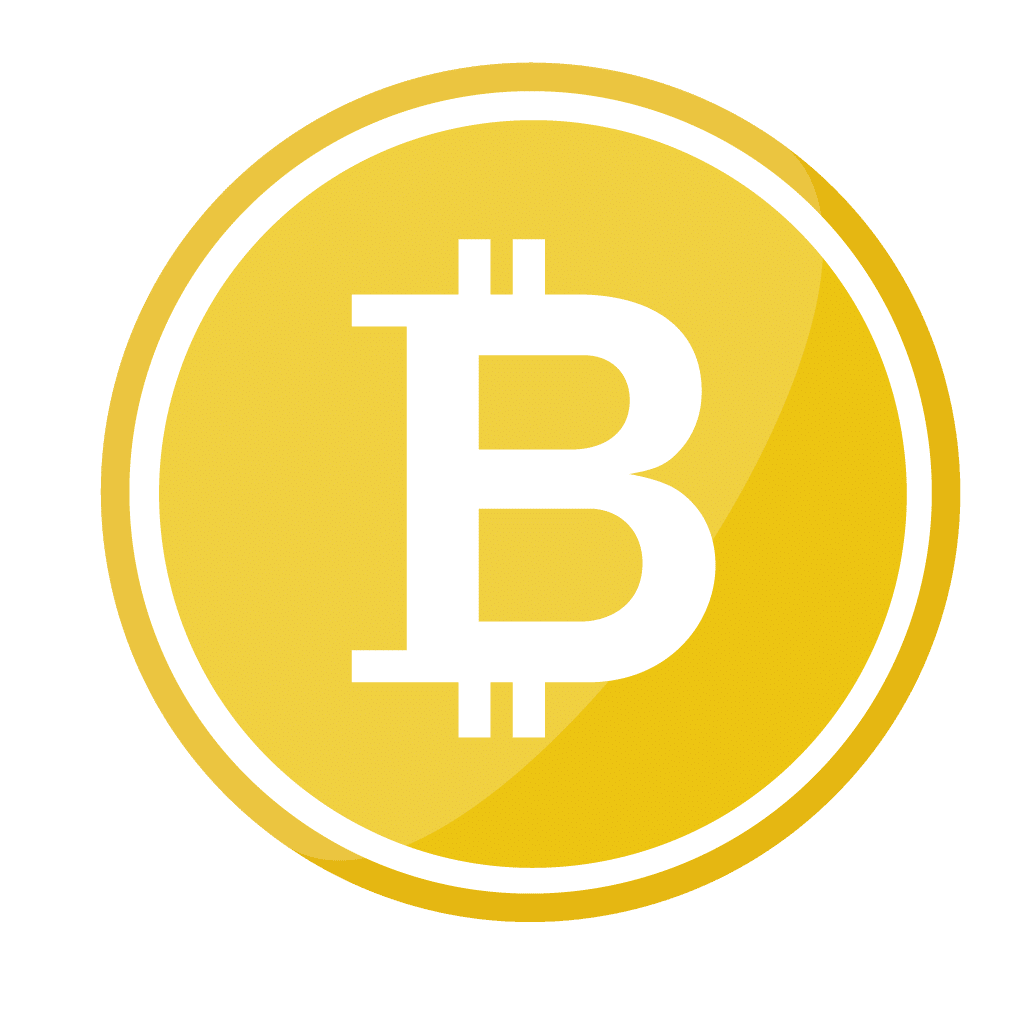
そこで、「仮想通貨(暗号資産)」の特徴も考えてみました。
「仮想通貨」は、国によっては、取引が禁止された歴史がある。
「仮想通貨」は、国や政府が鋳造した法定通貨ではない。
「仮想通貨」を様々な取引の決済に利用できるようになってきている。また、「仮想通貨」を取扱うの取引所も増加している。
「仮想通貨」での取引の安全や安定性を確保できるように法整備が進められている。
「仮想通貨」の広がりも、「宋銭」の流通の経緯とシンクロしているように感じます。
「宋銭」が流通した貨幣経済の発展の背景には、鎌倉時代における荘園公領制での農業や産業の技術の発展や「市」などでの商業の発展がありました。
これからの「風の時代」にも農業や産業、商業の発展や変革とその要請から
電子マネーや仮想通貨が、「貨幣経済」を姿や形から変えていくのかもしれません。
最後までお読み下さり、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
