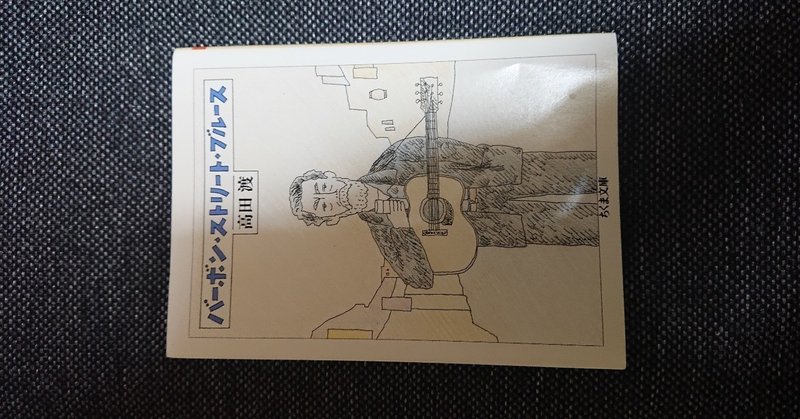記事一覧

一日一書評#42「バンド臨終図巻 ビートルズからSMAPまで/速水健朗・円堂都司昭・栗原裕一郎・大山くまお・成松哲著」(2016)
音楽の世界には、様々なグループやバンドがいる。古今東西多くのバンドが結成され、残念ながら解散していくこともある。それらが結成された理由は些細でありふれたものかもしれない。しかし、解散の理由となると、バンド一つ一つに存在する。不仲、お金の問題、事務所の問題など、様々な理由でバンドは解散していく。 そんな、世界中の有名なバンドや音楽グループの解散に至るまでの経緯をまとめた本が、この「バンド臨終図巻 ビートルズからSMAPまで」だ。タイトルの「バンド臨終図巻」は、山田風太郎さんに